方丈記 & 『我関わる、ゆえに我あり -- 地球システム論と文明』 [Book_review]
中村桂子が 方丈記を取り上げている。
今週の本棚:中村桂子・評 『鴨長明 方丈記』=浅見和彦、校訂・訳
(ちくま学芸文庫・1050円)
◇災害を見据えた古典が示唆するもの
「ゆく河のながれは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつむすびて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人と栖(すみか)と、またかくのごとし。」
高校の古文の時間に、この美しい書き出しは中世の特徴である無常観の表現と教えられたまま時は過ぎた。それがなぜか、東日本大震災後しばらく思考停止となり、積極的な読み書きができない中で、「方丈記」という文字に惹(ひ)かれたのである。読んで予想との違いに驚いた。みごとな「災害ルポルタージュ」であり、今何を考え、何をしたらよいかへの示唆が次々出てくるのだ。たった二〇ページの中に。解説に「災害を正面から取り上げた日本で最初の記録」とある。
長明が二十三歳からの九年間(一一七七~一一八五年)に大火、辻風、福原遷都、飢饉(ききん)、大地震と天災人災合わせての事件が続いた。今と似ている。安元の大火を見よう。「風にたえず、吹き切られたる焔(ほのほ)、飛ぶが如くして、一、二町を越えつつ移りゆく。その中の人、うつし心あらむや。」火元の樋口富の小路から末広に燃え広がり、京の三分の一を焼いた。公卿(くぎょう)の家十六が焼け、死者は男女合わせて数十人、馬牛は無数に死んだとある。焼跡を歩き現場調査をした記録である。
辻風も起き不安の中、反平家の動きに対し清盛が福原遷都をする。思いつきで「世の人、安からず、憂へあへる、実(まこと)にことわりにもすぎたり」である。新京の建設は難航し、結局還都となった。巨大な浪費と空しい結果だ。「いにしへの賢き御世(みよ)には、あはれみをもつて、国を治め給ふ」。煙の立つのがとぼしいと租税もゆるしたのに、今の世はなんだと長明は嘆く。天候異常で飢饉も来る。元号を「養和」、「寿永」と改めるがそんなことで救われるはずもない。いたいけな幼子が亡くなった母の乳房を吸っている様が描かれる。長明は、京都下鴨神社の神官の子として生まれたエリートだが、庶民、女性、子どもなど、人々の生活を確かめ、その視点で社会を見ている。
更に地震だ。「おびたたしく大地震(おほなゐ)振ること侍(はべ)りき。そのさま、世の常ならず。山はくづれて、河をうづみ、海はかたぶきて、陸地(ろくぢ)をひたせり。」「おそれの中におそるべかりけるは、ただ地震(なゐ)なりけりとこそ覚え侍りしか。」震源地は京都の北東、マグニチュード七・四と推定されている。最後に、「人みなあぢきなき事をのべて、いささか、心の濁(にご)りもうすらぐと見えしかど、月日重なり、年経にし後(のち)は、言葉にかけて言ひいづる人だになし。」とある。風化である。恐(こわ)い。
長明は都の生活を捨て、里に方丈、つまり一丈四方の庵(いおり)を建てて暮らす。縁者の妨害で下鴨神社の神官になれなかったという個人的問題もあったようだが、都の大きな家で暮らすことの儚(はかな)さを感じたのだ。この庵は組立て式、移動可能で事実最初の大原は寒過ぎたのか、伏見に移っている。庵内は寝床、法華経、普賢と阿弥陀絵像、琴、琵琶があるのみだ。のみと書いたがこれで充分なのだ。外をよく歩き楽しんでいる。
無常という言葉の受け止め方は難しいが、自然は常ならずは事実だ。長明は、それを受け入れ自律的に生きている。科学技術時代に生きる私たちも、天災・人災の重なった被害から立ち直るには、自然と向き合い、その中にいることを確かめながら、なお自律的に生きるしかない。一人一人が自らを生き、支え合い、地域に根ざし、自然を活(い)かした社会をつくることだ。これができなければ私たちは何も学ばなかったことになる。
毎日新聞 2012年3月11日 東京朝刊
作家、堀田善衛の『方丈記私記』を昔読んだ。あまりに形容詞過多、の文章に辟易した記憶がある(堀田のエッセイはたいていそうである)。
中村桂子の文章、最後の段落は精読するに足る。
・長明は、それを受け入れ自律的に生きている。
・科学技術時代に生きる私たちも、天災・人災の重なった被害から立ち直るには、自然と向き合い、その中にいることを確かめながら、なお自律的に生きるしかない。
・一人一人が自らを生き、支え合い、地域に根ざし、自然を活(い)かした社会をつくることだ。これができなければ私たちは何も学ばなかったことになる。
松井孝典(宇宙学者)が新著を出した『我関わる、ゆえに我あり -- 地球システム論と文明』。最後の章(第五章)、ヒトの直立二足歩行について次のように述べている。
つまり胎児が発達途上のママ、胎内から出てきたということ。本来なら、21ヶ月が妊娠期間といえる。。。 これは妊婦にとってハンディが大きすぎる。脳が大きいと分娩が困難になるからだ。ヒトはしたがって小さく産んで出産後時間を掛けて乳児の脳を大きくする、という道を選んだ。
千円も出すのなら古書店で文字の大きい装丁もがっしりした全集版から買うのがよい。岩波古典文学大系などの古典全集。各社から出ている。
井上馨 『原発賠償の行方』 新潮新書 [Book_review]
ガリガリの法理論者(元裁判官、現在弁護士。裁判員制度に反対)のみた100兆円を越えると言われる原発賠償問題。
共感したところ:
1 原発立地市町村は危険承知で原発を誘導したのであり、損害賠償に当たっては過失相殺の原理を適用して、賠償額を割り引くべきである。(立地市町村は加害者でもあるのである)
2 東電は破綻させるべきであった(経営者が変わるだけで電力供給には何の影響も与えない。サービス継続に影響するというデマを流した)。巧妙なトリックにより、東電を存続させた上、過失のない消費者に賠償を転化してしまった。加えて、他の電力会社にも賠償の負担をさせ、玉突きで料金値上げとなる。(東電株主や出資銀行、天下り官僚はウハウハ)。
疑問点:
菅首相が中電に対して(超法規措置として)浜岡原発の停止を求めたことをしつこく突いている。法理論的にはその通り(菅の命令?は違法)だろうが、しかし、中電は会社の経営判断をこれまで誤ってきたのである(地震学者の意見を無視)。経営判断を誤ればフクイチのように国を滅ぼすのだ。法理論で経営判断や国家施策を打ち出せるものではない。菅は経営者に対する経営アドバイスを行ったとみなせばよいのである。お馬鹿な菅は、恫喝電話一発で済ませればいいものを公表してしまった。アマゾン書評が指摘していたが、井上馨は、311の数日前、首相の命令!によりフクイチの運転を停止していたとしても、同じことを言うのだろうか?
本書の半分以上を費やしている第4章「法律的検討をする」に著者の主張は詰まっているが、問題は章のタイトルが示す<法律的検討>だけで、十分なのか?ということだ。
p143から:
「。。また浜岡原発を停止させるという点についても、法律的な根拠はなく要請するほどの緊急性があるかとなると、必ずしもそうともいえないと思います。中部電力に莫大な損害を与えてまで、一刻も早く中止要請をするほどの理由はないだろうと思います。必要な法律をつくってから停止要請をするのが筋だと思います」
井上馨は過去40年の反原発派がことごとく敗れてきた裁判闘争を知っているのだろうか?立法機関がどのような法律をこれまで作ってきたか?フクイチ事故が発生するまでなぜ、法律や司法が原発を阻止できなかったのだ?行政、立法、司法のいずれも原発阻止には寄与しなかった(どころか、推進役に回っていた)。一部国民と一部科学者の声を聴かなかった。こういう時、残された道は何であるのか?フクイチ大事故が発生した後でも、この暢気な提案しか出せぬ法律家。
つまりこの本は、法理によっては国家滅亡を阻止できないのです、と問わず語りに語っているのである。
#
この本を詳細に書評したブログが見つかったので紹介。
http://tanukinosato.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-3490.html
(数回にわたって扱っている)
岩波の謹告 [Book_review]
岩波書店HPの謹告に、コネ縁故採用の弁明が現れた。
##
■小社の「定期採用」報道について――
小社の2013年度定期採用をめぐって、新聞、テレビ、ネット上でさまざまな報道・論評がなされています。しかし、それらのなかには、不正確な、あるいは誤解を招く報道・論評も見受けられますので、この問題についての小社の見解を以下に表明いたします。
- 小社は、いわゆる「縁故採用・コネ採用」は行っておりません。「著者の紹介、社員の紹介」という条件は、あくまで応募の際の条件であり、採用の判断基準ではありません。ご応募いただいたあと、厳正な筆記試験、面接試験を行っております。
- この応募条件は、採用予定人数が極めて少ないため、応募者数との大きな隔たりを少しでも少なくするためのものです。
- 小社に入社を希望なさる方は、岩波書店著者にご相談いただくか、お知り合いの岩波書店の社員に直接ご連絡をください。いずれの方法もとれない場合は、小社総務部の採用担当者(03-5210-4145)に電話でご相談ください。
http://www.iwanami.co.jp/topics/index_k.html
##
採用条件。以下のように ( )内で条件を追加している。
http://www.iwanami.co.jp/company/index_s.html
| 応募資格 |
※岩波書店著者の紹介状あるいは岩波書店社員の紹介があること
(いずれの方法もとれない場合は、小社総務部の採用担当者に電話でご相談ください。) |
## 批判にビックリしてあわてて書き直した。。しかも、この書き方に不自然さを感じていのだから重傷である。コネも縁故もない、というのなら「紹介状は一切受け付けません」と書くべきだろうが。馬鹿者。「紹介状のない方は採用担当者に電話でご相談ください」。。。こんなお馬鹿な会社に入社しようと誰も思わないでしょ?と再考を迫っているのか。凝っている。ひょっとしてアタマいいのかも。
>小社は、いわゆる「縁故採用・コネ採用」は行っておりません。「著者の紹介、社員の紹介」という条件は、あくまで応募の際の条件であり、採用の判断基準ではありません。
だれかこの日本語の解説をしてくれないか。 <応募の際の条件>を満たさないのに採用も何もないだろーが。 アホか。
小社は、いわゆる「縁故採用・コネ採用」の方針を創立以来堅持しております。
。。と正直に書けばいいものを。 こういう不公正、かつ、非論理的な謹告を掲げる企業(出版社!)が、応募者に作文を書かせて、それを審査する、というのだからブラックである。<岩波の著者>たちもよく考えて欲しい。不公正な採用を行うと堂々と宣言している出版社から本を出すことは君等のポリシーに矛盾しないのかどうか。
岩波不買 http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2012-02-06
#
2/21
特集ワイド:岩波書店・募集要項の波紋 著者に「協力」依頼、存在していた「内部文書」http://mainichi.jp/life/job/news/20120221dde012100012000c.html
......取材を進めるうちに、記者はある「内部文書」の存在に突き当たった。
そこにはこうあった。
<社員各位 日頃お付き合いのある著者の中で、今回の社員募集に際してご協力を依頼できる方のお名前、所属および肩書き、送付先住所を教えてください。それを基に依頼リストを作成し、「依頼状と募集要項」を総務部から送付します>(抜粋)
A4用紙に横書きで印刷されており、日付は昨年12月21日、発信者は総務部長だ。
ここに書かれた通りなら、同社から本を出している数千人規模の著者のうち、「日頃お付き合い」があり「社員募集に際してご協力」を約束した一部の著者の周囲にいる学生ががぜん、有利ということにならないか。一般の学生たちには、岩波に「紹介」を頼まれた特別な著者を知るすべはなく、紹介状をもらうためのせっかくの努力も徒労に終わりかねない。
岩波不買 [Book_review]
先日読んだ雑誌『みすず』1/2月号合併号(書評特集)に石原千秋がつぎのように書いていた。岩波書店から2011年に刊行された翻訳書、ナオミクライン(Naomi Klein)『ショック・ドクトリン 上下』について。
「これも話題の書だった。新自由主義が大災害を好んで取り込んでいくことぐらいは誰でも知っているが、その具体例の豊富さが人を驚かせる。僕は「災難」が起きると饒舌になる人々を「ハゲタカ文化人」と呼んでいるが、それも「ショック・ドクトリン」の一部だったわけだ。この本が、すぐさま「叢書 震災と社会」(古井戸注・岩波の2012年新企画である)を企画してしまうような出版社から刊行されたのは、高度な皮肉なのだろうか」
岩波の雑誌『世界』は311以前から反原発を掲げて特集を何度も組んでおり、他の出版社から<震災後のタケノコ>のように排出されている反・原発本、震災本とは一線を画すもの、と評価していたが、出版社は企画するだけ、他人の原稿で喰っている会社である。応募条件に、機会均等に違反する紹介状必須(岩波書店・著者からの紹介状というのも笑わせる。著者の迷惑も顧みず。。というより、読者=顧客の迷惑なのだよ)という条件をつけた出版社が企画する、新しい社会、あり得べき社会、など知りたくもない。岩波は大企業ではないかもしれぬが出版社としては海外にも名が知れている。岩波は出版を通じて公平公正な社会、機会均等条件の確立を訴えていたのではなかったのか?おのれの企業だけは例外なのか?それでなくても雇用の厳しい現在の日本でなんと鈍感な企業だろうか?個人経営の零細出版社とはわけが違うのだ。前近代的な入社条件をつけるとはあきれてものがいえない。これを知ればナオミ・クラインもビックリするだろう。看板と中身の再検討が必要な会社の一つであったのにそれを見抜けなかった自分が情けない。
今年からイヤナミの新入社員たちは胸に<◎◎様ご紹介>という札をつけて働くのか?もう何十年もすれば(倒産している可能性が高い)、この会社はすべて<紹介社員>だらけになるのだ。寒気がする。
『世界』は20年以上、近所の小さな個人経営の書店を通じて定期購読していたのだが、今月号をもって購入停止する。

## 岩波HPから募集要項ダウンロードして貼り付けておく。
2013年度募集要項(岩波書店著者・社員紹介)
2012年1月 岩波書店
http://www.iwanami.co.jp/company/saiyo13a.html
募集の種別 2013年度定期採用(経験者含む)
担当業務 出版業務全般
採用人数 若干名
入社時期 2013年4月
(都合のつく方には、上記以前に入社をお願いする場合があります)
応募資格 A: 4年制大学卒業者(2013年3月卒業見込者を含む)
1982年4月2日以降生まれ
※岩波書店著者の紹介状あるいは岩波書店社員の紹介があること
応募書類 1. 入社志望書(岩波書店作成のもの)
2. 作文:「職業としての出版と私」
(岩波書店作成原稿用紙使用/800字以内、自筆、縦書)
3. 紹介状:岩波書店著者によるもの(岩波書店社員紹介の場合は不要)
4. 選考結果通知用ハガキ
[官製ハガキの表に、郵便番号/住所/氏名(氏名の下は 「様」 とする、「宛」「行」は不可)を記入してください]
※ 応募書類不備の場合は、書類選考の対象としません。
※ 応募書類の返却はいたしません。
エントリー
および
応募書類の
入手方法 ※エントリーおよび応募書類(「入社志望書」「作文用原稿用紙」)の入手方法は下記の2通りです。
1. 岩波書店のホームページより「エントリー」を行い、「エントリーNo.」を取得する。
エントリー終了後に、応募書類をダウンロードする。
[1月23日(月)午前9時~3月13日(火)午後4時]
《《エントリーNo.取得のボタンは左上にあります》》
2. インターネット環境のない方は、岩波書店総務部宛に 「定期採用希望」 と応募資格のA・Bいずれかを明記し、返信用封筒[A4判サイズ、表に郵便番号/住所/氏名(氏名の下は「様」とする、「宛」「行」は不可)140円切手を貼付]を同封して請求する。
[1月23日(月)午前9時~3月13日(火)午後4時(必着)]
「エントリーNo.」は、応募書類郵送の際にお知らせしますので、「入社志望書」「作文」の所定の欄に取得した「エントリーNo.」を記入してください。
※ エントリーを行っても上記の応募書類(1~4)は必ずお送りください。
エントリーの有無にかかわらず、応募書類の到着をもって正式な応募受付とします。
応募期間 2012年1月23日(月)~3月16日(金)[当日消印有効]
応募方法 提出書類一式をA4判サイズの封筒に入れ、表に「定期採用社員応募」と応募資格のA・Bいずれかを朱書し、下記宛に郵送してください。(郵送のみの受付となります)
※ 提出書類は、クリップでとめてください。(ホッチキスは使用しないでください)
選考方法 (1)書類選考/(2)筆記試験/(3)面接試験(3回)/(4)健康診断
筆記試験 4月8日(日) 試験時間:9時~12時40分(予定) (詳細については、書類選考合格者にメールまたは郵送で通知します)
面接試験 第1次:4月14日(土)/第2次:4月18日(水)/第3次:4月21日(土)
要項請求
書類送付先
お問合せ 岩波書店ホームページ(http://www.iwanami.co.jp/)
〒101-8002 東京都千代田区一ツ橋2-5-5
岩波書店 総務部
TEL 03-5210-4145(平日9時~12時、13時~17時)
主な待遇 給与:当社規定による 賞与=年2回
通勤費:月10万円まで支給
休日・休暇:週休2日制、祝日、夏期休業、年末年始休業、年次有給休暇、リフレッシュ休暇等
※「会社案内」は岩波書店ホームページでご覧ください。
※会社説明会・企業セミナー等は行いません。
※会社訪問はお受けしておりませんので、ご了承ください。
ケンゾー・タガワという男 [Book_review]
新潮社発行の雑誌「考える人」2010年春季号、特集・はじめて読む聖書、を取り寄せ、田川建三ロングインタビューを読む。
高校生の頃に洗礼、家族の影響もあって聖書研究の道を選んだ。。という若い頃。東大で西洋古典哲学を学ぶ。ドイツ留学を試みたが失敗(語学以外の原因)。知人のフランス人神父に「この者は博士論文を書くだけのフランス語能力がある」というウソ紹介状を書いてモライ、パリのストラスブール大学に留学(それまでドイツ語一本だったが、この留学でフランス語の方が楽になった)。新約聖書の権威、トロクメ教授について2年4ヶ月かけて博士論文を書く。この一部を日本語にしたのが『原始キリスト教史の一断面』。
日本に帰りICU助手(格下げ人事)。大学紛争の後、追放される。
2年間フランス語を教えて食いつないだ後、スイス人新約研究者(教授になった)に拾われゲッチンゲン大学(ドイツ)に。学術助手。2年間勤務。
フランス語にもどりたいな~、と思っていた頃、アフリカのザイール大学の教授にならないか、という誘いがあった。トロクメからの紹介。教え子がザイールに帰国して偉くなり、ザイール大学教授職をトロクメに照会してきたのだ。ザイール(現コンゴ)。
ザイールの生活は田川に大きく影響を与え、この生活があって初めて『イエスという男』が書けた、と言っている。プチブル・田川建三がほんとうの貧困を知った、という経験。それに帝国主義(=フランス)というものの実態(言語、など)。ローマ(ラテン語)と、ローマの支配地・ヘレニズム世界(ギリシャ語)の関係類推(支配の手段、と言語関係)に役だった。
(新約聖書研究者は、すべからく、最低5年のアフリカやアジアの貧困国生活を義務づけたらどーかね?貧困になれ、とも、病人になれ、ともいえぬ、から。凡庸な頭脳では、貧困の実態を体験する以外に新約聖書、ではなく、イエスのいた社会を追体験することはできまい。帝国主義も知らず、奴隷も植民地も知らず、大学、教会での研究・布教生活だけで新約聖書を語るのは無理ダス)
ザイールのあと、トロクメに呼ばれストラスブールで客員教授1年。そのあと、大阪女子大学でラテン語、ギリシャ語を教えて(78-99)、定年。現在、私塾で教えながら著作活動。
あとは省略。
イエス、と、ケンゾー・タガワとの差を考えた。
イエスはほとんど貧困といっていい家庭だろう。ケンゾー・タガワは誰が見てもブルジョア(プチブル)出身。若干の才能と根性はあったのだろうが、家産に支えられた研究生活といってヨイ。『イエスという男』初版を私は購入して読んだが、あとがきで田川はこの本の定価が高額になったこと(当時、3000円前後だったか)の言い訳をしていた。印刷などの諸作業を台湾?で行って値段を抑えた、と書いていたと記憶する。『書物としての新約聖書』は定価8000円、現在刊行中の『新約聖書、訳と註』はいずれも6000円前後だ。貧困層はとても購入する気になれない額である。イエスの言行録を必要とするのは生活の安定した新約聖書研究者であり彼らはイエスになろうとはツユほどもおもわない。貧困者はイエスを読む必要もない、イエスにナルのである。
研究・著述生活を終えたあと、ああ、オレってつっまんネェ仕事してきたのぅ。。と呟いてくたばって欲しい。
<...この世でもし誰かが祝福されるとすれば、貧困にあえぐ者を除いて誰が祝福されるというのか。この言葉には、そのようなイエスの思い、私の言葉で言えば逆説的反抗者としてのイエスの思いがこもっている。>(ケンゾー・タガワの発言、ロングインタビューから)
幸い 貧しき者
田川建三 訳・註 『新約聖書』 [Book_review]
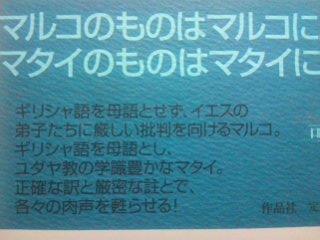
田川建三『新約聖書 訳と註 1 マルコ福音書/マタイ福音書』の帯
田川建三『原始キリスト教史の一断面』をとある本屋でふと手にしたのは77年10月27日のことである。
「福音書」は一つの文学類型である。。。いわゆる共観福音書は実のところ「共観」福音書ではない。。。
それまで所謂、新訳聖書に感じていたもやもや、とした閉塞感が一挙に解放される予感がして、この、冒頭の宣言にわたくしはトキメいた。。
断片的なメモ書きや口承・口伝レベルの資料しかない当時にあって、現在の福音書の型式を独自に作りだし、イエスの言動を単なる伝記でない仕方で記述した。。それがマルコという男である。
あれから三十余年経ったがこの本はそばから離れない本の一冊となった。田川建三はその後『イエスという男』を経て『書物としての新約聖書』を著し、いま、新約聖書の翻訳に取り組んでいる。
その経緯は田川建三HPに書いてある。
田川建三からのお知らせ
http://www6.ocn.ne.jp/~tagawakn/
(下記の新約聖書翻訳を含めた正誤表もこのHPにある)
田川建三訳の新約聖書は全六巻。作品社から刊行中である。
新約聖書・訳と註、作品社
●第3巻(第1回配本)、2007年7月発行、A5判、584頁、定価4800円(税別)
現在第2刷(2010年2月20日発行)
●第1巻(第2回配本)、2008年7月発行、A5判、878頁、定価5800円(税別)
現在第3刷(2011年3月11日発行)
●第4巻(第3回配本)、2009年7月25日発行、A5判、820頁、定価6000円(税別)
近いうち (2011年10月はじめ) に第2刷発行予定
●第2巻上(第4回配本)、2011年3月5日発行、A5版、534頁、定価5200円(税別)
●第2巻下(第5回配本)、2011年9月はじめ発行、A5版、約720頁、定価5600円(税別)
第二巻(使徒行伝)は上下にわかれるから、計7冊になる。現在、5冊を刊行中。さいわいなことに、我が町の図書館はこの田川訳新約聖書を揃えてくれている。昨日この5冊を借りてきた。
第一巻はマルコ、マタイの福音書である(この刊だけでも購入したいものだ)。マルコ(英語読みではMark)が最初にイエスの言行録を著したのは西暦50~60年代。このマルコが開発した独自の文学型式を踏襲して(その形式、内容の束縛から後続の記者~マタイ、ルカなどは逃れられなかった)、しかも、マルコの記述した型式は踏襲したものの、内容に異議を表明するために(共観したいのならばわざわざ別の書物を起こす必要もない)、マタイやルカは、マルコのイエス伝に、一部を削除、変形、さらに独自の資料を追加しておのれたち(教団)の思想を鮮明する要求に駆られ、そうした。かれらはイエスたちがパレスチナで使っていた方言~アラム語、ではなく最初から当時のヘレニズム(地中海東部)の事実上の公用語であったギリシャ語を使って福音書を記述した。しかも彼ら=記者はかならずしもギリシャ語に堪能であったわけではない(記者マタイはギリシャ語に堪能だった、という)。
第一巻『マルコ福音書・マタイ福音書、訳と註』に付した解説で田川はこう言っている:
「マルコ福音書。史上はじめて書かれたイエスという男の伝記。というよりも、イエスという男の伝記はこれ以外には書かれていない、と言った方がいいかもしれない。他の三つの福音書はこれを神の子イエスの地上での顕現の物語に作り変えようと努力したものである。(中略)
確かに、他の福音書もまた、マルコ福音書には記されていないイエスのさまざまな発言を伝えてくれてはいる。その点で、他の福音書もイエスという男の実際の姿を知るための貴重な資料となっている。従ってマルコだけに功績を帰するわけにはいくまい。しかし、この人がイエスの伝記を書こうと思わなかったら、あの人類史上稀に見るすごい人物の姿が後世に伝わらなかったのは確かである。そもそも、イエスの伝記を書くという発想そのものが、マルコの独創であり、彼がそれを実現しなかったら、ほかの人たちがその改作を作ろうなどという気も起こらなかっただろう」
現在田川は著作活動と私塾の講師を勤めることにより生活しているようだ(大学の教師はすでに辞めている)。彼は牧師でもある。イエス(という男が史上、実際にいたのかどうかわたしには関心がない)が、はたして<あの人類史上稀に見るすごい人物>といえるほどの男なのか?わたしには確信がない。というよりそういう物言いをわたしは拒否したい。イエスがイエスであるのはその言行によって、であると私は考えている。いつの時代であっても、無論現代であっても、イエスは存在しうる、とわたしは考えているのだ。彼は人間を差別しない。求めれば誰とも対話し、生きる希望と勇気を与えてくれる。身分や、財産や、信条、職業、性別、地上で身につけたゴミのような虚飾を一切排したところの人間そのものに語りかける男。そういう男(むろん女も)が、どの時代にイテもおかしくないではないか。ワタシハそういう男にナリタイのだ。だれも寝静まった深夜、眼前にイエスを呼び出しわたしは対話をしている。
それを、愛、と呼ぼうと、信頼、信仰、と呼ぼうと、絆、と呼ぼうと、イエスが発見したものはそれまで(ほとんど)誰も語ったもの=名付けたものはいなかった。ということは、それを著す言葉も無かった、ということだ。アラム語であってもラテン語であってもヘブライ語であってもギリシャ語であっても、使い古した日常語では盛ることのできない新しい、しかし、人間には誰しも備わっているサムシングをイエスは言い当てたのである。これは、イエスだけにゆいつの思想ではない、釈迦などとその思想は共通しているのだ。つまり普遍的なのである(たとえば、中村元『世界思想史 普遍思想』)。イエス、や、釈迦は普遍思想の発見者とはいえるだろうが、その発見されたものは当然ながらすべての(数億年の進化の結果として)ヒトに固有に備わっているものである。イエスや釈迦はちょうどゲノムの(最初のあるいは初期の)発見者のような位置にある。発明者ではないのである。
田川の翻訳はたとえば、第一巻900ページのうち本文(マタイ、マルコ福音書)は100頁、あとの800頁はすべて訳文に対する注記である。やっとこの歳になって註と訳をつくるだけの語学(古代ギリシャ語、ラテン語。。)になんとか自信がもてるようになった、と田川は述べている。
全6巻(7冊)の翻訳と並行して田川は『新約聖書概説』も執筆中という。この『概説』は『書物としての新約聖書』(750頁)を上回るページ数になりそうだという。
本書に注文を付けるとすれば:
1 ギリシャ語(田川が正本、と認めるもの)と、日本語の対訳にすべきではなかったか。原本が不在であるところに、これが正しい和訳である、と長い註とともに提出され、色々講釈を垂れてもらっても読み手にとって有難みは半減である。古代ギリシャ語など、いま、私には読めないがいつかは読めるようになるかも知れないし、これを機会にギリシャ語の勉強を始めたい、という若人がいるかもしれない。マルコなどはギリシャ語も得意でなかった、というではないか。使用されている語彙の数などたかが知れていよう。基本語の辞書も付ければよかった(できれば、現代英語、日本語、仏語、独語への訳語も)。(古代文化の)外国語への翻訳とは何か、を考える絶好の機会になる。
2 つまり、英語訳、仏語訳、独語訳も付すべきではなかったか。田川一人ではムリかも知れないので、協力者を得ることが条件になる。ただし、最終的な訳の校閲は田川にやってもらう(いわなくてもこの著者ならそうするだろう)。翻訳には田川による註の一部を含めて欲しい(田川註のかなりの部分を占める過去の聖書和訳に対するイチャモン・罵詈雑言などは削除する。田川の読者は過去の聖書和訳に興味を持っていない。最初からこうすれば、これほどぶ厚くならずに済んだはず)。
3 外国語訳も付すことにより海外研究者からの批評も期待できる。それを読んでみたい。『書物としての新約聖書』のかなりの部分、それにこれから出版される『新約聖書概論』も是非、外国語訳(抄訳でかまわないから)を出版してほしい。海外研究者との討論を期待したいのだが。
#
加藤隆は『新約聖書はなぜギリシア語で書かれたか』(大修館書店、1999)で次のように述べている(p127)。
「翻訳版によって聖書を読むことの問題
聖書は、オリジナルの言語のテキストを読むこと、正文批判の作業を経た上で確定されたテキストを読むことが望ましい。しかし多くの人は、翻訳版を通じて聖書に接することになる。しかし翻訳版はあくまで便宜上のものである。そして残念ながら、原文の意味を十全に伝える翻訳を作成することは不可能である」
当時の世界の僻地で生まれた新たな思想を、現代の僻地、日本で読むことの問題もある。しかし、記者マルコは当時のヘレニズム世界の事実上の公用語であるギリシャ語に堪能でなかったという。堪能であったマタイ(教団に属する)記者が、それでは、ギリシャ語を知らずパレスチナの方言=アラム語で語ったというイエスの思想を<正確に>ギリシャ語に置き直し得たのだろうか?これは原理的な問題だ。聖書の原文はギリシャ語だと言うが原本の記者(マタイもルカも、パウロも)が行ったのは新しい思想の翻訳作業ではないのか。過去の思想のゴミ捨て場である現在の語彙を使用して、新しい思想を表現する時点ですでに言いたいことの幾分かは減価せざるを得なかったはずである。
加藤隆、p135「翻訳に関する問題は他にもいろいろと存在するが、ここでは翻訳があくまで便宜的なものであることを示すことができれば十分である」
便宜的なのは翻訳だけでなく、正文も、であろう。新思想だけでなく、どんな思想でも、それをピタリと表現する言語などあろうはずがない。
加藤周一の受洗 加藤周一自選集第十巻(1999-2008)と加藤周一著作集第18巻 [Book_review]
と、
加藤周一著作集第18巻、平凡社、2010/9/15発行
を、図書館で借りて読んだ。双方とも編集者は鷲巣力。
いいたいことは二つある。
1 加藤周一のカトリック入信について
自選集第十巻の解説(13頁)のうち、7頁を費やして編集者は、丸山が死の直前受洗したこと、の理由を縷々説明している。加藤は、無神論者と己を規定していたが、(最)晩年になり、母と妹(ともにカソリック信者)のことを考えて、さらに、長年のカソリックに対する愛着から、カソリック信者として死んだ、という。
2008年8月14日深夜、加藤から鷲巣に次のような電話があったという(鷲巣力による要約である。おそらく長時間の電話の)。
「宇宙には果てがあり、その先がどうなっているかはだれにも分からない。神はいるかもしれないし、いないかもしれない。私は無宗教者であるが、妥協主義でもあるし、懐疑主義でもあり、相対主義でもある。母はカトリックだったし、妹もカトリックである。葬儀は死んだ人のためのものではなく、生きている人のためのものである。(私が無宗教ではーー鷲巣による補足)妹たちも困るだろうから、カトリックでいいと思う。私はもう「幽霊」なんです。でも化けて出たりはしませんよ」
この電話を鷲巣は
「加藤は死を覚悟し、そして、カトリックに入信するとその理由を明らかにした」と、私(鷲巣)は受けとめた。
。。と、理解し、上野毛教会に入信の意志を伝え、8月19日に加藤は受洗した。そして「ルカ」という洗礼名を与えられた。
以上のように経過を説明している。2008年12月5日に加藤は死ぬ(胃癌)。
鷲巣はつぎのように加藤を弁護する。p495
##
加藤のカトリック入信という事実を、驚きをもって受けとめる人もすくなからずいるだろう。「羊の歌」あとがきには、「宗教は神仏のいずれも信ぜず」という立場を明らかにしているからである。「神仏を信じない」ということばに、生きる勇気を与えられた人も少なくないに違いない。それゆえに加藤の入信を「意外な行動」あるいは「変節」だと感じる人がいることも想像はつく。だが、私は「意外」だとも「変節」だとも思わない。加藤の行動に、むしろ加藤の一貫性と加藤の世界を感じる。加藤の「理の世界」と「情の世界(家族愛のことを指しているのだろうーー古井戸)」の接点に、あるいは、「公人としての加藤」と「私人としての加藤」の接点に、「カトリック入信」が用意されていたのである。 自選集p495
##
加藤(および、加藤に寄り添う人)にとって、自分の思考はどのように変化しようとも、内的な一貫性(必然性)は、あるのは当然である(気でも狂わない限り)。しかし、「変節」と呼称しないまでも、神を信じない、と、言った人が、何年後かに神を信じる、と言い出せば、信条を変えたのだな、と普通の日本人なら思うのが当然ではないか。われわれは、生まれつきある信条や宗教を信じているのではない。あるとき、ある切っ掛けや条件で信じるようになるのである。その条件が解消あるいは変われば、思想や信条は変わって当然である。なぜ、晩年になるにしたがって、家族愛が大きく思考を占有するようになり、信条を変更することになった、と言わないのか。思想家(あるいは一般人にとって)信条の変更はただちに不名誉ということにはならない。いかなる信条を、いかなる理由で、変えたのか、を説明するのが公人の義務であるとわたしはおもう。できれば加藤自ら説明すべきであった。加藤は、己の信条を公にすることを職業とするひとだからである。加藤の家族(妹さん)は、このような加藤周一(兄)の入信の説明に満足しているのだろうか。加藤に近すぎる人(あるいは内在的理解力に富みすぎる人)を解説者に選んだのは加藤の不幸であった。
加藤の奥さん(矢島翠)は、最晩年加藤の病状が悪化するにつれ
「加藤周一が加藤周一でなくなっていく」
と嘆いたという。p488
わたしは、入信したこと、あるいは、入信の告白、打診の電話(鷲巣に対する)も、「加藤周一でなくなって」きたことの兆候か、とおもってしまう。加藤周一でなくなった後の加藤の公的および私的行動は無視してよい。 あるいは、加藤はもともと(若いときから)無神論者ではなかった。
2 自選集と著作集の重複について
平凡社の著作集は今回の18巻発行を持って第二期(第一期と合わせると全24巻)出版が終了した。これは、1997年までの著作しか収録していない。岩波版自選集は、第十巻が、亡くなる年=2008年までの著作を抜粋して収録している。鷲巣によれば、平凡社第三期著作集の刊行は未定だという。自選集、第9巻と第十巻は、1997年以後の著作のすべてを収録しているわけではなく、抜粋である。朝日新聞に毎月連載されていた夕陽妄語は著作集に、1996年までの全編が収録されている(21巻&22巻)。1997年以後の著作をすべて読みたい、という読者はどうすればよいのか?1997年以後の著作はそれ以前に比べて多くはなく、平凡社が著作集を刊行したとしてもほとんど、自選集9,10巻と重複し、岩波より後発で販売しても採算がとれるのか?出版社は読者のことを考えて企画して欲しいものである(自選集の発案・編集は加藤本人も係わっているのだから加藤の責任もある)。
##
内容に触れなかったが、自選集、著作集とも晩年にいたるまで集中力のある文章。驚異的だと思う。(別の記事とする)
加藤周一自選集 岩波書店
http://www.kinokuniya.co.jp/nb/bw/special_products/katoh_shuichi/index.htm
加藤周一著作集 平凡社
http://heibonshatoday.blogspot.com/2010/08/24.html
家族愛(というより、母と妹への愛)ゆえに、入信したという説明は、なぜ、若いときに入信しなかったのか、死の間際に駆け込み的に入信せざるを得ないいかなる理由があったのか、を説明していない。
編集者=鷲巣力もこれを気にする読者のため次のような解説を行っている。
自選集p493
「。。「わたしはもう幽霊なんです」という(加藤の)ことばで表現しようとしたことは、すでに私は死んでしまったのだ、ということだろう。だれが死んだのか。思想家、作家としての加藤、いわば「公人としての加藤」に違いない。「公人としての加藤」は死んでもなお「私人としての加藤」は死んではいない。「私人としての加藤」は、母を想い、妹に心をかけて、カトリックに入信する。とはいっても「私人としての行動」と「公人としての行動」はそう簡単に切り離されるものではない。」
この文章の後、二頁の説明(弁明)をおこなって、次のような結論を導き出す。
。。(『羊の歌』にある「宗教は神仏のいずれも信ぜず」という立場にもかかわらず、)
「加藤の行動に、むしろ加藤の一貫性と加藤の世界を感じる。加藤の「理の世界」と「情の世界」の接点に、あるいは「公人としての加藤」と「私人としての加藤」の接点に、「カトリック入信」が用意されていたのである」
私の理解では鷲巣氏は気の回しすぎ。
鷲巣>
「わたしはもう幽霊なんです」という(加藤の)ことばで表現しようとしたことは、すでに私は死んでしまったのだ、ということだろう。だれが死んだのか。思想家、作家としての加藤、いわば「公人としての加藤」に違いない。
ここで止めておくべき、と私は思う。すなわち、入信は、公人としての加藤が100%死んだあとの行動である、と。しかし、鷲巣氏はこのあと、公的な死、と、私的な死を分離して、2頁にわたって独自の解釈をくり広げる。加藤周一がみずからを幽霊、と言ったとき、公人として死んだが、私人としては死んでいない、という解釈は正しいのか?そうではなく、私人としても公人としても死んだ、と加藤は述べているとおもう。そうでもしなければ(幽霊にならなければ)入信などという行動はとれるものではない、と。信仰告白を、死後行うのでなく(そういう手続は用意されていない。。)、先回りして地上で行った。。
直前に死が迫れば、思想信条にかんする、地上の、あらゆる制約から解放される。いや、これは解放というより絶望の表現ではないのか?「加藤周一が加藤周一でなくなった」
矢島さんが一番の加藤理解者だとおもう。矢島さんはどうおもっておられるのか?上記の解釈は矢島氏も了解しているのだろうか?
将来、加藤周一伝があらわれるとき明らかになるのだろうが。
#
重要、とわたしがおもうのは、自選集解説(by鷲巣)によれば、加藤周一自ら入信する、との意思表示はなく、鷲巣との電話の後、鷲巣氏が(この電話は)入信の意思表示だと理解して、教会にその手続を取った、ということ。
なぜ、24時間生活を共にしている奥さんを差し置いてこのようなことが編集者にできるのか、という疑問が湧く。むろん奥さんの了承は得ているのだろうし、加藤周一も洗礼を受けたのだから、加藤の意志に反してということはありえないだろうが。一体、当時、加藤周一はどのような状態(精神、体力)だったのだろうか。入信のような重大な決定であれば、身の回りの面倒を見ている(以上の存在の)配偶者に意思を表示しておくのが当然とわたしはおもうのだが(加藤周一に入信の意志があれば、矢島氏にとおの昔に知らせており、その手続も依頼していたはず)。
鷲巣が伝えている、矢島氏「加藤周一が加藤周一でなくなっていく」という嘆き、が現実味を帯びる。
朝吹真理子 『流跡』 [Book_review]
先日、NHK-BS番組「週刊ブックレビュー」に著者がゲスト出演し、自作について語っていた。そのおしゃべりがずいぶん刺激的で面白かったので、早速近所の書店数軒に照会したらいずれも在庫がなかった。図書館に所蔵があったので借り出して読んだ(今年10月発売なのだが。。こんな評判の新刊小説が待ち合わせることなくスンナリ借り出せるのは珍しいことだ)。
この小説に要約できるストーリはない。ひたすらイメージが氾濫する小説だ、といってよい。冒頭、海中にせり出した神社が登場する。能舞台も備えている、というから私は地元の厳島神社を想像した。海中に大きな鳥居もあるのだから。そのうち、川の話になる。ゆいつ主人公らしき男は会社員を数年前やめて(同僚を殺したからか、勤め先の金を盗んだからか、判然としない)渡し船のナガシをやっているらしい。川にプカプカと水死体が浮かんでいる(よくあることだ、という。。。わたしは広島市の太田川に浮かぶ原爆死者を想像しながら読んだ)。この男、妻と一人の息子がある。妻とのコミュニケーションも儀礼的、息子には愛情を注いでいるが多分に計略的。計画的に愛情を注ぐ自分を客観視している。
しかしストーリなどどうでもよいのだ、この小説にあっては。ひたすらコトバ遊び、といってもイイ、細部の描写に精を出す。虫眼鏡を持って世の中を見ている、という感覚になる。
川の排水の臭気、腐った魚、生魚、腔腸類のぬめぬめした肌。倦怠。
BSインタビューに答えて、著者はあらかじめストーリなど考えず、一行一行をパソコンに打ち込み、打ち込んでは考え、また、打ち込む、という作業を継続した、という。終盤20~30頁の文章の流れ、リズム感はすばらしい。こういう具合。。(p80~81から引用)
。。。自分が死んだときの骨の焼き方ばかり考える。高熱によって皮膚のうちにたたえられていた液体がいくらかの水蒸気となり、清潔な燐酸カルシウムと細胞のかすもいっしょに煙として吐き出され、誰かがそれを吸う。空気といった流体にこまやかにまぎれ、光の粒子といっしょになったそれを知らずに吸い込む。この身体を構成していた有機的ななにもかもがこまやかに砕けて、目にもとまらない粒粒になってほうぼうに拡散してゆく。それが誰かの唇や頬をなぞったりとりこまれたりして肺にはいったりする。そうしていくつもの生体をとおりぬけてゆく。骨片もそのへんに撒いて腐葉土にでもなるか、海や川に流れて魚や腔腸動物にはまれたり、あるいは蒸発し積乱雲になって市に落ちるのもいい。やわらかいほとんど蒸気のような小糠雨となってはじめはゆるやかに髪を巻いた女のその一筋一筋の輪郭をなぞるようにすべりおち、皮膚のうちにしのびこんでゆく。血液にまぎれ、液胞としてうちにとりこまれながらたゆたう、身体のうちを浸す多量の液体のうちの、その女を構成するわずかなわずかな構成素としてしばらく流れてはふたたび体外にはみだし、海にそそがれる。終わりがない。そんな腑抜けなことばかり考える。死んだら記憶もみな無くなる。少年期の記憶も、今日の記憶も。記憶も燃えて、どこかにとんでゆくんだろうか。誰かがまるで自分の夢か自分の記憶であるかのように、この身体の体験のようなものを骨粉を吸いこむごとにみたりするんだろうか。この身体がいままで実体験としていた、いくつもの記憶も、誰かの細胞のかすを吸いこんでそれをふくめて自分の記憶のように思っているんだろうか。。。(引用終わり)
特段、深い思想が埋め込まれているわけではないが、ストーリもなく、登場人物の誰かが語っているというのでもない、こういう描写が長く続く。
この小説で頻繁にあらわれる文字は、流、水、海、川、死、雨。。などである。見たこともない漢字が使われる。オノマトペも多い。ケータイメールでしか使われないコトバも混じるから著者が誰かを知らなくても、若い女性、であることは容易に想像が付く。深刻な文章が続いた後、。。
はれ。ひやらひやら
とか、
お客さん、どちらまで
とか
がやがや
おなかすいたなう
。。のようなコトバが、突然、挿入され、ガラリと場面が転換する、この絶妙の間合。朗読に耐えるリズムがある。 (....突然、と言ったが、考えてみれば、すべての耳にする、目に映るコトバは本来、誰にとっても、すべて<突然>に現れるのだ。突然、でなくなるのは、記憶、予期、習慣による学習効果のなせるわざ、この<学習効果>に依存したままでブンガクができるか、と著者は問いかけている)。こんな言葉づかい有り?と思われる箇所も多々あるがそれでも読みとおすのに困難を感じないのは文体とイメージの流れに動的平衡(とでもいうべき一種の安定)があるのではないだろうか。局所的には、つまりセンテンスと次のセンテンスの間に時間の流れはある、ようにみえるのだが、広域的には時間の経過も、脈絡もない(認識できない。つまり、われわれの日常生活や人生のように。時空の認識や前後感覚は局所的にしかできない)、という停滞、あるいは、循環がある。
この小説は、冒頭と終局で著者らしき人がパソコンにこの小説を打ち込んでいる、という入れ子構造になっている(パソコン画面から読んでいる、のだったかもしれない)。しかし、この工夫は余計ではなかったか?入れ子を無くした方が、読後に謎と密度と印象が深まるのではないか(逃げ場を与えない)と思うのだが。
ストーリなど余計なものに神経を削がれることなく、ひたすら一行一行に身を委ねることができる小説。できあがったストーリに依存してそれを表現するだけなら誰にもできる。詩のような文字を百頁も紡ぎ出し、読者を飽きさせないのは言葉の貯蔵と運用が要求される力業である。
BS番組司会の藤沢周はこの小説を称して<小説以前の小説>と言った。(武満徹がデビューしたときその音楽を演奏不可能、音楽以前、と侮蔑した評論家がいた、というエピソードを思い出す)
わたしは読みながらドーキンス(生物学者)の、遺伝子が実体であり、人間はその遺伝子を載せて、遺伝子を発現させる入れ物=仮想体にしかにすぎない、という考え方を想起していた。文字、言葉、こそが実体であり、一時的に活動を休止しても再生されうる~永遠の生命を保つ。言葉で表現される人間を含む世界は言葉を運ぶ担体=虚構、仮構であり、発生し、必ず消滅する、生者必滅。人間と、それを取り巻く現実の世界、あるいは歴史、は文字という役者が演じる舞台にしかすぎない。。。
#
著者は大学院(博士課程)で鶴屋南北を研究している。この小説には古語や、難読漢字(フリガナがなければ読めないし、意味も分からない)が頻出。印象的なのは理工学用語(述語)が多いこと。著者は理工学書を読むのが好きなのだそうだ。タイトル「流跡」は流体工学の書物を読んでいるときに発見した述語。あ、これだ!と直感でタイトルに採用したのだそうだ。ぴたり、の言葉だ。ただし。。流跡は、古典力学の世界の述語。言葉は語られてしまった瞬間に、語ろうとしたことから、逸れてしまう(再度、そして永遠に、逃げた意味を追って言葉を継がねばならなくなる。。)、という人間の表現世界に内在する、コトバと実在(あるいは意味、表現対象)の間の不確定原理~量子力学的構造をこのタイトルでは表現しきれない、というウラミが残らないか。
行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。 (鴨長明)
万物は水 (タレス)

富永仲基 湯川秀樹・加藤周一の対談から [Book_review]
ちくま文庫、1月新刊、加藤周一『三題噺』。本編は、詩仙堂志、狂雲森春雨、仲基後語の三章建て。
出版社案内。http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480426710/
65年出版の単行本の文庫化。「二人一休」と、湯川秀樹との対談「言に人あり」が加えてある。この対談は江戸期(吉宗の時代)の大阪の思想家、富永仲基をめぐって語り合ったものである。対談は1966年12月『図書』に初出。
加藤周一・湯川秀樹の、この対談は別の出版社の対談集にも収録されている。これまでに何度も読んだが、素晴らしい出来である。文庫版にして50頁。今回再読してまた新発見するところがあった。
富永仲基は大阪の正体がよく分からない学者だが、加上、という学問進歩の仕方、にかんする学説を立てた。三十歳で死んだ。湯川の父や、兄弟も中国文学者であり(小川環樹もそのひとり)、父は富永仲基ゆかりの懐徳堂に教えに行ったことがあるそうだ。
加上、とは、たとえば、ある概念についての学説A,B,C、D..が並立している場合、それぞれを吟味し、Bにサムシングを加えたものがC,それに別のサムシングを加えたものがD..というふうに、旧学説になにかを加えて新学説が出来上がる、という思想の時間的発展を捉えるという方法=仮説である。
これで、儒教仏教神道が並立する日本の思想史をとりあつかうことができる。。加藤が岩波の思想大系の仕事(編集委員)をやりだしたときに、(ということは文学史序説の切っ掛けになったということ)仲基を見出した。
湯川が最後に、
「。。。仲基が考え出した加上、とか、「くせ」(<-無くて七癖、のくせ。日本人の思考態度日常生活における、くせ、である)の概念にしても、おそらく、ひじょうに高度な言語学みたいなものを体得しておったから、出てきたのじゃないか、そういう感じもするのですね。。。」
これに加藤が応じる:
加藤「『出定後語』のなかに、「言に三物あり」。ひとつは「言に人あり」。人によってことばは違う。これはまさに(湯川)先生のおっしゃったことで、同じことばでも、別の人がいえば、違うかも知れない。だから、その人の考え方とか体系というもののなかにはめ込んで考えないと、同じことをいったから同じ意味だと取っては、間違いだという。それから、時代が違えば、同じことばでも変わってくるし、別のことばでも同じことを意味することがありうるから、時代を考える。それから、三物の最後は類。これは語義の変遷の型の分類みたいなものです。そういう三つを考えたのです。」
湯川「なかなかいいところをやはり押さえていますね」
これで対談が終わるのだが。。和漢洋に通じた両碩学がかなでる二重奏を聴いているようであった。
対談中ふたりのやりとりは、たとえば、つぎのよう:
湯川「。。儒教というものは、人間哲学というべきか、社会哲学というべきか、どちらにせよ、いちばんもとの姿は、自然哲学でないわけですよ。つまり(論語にある)「怪力乱神を語らず」ということは、合理的だけども、怪力乱神を語らなければ、当時としてはもはや自然哲学はできない、今の人は、怪力乱神を語ることは神秘主義であって、それは自然科学に反するじゃないかと思うかもしれないけれども、昔にさかのぼれば事態はまったく逆なんであって、自然現象の原因は何だろうと考えた場合、簡単に合理的に割り切れるようになったのは、ずっとのちの話であって、はじめはどの民族でもやはり怪力乱神的なものを考えていた。そこから出発して、長い間にだんだんとそれが合理的な思想に変わってきたわけです。」
加藤「そのとおりでしょうね」
湯川「自然現象の原因について語ることを拒否すれば、自然哲学抜きの人間哲学、社会哲学になってしまう。そこから朱子は出てこない」
加藤「それから、「論語」には「死」を語らずともということもございますね。「生」さえわかっていないのに、なぜ「死」の話をするのか。今先生のおっしゃっている怪力乱神と死を除外するという「論語」の考え方は、現世的(此岸的)で、社会的(人間的)な考え方だといえるでしょう。当然、政治と倫理の問題になるわけですね。」
ここを読みながら私は漢字の起源~白川静のことを考えていた。
孔子(の弟子達)は漢字を使って論語を書いている。孔子は、現世のことしか語らず、怪力乱神を語るのを拒否した、が、漢字自体の起源は、白川静のいうことを信ずれば呪術の時代、怪力乱神を語る時代に遡る。白川はさらに、孔子の生まれは不詳、おそらく巫女の私生児であると推論している。
富永仲基を高く評価したのは同じ大阪の学者(出身は東北だが)内藤湖南、それに比較思想史の中村元である。
20年前に古書店で買い求めた中村元「世界思想史」、途中で挫折したが、再挑戦してみようと、いう気になった。
湯川「。。。インドでは仏陀という人は、それまでの、一口にバラモン教といってよいのかどうか知りませんが、いろいろな神秘的な思想があって、その上に、富永仲基流にいえば、仏陀自身が加上したのですね。」
加藤「もちろん」
湯川「しかし、そのときにも、彼もいうているように、やはり幻というものが大事である。仏陀というのはおそるべき神通力をもっておって、知恵もある。また広大な慈悲心もある。その中で神通力というのがわれわれ現代人には一番わかりにくい。初期の仏教について知ろうとすると、そこでハタといきづまるわけですね。すると加上ということは、あなたがおっしゃったように、儒教などの場合のほうが、考えやすいような感じもしますね。ところが道教となりますと、加上説は成立しないですね。。。(略)」
加藤「。。。けっきょく日本歴史というものは、仏教の衝撃(一般に外来イデオロギーの衝撃)と、本来日本的な世界観とがたえずたたかう戦いの歴史だと思うんです。仏教をこっちが変えるか、つまり日本化するか、あるいは仏教によって日本人の精神構造の全体が変わっていくかという対決。けっきょく荒っぽい言い方ですけれども、日本側が勝って、仏教のほうが変わった、ということでしょう。儒教との対決でも、儒教のはじめは朱子学ですから、形而上学的な、また自然学的な大きな体系ですね。そういうものが日本人の精神的な構造、世界観を変えるかどうか。根本的には日本的なるものが、儒教を非朱子化してしまう。そのとき、もちろん原始儒教の古典の権威にも頼りますけれども、けっきょく朱子学から日本儒教を解放したのは、根本的には日本側の伝統的精神でしょう。。。。外来の体系的世界観を変えていく過程は、仏教の場合には、ひと言で言えば世俗化だと思う。それから儒教の場合には、非形而上学化だと思うんです」
この主題は加藤がこの対談直後から朝日ジャーナルに連載した日本文学史序説で力説しているところだ。
しかし、湯川も言っているように(あるいは、昨年放映されたNHK ETVの連続番組「朝鮮半島2000年の歴史」でも明らかにしたように)、日本に漢字が伝来したのは仏教の経典、としてであった。それまでは、無文字なのだ。教典は(鉄も)半島から帰化人が持ち運んだ。その帰化人がわれわれの祖先なのである。帰化人(つまり日本人)やその子孫が取り込まれるような、どのような、思想ないし日常的思考方法が日本列島に存在していたのだろうか?謎である。加藤(あるいは宣長)がいうところの伝統的日本の思考の型。
中村元の『古代思想』。「第五章 古代的思惟 -- 結語」の全文を少し長いが引用しておく(中村元選集第17巻、522頁~)。
「ウパニシャドの哲人と、イオーニア学派の哲学者たちとは、ほぼ同時代(西暦前七世紀)に現れている。それは何故か?相互の思想的影響があったかということになるが、はっきりとはわからない。ただ、この時代の顕著な一つの事実は、この時代でもインドでも、鉄器使用が急激に盛んになったということである。この時代以前にも鉄器は使われていたが、しかしこの時代になって急激にひろがったと考古学者は報告している。鉄という材料をとって、それに熱を加えていろいろな道具を作るということが、当時の人々の生活において直接に経験されるようになった。すると、世界原因は一つだけれども、それが異なって現れてくるという思惟が成立しやすくなる。そのためにギリシアでもインドでも同時代に、ただ一つの世界原因を追求する哲学的思索が現れたのだと考えられる。
究極の原理を求めようとした点では、インドの哲人もギリシアの哲人も共通であった。ただしタレース、アナクシマンドロス、アナクシメネースなどの思弁は先駆的な科学的仮説とみなすべきものであり、これに反して、ウパニシャドの哲人には科学的仮説への志向は顕著ではない。他方、ギリシアの哲人が、究極的な原理を道徳的観念から切り離して考えていたのに、ウパニシャドの哲人は、究極的な原理を人生の安住の境地と見なしている。
これに対してシナでは、鉄は戦国時代の初めにひろく使われるようになった。殷代には白銅を多く使っていたという。しかし、いずれにしても金属が変容して種々のかたちを示すということは、日常生活において熟知されていたにもかかわらず、もとのものやブラフマンを求める思惟が起こらなかったということは、シナ人が形而上的思弁を好まなかったためではなかろうか。シナでは哲学的思惟の興起というこの段階ははっきりとしていない。シナ人は哲学的思惟に弱かったから、ギリシアやインドの哲学的思惟に対応する段階はどうも出てこなかったようである。
ひるがえって日本人の問題として考えてみるに、日本にはこのような哲学的思惟の成立に相当する段階がなかった。日本では古神道の民俗宗教の段階からいきなり普遍的世界宗教の段階に跳んでしまったのである。つまり飛躍したのである。この事情は東アジア、南アジアの大部分の諸民族や、また西洋のゲルマンの諸民族に共通に見られる思想史的現象である。
それぞれの文化圏における思想と生活環境ないし社会生活との連関については改めて深く追求検討されねばならないが、ただ古代の異なった文化圏において文明が一応の発展爛熟の段階に到達したときに、どこでも共通の問題がそれぞれ異なった仕方において論ぜられたという思想史的事実はここに明確になったと言えるであろう。」
#
さて、肝腎の本編であるが。
三章だての短篇集。それぞれ、石川丈山、一休和尚、富永仲基を主人公とする。石川丈山の出だしは、石川淳か、とおもわれる文体模擬?。一休は、谷崎潤一郎か?とおもわせる平仮名の多い長い長い文章。富永仲基の章は、仲基をめぐる弟、仲基の書籍を焚書処分にした奉行、三浦梅園、安藤昌益らと、加藤周一とおもわれる人物の対談。それほどおもしろくはなかったが、ガリレオやプラトンがその主張するところを架空対談によって著した、そのやり方でなければ伝えられないことがあるということは理解した。たとえば、加藤の一人語りによりこの章の内容を伝えようとすれば、遥かに入り組んだ日本語となる。読み手に与えるインパクトも薄まるであろう。
文庫化に伴って追加された湯川秀樹との対談、これは<富永仲基>の章にそっくり収まるのではないか、と。つまり、短篇中の加藤周一が、現代の物理学者&自然哲学者=湯川秀樹と対談した、という趣向で。17世紀の人物との架空対談と、現実のリアル対談とで構成されたコラボ。
丸山真男の<古層>、加藤周一の土着的世界観
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2009-02-22
『語りおくこといくつか』 加藤周一
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2009-10-03
加藤周一 1968年を語る “言葉と戦車”ふたたび
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2008-12-15
追悼 加藤周一
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2008-12-14
生と死 加藤周一
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2006-08-24
ハルバースタム『ザ・コールデスト・ウインター 朝鮮戦争』上下(文藝春秋) The Coldest Winter by David Halberstam [Book_review]
図書館にリクエストし、借りてきたのだが。。
http://www.bunshun.co.jp/cgi-bin/book_db/book_detail.cgi?isbn=9784163718101
。。読み始めた途端、すぐに本屋に走って買いそろえた。これは。。大岡昇平『レイテ戦記』には及ばぬがある面で凌駕している本である。
北朝鮮が38度線を越えて南の侵略を開始したのは1950年6月25日。3年間におよぶ朝鮮戦争こそは現在のニッポンをいまだに束縛している大事件であった。
明治以来のニッポンの半島政策の帰結であり、太平洋戦争・日中戦争の帰結であり、戦後の出発点であり、ニッポンの外交防衛政治のすべてをいまだに規制している。
であるのに、その全体像を、最新データをもとに描いた著作に一般人はなかなか触れることができない。そのような渇を癒してくれる著作である。ハルバースタムはいうまでもなく一昨年死んだ米国のリベラルなジャーナリスト。2007年4月23日交通事故死。亡くなったのは惜しみてあまりあるがこの著作は不完全なものではなく、彼がゲラに手を入れたあとの作品とのこと。最後にして最大の、とくにニッポンジンにとって、プレゼントとなった。
訳者があとがきで書いているが、膨大なインタビューをもとに兵士はいかに戦ったか、にも力を入れている(しかしこれはレイテ戦記にはおよばない。著者大岡昇平は兵士であったのだから当然か。レイテ戦記の詳細さで書いていたらページは倍になるだろう。)。しかし朝鮮戦争で重要なのは、兵士個人の戦いではなく、金日成、トルーマン、マッカーサー、スターリン、毛沢東などの指導者、それに安保理(理事国)にどういう情報が与えられ、戦いの現状と各当事者の動静どう認識し、どう判断し、どう行動したか、それに、何を目標としているのか、に尽きるだろう。読者はこれを頭の中で再構成し、自分がその立場にいたらどう行動するか、得られた教訓を現在の、各自の領域で生かす、ということになる。政治と軍事は人間が、しかも少数の、決断に依存するところが極めて多い、ということを、『レイテ戦記』も、このColdest Winterも教えてくれる。
大岡昇平『レイテ戦記』はこう述べている。「山本五十六提督が真珠湾を攻撃したとか、山下将軍がレイテ島を防衛した、という文章はナンセンスである」。しかし、武器も食糧も満足に与えず、投入した日本兵84,000人のうち実に95%、79,261人の戦死者をだしたレイテ島の惨めな敗北の責任を断じて兵士に取らせるわけにはいかない。これはあらかじめ敗北と分かっていた戦いであり、その責任は参謀本部にある。朝鮮戦争では米兵3万名の命が失われたが、マッカーサーが38度線を越えて北進しなければこれほどの死者は出なかった。38度線を越えた段階で中国軍の参加、つまり中米戦争となりうることはあらかじめ分かっていた。マッカーサー個人の妄念と名誉欲による進撃を阻止できなかった米政府と、北進を追認した安保理の責任は大きい(まるで、最近、どこかで見たような光景である)。
本書で印象的なのはマッカーサー、トルーマンをはじめとする米国の軍人・政治家や、金日成、李承晩などを描写し、人間とくに意志決定者達が危機においていかに振る舞ったか、逡巡したか、を眼前にいるかのごとく記述している。現在のニッポンの政治屋も必読ではないか。通常の歴史本では1~2行で済ませられるイベントをなぜ、この人間がそう決断したかを公式発言だけでなく、プライベートな発話や行動から描き出す。これこそジャーナリストの仕事である。 とりわけマッカーサーには7~9章を当てて両親の影響や、戦歴の分析を、金日成は第4章で詳述している。マッカーサー批判、トルーマン批判も厳しいがそれだけなら他の凡百の歴史家や著作家もやっている(大岡『レイテ戦記』もマッカーサー批判は厳しい)が、ここまで詳しい記述に接したのは初めてである。
マッカーサーを一躍有名にした唯一の成功した大作戦=仁川上陸、もハルバースタムに云わせれば単なる偶然。この偶然が導いた幸運が米国にとって地獄の一丁目、国連をも狂わせた。38度線を越え北進することを追認し、中国の参戦を招いた(イラク、アフガンとそっくり)。成功が必然か偶然かを評価し、指導者の力量を測るのが政治屋の任務だがいかんせん、ワシントンにはそのような力量の持ち主がいなかった(この程度の米国に敗れた日本、ともいえよう)。仁川の奇襲成功およびそれ以降のマッカーサー(国連軍)の作戦は、ニッポンの真珠湾以降の作戦とソックリである。ソ連の傀儡=金日成と、マッカーサーは、地力もないのにウンだけで勝負した指導者として好一対である。
マッカーサーを制御しきれなかったホワイトハウス。軍人が独走するとどうなるか、があきらかになる。全体主義国家=ソ連に担がれた軍人将軍を戴いた北朝鮮の不幸。 いまだに先に攻撃を仕掛けたのは南鮮である、と言いつづけている。しかし、戦中戦後の資料情報をいまだに公開しないニッポンが北朝鮮を嗤うことはできまい。
この本には主題として書いていないが(しかし朝鮮半島と日本の関係など予備知識は最小限度書き込んである。プロローグ~第三章、この部分だけでも有用)、半世紀以上朝鮮を植民地として独立意識を奪い続け、戦後の国連(米ソ)の介入を招いた日本の、現在の半島分断に至らしめている責任は大きい。
< 『ザ・コールデスト・ウインター 朝鮮戦争』解説 >
ハルバースタム、最後にして最高の作品
山田侑平(やまだゆうへい 『ザ・コールデスト・ウインター 朝鮮戦争』訳者)http://www.bunshun.co.jp/jicho/0911yamada/index.htm
引用
本書はヴェトナム戦争報道でピュリッツァー賞を受賞し、アメリカのヴェトナムとの関わり合いを描いた名著『ベスト&ブライテスト』で知られるデイヴィッド・ハルバースタムにとっては二十一冊目、そして最後の著作である。十年がかりでまとめた草稿を何か月もかけて手直しし、最後の手を入れて完成させた五日後、カリフォルニアでの自動車事故で不慮の死を遂げたからである。二〇〇七年四月、著者七十三歳のときだった。
(略)
本書にはさまざまな人物が出てくる。トルーマン、マッカーサー、アチソン、リッジウェイ、スターリン、毛沢東、彭徳懐、金日成、李承晩――歴史の舞台で動くかれらの姿が目の前に浮かんでくる。なかでもマッカーサーは、全体を通じて誤算の張本人、兵士に苦しい戦いを強いた乱心の将軍として描かれている。ハルバースタムによると、マッカーサーは「年老いて、頑固で、敵を人種的に軽蔑しており、ワシントンの『チャイナ・ロビー』および敗北したばかりの蒋介石の国民党政権と提携していた。その戦略諜報は夢想家のまとめたものだった。主人であるはずの政治家に対する軽蔑は、合衆国最高指揮官たるトルーマン大統領に敬礼を拒むところまで達していた」(英『エコノミスト』二〇〇七年十月六日号)。そのかれは朝鮮戦争を指揮しながら朝鮮の地で一夜たりとも過ごしたことがなかった。中国軍の動きに関するものだけでなく、自分に不都合な情報は一切受けつけようとしなかった。アジア人を軽蔑しながら、アジア人の心をいちばん理解していると自負していた。そのようなマッカーサーには、それにふさわしい部下がいた。情報担当のチャールズ・ウィロビーや第十軍団司令官のネド・アーモンドなど、かれの取り巻きも、その人を目の前にみるかのごとくに活写されている。
しかし、本書を本当に価値あるものにしているのは、こうした指導者の政策や命令によって厳寒の朝鮮で戦うことになった末端の兵士たちひとりひとりの物語を丁寧に描いている点だ。ハルバースタムは朝鮮戦争の元兵士たちとのインタビューを重ね、司令部のデスクからではなく、塹壕(ざんごう)で戦い、待ち伏せ攻撃に遭いながら死を免れた兵士たちの視線から、多くの重要な戦闘を進行形で再現した。戦争とは姿のみえない相手とミサイルを撃ち合うことだと錯覚されがちであるが、本書のこうした記述は、戦争が抽象的な概念ではなく、本質的に人間と人間との殺し合いであることを再認識させてくれる。ハルバースタムはこの本のあと書きで「平凡な一般人の崇高さに敬意を払うことを大事にしてきた」という。ハイペリオン社のウィル・シュウォルビ編集長のいうように、ハルバースタムの本領の一つは「自分たちにはどうにもできない力によって恐ろしい状況に置かれ、信じられないようなことをするよう要求された普通の人々の生き方を観察する」ことだった。
##引用終わり
翻訳には原本にない小見出しが付いている。これは100%有用というわけでもないが。。ノッペラボウの文章を読むよりは役立つ。ただ、残念ながら原本にはある索引がない。マッカーサー、トルーマン、金日成、毛沢東、あるいは、仁川、釜山。。など個別項目の記述を探すのに索引は必須である。ページ数が嵩むのなら、せめて、ネット上でいいから提供すべきではないか。
萩原遼『朝鮮戦争』(文春秋社、93年)や、チョット古いが戦争中の1952年に早くも刊行されたI・ストーン『秘史・朝鮮戦争 The Hidden History of the Korean War』(青木書店、66年)によれば、北朝鮮侵攻前から北では米国スパイが何百人も活動中であり、北からの侵攻計画は事前に承知だった、ということ。マッカーサーや政府も知っていて見逃したのは、<真珠湾攻撃は米国は知っていた>のを見逃した=陰謀なのか、北朝鮮の戦力を見くびっていたのか。本書にこれに関する記述はないようだ。陰謀であれば、真珠湾と同じく、大成功、といえよう。米国記者=ハルバースタムも意図的に詳述しなかったのか。
マッカーサーは司令長官の要件である現地に赴いての統率、をまったくしなかった(仁川作戦を除いて)。すべて東京(第一生命ビル=GHQ headquarters)からの命令である。驚いたのは、仁川奇襲作戦を東京記者クラブでは知らないもの無しだった、ということ。上巻p433
「通常、水陸両用作戦には意表をつく要素が決定的に重要である。しかし、この場合、妙なことにその要素は消えていた。東京では、何が、どこで、いつ起きるか、知らない者なしだった。戦争をめぐる一大センターだった東京記者クラブでは、作戦はすでに、<周知の作戦>のレッテルを張られていた」
米国民は「朝鮮半島で戦争勃発」、のニュースを聞いてあわてて、世界地図を広げ、朝鮮ってどこ?と、探し始めた。。という記述があった。ベトナムってどこ?アフガン、てどこ?フィリピンってどこ?イラクってどこ?ジャパンってどこ?
朝鮮戦争により戦後占領軍により進められた日本の民主化と非軍事化は一挙につぶれた。すなわち、マッカーサー指令によりレッドパージと、報道出版の検閲が復活した。朝鮮戦争の継続中に、ニッポンは単独講和に踏み切り、これは米国との軍事同盟(安保)と抱き合わせとなり、以後、ニッポンは再軍備を強要され、米国の軍事基地となって、途中、今日に及んでいる。
前世紀、いや、前々世紀末からの日本の執った朝鮮半島政策のありようによっては日本の歴史も大きく変わっていたはずである、と考えるのは繰り言であろうか?戦争を防止するのは結局のところ国民の民主化と、政府(および国連)による軍のコントロールの徹底に寄るところが大きい、とするならば、いまも同じ失敗による悲劇を世界のあちこちに見ている我々は、過去There & Then をなんども再点検し、彼は、彼らは、どう行動すべきであったかを我がこととして Here&Now 考えることは有意味である。
すなわち、もし、38度線で一旦事あれば、朝鮮(南と北)、ロシア、中国、米国、日本はどう行動するのか。各国&国連の政治的軍事的布置は当時と現在とでは支配層も次々世代に代替わりし、国力も大きく変わった(まず、当時、中国(共産党)はまだ国連未加入であり、もちろん、安保理常任国ではなかったが現在では軍事経済政治において大国になった。北朝鮮が現在では核保有国になった。日本は軍事政治面で米国の衛星国となっている。北朝鮮は当時、ソ連の傀儡であったが現在、中国ロシアとは一定の距離を保っている、とはいえ事あればこの関係は変わるだろう、等々)が、不変の側面もある(国境線も、軍事境界線も、地理気候条件は当然同じである)。北朝鮮の国内政治体制、それに日本との関係も当時とほとんど変わっていない。各国の政府と軍の指揮関係、各国&国連はどう動くか、の参照モデルに朝鮮戦争は現在でも十分なりうるとおもう。そう考えながら読むと興味尽きない本である。
追記:
書き残したことを箇条書きで。
1 冒頭で著者は滞在先のフロリダ州のある町の図書館を訪れた。ベトナム戦争関係の書籍は50冊あったが朝鮮戦争に関してはたったの5冊。米国において朝鮮戦争は思い出したくない、忘れられた(忘れたい)戦争である、と。日本はどちらの戦争も深く係わったし、このふたつの戦争から景気を回復させた<千載一遇>のイクサであった。私の近所の図書館を調べたが2:1くらいで朝鮮戦争関係の書籍がベトナム戦争関連書を上回っている。
2 また本書の第一章は、6月25日の北による38度線突破ではなく、10月からの朝鮮国連軍による北朝鮮(雲山)への進軍を描く。映画のシナリオのようである。本書には年表がついていないが、年表を脇において読まないと全体の流れが把握しにくい。
3 中心は米軍であるが、朝鮮国連軍は英国、豪州など多国籍軍が参加した。本書には書いていないが日本からも掃海艇が進駐軍の命令により出動し、日本人死者も出た。在日の韓国人も義勇兵として(数百人?)が参戦した。毛沢東は義勇軍として兵士を(300万人)送り込み、この戦争は実質的に米中戦争となった。
第三章「強国に挟まれた国」は朝鮮現代史を一筆書きで描いた章である。ここから引用してみる。p103:
「1945年の朝鮮は事実上、政治制度も固有の指導者層も存在しない国だった。赤軍が席巻した北では、ロシア人が早々にトップダウンで政治制度を押しつけた。金日成を指導者にしたのも同じ手口だった。南では生涯の大半を亡命生活で送った李承晩がアメリカの持ち駒で、嫌も応もなかった。李は当時、70歳。情熱的で自分本位、気分屋、強烈な民族主義者で愛国者、敵意に満ちた反共主義者で共産主義者に劣らぬ専制主義者だった。そう、熱心な民主主義者だったが、自分が自国の議会、官僚機構、その他すべての民主的機構を握っているかぎりにおいての話で、自分の意思に歯向かうことはだれにも許さなかった。日本とアメリカが李をつくったのだ。生涯にわたる裏切り、投獄、政治亡命、破約の数々が彼を変え、非情にした。李は祖国の厳しい近代史が野心的な若い政治家にきざんだ一つの典型だった。金日成も別の意味で同じ悲劇が残したもう一つの典型だった。」
たった10行で、当時の南北の指導者をさらりと活写するジャーナリストの<要約力>。多少の脚色はあったとしても読み物として飽きることがない。
4 I.F.Stoneの『秘史・朝鮮戦争』The Hidden History of the Korean Warは、ハルバースタムの著作が徹底した関係者取材によりいわば足で書いた本と言えるのに対し、新聞記事と公式発表のみを読み込んで、著者のテキスト解読力で書いた本である。ハルバースタムのこの本は朝鮮戦争から60年後に書かれたが、ストーンの著作はまだ戦争継続中に出版された(イラク戦争の内幕ものをいまから60年後に出版して誰が読むだろうか?)。ストーンは同書はしがき、で次のように述べている:
「。。。私はアメリカや国連の記録文書と、信頼すべき米英の新聞記事しか使わなかった。 (略) 私は本書が二つの目的に役立つと信ずる。それは冷戦の臨床研究である。また、戦争宣伝の研究であり、戦時に新聞と公式文書をいかに読むべきかの研究である。あからさまな嘘よりは、むしろ事実の一面を強調したり、省略したり、歪曲したりするのが戦争宣伝屋の手段である。本書は、読者が戦争宣伝屋の所産を検討する仕方、また自分で事実をふるいわける方法を学ぶのを助けるであろう。最後に、この本は、。。。朝鮮戦争の秘められた歴史である。もしテキストを綿密に調べ、さまざまの報告を照らし合わせれば、公式記録そのものの中に見出される事実なのである。 1952年3月15日 NYC」
余談:
私が小学生の頃、ラジヲのニュースから<李承晩ライン>や<拿捕>という言葉が連日のように流れていた時期があった。いま、Wiki<李承晩ライン>を検索してこういうものであったか、と知った次第。本書で描かれた李承晩なら、こういう政策を実施してもおかしくない、と納得した。
<李承晩ライン>@Wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E6%89%BF%E6%99%A9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3
戦火のフンナム(興南)と住居を失った避難民 戦争孤児が南にも北にもあふれた
写真:『秘史・朝鮮戦争』から
オサマビンラデンの仁義なき闘い [Book_review]
山内昌之先生が毎日新聞で書評した評判の『倒壊する巨塔』=The Looming Tower。
原本古書を買ったばかり。 図書館にも和訳上下本を予約したが、長い待ち行列。
ブログ書評をあれこれあさっているうちに段々読む気がしなくなったのも事実。
著者の執念はすごい。ビンラデン自身へのインタビュはもちろん実現していないが、周囲の人物へのインタビュを通じてオサマの身長まで割り出し、185㌢と確定させた(195㌢の大男、といわれていた)。
今週の本棚:山内昌之・評 『倒壊する巨塔 上・下』=ローレンス・ライト著
http://mainichi.jp/enta/book/news/20091004ddm015070008000c.html
(白水社・各2520円)
◇9・11--渦巻いたそれぞれの思惑
9・11同時多発テロは謎の多い事件であった。そのなかで、ウサマ・ビンラディンやザワヒリといったテロ犯罪者だけでなく、その好敵手たちの思惑や心理のひだまでくっきり描き出した本書は、歴史学とルポルタージュの長所を生かした力作である。『ニューヨーカー』誌のスタッフライターの著者は、事件の発端と因果関係に触れるだけでない。ビンラディンを育てたサウジアラビアの情報部長官トゥルキー王子や、ビンラディンらを追い詰める一歩手前までいった米連邦捜査局(FBI)の対テロ部長オニールは、その複雑な屈折感だけでなく、野心的で想像力に富み、情け容赦なく敵対者の一切合切をすべてだいなしにする点で犯人らとも性格的に共通する面が少なくない。
(以下略)
以下、力作のブログ書評。読んで損はない。
http://e-days.cc/cinema/column/oba/200909/28539.php
http://d.hatena.ne.jp/gnostikoi/20090814/1250243582
http://d.hatena.ne.jp/kingfish/20090914
ほかにもたくさんある。
倒壊する巨塔 ローレンス・ライト で検索すればドンドンでてくる。
NYT書評:
Plot Against America
http://www.nytimes.com/2006/08/06/books/review/06filkins.html
CIAはビンラデンやザワヒリの動向は掴んでいたが、対立していたFBIにその情報を渡さなかった。FBIの責任者オニールは女遊び大好き。FBIを退職してWTCに勤務しだした直後911を迎えて殉死。
米国アマゾンでは300名以上の読者が書評している。
http://www.amazon.com/Looming-Tower-Qaeda-Road-Vintage/dp/1400030846/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1254625373&sr=1-1
米アマゾンで一番最初に書評したのはJohnさん。
著者の講演を聴きに行ったそうだ。↓
September 29, 2006
By John - See all my reviews
I saw the author last night at a book signing/lecture, and wrote down some of his main points. I hope it is o.k. with him that I share them here, and what he said, because I found if very fascinating. Mr. Wright is a very intelligent, "gentle" man who obviously cares about things and people, and I found him very likeable, becuase he has a good sense of humor and he did so much research for this book, and travelled extensively. He said he interviewed over 1,000 people in the Arab world for this book.
Some of the main points of what he said:
箇条書きに著者の意見をまとめている。箇条書きの最後。著者のビンラデン処分案(捕まえた場合)は次のようである。
- The way to deal with Bin Ladin, if he were caught: try him before "Sharia courts". Take him to Kenya and Tanzania and make him confront the 150 Muslims who he blinded by the 1998 bomb blasts. Take him around and try him by sharia law. Take him to Saudi Arabia and ask for his execution. Make him look like he violated his own standards. Don't kill him, because then you make him a martyr.
「ビンラデンを捕まえたとする。彼をSharia法廷の前で裁け。ケニヤとタンザニアに連れて行って。1998年の爆破で盲目になった150人のムスリムと対決させよ。Sharia法に照らしてオバマを裁け。サウジアラビアに連れて行って、死刑に処すべきか打診しろ。オバマをして、彼自身の法を犯したことに直面させろ。彼を殺してはならない、それでは彼を殉教者に仕立てることになる。」
(フセイン@イラクの死刑判決の前、即執行後にも同じことを著者は言ったのだろうか?)
この著者にはつぎの作品として、
ブッシュについて、
ブッシュの対テロ戦争を熱狂的に支持して何十万人のアジア市民を虐殺させた米国の国会議員、と、米国民、
あるいは米国、という国家について、
世界経済を滅ぼしたウォールストリートの金亡者について、
。。書いてもらいたい。ビンラデンとそっくりの小人物たちの群れ。
その前に、Wrightさんには、ブッシュや米議員たちに、おのれのテロ戦争で何が現地で起こったか、グランドゼロを目に焼き付けてくるように要請して欲しいね。「ブッシュ、チェイニー、ラムズフェルト等を、死刑にしてはならない、殉教者になるだけだ」
オサマもザワヒリも捕まってはいない。結局、なにがどうなったのか?世界経済と市民の生活を<倒壊>させたウォールストリートのギャング共が復活しているのと同じく、オサマやザワヒリも復活するだろう。
Osama bin Laden と Ayman al-Zawahiri
この作品の最後はアフガンの光景。
ザワヒリと仲間が山に向かうところで終わる。
Zawahiri and the masked Arabs dissppeared into the mountains.
(なんだか、映画『シェーン』、のラストを思いだした)
本作品を映画にするなら深作欣二監督に。
あ。。もう死んだか。仁義なき闘い。
『語りおくこと いくつか』 加藤周一 [Book_review]
昨日明け方、夢に加藤周一老師が出てきた。
老師の夢を見たのは初めてである。
前の晩に加藤の新刊講演集を読みながら、昨年末NHK TVで見た入院直前の老師の姿、鬼気迫る末期の相が頭に浮かんだ、それで夢にも出てきたんだろうか。にこりともせぬ暗い顔だった。実際にはこの眼で老師の姿を拝んだことは一度もない。夢では、車座になって(と言っても聴衆は一切いないんだが。。)加藤がしゃべっていた。わたくしはなんだか事務局みたいな役割で。。加藤センセ、どーぞイッパイ、と、ヘリクだってお酌したり。
昨日図書館で借りたのは次の新刊講演集二冊:
加藤周一『語りおくこといくつか』加藤周一講演集第4巻 2009/7
加藤周一『戦後を語る』 同、別巻 2009/6
(両方ともかもがわ出版)
80年後半から死ぬまでの講演を集めている。
『戦後を語る』
憲法と平和について。重い内容。疲れる。「憲法は押しつけられたか」を特にシッカリと読んだ。若干の異議がある(別に論じたい。加藤は米国が押し付けたのは、政府に対してであって国民に対してではない、と言っている。同じことだ。国民が総意で民主的に<明治憲法存続>を選択することが占領下でありえたか、を考えればわかる。米国の自己都合にしかすぎない。現在の北朝鮮のような体制もゆるさず、さりとて完全に民意で国を動かしてもらっても困る。。という底意があった。すなわち、現在の天皇制民主主義=植民地状況は必然であった。米軍のアジア人=People観念がいかなるものかは、日本各地への無差別攻撃、マニラ、戦後の朝鮮、ベトナム、アフガン、イラク。。への一般市民に対する無差別攻撃で露骨に示されたではないか)。
加藤は「東京裁判」についてどこかで発言しているんだろうか?
『語りおくこといくつか』
これはとくに戦争平和以外の芸術、文学の話題。丸山真男についての講演がおもしろかった。とくに丸山の『闇斎学と闇斎学派』について、など。この有名な丸山の論文は、丸山が東大をヤメテ70年代に書いたのだが、68年の全共闘闘争の影響が色こく残っている、と加藤は言う。左翼運動の正統性=連合赤軍などにも加藤は言及していないが絡んでくるだろう(内ゲバの論理。闇斎派内の闘争と処罰、破門はまさに内ゲバ、である)。思想の<正統性>と、血の正統性(中国の皇帝、日本の万世一系など)を丸山は分けて論じている。前者はオーソドクシ、O-正統性、後者は、レジティマシ、L-正統性。マクス・ウェーバー学派、丸山真男である。
この丸山論文は岩波の日本思想大系『山崎闇斎学派』の巻末解説、全70頁の力作である。わからないところも多々あるが今日昼、再読した。(岩波の思想大系本、いまアマゾンマーケットプレースから数百円~1000円前後で入手可能。タダ同然である)。
丸山が、<歴史の古層>=通時的、を改めて、音楽の<通奏低音>=共時的、と言い直した理由が明確にわかった。
丸山論文の<むすび>を引用する。日本思想大系31、663~664頁。
「わが国における儒学移入の淵源の古さにもかかわらず、また日本近世の程朱学の複数的な源流にもかかわらず、程朱学を理論と実践にわたる世界観として一個一身に体認しようとした最初の学派は闇斎学派であった。それは崎門派が自認したことだけではなくて、同じ儒学内の正面からの敵手であった古文辞派からも 「(中略) ・・」 というフェアな評価も出されていた。稲葉黙斎は「吾党ノ学ハ、ハヅミガヌケルト役ニ立タヌ。ハヅミ斗リデ持テヲル。林家ナドハ、学者の事(ワザ)ガナル故、ハヅミガナクソテモ儒者モ通ラレルガ、吾党ノハ事ニモカマワズ故、惟ハヅミ斗リデ持テオル」といって、「吾党ノ学」をいみじくも「ハヅミ」という形容で特徴づけている。かしこにおいて崎門の「絶交」が林家の「阿世」と対比されたように、ここでも「ハヅミ」は林家の事(ワザ)、つまりタレント性と対比されているわけである。「ハヅミ」はたしかに崎門の俊傑たちを、それぞれの仕方で「行き過ぎ」させる動力でもあった。けれども、この行き過ぎによって闇斎学派は、日本において「異国の道」 --- 厳密にいえば海外に発生した全体的な世界観 -- に身を賭けるところに胎まれる思想的な諸問題を、はからずも先駆的に提示したのではなかったか。そこに闇斎学派の光栄と、そうして悲惨があった。」
加藤周一は、この論文は丸山における68年がなければ生まれなかったろう、という。68~69年の学派ならぬ<敗者たち>に一瞬でも<光栄>は訪れたか。
2004年、萩市でおこなわれた対話でつぎのようなやりとりをしている。「宗教をめぐる対話」の冒頭近く。『語りおくこといくつか』p103から。
- ではキリスト教の<神>について
K: カトリックの場合、一つ教会ですから非常にはっきりしていますが、その<神>を信仰しているかと問われれば、私は信仰していません。
- では<神>という存在を概念として認められませんか。
K: ・・・つまり、存在は概念ではないのです。同じではない。<神>の存在を信ずるかといわれれば、カトリックの<神>の概念にしたがって、存在するとは思わない。
- <神>に対する<怖れ>も持っておられませんか。
K: 存在を信じていないのですから<怖れ>もない。もちろん。
(以下略。この対話は加藤の宗教観が明確に述べられていて面白い。全20頁)

加藤周一著作集月報に、誰かが書いていた。
日頃からジーパンを愛用する加藤を外国の空港ロビーで見掛けた、と。
手に大きな紙袋をもって飄然と歩く壮年時代の加藤。
小熊英二 『1968 若者たちの叛乱とその背景』
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2009-09-10
加藤周一の洗礼と『日本人の死生観』
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2009-06-26
加藤周一 1968年を語る “言葉と戦車”ふたたび
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2008-12-15
追悼 加藤周一
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2008-12-14
生と死 加藤周一
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2006-08-24
小熊英二 『1968 若者たちの叛乱とその背景』 上・下、(新曜社、2009/7) [Book_review]
上下巻、合計2000頁(計1万五千円)の<大冊>であるが、日本の学生運動全体を描こうとおもえばこのボリュームでも不足だろう。下巻で扱われた連合赤軍(16章。この章が一番出来がいい)だけを詳細精密に記述するのにも2000ページの書籍が必要であろう(日本の書籍はだいたいにおいて記述の絶対量=文字数、が足りないのがおおい)。
わたしは図書館で借りて、昨日と一昨日の二日かけて読んだ。上巻を読んだ時点では不満が数々残ったが、下巻とくに、15章「ベ平連」(約200ページ)、第16章「連合赤軍」(約170ページ)の記述を読むにいたって、著者の執筆能力に感嘆した。ベ平連についてはすでに数巻にわたる資料集が出版されており、小田実自身もぶ厚い回顧録を残している。連合赤軍についても映画を含め多くの書物が出版されている(わたしはまとまった単行本を読んだことがない)、ということを考慮しても、これだけの限られたページ数で過不足無く説明しきる筆力はたいしたものである。こういう本は通常速読を許さぬものだがこの本(というより小熊の書いたものはいずれも)は速読が可能である、ということは日本語の文章がよい(読み返さなければ意味を把握できない日本語が最近多い)、ということなのだろう(内容も、というわけにはいかないが)。
わたしは1969年年1月19日当日、偶然にも、東大安田講堂陥落を某書店を訪れた際、店内に設置されていたTVで実況中継を見た。(TVを観るために本屋に出向いたわけではない。その日は週末であったはずである。暦を調べたら19日は日曜日。TVの視聴率が高かったワケだ)。
#
以下、読書中のメモから拾い出した感想をアトランダムに記す。
1 この本のタイトルにまず違和感がある。著者も日本の60年代~70年代の学生運動を総称するに、通称されている世界革命1968という命名はふさわしくない、と本書中でもたびたび異議を称え、説明している。であれば、内容に則して『60~70年代日本の学生叛乱』とでもすべきだったのではないか。私見では1968年という限定は出来ないが当時の世界の情勢、冷戦のなかの繁栄、ベトナム戦争の実態(日本の関与と関与を隠蔽する仕組み)、は陰に陽に学生の心理に反映しておりこれが背景にあると思う。つまり、高度成長期(から、現在に至るまで)の世界を覆っていた、藤田省三のいう人間を商品化する<全体主義>の蔓延が背景にある(著者は結論部下巻p777でいう「ひと言でいうなら、あの叛乱は、高度経済成長にたいする集団摩擦反応であったといえる」)。
2 学生の叛乱はなぜ起こったのか?著者によれば、60年安保を闘った学生(&労働者)たちとはあきらかに発端は異なる、という。経済的に一定の水準を達成し高度成長を謳歌し始めたニッポンで自己のアイデンティティを確立するためのアガキであると、著者は言う。しかし、1965年(慶大)から始まり、日大、東大全共闘の壊滅(1969年)、それに引き続く全国の多数の大学で起こった紛争の収拾の短い歴史を、自己のアイデンティティを確立とか、若者特有のニヒリズムからの脱出だけに求めるのは安易すぎるとおもう(それだけなら、近代に普遍的な年代的現象といったほうがよい)。各大学の闘争を子細に見れば、当局による学生のスポイル、学生の参加を認めない非民主的学内事務運営、当局と学生の間のコミュニケーション不全が原因としてあったはずである。小熊は、学生に問題を言語化する能力がなかった、と言うがこれは誤認ではないか。東大紛争の収拾に当たった加藤一郎(元東大総長代行、のち総長)は、当時を振り返って次のように言っている(下巻p854。結論の章から):
「大学が権力だと攻撃されたけれど、大学は権力なんかいくらももっていないんですよ。どうも国家権力に直接対決できないものだから、それに付随するものとしていちばん弱い大学を的にしたという面があったと思うのですがね。この点はちょっと学生のほうが卑怯だったと思いますね。文句があるんなら政府に言ってくれと言いたくなる」(1991年)
まったく「主体性」のかけらもない発言である(これは闘争後20年後経過した時点における発言である)。加藤一郎(に代表される大学当局)は大学に権限がないことをなぜ文部省に問題提起しないのか?学生に自治権を与えないことのいいわけに当局が文部省から権限委譲されていない、と言って済ませるこの退行的現象。<言語化>能力は、問題認知能力があることが前提。加藤ら、当局に言語化能力があるといえるか。この加藤発言を引用した直後に、東大安田講堂突入や連合赤軍浅間山荘突入を指揮した後藤田正晴(当時、警察庁長官)の次の(回顧)発言がある:
「結果として彼らの狙いは成功しなかったのですから、無駄だったなという見方をする人は多いかもしらんが、私は無駄ではなかったと思う。ああいう動きがあったからこそ[福祉制度や公害対策があるていど整備された]今のような世の中というものが形成することができたんだという気がする。あれを反省材料にしながら、こうしなければいけないという施策を打ち出し、それを国民が受け入れていくというようなことになった」(1995年)
3 若者たちの叛乱がおきた要因を結論(下巻p777以降)で述べている。箇条書きにしてみる。
(1) 大学生数の急増と(大学の)大衆化。結果として、マスプロ教育が一般化し、学生・教員間のコミュニケーションが希薄になった。
(2) 高度成長による社会の激変。経済格差、と、貧困のため大学進学できない友人に対する同情など。
(3) 戦後の民主教育、という下地があったこと(下巻p784)。この背景から出た「戦後民主主義」批判と「進歩的文化人」批判。
「彼らが批判されるべき点」として次の諸点をあげている(下巻p811以降)。
(1) あまりに無知かつ性急に、それ以前の「戦後民主主義」を一面的に批判しすぎた
(2) 運動後の去就(転向)。闘争後、さっさと高度成長化の企業に就職した。運動に留まった者の割合(歩留まり)がそれ以前の学生運動に比べて格段に低い。
(3) 運動のモラル。一般民間人やその資産を襲撃することがあった。
(4) 運動内の責任意識が無いこと。作戦指揮の拙劣のため負傷者逮捕者を出しても責任を感じていない。
上記の結論は何の新味もない。考えなければならないのは、私見によれば、60年代70年代の学生叛乱から、当事者を含む日本人(といってもほんの一部の、だが)はナニを得たのか(時代経験として、である)?あるいは大学はどう変わったのか?教育行政はどう変わったか(端的に言えば、教育に行政=文科省は不要なのだ、ということだが)?ということである。言い換えれば、もし、いま同様な問題が大学で発生したとき、学生、当局と文部省はどういう反応をするか、ということだ。小熊英二(慶応義塾大学・教授)はこの問題に答えず、自分でストーリを作って問題を70年代(連合赤軍問題とともに)で封じ込めてしまっているように見える。これは<研究書>であるゆえの性格か?
4 山本義隆(元東大全共闘議長)は、釈放後、科学書を何冊も執筆している。物理学界でも定評のある『重力と力学的世界』(現代数学社、1981年)を執筆の途中(雑誌連載中)、つぎのようなことがあった:
「。。<共同利用研究所>と称される東京大学物性研究所に図書の閲覧を申し込んだのですが、よくわからない理由で拒否されたことは、やはり記しておきたく思います」(同書、後記、p462)。
紛争の発端となった、大学(とりわけ医学部)でいま何が起こっているか?を著者は追跡調査する必要があったのではないか?70年代、紛争は終結したが問題の解決はなされていない、と私は考えている。<叛乱>が起こっていないコト、起こる気配もないことはよいことか?小熊教授に尋ねてみたいことである。(山本義隆の発言も聞いてみたい。山本氏の専攻=科学史、と無関係でもあるまい)。
引用する。上巻p701
「。。安田講堂攻防戦のあと(雑誌『世界』1969年7月号)、法学者で東大名誉教授だった我妻栄はこう述べている。「終戦とともに、これらの(大学を追われた)進歩的な学者はみな大学に戻ってまいりました。そして、教授たちは、だれはばかることなく、自由に自分の研究や思想を講義し、外部に発表できるようになりました。われわれは快哉を叫びました」「しかし、それだけでは問題は尽きなかったのです。いまにして考えますと。・・・・大学の管理運営自体について考えなおさなければならなかったはずです。しかし、われわれはこのことに十分気がついていなかった。
(中略)
しかし、東大闘争以前は、彼らは敗戦で獲得した研究や言論の自由に満足してしまい、大学運営や学生との関係で教授が権力をもっていることには、戦前いらいの慣行をひきずったままだったのである。」
我妻栄という民法の権威にしてこうである。大学内の<戦前の慣行>はいま、変わっているか?いつ、変わったのか?小熊の前著『<民主>と<愛国>』に言う第一の戦後、第二の戦後を経た<民主>はどこに存在したのか?どこにも。<戦前>の人的組織も思想もそのまま保存され(たとえば、文部官僚、内務・軍(防衛)官僚、裁判官、警察、学閥などは戦争をスルーして、そのシステムは現在も生きのびている)、個人の思想も根底では(たてまえ、ではなくホンネでは)<戦前>のままだった、ということ。小熊英二が前著で縷説した<戦後思想>なるものは少数の思想家の脳内表層現象、国民の実生活を規制する制度にインプルメントされた<思想>は戦前のままである、ということだ。
マルクス主義経済学者で東大名誉教授の大内兵衛は雑誌『世界』69年3月号の巻頭「東大はほろぼしてはならない」でつぎのように発言した(上巻p955):
「1月19日の夕方、一年に及んだ大学の不法占拠が解かれ、警視庁の機動隊が安田講堂を占拠して、中にいた374人全員を逮捕した。その前日からかたずをのんでテレビの前に坐ってみていたわたくしは、これでいい、これでいい、これで入試もやれる、これで東大は滅びないと思った。・・・・学園や学問のことなどロクに考えていないとわたくしが判定している不逞の徒によって、しかも学問のためという口だけのスローガンで、暴力的に占領されているということは、わたくし自身が自分の家の中でドロボウに手ごめにされているような苦悩であったからだ。そしてそれがいま警察が来てくれてその暴力から解放してくれた。これはありがたいと思ったのである。不逞の暴力にまけていたわたくしは、むろんくやしがったが、老いぼれの弱虫であるから、まったくしかたがなかった。同様に大学も暴力には全く無防備なのであるからああいうとき警察にたのむのは当然であり、それゆえに警察は余計にありがたい、おかげでぼくも助かり、本も助かり、研究室も助かった、これはありがたい。なんといってお礼をいったらいいだろう。もらってくれるならお菓子の一箱ももってどなたさまもご苦労でしたといってお礼にいきたいような気がした。(中略)
昨年の1月医学部の教室占拠がはじまったとき、その瞬間から警察にたのんであれを排除すべしとわたくしは考えていた。(中略)
日本の大学と警察とが相互に接近し相互に理解してそれにより今日の日本の大学の無警察状況が改善されるならば、大学と警察との関係の間には相互の尊敬と感謝の途が通ずるに相違ない。そして明治以来の両者のコムプレックス的誤解がとけるならば、これまた日本の民主化の新しい一局面であろう」(引用終わり)
歳はとりたくないものだ。この巻頭言を載せた岩波書店『世界』編集部の度量に驚嘆する。これを読んだ大内兵衛の教え子や弟子達は旧師の著作を古書店にたたき売ったのか(あるいは拍手カッ采したのか)どうか、小熊教授には追跡調査をおねがいしたいモンである。
著者は「結論」(下巻)の末尾p866に次の文章を置いている:
「かくして、本書は序章の約束どおり、始まりの言葉に立ちもどる。「私にはなにもないの。それでは闘ってはいけないのでしょうか?。」この言葉が一人の少女から発された40年以上前の地点から、私たちは再度出直すことを求められているのである。
再度、同じ所から出直せと言うのか?
著者はその一頁前p865でつぎのように書いている。
「「あの時代」の若者たちは「戦後民主主義の欺瞞」の一語のもとに、数多くの遺産をなげすてた。しかし、一度目は悲劇だが、二度目は喜劇である。おなじ失敗をくりかえさないためにも、「あの時代」の叛乱の性格を理解すること、そしてそこから現在のわれわれの位置を把握することが重要なのだ。たんなる懐古趣味としてでなく、「あの時代」の叛乱を検証することの現代的意義は、ここにあるといってよい。」
すでに喜劇は眼前で演じられ、同じ失敗をくり返しているのではないか?問題は媒体が無ければ発現しない。問題が発現していないことは問題の不在を意味しない。媒体の不在あるいは機能不全の可能性があるのだ。文字面の<戦後思想>の存在は、その思想がインプリメントされていることをただちに意味しない。思想と現実の乖離があり、コミュニケーション不在であれば、物理的暴力による解決の試み、そして、現実の敗北、は必然であった。現実の敗北は思想上の敗北ではない。
追記:
本書、それに前著『<民主>と<愛国>』、前々著『<日本人>の境界』の、いずれにも冒頭に約10頁の序章が配され、その中ほどから「研究対象と研究手法」を記述している。著者によれば「研究手法などに関心のない読者は、以下の部分はとばして先に進まれたい」ということ。これらの書物が研究書と呼べるものかどうか(とくに本書と、前著)は議論があろうが、かりにそうだとして、<研究対象と研究手法>は、内容と不即不離の関係にあるのであり、本書(ならびに前著、前々著)を手にする人びとにとって必読なのではないのか?(内容を読んで私はそう思った)。
追記2: 叛乱学生のモラルについて。
叛乱学生が大学施設(公共物、私物)を破壊したことに批判がある(叛乱生に同調する人びとからも)。丸山真男は全共闘学生のやったことはナチス以下だ、と叫んだという。誰であっても眼前で破壊が起これば丸山教授と同じ反応を示すだろう。しかし、彼らによる破壊がなかったとして、丸山の特権体質をだれがいつ明らかにしえたろうか?学内の陰湿な管理体制をだれが学外に曝露し得たろうか。丸山真男の特権体質はたとえば『自己内対話』を読めばアキラかである(丸山門下から特権意識をもつ官僚が排出されるのも当然のことだ、と納得した)。
追記3: 東大闘争過程で文部省の大学闘争対処が始まった。以下、第11章『東大闘争(下)』、p827から引用:
文部省の対策と加藤新執行部の登場
東大闘争に共産党が介入する一方、文部省側は頻発する大学闘争への対処を始めていた。
まず68年11月6日と7日、国立大学学生部長会議が文部省によって開かれ、東大をはじめと75大学の学生部長が集められて、学園紛争対策が協議された。この会議で文部省は
(1)大学運営への学生参加には限度がある。
(2)学生のいう「大衆団交」には応じるべきではない
(3)授業拒否(スト)に起因する留年問題でもたやすく卒業・進級を許すべきではない。
(4)紛争の激化・波及にそなえ各大学間の連絡を緊密にする、という方針を確認した。
とくに文部省が警戒していたのは、協議会の設置だった。68年9月には、富山大学経済学部で、教授人事に学生の意見を反映させる協議会が生まれていた。文部省側はこれを批判し、「教授人事や教育内容、国費である予算を行使する行政面にまで、行政上の責任をもたない学生が参加することなどは、ありえない」という方針を明確にした。
本書中でも言及がある『全共闘白書』(新潮社、1995)。闘争に参加した当事者(当時の学生)500人へのアンケート結果、座談会など。
『1968 若者たちの叛乱とその背景』 内容
●上巻
序章
第一部
時代的・世代的背景(上)―政治と教育における背景と「文化革命」の神話
時代的・世代的背景(下)―高度成長への戸惑いと「現代的不幸」
セクト(上)―その源流から六〇年安保闘争後の分裂まで
セクト(下)―活動家の心理と各派の「スタイル」
第二部
慶大闘争
早大闘争
横浜国大闘争・中大闘争
第三部
「激動の七ヶ月」―羽田・佐世保・三里塚・王子
日大闘争
東大闘争
●下巻
高校闘争
六八年から六九年へ―新宿事件・各地全共闘・街頭闘争の連敗)
第四部(一九七〇年のパラダイム転換
べ平連
連合赤軍
リブと「私」
結論
ブルクハルト、クロード・シャノン、上野千鶴子・辻元清美 [Book_review]
ちくま学芸文庫、今月の新刊から。。
http://www.chikumashobo.co.jp/search/result?desc=true&k=302&order=1&v=20&x=1&y=1
夕べ閉店間際の喜久屋にでかけて、
ブルクハルト『世界史的考察』
加藤『言葉と戦車を見すえて』
の二冊を買った。
ブルクハルト。。の本は1868年前後(日本の明治維新ころ)の講義録。
国家と歴史、宗教について述べている。本屋で立ち読みしただけだが。。ズバリ、ズバリ、と言い切る迫力ある文章の連続でのけぞらせる。どの頁を読んでも考えさせる文章だらけ。巨匠の貫禄である。
たとえば、ルソーの国家論について。。p56
「国家を樹立しようとするにあたって契約ということがなされるとする仮説はばかげており、これはルソーが(契約による新たな社会により不平等を是正。。)理念的、仮説的一時しのぎの説として考えているだけのものである。というのも、彼はこれを、過去にあった事実として示そうとしているのではなく、自分の説に基づいた、国家のあるべき姿として示そうとしているからである。いまだいかなる国家も、真の契約、すなわち、あらゆる面から自由意志によってなされた契約によって成立したことはない。実際また、震えおののいているロマン人と圧倒的勝利を収めたゲルマン人とのあいだで行われた領土の割譲や和解は、真の契約ではない。それゆえ、これからもいかなる国家もこのようにして生まれることはないであろう。また、もしある国家がこのようにして生まれるならば、その国家は脆弱な産物であろう。それは、絶えずその根拠をめぐって争いが起こると思われるからである。」
ロベスピエールについてこう言っているp394.
「だが、ロベスピエール。。にさえも、非常な熱烈さ、否定し得ぬ歴史的重要さにもかかわらず、なぜ偉大さがないのであろうか?このような人たちは、決して普遍的なものを具現していないのであり、むしろたんに一つの党派の綱領と憤怒を具現しているにすぎないのである。彼らの信奉者たちは彼らを宗教の開祖たちのあいだに加えようとするであろうが、そうしたければするがよい」
この短い引用でブルクハルトの趣味(悪趣味)がわかるだろう。
偉大さ、について著者は多くの言葉を費やしている。たとえば。。p392
「歴史は時として、一人の人間のうちに突然己れ自身を圧縮し、それ以後、世界がその人の意に従うというようなことを好むものである。
こうした偉大な個人は普遍的なもの、静止と運動とが一つの人格のうちに同時共存している人たちである。彼らは国家、宗教、文化および危機を包括しているのである」
ブルクハルトは審美家である。観察者である。行動者ではない。
(加藤周一にも似たところがある。加藤周一の美点は時局論にはなく、美術史、文学史にある)
文庫本だがコンパクトな人名索引と事項索引がついている。索引がなければこの本の有難みは9割がた落ちるだろう。
こういう本は文庫本だけでなく、ハードカバーあるいは岩波文庫のラージプリント版のような仕上げで読みたいモンである。
#
クロード・シャノン(ベル研の伝説的学者)の『通信の数学的理論』も新訳でちくま学芸文庫本に入った。シャノンの情報理論の実用的価値は、一定量のノイズのある、一定の帯域幅を持つアナログ通信回線でどれだけの速度でデジタル情報を伝送できるか、の理論限界を示したことである。70年代、電話回線を通じてアナログ変調したデジタル情報を送信する<モデム>が幅をきかした。この本(英語版ペーパーバック)の読書会を新入社員数人でやっていた頃だ。現在、モデムと言えば、チップ化され吹けば飛ぶよな存在になっているが、当時、電話回線に使用するモデムといえば、たった9.6㌔bpsのスループットもなかなか出ず(とくに国際回線では)、装置の重さも何十キロもあり、男一人で持ち上げると腰痛になるくらいの重量級だった。測定したノイズと実効バンド幅をシャノンの公式にあてはめると数十㌔bpsという上限値が得られた。重たい装置だがかなりいいセンいってるジャン、という結論を得て納得した。
#
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480065018/
ちくま新書、広井 良典の新刊 『コミュニティを問いなおす ─つながり・都市・日本社会の未来』は、立ち読みにとどめた。
「高度成長を支えた古い共同体が崩れ、個人の社会的孤立が深刻化する日本。人々の「つながり」をいかに築き直すかが最大の課題だ。幸福な生の基盤を根っこから問う。」
2006年ちくま新書『持続可能な福祉社会』の第7章「コミュニティ論」を全面展開しているようだ。前著では、農村や都会で従来型の共同体が崩壊した後、もとめられるのは「独立した個人としてつながる」という通路(個人をベースとする公共意識や言語化された規範原理)である、と広井は言う。これは、上野・辻元が求めている形と軌を一にする。
広井、と同じ問題を共有していると思われるのは岩波新書7月刊行の上野千鶴子・辻元清美『世代間連帯』である。http://www.iwanami.co.jp/hensyu/sin/sin_kkn/kkn0907/sin_k478.html
われわれ(とは、誰のこと?)の生活上の問題を取り上げて論じている。二人のやりとりは目配りがきいており有用だ。問題は、ズバリ、格差と貧困である。男女、結婚の有無、社員・非正規社員、組合員・非組合員、高齢者・若年者、。。の間の経済的、つまり、ウェルフェアネス=厚生の格差(不公正)、具体的には所得、年金、介護の差別、がなぜあるのか、格差はなくすべきなのか?解決するための社会連帯と、それを支える哲学。社会を分断しようとする企業と、企業の意を受けた官僚の政策。12歳の年齢差がある二人には、意見が割れる場面があり、それが対話を活気づかせている。p235で、上野千鶴子が政治学者・山崎望の民主主義論の一節を引いている。
「代表制民主主義とは、市民参加を促進するよりは抑制する装置である。代表制であることでエリート政治であり、エリート政治であることで民衆を信頼してない衆愚政治観にもとづいており、政治参加を数年に一回の投票行動に制限することを通じて市民の政治参加を抑制するシステムである」『現代規範理論入門』
官僚政治の問題を長年放置しているのは国会議員の責任である。政党政治が機能不全をおこしている、ということにほかならない。民主主義の危機、というより、民主主義は歴史上、格差の問題を解決したこと(解決しよう、としたこと)があったのか?と問うたほうがよい。利権しか目のない議員や政党に、<逆マニフェスト>をつきつけ、選挙結果を最終的なものと見なさず、勤務評定を<市長>が、ではなく、国民諸階層が行って退場を迫る仕組みをインプルメントすべきでる。能力主義でなく、公正を原理とする社会哲学を上野や広井など社会学者に提示してもらいたい。
ブルクハルトが民主主義を無条件に評価していないのも一理あるような気もする。
加藤周一の洗礼と『日本人の死生観』 [Book_review]
加藤周一が亡くなる(12月5日)前、8月19日に教会でカトリックの洗礼を受けていたとのこと。 加藤自身は、神父(カルメル会)につぎのように、洗礼を望む理由を語ったという:
「ひとつには自分は宗教そのものに対する関心を持つ環境にいたこと。
その上で母親と妹がカトリックの洗礼を受けていて、自分も亡くなったときに母と将来は妹とも天国で会えるようになりたい」
感想:
加藤周一らしくない。(洗礼したことではなく、つぎの発言が)
<ひとつには自分は宗教そのものに対する関心を持つ環境にいたこと>
宗教そのものに対する関心なら宗教者だけでなく無神論者であっても(宗教者以上に)持っている。洗礼の理由にはならない。
<母と将来は妹とも天国で会えるようになりたい>
これは理解できる。男は、マザコンだ。
加藤周一は、共著『six lives/six deaths-- Portraits From Modern Japan』(岩波新書に翻訳あり)で正宗白鳥(加藤の担当)を描いていたが、死の直前、洗礼した正宗についてどのように書いていたか。。いま本が見つからない。
『日本人の死生観』上下、 加藤周一、M.ライシュ、RJリフトン; 矢島翠 翻訳(岩波書店)1977
宗教は阿片だ、とおもうが、阿片を飲んで、道徳的に悪いということはない。個人の価値観の問題だ。思想家は価値選択について責任を取る必要がある。どのような個人であっても生死に関しては思想家でありたい。
死の直前に思想が変化するということはある。生前の著作の読み方はこの発言で変わることはあるか。一面では、あるし、他面では、ない、といえる。著作、というものは、有限な人間の、ある状態における制作物であるから。
追記:
『日本人の死生観』の、下巻、正宗白鳥の項を再読した。
加藤が正宗白鳥に全般的に、好意的であるのが予想外であった。(本記事コメントを参照ねがう)
知的境位、として、加藤と白鳥は近いところがあるのではないか、という気がする。明らかな相違点として、白鳥は政治的活動を一切していない(積極的には)。しかし、これはそれほどの差ではない。世界や文物に対する興味、は両者とも強い。
雑種文化論者=加藤は、キリスト教の受容について、<日本的>な変容をした後、受け容れた、と書いているが、これには追加説明が要る。イエス以後、キリスト教が世界宗教化するにあたり大きな変容を被ったのは周知のこと、一般に、宗教だけでなく、あらゆる文化が他の特殊地域に根づくとき(グローバル化するとき)、なんらかの変容を被るのはキリスト教だけに限らない。キリスト教はオリエント起源であり、西欧に根づく(世界宗教化)には大きな変容を被った。受容に先立つ変容は、日本だけの特殊現象ではないし、集団のみでなく、個人レベルの受容においても同じ現象がみられるはず。土着~外来、という対立もしくは変容は世界に普遍的にみられる現象である、とおもう。加藤等が正宗白鳥に観察した、キリスト教受容にあたっての<日本的甘え>は、加藤周一の末期にも見られた、ということ。
『日本人の死生観』下巻から引用する。
正宗白鳥の章、p63。
「こうした一般的な世界観に向かって容赦なく自己を駆り立てた点においてのみ、白鳥は普通の日本人と違っている。彼は自分の信念と矛盾を意識していたが、他の日本人にはそうした意識は薄かった。キリスト教との対決は、周囲の世界に対する白鳥のとぎすまされた感受性において、決定的な役割を演じているようにみえる。いわば彼の「夢物語」が白鳥の現実感を先鋭にしたのだ。こうしてキリスト教は、白鳥が、キリスト教とは対極に位置する此岸的な人生観のこの上なく強い主張者となる上で、力を貸したのである。白鳥は、いわば土着の、通俗的な世界観における良心となったのだが、それは彼が近代日本における沈黙の大衆のひとりだったからではなく、周縁に位置して発言する少数派に所属し、大衆とともに暮らしてはいるものの、真にその一員となることはなかったからである。 ---- そのような関係が生まれたのは、彼の文学的才能と、キリスト教との真摯な対決がはたらいていたためだった。しかし白鳥は、十八世紀に儒教と対決した本居宣長がその著作でなしとげたようには、そうした基盤の上にみずからの体系的な思想をきずき上げることはなかった。この意味で、社会の広範な変化をすりぬけて通っている白鳥の文学様式は、それ自体、日本の文化的継続性の象徴だったのである」
同じくp107。
「白鳥はさまざまな矛盾とともに生き、事実、矛盾こそ彼の人生であった。彼は一面では、心のなかにそんなものはないとうち消す懐疑的な声が、つねに人より強かったにもかかわらず、「死を超えた何物か」についてのキリスト教の福音を、ほんとうに信じていたのかのようにみえる。二つの信念はしばしば葛藤を生じたが、それらをともに維持した白鳥の力は、人に感銘を与えずにはおかない。矛盾を分析しようとするよりも、白鳥は矛盾を受けいれ、みずからの文学の仕事の上でのできごと、情動へと注ぎ込んだ。二つの矛盾と、それらを混淆させようとする彼のたたかいが終わりを告げたとき、彼はいつ死んでもよかったのである」
以上は、加藤、リフトン、ライシュの共著部分である。以下は、加藤による本文への「おぼえがき」から。p109。
「ここで真に問題となるのは、白鳥がその晩年に本心からキリスト教に帰依していたかどうかではなく、彼がキリスト教のうちに、そしてキリスト教をつうじて、何を見たかなのである。」
「最後に自分のキリスト教に対する郷愁を認識した白鳥は、人生の「現実」の一部として、非現実的なるものを信じようとするみずからの熱望に気づいたのである。こうして、最終的には、非現実も現実と同様に、彼の関心の領域となった。
では、白鳥にとってそれほどの重要性と圧倒的な力を持っていた非現実とは、何だったろうか。それは一点に集約できると、私は思う。何をしようとも、人は究極的には救済される ---- みずからの力によってではなく、それが母親であろうと、キリストであろうと、阿弥陀であろうと、自然ないし神の支配による、究極の世界秩序であろうと、人の上にあってすべてを許したもう、いつくしみにあふれた力によって。こうした楽観主義には、「神曲」におけるダンテの「希望」、親鸞の「善人なおもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」に、共通するものがある。すべてを抱擁する恕しの観念は、これらの場合にもまた顕著である。白鳥がキリスト教のうちに信じたものは、必ずしもキリスト教特有のものではなかった。他のことばでいえば、決定的な意味をもっていたのはキリスト教ではなく、キリスト教にも他の宗教にも共通ななにものかであった。(略)「人間、重病にでもかかると、どんな神にでも仏にでもすがる気持になるのであろうが、当時の私は、キリスト教に接触してゐたので、キリスト教の神に祈る気持ちになつたのだ」。また、「自分が臨終の折に、『南無阿弥陀仏』を口ずさむか、或いは、『エスキリスト』を呟くか、いづれであらうかと空想してゐる」ともいう。白鳥はこれに続けて、すべては彼の内面における日本の伝統と外来の文化の均衡によると述べている。明らかに問題点はキリストか仏陀かの選択ではなく、そのいずれかを彼が必要としていたという事実である。
白鳥がキリスト教を変えたようには、キリスト教は白鳥を変えなかった、と言えるかもしれない。私の考えでは、これは日本における仏教の歴史ときれいに対応する。彼岸の信仰体系としての仏教は、日本人の此岸的な心性を変えはしなかった。反対に、日本人は仏教を日本化する過程の一半として、仏教を此岸的にした。白鳥はキリスト教を日本化してはじめてそれを受けいれたのである。この意味で、彼は日本文化に共通の型を代表していた。
(略)
日本でキリスト教徒になることは、非常な少数派の一員になることであり、はっきりした考えに立っての決断を意味していた(そしていまでも意味している)。仏教とは異なり、いくぶんマルクス主義に似て、キリスト教は観念・価値・信仰の包括的な体系であり、大勢順応を迫る社会の圧力に抵抗する意志をもつ個人によってのみ、意識的に受けいれられるものである。白鳥がひとつの宗教体系にこうして意識的に身を挺したことは、のちになってそれを放棄したにせよ、たしかに彼がその作品をつうじて、現代日本におけるほかの作家のだれひとりとしてそれほど持続的かつ明瞭には述べていない人生の究極的な意味や、来生などの問題に、接近する背景となった。この意味で、キリスト教は彼を独特な作家にしたのである。
この点をふまえた上で、死における白鳥の甘えの感情は、現代の日本人の大多数が共有しているものだということに注意すべきである。彼はみずからが願ったとおり、その生においても死においてもひとしく、現代日本の鏡であった」 (引用終わり)
##
白鳥に私淑し最期を白鳥の奥さんとともに見取った深沢七郎の文章(朝日新聞)を全文掲載する:
九月五日、私は北海道で正宗先生が入院したことを知った。病気の様子は十日間ぐらいで退院するらしい。が、北海道もそろそろ寒くなってきたので渡りどりのような私はそろそろ北海道から移動しようと思っていたところだった。それで、すぐに東京へ立つことにした。六日の夕方、羽田に着くと私の弟が迎えに来ていて、弟は前日、病院へお見舞に行ったのだそうである。その時、先生の奥さんは弟の顔をみると「深沢さんが来るにはまだ早すぎますよ」と軽く笑いながら言ったそうである。これは、私が駆けつけるということは「死ぬ時だ」という意味らしい。ふだん、そんな風なことを言っていたからである。とにかく病気はたいしたことないらしいが、遊びに着たのではなく駆けつけるつもりで来たので、羽田からすぐ病院へ急いだのだった。
その晩、八時ごろ、病室のベットの先生にお会いしたのだが、軽い症状だと思っていた私は顔色の様子で(これは、とても、むずかしい)と不安に思えたのだった。やはり、不治の病因があったらしい。それに老齢なのである。いちじ、快方に向かったが退院もできないまま、だんだん衰弱していった。先生自身は初めから知っていたらしい、(僕の身体は、僕がよく知っている)というようなことを言っていたが、あの日、十月六日である。終えんの日の近づいたことを私達-奥さんと看護婦さんと私-は先生自身の口から知らされたのだった。「神様は、きっと、やさしく抱いて天国へみちびいて下さるから」という言葉は、弱い、悲しい言葉ではなく、信ずるものを強くつかんだ言方なのである。ふだん、聖書を読むことが好きだということは知っていたけれど、こんなにもキリストを深く信じていることを私は知らなかったのである。
また、「僕は内村鑑三のものをよく読んだ。植村正久の講義を熱心に聞いたものだ。このふたりの先生を恩師だと思っている。植村先生の娘さんがYWCAの会長をしているからそのひとにお祈りをしてもらって葬式をしてもらいたい」というようなことを言うのである。そうして、若いころ、かすりの着物をきて、すみの方で植村先生の講義をきいていたころの様子を感慨深そうに語るのだった。その時、私は内村鑑三という字を新聞などでよく見るような気がしたのだった。そうして、そのひとに正宗先生の気持を伝えたいと思ったのだった。
「その、内村というひとは、どこにいますか?」ときくと、「そんなひとは生きているものか。三十年も、もっとまえに死んでいる」と声を大きくして言うのである。(それではダメだ)と私はちょっと残念に思った。そうして、もうひとりのほうのこと、植村環先生のところへ奥さんと一緒に葬式のことを頼みに行ったのだった。その夜、私は考えたあげく、(あんなに、キリストを信じているなら、洗礼を受ければいいのに)と思ったのだったが、私はそんなことをすすめるのは僭越(せんえつ)のような気がして言出せなかったのだった。が、次の日思い切って、私は覚悟をきめて言いだしたのだった。「先生は洗礼を」と言うと、「僕はずっと昔、若いころ、植村先生のみちびきで洗礼を受けた」と言うのである。(ああそうか、よかった)と私は安心した。いままでそんなことを話してくれたことはなかったのである。
洗礼を受けたなら洗礼の名があるのではないかと思ったので、「洗礼の名は、なんという名ですか」ときくと、「そんなものはない。ただ、あたまへ水をかけただけだ」と軽く話すように言っただけだった。(キリスト教徒だったのだナ)と私は安心した。病床で「僕が死んだらだれもこないようにしてくれ。花輪とか香典ももらいたくない」と何回も言った。「お通夜も、家の者だけ、二、三人でいい」とも言った。人に同情されるとか心配をかけることが大きらいの人だったのである。
昭和37年10月30日 朝日新聞
加藤周一 1968年を語る “言葉と戦車”ふたたび
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2008-12-15
追悼 加藤周一
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2008-12-14
生と死 加藤周一
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2006-08-24
養老孟司は科学者か? [Book_review]
本日6/21の書評をじっくり読んだ。
今週の本棚:養老孟司・評 『稲作漁撈文明…』=安田喜憲・著
◇『稲作漁撈文明--長江文明から弥生文化へ』
(雄山閣・5040円)
http://mainichi.jp/enta/book/hondana/news/20090621ddm015070005000c.html
この書評中、肝腎の『稲作漁撈文明…』の内容に触れるのは全体の1/4だけ、書評全文を読んでもらうと分かるが、あとは本書の内容とは関係のない養老の持論の展開あるいは垂れ流し。こんな書評ならラクチン、本を読まずに書けるだろう。これを読んで、全国の図書館司書は、うちの図書館でも、税金五千円を使って、是非本書を購入しよう!と思うのだろうか?
次の記述はミスリーディングではないか?
「物的根拠の利点は、間違ったときに原因がわかることである。当たり前だが、人は神ではないから間違える。しかし物的証拠に基づいていれば、訂正が可能である。最近の裁判でDNA鑑定の問題が生じたが、物的証拠だから誤りの訂正が可能だった。物的証拠の利点は確実さではない。訂正可能性である。そこをほとんどの人が誤解している。反証可能性こそが科学の基礎である。」
養老は足利事件の問題点を知っていたのだろうか?あるいは今、知っているのだろうか?知っているなら
<物的証拠だから誤りの訂正が可能だった>
などと簡単に言えるわけがないはずである。
「物的証拠という科学の衣装を纏った迷信があるから、多くの検察官、裁判官、取り調べ担当者、証人に誤りの訂正ができなかった」、というべきではないか。
そもそも、20年経過してやっと誤りを認めたことをもって、誤り訂正が可能だった、と言えるのか。
一般に捜査で誤りが訂正されうるのは、証拠が万人に公開され(検察に独占されず)、誰でも検証でき、実際審理に当たる裁判官が検察に従属していない公正な判断力の持ち主であることが、最低限必要である(これ以外に、いくつものハードルがある)。
狭山事件には犯人が書いた脅迫状が残っており、弁護側証人はこの脅迫状は石川容疑者が書いたものではない、と認定したが採用されなかった。
新聞報道によれば足利事件の場合、
1 容疑者のDNA型特定がそもそも誤っている。
2 被害者の衣服についていたというDNA型特定も、90年当時の鑑定法では疑問点が多く、とても、容疑者の型と<一致>と断定できない。
しかも、DNA型が一致したからといって犯人とは断定できないことは血液型の一致と同じである。無論、異なっておればその時点で無罪となる。そういうものである。DNA型は無罪の証拠にはなるが、有罪の証拠にはなりえない、ということである。
養老は
<そこをほとんどの人が誤解している。反証可能性こそが科学の基礎である>
とまで言っている。誤解しているのは一部の人間だけ、足利事件においては<検察、裁判官>だけではないか?あるいは養老も、だろう。一般人だって、証拠の危うい用い方にもとづく推論のおかしさは直感的に気づくものである。養老は勢い余って<反証可能性>までもちだす。なにをか言わんや、である。足利事件は<反証可能性>の問題以前の、偽証、無理解、偽造、誤判断が引き起こしたのであり、裁判所も検察の偽造と予断を見抜けなかった。つまり科学以前の問題なのだ。科学的知見そのものと、現実社会における科学的知見の正しい運用、の間には制度(誤りやすい人間が運用する)という巨大な溝がある、ということ。運用を誤った制度化なら、<科学の捜査への適用>はない方がマシどころか、権力に悪用されるのがオチなのである。
(注)反証可能性とは哲学者カール・ポパーが発案した概念だが、そのポパーは人間は誤つものである、人間から可謬性(fallibility)は絶対に除去できない、という理由をもって死刑に反対している死刑反対論者なのである。反証可能性くらいなら言及するが、死刑反対などとは養老は絶対に言わない、安全なひと、である。足利事件では判決が<無期懲役>だったから再審への道が開けた。<死刑>だったらこういう訳にはいかない可能性もあった。<反証可能性>を真剣に考えるなら、<死刑反対>という思想に真っ直ぐ結びつくのである。
#
書評の見出しは、「自然界の証拠に基づく大胆な推論」。大胆な推論、が必要であるのなら、この自然界の遺物がまだ<証拠>と言えるまでには人間の知見が成熟していないこと、そう専門家集団に認定されていないこと、すなわち、<証拠>とは言えないということではないか。
小田実 『大地と星輝く天の子』 (岩波文庫) [Book_review]
出版社(岩波)の案内:
小田実『大地と星輝く天の子』
http://www.iwanami.co.jp/shinkan/index.html
ソクラテスはなぜ告発されたか.籤で選ばれた陪審員が耳を欹てる哲学者の弁明とは.性的人間,革命家,泥棒,巫女,よそ者蠢く敗戦後アテナイの姿──爽快に猥雑に展開されるダイナミックな現代絵巻の一部始終は,裁判員制度の始まる日本人にも他人事ではない.初期代表作を一人でも多く読んでほしい
http://www.iwanami.co.jp/shinkan/index.html
評決は死刑と出た.ソクラテスの平静と巷(ちまた)に広がる波紋.クリトンら弟子たちの奔走も空しく,迎えた刑執行の日──裁判の仕掛け人は告発人は? 外国人(よそもの)は奴隷は? 娼婦は巫女は? 人が人を裁く意味をめぐって,揺れるアテナイ社会.市民それぞれの運命を大胆に描く裁判小説が,限りなくわれわれの現代に迫る.全2冊
出版社(岩波書店)挨拶
http://www.iwanami.co.jp/hensyu/bun/
★ いよいよ裁判員制度の始まる五月、文庫の〈裁判小説〉も完結篇(裁判員制度も利用する出版社の商魂)。
われらがソクラテス裁判の評決は「死刑」と出た。なぜ、死刑だったのか。二回の投票のうち一度目は無罪か有罪かを問うもので、結果は意外な僅差で有罪。そのとき無罪に投じた人たちの票は、刑罰の種類を決める二度目の投票では、当然、軽いほうの刑罰を選ぶと思われた。それが、国外追放ではなく罰金刑でもなく、告発者の一人が口にした「死刑」という言葉へと、一気に傾斜していった理由は?
いやいや、原告および被告ソクラテスの弁論、投票の成り行きや結果への波紋は物語を読んでいただこう。本書の読み所としては、古代ギリシアでの裁判の方法、男女の風俗、外国人の役割など社会史的側面があげられる。だが一層興味深いのは、市民が何をもって「罪」と考えるか、また罪の重大さと「罰」の妥当さへの社会的判断はいかに形成されていくか、の根源的問いではなかろうか。この点で、この小説は、古代から現代へと大きく開かれる。人が裁き・裁かれる際に直面する葛藤は登場人物ごとに異なるが、「世間」「世論」という個人を越えた集合心性と、無定形なその膨張が惹起する不穏な動きを追う眼は、いかにも小田実らしい。この初期長篇は、『何でも見てやろう』で一躍有名になった若い作家が、西洋古典の異色の案内人さながら自由自在に人物を造形し、古代アテナイに敗戦後の日本人の心性まで映し出してみせただけでなく、あくまで市民に視座をすえた小田実、誰もが知る、あの、生涯行動しつづけた作家の眼力を、すでに具えていたことを立証している。
作家として友人として小田実を長く深く知る柴田翔氏の解説のほか、付録に未公刊の小田実『私の自伝的文学論』を収めた。いささか無謀な試みだが、巻末に<旅と小説の略年譜>を付した。2ページ見開きで見る小田実の生涯――短いやないか!! と、小田さんは怒るでしょうか。(死なないと文庫化してくれへんのか!と苦笑するでしょう)
小田実の小説が岩波文庫に入るなぞ予想もしなかった。
彼の尊敬する戦後派作家、中村真一郎、堀田、大岡、安岡、武田泰ジュン、。。野間宏を除いてまだ岩波文庫(緑)になっていないのではないか?
小田実の小説を岩波文庫にするバヤイ、どの作品がいいだろうか?
『アメリカ』『HIROSHIMA』『現代史』。。
それとも、トルストイ『戦争と平和』の倍もある『ベトナムから遠く離れて』か?
http://www.odamakoto.com/jp/Profile/1990.shtml
岩波書店は『大地と星輝く天の子』を選んだ。
『大地と星輝く天の子』を収録した「小田実全仕事」第三巻「この巻のためのきわめて短い注釈」として、小田はこの作品についてチョロリ、と書いている:
「ギリシヤ語を学ぶようになって、最初に読んだ本が、プラトンつくるところの『ソクラテスの弁明』であった。なかに、おしまい近くのところだが、「わたしに死を課した諸君、諸君に私は言いたい」とソクラテスが語るところがある。それは決然とした裁断のことばだが、私は読んで慄然とした。こんなふうにソクラテスにさえ見放された人間たちはどこへ行けばよいのか。私自身が、そうした人間たちの一人ではないのか----私は、そのとき、そんなふうに考えたのである。
その思いは長いあいだ、私の胸に重苦しく残っていて、60年の1月から2月にかけてはじめてギリシヤを放浪して歩いたときも、日本についたあともとりついて離れないで、ついに、この『大地と星輝く天の子』になった。63年の正月に書き始め、半年かかって完成した」
かくて、文庫本にして800頁の小説ができあがった。
内容は三部構成。
第一部: 鳥とネズミとカエルと矢と
第二部: 裁判
第三部: 死まで
第一部ではソクラテスとその周辺にいる俗物たち、この裁判~死刑事件がおこる直前の30年におよびペロポネソス戦争の実像、市民と奴隷達の野卑、喧噪、二日酔い、打算、裏切り、好色、怠惰、痴話喧嘩、貪欲、取引、いいかげんさ(ボチボチ)に満ちた生活が描かれる。ソクラテスの扱いは英雄的である(それ以外に描きようがない)。
第二部: 陪審として金欲しさに裁判所にやってきた市民達。ソクラテスを告訴した俗物=メレトス(イエス伝でいえば、イエスを売ったユダの役割)。ソクラテスの長い、反論。500人(小田実の小説ではなぜか501人を通している)の陪審が280対220で有罪に。刑罰を決する前、ソクラテスが示したでかい態度にがまんならず、大差で死刑判決に。(ちょうど、現在のニッポン、民主党=小沢党首が、反検察を押し出してデカイ態度をとったため、小澤が怖いマスゴミと、アホな国民の反撃を喰らったのと似ている)
第三部: 刑務所におけるソクラテスとその死。。しかし、これを匂わせるだけで、小田は直接毒杯を飲む場面を描いていない。
バタイキスコスは今年の陪審員に登録されていたが、その日の裁判に出廷できるかどうかは籤(クジ)によった。彼は籤運に強い方で、このところつづいて3オボロスにありついているのだが、そんなふうに今日もうまく行くかどうか。神に祈れ。ノッシス。英雄バタイキスコスの出陣だ。彼がぶじに民主国アテナイ市民としての責務を果たし、3オボロスを手に入れることができるように、ノッシス、神に祈れ!
街路にはすでにかなりの人間が歩いていた。急がなくてはならぬ。おくれてしまっては、籤を引く権利さえない。3オボロスにありつかなければ、今日一日、アゴラで働かなくてはならないだろう。まる一日働いてたったの1ドラクマ。光輝ある自由市民も奴隷も在留外人も変りはなかった。たったの1ドラクマ。額に汗して、重い石材をかつぎ、うんうんうなり、現場監督の眼をぬすんで苦心して油を売って1ドラクマ、つまり、6オボロス。そこへ行くと、裁判で稼ぐのは楽だった。ベンチに坐ってらくらくと居眠りしているうちに時間はすぐたち、3オボロスが降ってくる。急がなくてはならぬ。急がなくてはそいつが降って来ないのだ。日傭とりのテウクロスは懸命に歩いていた。ペリクレスもやって来ることだろう。もう一人の仲間のアンドキデスは今年は陪審員の名簿にのっていないので裁判があるたびに地ダンダふむのだが-----ペリクレスがおくれるといい。おくれるように神に祈ろう。あいつがおくれると、同じ仲間のすくなくとも一人ぶん3オボロスにありつくチャンスがそれだけふえる。ペリクレス、寝すごすがいい。そして、急げ、テウクロス。おまえはダテに年をとっているのではないのだぞ。
バスクレスの足どりに元気がなかった。一歩一歩が「寝とられ男、寝とられ男」と言っているような気がした。確証はいぜんとしてなかった。マルプシアスはキュノサルゲスで会うと、「やあ元気かね、助平オジサン」と大声をあげて馬鹿笑いし、それから思わせぶりに「奥さんはお元気かね」とたたみかけて来る。バレクレスは「まあね」とか「元気よ、元気すぎて困るよ」とことばを返すのだが、口調は昔と変わらず元気いいものであるのに、どこか受身なところがあった。
あれから、彼は何度も不意打ちに帰ってみた。異状はなかった。いつだって、クリテュルラは「あら、今日は早いのね」と何事もなかったように彼に飛びついて来た。そういうとき、バスクレスは彼女を引き倒して着物をまくり上げるのだが、「いやだわ、まだ早いわ」とクリテュルラはくっくっくっと笑声をあげ、ほどよく肉のついた両股をひろげる。 (p158.第二部。『小田実全仕事』版)
筋書きと、ソクラテスの演説はプラトンの原作通りだろう。プラトン『パイドン』は、ソクラテスが毒杯を飲み、家族や友人が泣き叫ぶのを押しとどめ、カラダが硬直し始め、床に横たわって死ぬ。友人が瞼を閉じさせてやるまでを詳細に記述する。これはこれで感動的なのだが小田の小説は視点がこの場面、ソクラテスにはなく、死に追いやって、死の瞬間にはソクラテスのことなどスッカリ忘れ、死後市民に英雄視されるのを恐れる告発者や、俗物市民の側に視点を置いている。
法廷でソクラテス=70歳、の演説を聴いたプラトンはこのとき28歳。
小田実がベ平連活動に(鶴見に依頼されて)係わりはじめたのは65年のことだ。小田は、市民が、ここぞというとき、いかに愚劣な言動に走るか、を、しっかりと認識していたはずである。徒党を組まず、個人として参加し、個人として撤退する、というベ平連の行動スタイルはアテネのいい加減なデモクラシから学んだに違いない。
#
保坂幸博『ソクラテスはなぜ裁かれたか』によれば、 ソクラテスは宗教的存在であった、という。ギリシャ哲学がそも、宗教的性格を当初はもっていた。ソクラテスが裁かれたのは民事でも刑事でもなく、宗教裁判である。
なぜ裁かれたのか?
ソクラテスを告訴したグループは、ペロポネソス戦争敗戦後の不安定な政治状況を乗り切っていくうえで、ソクラテスの存在が邪魔であった。そこでソクラテスの活動(アテネの老若男女だれかれとなく捕まえては議論をふきかける)が邪魔であった。活動を圧殺しようとした。それが裁判の真相という。
プラトンは『ソクラテスの弁明』『クリトン』『パイドン』で、ソクラテスの法廷における反論、牢を訪れた友人クリトンが脱獄を薦め、ソクラテスが拒否、それに、最後の場面。。が記述される。これは真実なのか?田中美知太郎によれば、プラトンほどの創作者ならば(史実かどうかは別にして)、ソクラテスくらいの人物と事件の創作は簡単にやれたろう、という。
#
以下、開高健の解説(講談社文庫版、1970年)からの引用。開高健は林達夫の古代アテナイの「民主主義」に関する記述をつぎのように要約している。
#
その時代の人口のほぼ半数は奴隷であって、政治的、市民的、いっさいの自由をあたえられず、切り捨て御免、芝居を見ることも許されない。だからアテナイの民主主義は人口の半数を完全に除外したもののうえにあった。のこる半数の自由民の投票有資格者二万五千人のうち、現実に人民議会の討議に「参加」したのはたいていの場合四千人そこそこ。この「市民意識」を持った人口のうちで政治に熱心だったのはアテナイ市民というよりは郊外の農民であり、市民のうちで「参加」したのは中流商人が多く、その「参加」の「心情」は半ばひまつぶしであったと推定され、「ルンペン的、冒険的人員」もたくさん野心家に買収されて投票にでかけたのではないかと推定される。そして、現実をうごかしたのは議会というよりは銀行家や経営者、およびそれと結びついていた自由民の労働者たちであり、彼らは議会を公然無視してこっそりと、しかしたくみにアテナイを支配したと推定される。「アテナイの民主主義も、結局は勢力ある比較的少数者の支配、一種の寡頭政治だったといわなけばならない。」
奴隷の底知れない低賃金労働をかかえこむおかげで金持ちはいよいよ金持ちになり、貧乏人はいよいよ貧乏人となり、両者は手段を選ぶことなく、隣国の援助を借りてまでも流血闘争をやった。
争闘の結果として社会は疲弊し、富者はいよいよ富み、貧者はいよいよ飢え、失業者が増え、危機が昂まる。そこで解決が戦争に求められる。土地、資源、奴隷、市場を求めての戦争が開始される。ペロポネソス戦争がじつに27年間にわたって続行される。しかし、戦争によって富者が必ずしも富むとは限らない。アテナイは崩壊する。
#
開高健は、。。
いかにアテナイが、「無知と俗悪との無政府状態」であったとしても無知者は無知者、俗悪者は俗悪者なりに一つの生を生きようとし、生きていたのだということを実証するため作者はクロかシロかと断定したがる安易を峻烈にこばみ、その結果として作品をこんなにも膨張させてしまったのである。生きることの手のつけようのないむつかしさを実証するためにいささか書くことに不手ぎわだったのではないかと思われるのである。誠実が過度すぎたのである、
。。という。そして結論として、つぎのことばで「解説」を締めくくる:
「作者は何を言いたかったのか?
私は一つ深い絶望を嗅ぐのだが」
絶望か?
この小説を書くことにより脱出口をみつけたか?
しばらく、保留。再読しよう。
追記:5/17
書店で文庫本(下巻)を読んだ。柴田翔が解説を書いている。それに小田実の小説作法に関するエッセイの寄せ集め(20頁くらい?)がオマケについていた。柴田翔が書いているが、40年前、雑誌『人間として』の編集会議(小田、柴田、開高、高橋、真継)の席のこと。小田は一枚の紙にしゃべりたい項目を乱雑に並べて、その個々の項目をネットワーク上に鉛筆で結びつけている、そしてこの紙をわきにおいてオモムロニ熱を込めてしゃべり、チャンとシャベリ終わったときは筋の通ったハナシとして展開し終えていた、という。巨大な小説をいくつも書いた頭脳の一端である。<小説作法>というより、この構想力は努力して得られるものではあるまい。なにが小田を作家にしたか。根源が知りたい。小田が何度も語っている、人間の命を虫けらのようにあつかったコッカ、そのコッカを操っているのも同じ人間、この人間という存在とはなにものであるか。これを明らかにせずに死ねるか、という終戦時、焼け野原の故郷(大阪)に立った小田の怒りが根底にあるのではないか。。。などと思っている。
小田実の考えてきたこと
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2008-03-27
追悼小田実
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2007-07-30
『独立外交官』 と 『岡本行夫現場主義を貫いた外交官』 [Book_review]
本日(4/12)の毎日新聞書評欄。養老猛司がとりあげているのは
『独立外交官 Independent Diplomat』 - 国際政治の闇を知りつくした男の挑戦
原著名 Independent Diplomat: Dispatches from an Unaccountable Elite (Crisis in World Politics)
著者:カーン・ロス(Carne Ross)
http://www.eijipress.co.jp/guide/2045.php
本体1,700 円+税
四六判 上製 304ページ
ISBN10 : 4-86276-045-7
ISBN13 : 978-4-86276-045-6
9.11、対テロ戦争、コソボ……だれも知らなかった「外交」の真実
経済危機、テロ、環境、貧困……世界中に影響する国際問題の現場で何が起きているのか?
イギリス外交官として最前線で活躍した著者は、イラク戦争に反対して職を捨て、大国に虐げられた人々を支援する「独立外交官」の活動を開始する。国際社会の不条理を抉る衝撃のノンフィクション。
「僕は国益のために働くのをやめた」
著者:カーン・ロス(Carne Ross)とは。。。
15年以上にわたってイギリス外務省に勤務。1997~98年、英外相故ロビン・クックのスピーチライターを務める。その後4年半、国連安保理イギリス代表部に、中東問題の専門家、一等書記官として勤務。
2004年、外務省を辞め、外交コンサルティングの非営利組織インディペンデント・ディプロマット(Independent Diplomat)を設立。国際政治の場で軽視されている、貧しく経験も乏しい政府や政治集団に、外交上のアドバイスと支援を提供する。支援先は、コソボ、ソマリランド、西サハラのポリサリオ運動の他、各種のNGOや国際機関。2008年のコソボ独立に貢献。
インディペンデント・ディプロマットは多くの賛同と支持を得て、2009年1月現在、ロンドン、ニューヨーク、ワシントン、ブリュッセル、アジスアベバの5拠点で活動している。2005年、ジョセフ・ラウントリー公益信託によって「公正で平和な世界のためのビジョナリー・ピープル」7人のうちの1人に選ばれた。
www.independentdiplomat.com
訳者:北村 陽子(きたむら・ようこ)
毎日新聞、養老猛司による引用箇所、と、養老の短いコメントを引用。これが、養老によると本書の結論である、らしい。「」内は書評者=養老による訳書の引用である。
##
「最も大きな誤解が一つある。嘘とは言えない。ほとんど無意識だからだ。この誤解は、フィクションと言ってもいいが、政府も、統治される側も、一致協力して信じている。-- そう考え萎えなければ居心地が悪すぎるからだ。
それは、政府、政治家、官僚が、偏見なしで世界を見、そのさまざまなシグナルを私欲ぬきで解釈し、客観的な、ほとんど科学的な厳密さをもって「事実」と「判断」をわけることができるという、理想に満ちた誤解だ」
政治や官僚制が理想的なのではないと、だれでも知っている。でもやっぱり人は「居心地のいい嘘」のほうをとりあえず採用する。
「『道義的責任を負わない』という信念は、政府官僚に広く受け入れられている。『言われることをやるだけだ』と。
この思考習慣は、まぎれもなく『道義的無感覚』という強力で危険なものにつながる。湾岸戦争の緊急事態ユニットでは、感覚の麻痺というよりは、完全な無関心のように感じられた。自分たちの行為の道義的影響について心配するのは、僕たちの仕事ではない、というだけだった。心配すべきだと考えたりすれば、『救いがたくナイーブ』だとみなされただろう」
著者はイラク問題についての自分の意見を英国外務省に提出し、勤めをやめる。「イギリス外務省で実践した従来の外交で、自分は道徳観を失い、信条も意義も見失った」からである。「自分が運営と擁護に手を貸したシステムは、世界の現実からも、自分が大切にしているものからも、外れていたような気がする」。著者はそう述懐する。
いまは世論の圧倒的多数が組織人である。私は著者の声を、組織人の良心の声として聴いた。こうした「個人」を生み出すのが、英国社会の良識であろう。ひるがえって、この国ではどうであろうか。
##引用終わり
Independent Diplomat は独立外交官と訳されている。現状、こう訳すよりしょうがないのだが、一般人に分かり易くいうには、養老が冒頭で言っているように<雇われ外交官>がピタリである。<政府から独立した(民間の)>外交官、の意味だ。したがって<外交官>じゃなく、政府外の外交専門家とでも訳すのが意味上は正しい。Diplomat とは 外交官、だけではなく、未組織の外交(専門)家もいみするはずである。著者カーンロスは英国外務省をやめて、代わりに、英国を代表とする「大国」が仕切る国連外交の世界で、コソボとか、ソマリアとか、自分たちの声を聴いてもらえない弱者達を代表する「雇われ外交官」となって働いた。
ところで。。。1ヶ月前におなじ毎日新聞が、書評欄で
『岡本行夫現場主義を貫いた外交官』 著者=岡本行夫 五百旗頭真 伊藤元重
をとりあげてべた褒めしていたのには、わが目を疑った(今週の本棚:森谷正規=書評者)。http://mainichi.jp/enta/book/hondana/news/20090315ddm015070040000c.html
http://item.rakuten.co.jp/book/5923903/
引用する(湾岸戦争を論じている):
「 その後の輸送協力、物資協力では、北米局北米一課長であった岡本を始め担当官が奮闘するが、航空機、船舶のチャーターなどでつまらない障害が続出して、順調に進まない。申し訳ないがドタバタ劇の連続で、経緯を書くと長くなるが、ことが戦争となると協力行為でさえ各種の法律が障害となるのが、日本の実情だ。だが、懸命に努力する人々が官にも民にもいて、それなりの成果があった。中東派遣軍の総司令官からの感謝状が届いている。
しかし、結末は無残であった。90億ドルもの追加拠出をしたにもかかわらず、勝利パレードに約30カ国の大使が特別席に招待されたのに、日本国大使は一般席であった。
この直後に、岡本は外務省を退職したが、23年の勤務の間、現場で動き回るのが楽しみであった。その現場は凄(すご)い。サミットは1975年に開かれた第一回から関っていて、メモ取りを命じられ、それは6年も続いて、各国の首脳にじかに触れることができた。サミットは首脳それぞれの個人としての実力と識見が試される苛酷(かこく)な知的バトルの場だと岡本はとらえたが、欧州の首脳たちが哲学的な発言をして教養の勝負であり、そうした場でアメリカの大統領の存在感は大きくないことを見てとった。こうした現場で、非常に深い国際感覚を養うことができるのだ。
岡本は、イラン制裁、モスクワ・オリンピックのボイコット、米艦船の核持ち込み疑惑、池子米軍住宅建設問題、日米武器技術交流、FSX開発など安全保障にかかわる重要な外交事例に携わっていて、その内情をいま知ることができる。多くは外交でありながらむしろ国内問題になっていて、与党、野党、地方自治体、住民、各官庁などのぶつかり合いである。それに真正面から切り込んでいくのが、岡本のやりかたであった。こうした実情を詳しく知ってこそ、外交が身近なものになって、私たちも真剣に考えることができる。
岡本は、昇格すると自分が切り込み隊になれず、燃えなくなるのは面白くないと、45歳で退職し、コンサルタントとして自立の道を歩んだが、首相補佐官に二度なって、外交に関ってきた。
一度めは橋本内閣での沖縄問題担当だが、梶山官房長官に「沖縄は気の毒です。配慮してやってください」と言って、では貴方(あなた)是非にと頼まれて受けた。沖縄振興に全力を上げて取り組んで、名護市への国立高専の設置など多くの成果を上げた。補佐官というと表に出ないようにも見えるが、岡本は沖縄各地とそれに各省庁を走り回った。
二度めは小泉内閣のイラク戦争担当であるが、アメリカとの深い付き合いが買われた。岡本はイラク戦争に反対で新聞にも書いたが、戦争の直前にアメリカに行って、3日間で十数人の要人と会って、まず反対論を述べて、戦争の見通しと日本の立場について、突っ込んで話し合った。
このような岡本の行動を知って、いま火だるまになっている官僚について深く考えさせられる。「渡り」は論外であるが、官僚の後半生がどうあるべきかは重要な問題である。若い時には猛烈に働いていて、岡本は残業時間は200時間を越えていた。重大な職責を全うする意気込みで頑張るのだが、岡本はさておき、一般には将来の栄達も頭にあるだろう。それが望み得ないとすれば、優秀な若者が官僚を志望しなくなるが、それで良いのか。」
## 引用終わり。
「戦争の直前にアメリカに行って、3日間で十数人の要人と会って、まず反対論を述べて」。。。<まず>反対論を述べて、が笑わせる。
「渡り」は論外、として、<自立>すればいいものでもない、ということが岡本行夫をみればわかる。コンサルタントとして政府を支援するのならこれほど政府にとって有り難い<自立>もない。ニッポンには、クレバーな男もいたものである。政府からいくらで雇われたのか知らないが、岡本が受け取ったコンサルタント料を明らかにするなら、そのお値段によっては、森谷の心配する<優秀な若者が官僚を志望しなくな>っても、ちっとも心配はいらないだろう(国民にとっては、<渡り>をやってくれていたほうが、なんぼかマシだろうが)。
外務省は、カーンロス氏その他、「雇われ外交官」を大量採用してはどうか。すくなくとも、<渡り>の心配はなくなるだろうし、現状より、マズイ外交、というのも考えにくい。
『岡本行夫現場主義を貫いた外交官』という書名は正しくない。岡本は民間コンサルタントとして<活躍>したのであるから。『岡本行夫:米国にぬかづく「日本の雇われ外交官」』がピタリである。
外交官も雇われ外交官も、政府の方針のもとに動くテクノクラートである。優秀であってもなくても、行動の成果を認証するのは政府である。政府がアホでは雇われであろうとなかろうと、外交官の活躍の場はないハズである。
日本が雇用するなら、Independent Government(IG)かな。
#####
本書へ寄せられた推薦
光り輝くような若手外交官だった著者は、「ブッシュの戦争」に付き従った英国に深く絶望しキャリアを捨ててしまう。だが、問題の核心はより深いところにある。主権国家のくびきに縛られた現代外交のシステムは、戦争や地球温暖化といった難問に挑むには無力だと悟ったからだ。地球市民のための自立した外交官になろう――。
本書はその軌跡を鮮やかに綴った現代の「出エジプト記」だ。
外交ジャーナリスト 手嶋龍一
-----------------------------------------------------------------
現場の第一線から届いた外交の実像。こんな本はめったにない。著者は、今日の外交における多くの誤りを見きわめ、説得力のある解決策を示している。
投資家、オープンソサエティ財団 ジョージ・ソロス
-----------------------------------------------------------------
外交官の愚かさ、無知、無関心が明快かつ正確に描かれている。著者は、その誠実さ、文章に込められた機微と品位、自分を見つめる透徹したまなざしによって、書き手としてだけでなく一人の人間として、深く感動を与えてくれる。
作家 ロリー・スチュワート
目 次
第1章 国連安全保障理事会
第2章 大使館
第3章 選ばれた事実
第4章 理想に満ちた誤解
第5章 対立の構図
第6章 国益とは何か
第7章 道義的責任
第8章 何かが欠けている
第9章 戦争への道
第10章 独立外交官
第11章 外交の終わり
###
著者紹介2007年3月
Rebellious Diplomat Finds Work as Envoy of the Voiceless
http://www.nytimes.com/2007/03/03/world/europe/03ross.html
●他の書評
独立外交官 国際政治の闇を知りつくした男の挑戦
http://www.ringolab.com/note/daiya/2009/02/post-922.html
##引用
イギリスのエリート外交官だった著者は15年間に、パレスチナ問題、湾岸戦争、アフガニスタン侵攻、イラク侵攻など現代史の最前線で活躍してきた。先進国の代表者として著者の属した「われわれ」は常勝チームだった。しかし、国連常任理事国のような一部の有力国が圧倒的な情報力や交渉力を持ち、多くの貧困国は発言権さえ与えられない国際外交のありかたに大きな疑問を持った。そこでイギリス外務省を退職し、外交コンサルティング組織「インディペンデント・ディプロマット」を設立、国際社会で弱い立場の国や人々のために自身の能力と経験を使うことを決意した。
著者は国際外交の問題点を次々に指摘していく。民主的でないこと、外交官と国家の同一視、エリートと市民の無責任な協定関係、国際関係を競争ととらえる思考法、時代遅れの国益の駆け引き思考、事実認識の構造的欠陥、「世界は理解可能だ」という思い上がり、根深いところの不均衡、不公平など。
問題は山積みだが、国際関係というメタレベルのコミュニケーションには愛やこころ、哲学がないことが最大の問題であり、著者が外務省を辞めて独立した最大の理由でもあるように思える。極めて有能で合理的判断のできる外交官達が、有能で合理的であるが故に人間らしさを失っていく様子がこの本に描かれている。
##
読者書評@日本
http://goods.hanamoku.jp/detail/4862760457.html
書評(英文)
Independent Diplomat, by Carne Ross
Cameos from the corridors of power
By Anne Penketh
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/independent-diplomat-by-carne-ross-440345.html
書評への著者の応答
Volume 54, Number 17 · November 8, 2007
'Are Diplomats Necessary?'
By Carne Ross, Reply by Brian Urquhart
http://www.nybooks.com/articles/20802
Independent Diplomat (ID) という非営利団体がある。 カーンロス(著者)が設立者だから、上記書名はこの組織名を直接指しているのかもしれない。
http://www.independentdiplomat.com/
Independent Diplomat (ID) is a unique new non-profit venture in the world of international relations, diplomacy and conflict prevention.
TIME誌記事
Carne Ross
By Jumana Farouky Thursday, Apr. 03, 2008
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1727734,00.html
##
原著
http://www.amazon.com/Independent-Diplomat-Dispatches-Unaccountable-Politics/dp/0801445574/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1239486400&sr=1-1
アマゾン米の評価は☆☆☆。評者はたったの二人
http://www.amazon.co.uk/Independent-Diplomat-Dispatches-Unaccountable-Politics/dp/1850658439
アマゾン英、では☆☆☆☆☆。でも評者はたったの一人。
##読者評引用
By Joeinbrux - See all my reviews
This is a fascinating insight into the world of international relations. It discusses crucial questions regarding how diplomacy works, the shortcomings of international relations as an academic subject, democratic deficits in international organisations and a range of other issues.
No student of international relations should graduate without having read this book first.
#
Diplomat at large
Stephen Moss
The Guardian, Monday 20 June 2005
http://www.guardian.co.uk/politics/2005/jun/20/interviews.iraq
He was a Foreign Office diplomat on the fast track to an ambassadorship and knighthood. So why, after 15 years at the top, did Carne Ross turn his back on the power and the status to go freelance?
大佛次郎論壇賞、湯浅誠氏の『反貧困』に <反=社会>賞をケーダンレンが同時受賞 [Book_review]
大佛次郎論壇賞、湯浅誠氏の『反貧困』に
http://www.asahi.com/culture/update/1213/TKY200812130197.html
第8回大佛次郎論壇賞(朝日新聞社主催)は、反貧困ネットワーク事務局長、湯浅誠氏(39)の『反貧困――「すべり台社会」からの脱出』(岩波新書、税込み777円)に決まった。賞牌(しょうはい)と副賞200万円が贈られる。
ますます深刻さを増す、この国の「貧困」の問題を、どうとらえ、いかに解決すべきか。受賞作は、この課題に正面から取り組む。貧困は、社会と政治に対する問いかけであり、その問いを受け止め、立ち向かえる強い社会を作ろう、という著者のメッセージに、選考委員全員の強い支持が寄せられた。
贈呈式は、09年1月28日、東京・日比谷の帝国ホテルで、朝日賞、大佛次郎賞と共に行われる。
湯浅誠『貧困』は、<溜め>とか<居場所>というボキャを新設して、派遣労働者~ワーキンブプアの実態をあきらかにし、なにが彼らに必要か、を論じたレポートである。(もっとも、溜め、は使い慣れた言葉で言えば、セキュリティネットのことであり、もっと遡れば 憲法が保障する、基本的諸権利のひとつである)
私はこの著作というより、湯浅誠たちが実践している<もやい>活動に賞を与えたい。政治や企業、マスゴミがかれらの行動から<モラル>を脱落させている今、貧困層にとって、<もやい>が繰り広げている活動は希望の星となっている。
同じ人間として生まれているのにどうしてこういう苦しみを味わわなければならないのか。この給与では生活できない、子供を抱く気にもなれない。死にたい。。。<もやい>が手を差し伸べているのはこういう叫びをあげている人たちである。 こういう境遇のひとたちを生み出したのは誰の責任か?
大量の解雇者を出しながら、正社員や役員の給与賞与はカットするでもなく、株主への配当は増額し、かつ、史上最高の内部留保を計上しながら、「内部留保を切り崩してまで派遣の雇用を守ろうとはおもわない」とシャーシャーとうそぶくトヨタの経営陣。
<合法的>であれば人の命を奪っても見て見ぬふりをする人間たちを経営者として奉ずるのが現代の日本流経営である。その<法律~派遣法>とは、産業界~ケーダンレンがカネで、国会議員と政府を買収して立法化されたモノである。
#
なお、特筆すべきこととして。。。今回、大佛次郎論壇賞とともに、<反=社会>賞が、貧困層を生み出した元凶である ケーダンレンに対して授賞され、副賞として<反=賞金>2000億円を解雇された労働者支援活動に支払うことを課された。本来、派遣労働者に対して支払われるべき金額の一部として、である。 関係者による続報によれば。。。経団連組長~御手洗氏は受賞を拒み、<反=賞金>支払いも拒否しているとのことである。同時に<反社会的=無作為>賞が、 衆参両院議長ならびに代々の厚労大臣、さらに、<派遣法>をみとめた既成労組に授与されたが、いずれも受賞を拒んでいるらしい。
<もやい>とは:
http://www.moyai.net/
トヨタ赤字の意味するもの トヨタ・キヤノンは市場から撤退せよ
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2008-12-23
これが人間の住む国か
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2008-12-17
トヨタ車をボイコットせよ 経団連は民主政治の敵である。
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2008-11-17
祝・開村 派遣村@日比谷公園
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2008-12-31
追悼 加藤周一 加藤周一が観察し、考え、書いたこと [Book_review]
「中肉中背、富まず、貧ならず。言語と知識は、半ば和風に半ば洋風をつき混ぜ、宗教は神仏のいずれも信ぜず、天下の政事については、みずから青雲の志をいだかず、道徳的価値については、相対主義をとる。人種的偏見はほとんどない。芸術は大いにこれをたのしむが、みずから画筆に親しみ、奏楽に興ずるには至らない。---こういう日本人が成りたったのは、どういう条件のもとにおいてであったか。私は例を私自身にとって、そのことを語ろうとした。
題して「羊のうた」というのは、羊の年に生まれたからであり、またおだやかな性質の羊に通うところもなくもないと思われたからである」
岩波新書『羊のうた』(1968/8/20)あとがき、から。
『羊のうた 正・続』は加藤周一が幼児から壮年(1960年、新安保条約の成立)にいたるまで加藤周一が観察し、考えてきたことを書き記したものである(初出は朝日ジャーナルの連載)。冒頭の2つの章「祖父の家」と「土の香り」は加藤周一を知るのに重要である。
「祖父の家」から:
「前世紀の末に、佐賀の資産家のひとり息子が、明治政府の陸軍の騎兵将校になった。日清戦争に従軍するまえに、家産を投じて、馬二丁と馬丁を貯え、また名妓万龍をあげて新橋に豪遊し、イタリアに遊学しては、ミラノのスカラ座にカルーゾーがヴェルディやプッチーニを唱うのを聞いた。それが私の祖父である。」 (p1)
「私の父は祖父を好まず、その「放蕩」を非難していた。妻以外の女との交渉は、悪事のなかの最悪のものであった。カトリックの尼僧が経営する学校で育った母は「放蕩」を悪事とすることで父とちがわなかったろうが、そのことを非難するよりも、むしろ説明しようとしていた。」(p7)
「私は一体こういう祖父の血をうけついでいるのだろうか。しかしそもそも血統なるものを、私は、若干の遺伝的体質以外のことについて、まったく信用しない。そういうことがあるかもしれないが、たとえあっても知ることができないとすれば、考えの上でそれを除外する他ないだろう。そういうことよりは、子供の私が、身の廻りに「放蕩者」といわれる人物をもっていて、その人物について、おそらく多くの失敗を想像することはできても、悪事を想像することはむずかしかったという事実に、意味があるにちがいない。」(p9)
「土の香り」から:
「私は田舎で暮らしたことがない。しかし田舎とのつながりが、全くなかったわけではない。父の生家は、関東平野の熊谷にちかい村で、徳川時代には帯刀を許された名主の家である。1920年代には、村の森林と耕地の大部分をもち、みずから農を営みながら、大勢の小作人に君臨して、豊かに暮らしていた。(略) 次男、つまり私の父は、浦和の中学校に入ったときから村を離れ、東京で医を業としていたので、農家を襲ぐことは問題にならなかった。」 (p13)
「しかし私と田舎との関係が、一方では村の子どもたちから見られる関係、他方では宴会の男女を見る関係からはじまった、ということには、注意しておく必要があるかもしれない。相手に見られながら相手を見るという相互的な関係は、はじめからなかった。私は他所者であり、おそらくいつまでも、他所者として生きるだろう。それは必ずしも田舎との関係が、私にとって薄かったということではない。」 (p24)
『続・羊のうた』には、東京帝国大学医学部と米国軍医師団が共同で45年秋、ヒロシマに送った「原子爆弾影響合同調査団」の一員として加藤周一は原爆で崩壊したヒロシマを訪れたときの見聞を記している。『続・羊のうた』の「広島」の章:
「広島には一本の樹さえもなかった。見わたすかぎり瓦礫の野原が拡り、その平坦な表面を縦横の道路と掘割りの水が区切っていた。石垣の建物のいくつか、崩れ落ちずに立っていたが、その窓は破れ、壁は半ば崩れて、近づくと建物を透して向こう側の青空が見えた。人の住むことのできる家は一軒もなく、しかし、その焼け野原には陰のようにいつも誰かが彷っていた。国民服の男の埃に汚れた顔は、放心して現(うつつ)ないようにみえた。子供たちの顔は、火傷の瘢痕(はんこん)にひきつり、髪の抜けた女は、風呂敷で頬かぶりをして、太陽の下を逃げるように歩いていた。爆心から遠く破壊を免れた郊外の病院には、まだ病人があふれていて、歯ぐきを腫らし、傷口から膿を流し、高熱に昼も夜も苦しんでいた。それが二ヶ月まえでは広島市民であった人々の生きのこりであった。
1945年8月6日の朝まで、そこには、広島市があり、爆撃を受けなかった城下町の軒並みがあり、何万もの家庭があって、身のまわりの小さなよろこびや悲しみや後悔や希望があったのだ。その朝突然、広島市は消えて失くなり、市街の中心部に住んでいた人々の大部分は、崩れた家の下敷になり、掘割にとびこんで溺れ、爆風に叩きつけられて、その場で死んだ。生きのびた人々は、空を覆う黒煙と地に逆まく火焔の間を郊外へ向かって逃れようとして、あるいは途中で倒れ、あるいは安全な場所に辿り着くと同時に死んだ。さらに生きのびた人々も、田舎の親類家族と抱合い、九死に一生を得たよろこびを頒つと思う間もなく三週間か四週間の後には、髪の毛を失い、鼻や口から血を流し、やがて高熱を発して、医療の手もまわらぬままで死んでいった。それから二ヶ月、辛うじて難を逃れた人々は、親兄弟を失って呆然とし、みずからも「原爆症」の恐怖に怯えて、追いたてられた獣のように、あてもなく焼け野原を歩いていた。もはやそれは嘗ての広島市民とは別の人間であり、あたかもそのことが無かったかのように、彼らが以前の人間にたち戻ることはできないだろうと思われた。
(略)
理解を越えたもの、すなわちそこから意味を抽きだした時間に、その意味の直ちにいろ褪せるもの、しかし、それと向きあっている限り人間の全体を抗し難く規定してやまぬもの -- 私はそれを経験しなかった。しかし経験した人々を見たのである。広島についてのすべての言葉は、それがどれほど納得できるものであっても、聞く度に私に「ああ、それはちがう、どこかちがう」という気をおこさせた。 (略) 私は広島を見たときに、将来の核兵器については何も考えていなかった。後になって、核兵器についても考えるようになったが、そういう私自身の考えと、広島の人々を沈黙させた経験との間に横たわる遥かに遠い距離を、私はいつもくり返し想い出したのである。」
 hiroshima after bombed
hiroshima after bombed「広島の第一印象は「広島はこんなにも平らだったのか」ということでした。建っている家が一軒もない」(講演『ヒロシマ・ナガサキ50年』)
#
加藤周一の代表作は何だろうか? わたしは、
「天皇制を論ず」1946/3
「日本文化の雑種性」1955
「日本文学史序説」1980
を挙げたい。
日本文学について加藤周一は1960年前後から多くの論文を発表しており、「序説」は60年代のカナダの大学での講義、さらにそれを文字化した朝日ジャーナルへの連載を元にしている。『序説』の姉妹編として『日本美術の心とかたち』(1997、著作集20。これは1987年のNHK番組を出版したもの)、さらに、比較文学的見地から時間と空間の表現の特徴を整理した『日本文学における時間と空間』(2007)がある。
鶴見俊輔は、加藤の評論中もっとも重要な作品として<雑種文化論>をあげている。
「それ(雑種文化論)は、異国からきたという区別なく、日本文化の中に織りこまれ、とけこんでゆく事実に注目したからである」 (2008/12/10 毎日新聞夕刊、『加藤周一さんを悼む』)
<雑種>とはなかなか伝わりにくい概念である。最近、上野千鶴子(平凡社の加藤周一セレクション5の解説、1999)がその解釈を述べており、小坂井敏晶も『異文化受容のパラドクス』(朝日選書、1996)で加藤<雑種>説の修正を試みている(文化を受容するさいの<免疫システム>)。
加藤周一の言いたいのは次のことである。
「。。。日本の文化の特徴は、その二つの要素(注:西洋的、と、日本的と)が深いところで絡んでいて、どちらも抜き難いということそのこと自体にあるのではないかと考えはじめたということである。つまり、英仏の文化を純粋種の文化の典型であるとすれば、日本の文化は雑種の文化の典型ではないかということだ。私はこの場合雑種という言葉によい意味もわるい意味も与えてない。純粋種にしても同じことである。よいとかわるいとかいう立場にたてば、純雑種にもわるい点があり、雑種にもおもしろい点があり、逆もまた同じということになるだろう。雑種とは根本が雑種だという意味で、枝葉の話ではないということをはっきりさせておく必要がある。枝葉についてならば英仏の文化も外国の影響を受けていないどころではない。インドや中国の場合にはなおさらであって、日本の文化を特に区別して雑種の典型だという理由はない。」 (加藤周一セレクション5から『日本文化の雑種性』 p42)
「日本主義者は必ず精神主義者となり、日常生活や下部構造がどうあろうと、精神はそういうものから独立に文化を生みだすと考える他はない。ところが念の入ったことに、そう考えた上で行う議論の材料、つまり立論に欠くことのできない概念そのものが多くは西洋伝来の、和風からは遠いものである。自由とか人間性とか、分析とか綜合とか、そういう概念を使わずに人を説得する議論を組みたてることは、議論の題目によっては不可能であろう。日本の文化の雑種性を整理して日本的伝統にかえろうとする日本主義者の精神がすでにほんやくの概念によって養われた雑種であって、ほんやくの概念をぬきとれば忽ち活動を停止するにちがいない。日本の伝統的文化の影響から区別して拾い出すなどということは、今の日本では到底できるものではない」 (同、p43)
私なりに言い換えれば、純粋種とはたとえば、鉄(純粋なFe)あるいは炭素(C)であり、これは科学的には純粋であるけれど、生活の用途としての使い道は制限される。この二つを化合させて(溶融)、<鋼鉄>(スチール)に変成すれば硬度が高まり、溶けにくく、錆びにくい、したがって用途が一挙に広がる。<純粋>も<雑種>も、価値があるかどうかは条件による。無条件の価値などはない、その観点からすれば純粋種と雑種は等価である、ということだ。純粋を誇るのでもなく、雑種であることを卑下するのでもなく、開き直るのでもない。(<雑種>の命名はいかにもマズイし誤解を与える。ついでにいえば、純粋種、雑種というときの<種>は、生物における種とは異なり、実体のない、すなわち、人間がつくりあげた虚構である、とおもう)。
この短い論文は先見の明に満ちた問題作といえる。雑種の概念を使って論文中で、日本の近代の概念の洗い直しも迫っているのだ。
さらに、この<雑種>概念を文学や思想に拡大させて適用し(外来の思想を、いかに変容させて日本土着思想に織り込んだか)、日本の土着思想を探ろうとした試みが『日本文学史序説』である。『序説』とは、土着思想を近代合理主義に照らして否定し、さらに、ニッポンを愚劣な戦争に巻き込んだ天皇制国家機構を生み出した特殊日本的な世界観がいかに生まれたのかを探るための試論であった。加藤周一が戦中、戦後から貫いた思考を展開させた書といえる。しかし、『序説』のなかでは<土着思想>が何であるかはついに明らかにされていない。丸山真男のいう<古層>とおなじく、実体のない単なる補助線的な中間概念=作業仮説、ではあるまいか。。。
1946年3月に発表した「天皇制を論ず -- 問題は天皇制であって、天皇ではない」(加藤周一セレクション5に収録)は、痛烈な天皇制批判文書である。この論文を引くのは控えるが、加藤周一セレクション5の該当論文への著者による追記を掲げておく:
「。。。1945年、敗戦が事実上決定した状況のもとで、降伏か抗戦かを考えた日本の支配者層の念頭にあったのは、降伏の場合の天皇の地位であって、抗戦の場合の少なくとも何十万、あるいは何百万に達するかもしれない無益な人命の犠牲ではなかった。彼らにとっては、一人の天皇が日本の人民の全体よりも大切であった。その彼らが、降伏後、天皇制を廃止すれば、世の中に混乱がおこる、といったのである。そのとき彼らに向かって、無名の日本人の一人として、私は「天皇制を論ず」を書き、「恥を知れ」と書いた。日本国とは日本の人民である。日本の人民を馬鹿にし、その生命を軽んじる者に、怒りを覚えるのは、けだし愛国心の然らしめるところだと思う」 (セレクション5、p207)

日本の文化・思想の型を<時間と空間>概念を、世界の他文明のそれと比較して特徴を論じたのが『日本文化における時間と空間』であり、さらに、焦点を日本美術史にあてて論じたのが『日本美術の心とかたち』である。『日本美術の心とかたち』を読みはじめたのは、実は、数日前からである。読み始めた途端、わたしは、その文章の端正、簡潔にして、リズム感のある行文に一驚した。これは『文学史序説』以上の傑作と言えるのではないか、と。
『心とかたち』は、まず次のように始まる。
<はじめに形ありき>
「 縄文の形
日本列島の住人は、旧石器時代、その内陸に住んでいた。新石器時代には海岸へ出て、およそ一万年ぐらいの間、紀元前200年頃まで外部から孤立した条件の下で、土器をつくって食物を煮たり貯えたりし、いわゆる「貝塚」を残した。その土器が「縄文土器」である。
日本の美術史をそのときから始める理由は、何よりもそこに形と文様のおどろくべき独創性があったからである。たとえば深鉢の開口部をとりまいて、渦を巻きながら火焔のように立ち昇る複雑で立体的な装飾は – それが火焔であるか否か、どういう象徴的意味をもつかは別として、その力強く、激しく、動的な形が、その後の日本の造形的世界にみられないばかりでなく、世界の他の地域においてもおそらく土器としては例が少ない。また縄文土器は、本州の東部を中心として日本全土に及び、地域的にも時代的にも、その形の豊富な多様性を示す。旧大陸でも新大陸でも、また南太平洋でも、多くの新石器文化が知られているが、これほど独創的で多様な形を生みだした例は多くないだろう。日本の新石器時代、縄文時代の文化が、その少い場合の一つであることはあきらかである。
もし美術史を人間の生みだした形の歴史と考えれば、日本列島にこのような独特の形の土器が出現したときから、日本の美術史が始まったのである」 (著作集20,p5)
あるいは、<水墨・天地の心象>。
「 抽象的表現主義
水墨画は、紙(または絹布)に墨を含ませた筆で描き、時に淡彩を加え、時に彩色を用いない。彩色を用いない場合の材料と用具は、書に同じ。筆は線を引くのに適し、面を塗るのには適しない。したがって、水墨画は、対象の輪郭を描くことから始り、その線は、太く細く、墨の濃淡も自在で、表情に富む。線の性質を決めるのは、もちろん、筆の種類にもより、墨に加える水の量にもよるが、紙と筆先の接触面、および筆を動かす速さの加減による。一点につけた筆から墨は滲みだすから(毛細管現象)、筆はある速さで動かさなければならない。しかも一度引いた線を、画家は手直しすることも、消すこともできない。すなわち原則として、水墨画は一気に描きあげられなければならない」 (p159)
この文章を引き写しながら、わたしは谷川俊太郎の詩集『定義』を思い浮かべた。
##
加藤周一とサルトルについて。
フランスの哲学者サルトルは加藤周一の友人であり、加藤はこの哲人にして政治的行動家を敬愛してやまなかった。サルトルとの交渉がなければ加藤が後年、護憲運動を発起し、死ぬまで活動を続けたか、疑わしいとさえ私は思う。1966年サルトルは、ボーヴォワールを伴って来日し、数多くの講演と座談会、インタビューをこなした。1966年10月12日に、日本滞在日程の締めくくりとして行われた『現代状況と知識人』と題する座談会を再読した(『加藤周一対話集2』かもがわ出版。座談会参加者はサルトル、ボーヴォワールのほか、大江健三郎、阪本義和、鶴見俊輔、日高六郎。司会を加藤周一がつとめた)。この座談会は核兵器やベトナム戦争など政治的な話題に及ぶ白熱したものであった。締めくくりに司会者・加藤周一から「最後に広島の印象についておうかがいしたいのですが」との求めに応じて、サルトルとボーヴォワールが3頁にわたって<対話>を繰り広げている(この座談会の直前にサルトルとボーヴォワールは広島を訪れている)。この座談会を、以前わたしは読んでいるはずなのだが、今回、読み直してショックをショックと、感動を同時に受けた。サルトルとボーヴォワールが、短期間の広島滞在にもかかわらず、表面的でない認識に達していること、二人で交わした<対話>の絶望と深さ、に対してである。以前読んだとき、恥ずかしいことに私はこれに気づかなかった、あるいは、すぐに忘れてしまっていた。
サルトル: 実に悲惨な印象を受けた・・・・・・・。
ボーヴォワール: その通りだわ、実に悲惨だった・・・・・・・。
サルトル: 悲惨な印象を受けた。この点でこそ、大江氏の提唱する運動が正当化されると思うのです。つまり、広島は近代的な都市だ、まるで原爆など落ちなかったような近代都市だ。苦しんだ人々のことなど全く忘れてしまっている。原爆記念館はある、しかしそんなものは何の役にも立たない、第二の死だ。一方に・・・・・・・。
ボーヴォワール: 一方に、全く打ち棄てられ、自ら非人(パリア)であると考えているような人々がいる・・・・・・・。
サルトル: 完全に打ち棄てられている。しかも同じ広島市民から連帯意識も持たれていない。政府が無為無策でいるだけではない、市当局も・・・・・・・。
ボーヴォワール: 彼らになにも与えられないでいる。
サルトル: 市当局も彼らのために、少額でも特別税を徴収することを考えない。彼らの救済のためにはなんでもないことなのに。しかもこの人たちは自分の生きていることにむなしさを感じているのだ。彼らは・・・・・・・。
ボーヴォワール: 心理的には非人(パリア)意識を持っていたのです・・・・・・・。
サルトル: 彼らは非人だ。実に酷いことだ。この事実こそ、原爆が全く忘れ去られつつあることを証拠だてている。またそれだからこそ、平和運動を推し進めることが必要なのだ。しかし、実になにか・・・・・・・。とにかく広島での印象は無惨なものだった。今なお苦しんでいる被爆者を見たから無惨なのではない。彼らは少なくとも看護を受けている。そうではなくて逆の理由からだ・・・・・・・。
ボーヴォワール: 彼らの肉体的苦痛は精神的苦痛に比べたらなんでもないからなのです・・・・・・。
サルトル: そうだ、その上彼らは精神的に苦しんでいる人々なのだ。彼らはたとえば彼らの体験について、こういうことを言っていた、「確かに当時、私は大変苦しみました。しかしそのこと自体は余り重大ではないのです。ただ社会には復帰できませんでした。やっと両手が使えるようになってから、復帰できたのです、働くことができたからです。」彼らが求めているのは唯一つ、仕事だ。ところが、彼らにはこの仕事が与えられないことが多い。第一肉体的に弱い人々が多いから困難だ。彼らには被爆者相互の連帯意識もない。彼ら自身そう言っている。だから、被爆者の間にさえも、連帯的運動を組織できなかった。そこへもってきて、さまざまな原水爆禁止運動があり、反目しあっている、しかも、被爆者の置かれている事態を利用している。そこにさらに、広島という名のあの都会があるというわけだ・・・・・・・。
ボーヴォワール: 広島がシンボルとして利用されているのを見るとゾッとする。一方で、被爆者は完全に忘れられ、政府の援助も受けていないのに。なにかこう、見るに忍びない気がしました・・・・・・・。
サルトル: そうだ、本当に見るに忍びない・・・・・・・。
ボーヴォワール: シンボルがあることは重要です、とくに広島を語るときには。私たちだって、広島にシンボルを見出すつもりでいたのです。ところが、被爆者に会ってみると・・・・・・・。
サルトル: そう、彼らに会うために病院に行ったのです。不愉快なことになるかもしれぬとは思っていた。しかし全然そうではなかった。もちろん、そういう見地から彼らに会ったのではないからだ。そうではない。病室に入ったときは、カメラマンが25人もいて、テレビ局の人間もいた。そんななかに、婦人の被爆者が三人、われわれは花をもたされて・・・そういうことが実に不愉快だった・・・・・・・。
ボーヴォワール: 私は花束を持たされて、婦人のひとりに贈ることになって・・・・いかにも不愉快でした。しばらくしてやっと彼女たちと話すことができたのですが、彼女たちの言ったことはそれはもう堪え難いことでした。それに彼女たちの態度も慄然とするものでした。それも、だれひとりとして、あの人たちが全くうちひしがれた人たちであることを知ろうとしないからです。それに、ほら貴方に言ったひとがいるでしょう・・・・・・・。
サルトル: ああ、あの・・・・・・・。
ボーヴォワール: あの、年寄りのなかにはなにか自分の罰のように考える被爆者がいると言っていたひと・・・・なにか自分が悪いことをしたに違いないなどと・・・・・あの人たちは、全く打ち棄てられている・・・・・本当に堪え難いことでした。
加藤: 大江氏は『ヒロシマ・ノート』でまさにそのことを言っているのです。
ボーヴォワール: ああ、あの本を書いたというのはこの方ですか。やはり同じ印象を持たれたわけですね。 (『加藤周一対話集2』p245~247)
加藤周一は講談社『人類の知的遺産』シリーズの一冊である『サルトル』を担当し、サルトルの伝記と著作解説を行っている(加藤周一著作集16に収録)。加藤周一は、日本滞在中のサルトルとの討論から受けた印象を次のように述べている(著作集16,p191)。
「会話の知的密度は高く、具体的な観察から抽象的な分析に移り、また逆に抽象的な水準から具体的な話題へ移る精神の働きは、おどろくべき速さを備えていた」 (p191)
「サルトルはどこでも常に考えていた。しかし誰かが彼に話しかければ、それが予定された会合でも、行きずりの出会いでも、常に注意深く最後まで相手の話を聞いた。彼の前にあらわれるすべての人間は、彼と対等であった。世界的な名声の有無、知的能力の隔絶ということが、たしかにあって、しかしそれを無視する意志、あるいはむしろ習性となった態度が、私の知る限り一度でもあいまいであったことはない。それは傍から見ていても、素晴らしい見事な光景であった。彼は人間を決して差別しない、アルジェリア人も、ユダヤ人も、女も、労働者も、学生も。私が近づいて見たサルトルは、人間的な温かみがその身体の全体から自然に溢れだしてくるような人物であった。そこには優しさがあり、誰に対しても開かれた心があった。」 (p193)
長々とサルトルについて引用するのは、もちろん、私が著作から抱く加藤周一の印象と、サルトルの姿があまりにもピタリと、重なるからである。
「サルトルに会ったら、彼の考えを訊いておきたいと思うことが私にはあった。弁証法は世界を叙述するために必要であるか(この場合の「必要」は、論理的な意味での「必要」である)。「必要ではない」と彼は言下に応じた。それならば、弁証法は認識を導く原理であり、世界の現実を発見するための手段heuristiqueであると考えているのか。「その通りだ。私は弁証法がheuristiqueだと繰り返しいってきたのだ」 -- それは立ち話であった。」 (p192)
サルトルの著作は70年前後、私も夢中になって読んだ。とくに、『シチュアシオン』、と、『弁証法的理性批判』、『弁証法的理性批判』の序説である『方法の問題』。『方法の問題』でサルトルが述べた探究の論理(手段)としての<前進的・遡行的方法>こそは、弁証法なのだ(発見的手法としての)、とサルトルは言っているのであろう。わたしは、デューイのプラグマティズム(探究の論理)と、これを重ねて理解した。
ひとが存在することの意味は、その人を失ってからでないと覚知できない、ということを、加藤周一においてわれわれは再確認することになる。
加藤周一が毎日新聞のために書いたサルトル追悼文、その冒頭と末尾の文章をかかげる(毎日新聞、1980年6月3~4日):
「交通労働者の罷業でバスも地下鉄も止まっていた1980年4月のニューヨークの客舎で、私はサルトルの死を聞いた。人間は死ぬ、サルトルでさえも。 --- 私は頻りにその人のことを思った。」
「彼は避けがたい死が近づくのを知っていたが、死についてではなく、生きることの意味について、考えることをやめなかった。」
世界を異邦人のごとく旅し、観察し、思考し、書いた文人・加藤周一、死す。東京世田谷区の病院にて、12月5日(金)14時。享年89歳。病名、多臓器不全。
関連記事:
生と死 加藤周一
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2006-08-24
小田実の考えてきたこと
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2008-03-27
追悼小田実
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2007-07-30
検察による捏造事件 『いったい誰を幸せにする捜査なのですか』草薙厚子 [Book_review]
さらに、草薙厚子の新刊『いったい誰を幸せにする捜査なのですか - 検察との50日間闘争』が4月に発行されているのを知り購入した。光文社 2008年4月30日刊。
『僕はパパを殺すことに決めた』(以後、『僕パパ』と省略する)で驚くのは、供述調書(少年と父親の供述がほとんどを占め、少年の実母や学校教師の供述が加わる)の引用の多さ、である。その内容はほとんど、父親の少年に対する暴力と威嚇的発言、さらに、父親と母(少年の実母と、継母)の供述調書をそのまま引用している。
注:この少年は幼いとき父母が離婚しており、弟妹は継母の子供である。
父は継母にも暴力を振るっている。結婚した当日から暴力を振るうというのだから、通常ではない。いまならドメスティックバイオレンス、で訴えられてもヨイほどのものだろう。この父親は医者であり家系が医学薬学を生業としており、息子も医者になることを期待されていた。小学校低学年の頃から父が厳しく勉強を教えており、サボったり点数が悪いと折檻に近いお仕置きを受けている。殴る蹴る、頭にシャープペンの芯でこづく、など。日常的に父親を恐れておりそれは物理的暴力だけではなく、言語による暴力にも及んだ。「嘘をつくと殺すぞ!」と脅かされていたがこの少年はこれを真に受けていたようである。これが、高校一年のときの事件(自宅への放火、結果兄弟と継母の焼死)につながった。英語の点数が悪かったのだがそのまま伝えると叱られるため嘘をついたのである。嘘がバレルと殺される、その前に殺してしまおう、と父が寝ている自宅の放火を計画した。ところが、当日、父親は病院に泊まっており自宅にはいなかったのだ。少年はこれを知りながら放火に及んだ。。
16歳の少年が、『殺すぞ』と父親に恫喝された場合それを、本当に殺される、とおもうのか?父親がいないとわかっていながら、何の恨みもない(むしろ庇ってくれている)継母それに弟妹の寝ていることを知っている自宅に、なぜ放火したのか。 これがこの事件の核心である。
わたしはこの書物を読みながら、この少年に感情移入するようつとめた。父親からこれほどの暴力を10年にわたって受け続ければ、通常の感覚で生活できるわけが無かろう。判断力も思考力も通常の少年と、かけ離れてもおかしくないのではないか? 殺すぞ、と父親から脅されれば文字どおり殺されなくても手ひどい暴行を受けるということは予想できる。また、一旦計画して放火を途中でやめられなくても仕方がないのではないか?そもそも放火を計画すること自体、せっぱ詰まっており通常の判断力は失われているのである。
このように考えて私は少年の行動を理解しようとした。ところが、草薙厚子は『僕パ』の終章近くになって、唐突に、 <広汎性発達障害>をこの少年はかかえていた、と言い出す。この症状に掛かっているものは、次のような行動を取る、という。
・言葉を文字どおり受け取る。たとえば、<殺すぞ>といわれればそれを真に受け、殺されるもの、と考える。
・一旦計画すれば、途中で変更できない。上記の例で言えば、父親がいないという予想外の展開になっても追随できず、書記の計画を一本道に遂行するより他の行動が取れない。
しかし、この少年が起こした事件が<広汎性発達障害>に起因するのであればこの本の90%以上を占める父親のドメスチックバイオレンスにあたる行為の延々たる記述は何なのだ?読者にあらぬ<予断>を与える記述は不要ではないか。これでは著者が本書を書いた理由の一つに上げている祖母の「少年の継母が死なねばならぬ本当の理由を知りたい」という願いにも答えていないのではないか。すなわち、放火事件が<広汎性発達障害>であることを訴えたいのなら、前著の大部分は<広汎性発達障害>とは何かの説明に当て、この症状に該当する事件の事例を挙げ、その対策を述べるべきなのである。父親による長期間の家庭内バイオレンスの有無など、事件には関係ない、というのが、<広汎性発達障害>主因説の眼目なのだ。であるのに、『僕パ』で著者は、原因は父親である、と著者の判断を地の文章で何度もくりかえしている。草薙はどこまで広汎性発達障害を理解しているのか、私は疑問におもう(鑑定人である崎浜医師もこの疑念を持ったのだ)。この本が水準以下であるのは、警察の作文をそのまま多量に引用しているからではない。ライターの執筆意図がふらついており、草薙が強弁するに反して、<事件の原因が広汎性発達障害にある>と解釈できる内容になっていないからである(わたしも、それに惑わされた)。
この事件の起こった直後、新聞雑誌の報道は、この家庭と少年に何が起こっていたのか、真実を伝えていなかった、という思いが著者にはあった。しかも、実母と父からは取材を拒否され、継母は亡くなっている。この情況で草薙(および講談社)は、広汎性発達障害の専門家でもあり、偶然、本事件にかんして裁判所から精神鑑定を依頼された崎浜盛三医師にアクセスし、同医師が裁判所から預かっている各種資料のうち供述調書を見せてくれるように同医師に強く依頼した。(この経緯は本記事最後にた講談社が設立した社外調査委員会の報告書を見られたい。本記事の最後にアドレスを掲載)。
わたしは、講談社調査報告書をプリントアウトし精読し、その後、書店で『いったい誰を幸せにする捜査なのですか』を購入した。冒頭書いたように、例によって大げさなタイトルからまた、草薙の言いたい放題を書いているのだろう、と最初に考えた。この本の内容は、昨年9月14日、草薙の自宅、所属事務所、崎浜医師の自宅と勤務先に対し強制捜査が行われこと、およびそれに続く、著者に対して行われた合計19回、二ヶ月に渉る事情聴取で占められる(この間、出版社や医師に対しても事情聴取が並行して行われている)。
ところで。。。草薙厚子が自宅への家宅捜査と19回に及ぶ著者に対する事情聴取の様子を述べた総計270頁に続いて、この本の最後に掲載されている解説と参考資料の18頁:
・解説「なぜ検察は暴走したのか」(清水勉弁護士)と、
・参考資料「供述調書を見せたことは後悔していない」(崎浜医師へのインタビュー)、
を読んで私は一驚、これこそ事件の<真実>であるという感を深くした。これが真実であれば、誰を幸せにする捜査、でもない、そもそも捜査などヤル必要がない、というよりヤッテはならない、この事件は被害者が訴えてもいないのに検察がでっち上げたトンデモ事件なのである。この18頁さえあればこの本全体は不要、というくらいのもんである。
清水勉弁護士は、この書物の元になる原稿を草薙が執筆中、読み続け、助言を行っていたという(清水弁護士がそれ以上この事件にどう係わったのかは不明)。
清水勉弁護士の解説を引用する:
検察による事件の捏造
この本は、突然の家宅捜査に始まる奈良地検=大阪地検(大阪高検)による異常きわまりない捜査を、被疑者(「犯罪者」ではない。犯罪をしたと疑われているだけの人で、それなりに社会生活を営み、家族や仕事がある)として捜査され取り調べを受ける立場に立たされた著者(草薙)の闘いの記録だ。
鹿児島県志布志の選挙違反捜査では、鹿児島地検が鹿児島県警による事件の捏造(というよりは<捏罪>、と表現すべきだろう)に捜査段階から加担していたことが明らかになり、最高検も問題の根深さを認めざるを得なくなったという経緯があるが今回の捜査は奈良県警を最初から蚊帳の外に追いだした形での、大阪高検=大阪地検=奈良地検による<捏罪>である。検察独自の判断による暴走という意味では、志布志湾事件よりも遥かに問題の根は深い。
著者はジャーナリストとして自分の体験としての検察捜査の異常ぶりを書いているが、それより遥かに異常な、告訴の異常ぶりについてはあまり説明していない。と言うより、この点は、少年事件や犯罪捜査の実務経験がないとわからないところである。
日本の捜査実務は、刑事裁判官の安易な令状(強制捜査、逮捕・拘留状)交付(警察・検察が申請すれば、ほとんど100%認められているのではないか)によって、日々、被疑者やその家族、仕事、生活に壊滅的打撃を与えている。
だが、これから説明する異常さはこれとは異質の、特別な異常さだ。
私は特別の能力があって、いま、この解説を書いているわけではない。一般的な弁護士よりはいくらか多くの少年事件を手がけてきたという程度の弁護士だ。その程度の弁護士でも今回の捜査の異常ぶりはよくわかることで、この解説を引き受けた。
捜査の異常ぶりは告訴の異常ぶりに端を発している。告訴の異常ぶりとは、具体的に言えば、少年と父親が、崎浜盛三医師、著者(草薙)、「氏名不詳者」の三人を被告訴人として秘密漏示罪で告訴したという事実だ。これは捏造の疑いが強い。
以下説明していくことにする。 p293-294
以上長い引用を行ったが、これ以降、12頁に渉って詳細だが分かり易い捏造の内容が説明されている。全文引用するわけに行かないので箇条書きにする。詳細は、是非本書を手に取って頂きたい。以下は要約である。
1 告訴意志
秘密漏示罪(刑法134条)は親告罪である。つまり、被告者の告訴がなければ検察官は公訴を提起できない。本件の場合、父親と少年が告訴人になっている。しかし、諸事実から判断してこの二人が告訴するなどありえないことなのだ。告訴意志がないのに、告訴状を有効とすれば今回のようにヤメケンが被害者名義を借用した告訴が世の中に溢れ、強制捜査が日常的に行われる社会になる、と清水弁護士は警告を発している。そうならないような仕組みに現在の法律はなっているのだ。
2 告訴内容
告訴内容は、崎浜医師が調書を漏洩したといっているが、そもそも、調書の所在がこの二人に解っているわけがないし、調書は同医師だけでなく、捜査機関、家裁、弁護士ももっている。少年と父親が、どうして、崎浜医師が著者・草薙に閲覧させたと解るのか。
3 本の内容を知らずに告訴?
少年院にいる少年と家族は会話内容が制限される。『僕パパ』の記述内容について父と少年がハナシをし(告訴に至る)ことは考えられない。
4 検察と元検察官の<談合>による告訴受理
上記諸々の疑問を解消できる答えが一つだけある。
それは、この告訴が少年と父親から弁護士に持ち込まれたものではなく、告訴代理人である元検察官の弁護士らと奈良地検・大阪地検・大阪高検側が事件にすることを最初から仕組み、便宜上、少年と父親の名義を利用した、という構図だ。
ここから、草薙の書いた文章を引用しよう。25章「ブラックメール」から
この本を書くために取材していると、さらに意外な事実が分かってきた。実はこの事件の刑事告訴の代理人は3人いるのだが、その3人ともヤメ検(検事を辞めた弁護士)だったのだ。「関西のドン」である元検事総長の土肥孝治氏と本田重夫氏、浜田剛志氏である。彼らは共に、大阪高裁から歩いて10分程のところに建つ、いわゆる「ヤメ検ビル」に事務所を構えているということが判明した。p289
検察捜査の引き金になったのは、ある、捏造されたブラックメールである。詳細は省略するが、清水弁護士が言うには。。p303
。。。ブラックメールは全くの捏造だった。。検察は強制捜査を開始して狙いがはずれたことにすぐに気がついたはずだ。検察はそこで捜査からさっさと撤退すべきだった。告訴代理人団を説得して告訴を取り消させるべきだった。それが真っ当な筋というものだ。しかし、法務省をバックに組織的に取り組んできて、すでにマスコミを使って大々的に報道させてしまっているだけに、捜査からの撤退は検察の軽率さと暴走ぶりを社会にアピールすることになってしまう。そんな恥さらしなことは絶対にできない。何としても<形を作る>必要がある。これに利用され犠牲にされたのが崎浜医師である。検察とはなんとも身勝手な組織だ。p303
崎浜医師は、本書の参考資料(インタビュー記事)「供述調書を見せたことは後悔していない」に、簡潔に事件の解釈(広汎性発達障害とはなにか)を示し、おのれの信条を明らかにしている。長めの引用を行うことを赦されたい。
p308
事件を起こした少年は、幼いころから父親に猛勉強を強いられ、成績が悪いときには暴力を振るわれていた。放火の引き金となったのは、テストの点数が悪くて父親に嘘をついたことだ。以前に嘘をついたとき、父親から「今度、嘘をついたら殺すぞ」と言われていた少年は、「殺される前に殺そう」と放火した。ただその日、父親は勤務先に宿泊し、家にはいなかった。
審判では、父親の不在を知りながら、なぜ少年は火を付けたかが争点になった。理由が見つからないからだ。そこで、精神鑑定を求められ、私は少年を特定不能の広汎性発達障害と診断した。
少年が広汎性発達障害であることを考えれば、父親が不在であるにもかかわらず放火した点は容易に理解できる。広汎性発達障害の子供は、一度決めた計画に固執する傾向にある。少年は、継母等を恨んで殺害しようとしたわけでも、継母らを殺すことで父への恨みを晴らそうとしたわけでもない。単に現実に合わせて計画を変更できなかったのだ。
また、周りのことに気が回らないのも、この障害の特徴だ。継母らの生命に危険が及ぶかもしれないことは、放火の際、少年の意識に上らなかった。火を付けて逃げることに集中するあまり、普通の子供なら考える点に思いが至らない。
供述調書を第三者に開示することが罪になるかもしれないとの認識はあったが、きちんと世間に伝えてくれて、それが少年への誤解を解くきっかけになるなら、私は見せるべきだと思った。調書の流出と、少年が誤解されたまま生きていくことを天秤に掛けたときに、少年の人生が良くなる方を選択したいとおもったのだ。
この気持ちは、どんなに説明しても検察には理解してもらえなかった。検察は、調書の流出に重きを置く。少年の人生を重く考えるのは、医師ならではかもしれない。私は、今回の事件を通して、「患者のことを考える」という職業的な意識が染みついていることを再認識させられた。
この一件を私が患者の個人情報を漏示したと勘違いしている人がいるが、そうではない。秘密漏示罪は、医師や弁護士などが職業上知り得た情報を正当な理由なく第三者に漏示することだが、私と少年は医師と患者の関係ではないからだ。
また、個人が特定されるような情報の流出によって、少年の更生が妨げられると少年法の観点から私を非難する人もいるが、「殺意をもって三人もの人間を殺した」と思われ続ける方が、よほど少年の更生を妨げるのではないだろうか。
出版された書籍が少年の障害への理解を助ける内容になっていない点は、非常に残念だ。同書の誤った情報やそこから生じる誤解は、正していく必要があると感じている。しかし、私が逮捕されたことやこうして話していることも含め、情報を出したことが、皮肉にも少年の事件への理解を深めるきっかけになっている。少年のこれからの人生を思ってやったことなので、供述調書を見せたことを私は後悔していない。
ネットでブログ記事を検索すると、崎浜医師に対する、漏示への誤解が非常に多いので敢えて、長文を引用した。これを読んでも、誤解があるならそれはもはや人間観、価値観の相違と言うしかない。書き写しながら、いったい、崎浜医師というひとはどういうひとなのだろうか、という気が何度もしてきた。著者や出版社に恨み言のひとこともいわず、少年の将来のことだけを心配しているのである。清水勉弁護士とともに、これぞプロフェッショナル、といいたい。検事らとは人間の品格が違う。私は感動した。
清水弁護士は崎浜弁護士とは会ったことはないが、「崎浜医師は私と同じようなことを考えている」と述べ、p306
「少年はモンスターではない。自分の行為(放火)で家族を死なせてしまったことに違いないが、殺人者(故意に人を殺したもの)ではない。危険な人物でもない。彼を断片的な情報で得体の知れない殺人鬼にしてはいけない。彼がふつうの社会生活ができるようになるために、彼も周りの人も彼の病気についてちゃんと知らなければならない。それには『僕パパ』では足りない。「正しくしていく必要がある」。崎浜医師の真意は著者は責任をもってちゃんと書け、書かないなら私がやる、ということだ。
崎浜医師は刑事被告人になりながら、ただひとりで少年(の人格と人生)に真正面から真剣に向き合っている。崎浜医師のこの言葉を検察は受けとめなかった。さて、裁判所、マスコミ、社会はどう受けとめるのだろうか。」
。。と問うている。
この二人の声を草薙厚子はどのように聞くのだろうか?草薙の「検察との50日間闘争」は終わったが、崎浜医師の公判はやっと4月に始まったばかりであり、この先どういう展開になるのか予断は許さない。NFとしての 『僕パパ』の出来に、草薙はまだ自信をもっているのだろうか?私見では、草薙が広汎性発達障害を事件の主因として読者に訴えようとするならば、この障害に関する説明を大幅に増やし、この事件だけでなくこの症例が該当する事件を多く取材により取り上げるべきであったのだ。専門家と討論すれば、警察の書いた供述調書を多量に引用せずとも、新聞の半ページのスペースがあれば、より分かり易く書ける内容であるはずだ。
しかし、おのれの事情聴取の経緯を描いた『いったい誰を幸せにする捜査なのですか』は面白かった。ある朝突然自宅に検察が現れて行われる証拠物件の押収とはどのように行われたか、事情聴取はどのように進行したのか、が臨場感をもって描かれている。さらに事情聴取における検事の態度や行動、言動(脅しや泣き落とし)。取り調べに当たった検事のレベルがあまりに低いこと、検察の作戦が稚拙であって、草薙も余裕で対応できたからだろうが、検事の生態をオモしろおかしく描いている。さらに、この本では、讀賣新聞や朝日、それにNHKが検察の誤ったリーク情報を平気で流し、虚報とわかったあとでも謝罪しない、という最悪の報道機関であることを曝露しているのはいまさらながら有用であった(読売に情報をリークし続けている検事の名前を草薙が調べて教えたときの、担当検事の慌てブリが可笑しい。結局、草薙厚子は当然ながら不起訴となったのだが、草薙があまりに担当検事をいじめたから、担当検事が人格破壊を起こしてしまった、と担当検事の上司から泣きが入った、というのはもっと可笑しい。人道に反することをやれば検事だって人格破壊する)。
不思議なのは、前記事で引用した講談社の社外調査委員会が作成した調査報告書である。調査委員会は草薙や出版社、弁護士からも事情聴取をしているはずであり法律専門家も調査委員に加わっているのに、漏示罪がそもそも成立していないのではないか、という疑いをまったく抱いていない。著者のマズイ執筆技術が公権力の介入を招いた、と、介入の責任を著者に押し付けている。清水弁護士が指摘するように、そもそも、漏示罪に公権力の介入余地はまったくないし、介入は違法なのだ。すなわち、調査委員会委員は法律を解する能力を欠いていた、ということである。この調査報告書で、アッと驚くのは、草薙らの取材過程を詳細に述べていることである(情報源秘匿、というのは常識であるのに、外部調査委員会がそれをバラしてどうするの?)。とくに、あきれ果てるのは、草薙が使用していたICレコーダの記録から、鑑定人との会食場面の会話をそっくりそのまま文字に起こして報告書の内容としていること。どのようなものかを報告書から再録しよう:
###
9月28日の夜、筆者、記者、鑑定人は、前回と同じ割烹料理屋で会った。
筆者はここで、少年の審判が出る時期に合わせて、週刊現代や月刊現代にレポートを書きたいと考えていること、少年の家庭環境や、通常ではなかなか理解しにくい思考・行動のありよう等から広汎性発達障害の問題に焦点を当てたいことなどを語り、鑑定人の手もとにある供述調書を見せてもらえないか、と話を切り出している。
筆者「ある程度、ちょっと見、あれなんですよね。だからそれを、みんなが持っているということで、先生にターゲットを絞られないためにも、私がある程度見たほう、見て、それをどこにも出さないので」
鑑定人「あっ、そう……うーん」
……
記者「先の話になりますけど、本当に原稿の最終チェックまで、先生にしていただいて、危険を回避する方向でやっていきたいんですけども」
……
鑑定人「コピーはダメ(笑)」
筆者「取りにいく、取りにいきます(笑)」
記者「もちろん、コピーはダメよ。その場で見るんやったら構へん、という形が、先生にとっては心理的に負担が少ないのかなと思いますけどね」
鑑定人「コピーしたら、絶対ダメだからね。よう裁判所の人も、電車とかに置き忘れるんですよね」
……
筆者「見せていただければ、私がこうメモして」
鑑定人「調書を見ても、たいして役に立つのかなあと思うけど。あれはもう、書き方も決まっているんでね」
……
(供述調書の信頼性などをめぐっての話のあとで)
筆者「警察って、ほんとにダメ。ダメダメダメ。私は警察なんて、信じてませんから。だから、調書ってのも、全然信用しない。少年犯罪のなんて、みんなそうよ。ろくでもない。うーん、まあ、いい方法で、だから先生のでもあれ、まあ、鑑定でも調書でもいいんですけども、鑑定のなかの調書を入れるのでもいいですけども、なるべく、あの、鑑定した先生のそういう匂いみたいなのを消したい。消したほうが、安全のためにいいと思って」
……
筆者「まあ、だから先生が、この日に来てくださいっていうなら、私、行きます。それでいいですか?」
記者「調書、見られる日ね」
筆者「調書。調書、どうですかね? 先生の家に行くっていう」
記者「どうなんですかね?」
鑑定人「別に全然構わないけど」 11
……
記者「たとえば、先生のご了解を得られるならば、先生がね、労働しているときに見せていただくことは可能でしょうか?」
鑑定人「……(約4秒間の沈黙のあと)ああ、いいよ」
(鑑定人のスケジュールの話がつづく。10月13日が鑑定書の提出日になっていること、その後はあまり長い間、調書を手もとに置いておくことはできないかもしれない、等々の話のあとで)
筆者「13日は、先生が鑑定書、持っていくんでしょ。その前までには、調書は全部見たほうがいい。返すかもしれないし」
###
まったく、再掲するのもアホらしくなるほどの内容だ。録音を公開することを前提としない、取材過程の会食場面のヤリトリとは誰であっても(若干、軽すぎ、という気はするが。。)こんな内容になる。ICレコーダの保持者である草薙が抵抗するのももっともであるし、これをそのまま報告書に掲載する神経がわからない。オドロキあきれ果てた、というほかない。いくら出版社が私的に設立した調査委員会とはいえ、遵守すべき常識というものはあるのではないか?(調査委員会は報告書をとりまとめるに当たり何度か会合を開き、会食も行ったはずである。その会合や会食における会話をICレコーダに記録していたとして、その記録を<笑い声>まで含めて、全て公開できるのか?尋ねてみたい)取材源や取材過程を公開してどうするのか。調査委員会の耄碌ブリがわかろうというものである。公的介入を招いた、と非難しているが、その介入の妥当性を疑いもしていない。調査委員会は検察の回し者なのか?しかし、検察であっても供述書には、こういう私的な会話を引用するのをはばかるのではないか。調査委員会報告書は、調査委員がいかに間抜けであるかを示した書き物を出ないシロモノであった(こんな報告書に異議を挟めない出版社も哀れである)。
したがって、この調査報告書に対して草薙厚子が提出している異議と、抗議は正当なのである。
「奈良県で起きた医師宅放火殺人事件の加害少年の供述調書を引用したノンフィクション「僕はパパを殺すことに決めた」(講談社)について、「取材源との約束に反した本作りを行ったことは、重大な出版倫理上の瑕疵(かし)がある」と断じた調査委員会(委員長・奥平康弘東大名誉教授)の報告書には「事実誤認がある」として、同書の筆者、草薙厚子さんが21日、東京都内で会見し、調査委に抗議する申し入れ書を送ったことを明らかにした。
草薙さんは「(調書のコピーをしないなど取材源との)約束は事実でない。報告書は乱暴な作りだと思う」と指摘。申し入れ書では、事実認定に使われた草薙さんのICレコーダーの会話記録は無断使用であり、本人への事実確認もなかったとして、謝罪や訂正を求めている。」
調書引用本 筆者が調査委に抗議 http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/m20080422021.html
供述調書の引用にはケチを付け、検察介入の違法性は疑おうともしないが、私人のICレコーダの無断使用や内容曝露は平気で行う、調査委員会とは何なのか?検察の回し者、といわれてもしようがあるまい。
草薙が本書p215で述べているが、毎日新聞論説委員牧太郎氏の、「調書は社会的共有の情報ではないのか」という視点も重要である。多量の丸ごと引用はともかく、<漏示>を構成するには要件をヨリ高く設定すべきであろう。
もし、『僕パパ』が出版されず、崎浜医師(鑑定人)の意見が全く考慮されず、検察・警察の意見のみが採用されたらどうなるか。さらに、このような検察による捏造裁判がまかり通ったらどのような世の中になるか。というより、現在のシステムはドップリと検察のヤリホーダイシステムになっているのであり、そこに風穴を開けようとしたものは葬られてきた、と解釈すべきだろう。これは調査委員会が一顧だにしていないことである。
草薙厚子は清水弁護士の【解説】を読んだのであろうか?読んでいるにしては、この書名『いったい誰を幸せにする捜査なのですか』は、いかにも間が抜けている。事件の発端たる告訴自体が成立していない、と弁護士はいっているのだから、そもそも、捜査などあり得ないのだ(違法にきまっている)。いったいあなた達(検察)は人間ですか、と問うべきだろう。
ところで、今、父親(医者)はどうしているのだろうか?弁護士に相談し、捏造された告訴(傑作なことに少年と連名で。。)をサッサと取り下げるよう措置しないとあとで、検察とともに大恥をかくことになる。それよりまえに、裁判所は告訴を独自に調査した上、崎浜医師に対する公判を即刻中止すべきであろう。 検察とグルになっている、と思われたくなければ。
追記:
本書を読んでどうしても納得できないことがある。第17回の事情聴取で、草薙が供述調書を撮影したDVDを自主的に担当検事に提出したことだ。しかもこれは講談社側がつけた草薙への弁護士が、同意したのである。(出版社利益を代表する弁護士とは別にライターは独自の弁護士を用意する必要がある、と言うことだ)検察として今回の草薙に対する強制捜査の結果「金銭の授受や情が絡んでの事件性はない」という判断をせざるを得なくなった、しかし、検察として強制捜査の結果、重要な証拠物?、すなわち供述調書の入ったDVDは押収したということにしなければ格好が付かぬ、これが入手できれば、崎浜医師の拘留期間延長が阻止できる、という検察の取引に応じたのだ。 草薙は「私はどこか釈然としなかった。講談社は所有権を放棄するという考えだったため、私の所有物として、判断しなければならなかったのである。したがってこれは本当の強制押収ではない。こちらから自発的に渡したというのが真実だ」と書いているp246。このDVDは講談社が安全のため、別の保管場所に移していたものだ。これを易々と、あろうことか、こちらから自主的に検察に渡すとはどういうことか。これで「50日間闘争」といえるのか?しかも、崎浜医師の拘留期間延長阻止を理由にあげたのでは、崎浜医師こそいい迷惑である。どこまで迷惑を掛け続けたら気が済むのか。(講談社=弁護士と、検察の間に、草薙の知らないところで、別の取引があったのではないか、と疑わせる)
参考:
講談社は社外委員会を設けて客観的な調査を行い、その成果物である調査報告(4月8日付)を、講談社の見解と共に同社HPに発表している。以下のページからダウンロードできる。
http://www.kodansha.co.jp/emergency2/index3.html
調査委員会の構成はつぎのとおり。
奥平康弘(委員長) 東京大学名誉教授
清水英夫(委員長代行) 法学博士 青山学院大学名誉教授
吉岡 忍 作家
升味佐江子 弁護士
山田健太 専修大学准教授
追記:5/18/2009
『講談社から皆様へ 崎濱盛三医師への判決にあたっての見解』
という一文を2009年4月15日付けで 講談社がHPに掲載したのを知った。
http://www.kodansha.co.jp/emergency2/index4.html
引用:
本日、奈良地裁から崎濱盛三医師に対して、きわめて不当な判決が下されました。
まず、この判決は崎濱医師および弁護団の正当な論証をあえて退け、検察側の主張を単に追認しただけの理不尽なものであり、強く抗議します。あわせて、弊社刊『僕はパパを殺すことに決めた』(草薙厚子氏著)に関連して、いわれのない罪に問われた崎濱医師に心よりお詫び申し上げます。今後とも崎濱医師にはできうる限りの支援を続けてまいります。
弊社は、本来あってはならない報道に対する公権力の介入を引き起こしてしまった社会的責任を重く受けとめています。その反省のもと、今後も萎縮することなく真摯に出版活動を行い、社会に貢献してゆく所存です。
(以下略)
関連記事:
暗黒裁判の国、日本。 『公認会計士vs特捜検察』 細野祐二著
http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2007-12-09
小田実が考えて来たこと [Book_review]
昨日、本の整理をするつもりが、ぽろりと出て来た小田実『激動の世界で私が考えて来たこと』(1996年、近代文藝社)に読みふけってしまった。一度読んだはずの本だが。
この本は小田実が89~95年にわたって書いた小文がおさまっている。530頁の本だ。この時期、小田実は
95年『ベ平連 回顧録でない回顧』 (月刊誌世界に連載したモノをまとめた)
96年『被災の思想 難死の思想』
という大著(700頁前後)を立て続けに出している。95年初頭、小田実自身が神戸大震災に遭っていることを考えると凄まじい体力精神力と言うしかない。
この本の最後、95年は阪神大震災が襲った年。小田も被害者として絶望と怒りの日々を送り、執筆活動をしているような精神状況肉体状況でないにもかかわらず、とにかく書きついだ。この大地震がなければ小田の眼にも見えなかったものが見えてきた、それをわれわれは小田の文章から知ることができる。不幸中の、<サイワイ>とせねばなるまい。
冒頭に序文として、1988年に開催された日独戦後文学を比較する会議のために書いた英文の翻訳(和訳)が置かれている。A Writer In the Present World~「現代世界のなかの作家」。これは小田の思想の要約ともいえる文章である。このなかで、西宮に戦争末期計画され、着手された地下トンネルの話が書いてある。敗戦時、小田実はまだ少年だったが大阪を襲った8月14日の大空襲の意味が分からなかった。天皇制存続のためだけのために死んだ多くの人々の無意味な死を、玉音放送を直接聴いた小田は再確認している。
小田は序文にもうひとつ、革命家・堺利彦について書いた短文を序文に追加している。堺利彦には『家庭の新風味』という著作がある、と。その抜粋を載せている。子供は「つぎの時代の働き手」であるという原理を定立した後で「子に対する尊敬」を説いている。その、ほんの一部を引用(p23から)。
。。わが子はわが力をもって作ったのではない、ある不思議な力をもって作られたのである。。。そこでわが子とはいうものの、まったくのわが子ではなく、不可思議(すなわち神)の子といってもよい。我々は神の子をわが子として産むのである。。。。 神に対しては「さずかりもの」、社会に対していえば「あずかりもの」、けっして親の私有物ではない。「あずかりもの」であるから大切にせねばならぬ、「さずかりもの」であるからに尊敬せねばならぬ、私有物でないから親々の勝手にしてはならぬ。これが子に対する根本の心得である。
こういうところを評価するのが小田の小田たる所以か。
#
本書では、幕末明治維新以後、日本は欧米、とくに米国になにをされたか、なにをアジアでやったか。小田の歴史観、アジア観が繰り返し熱く論ぜられている。
92年に小田は米国NY州ロングアイランド島にあるstony brook universityに教えに行っている。30年前にできた州立大学。東西に長いロングアイランドの中ほど、NYCから車で飛ばせば一時間ちょい、のところらしい。蔵書数では全米一を競う図書館もある、という。
小田は客員教授として、日本文学を教えに行った。日本文学と言っても日本語を読める生徒はいない。すべて翻訳=英訳、だそうである。小田の講義もすべて英語。小田の英語はどんな英語?
「私は英語は決して上手ではないが、表現力ゆたかという定評はある。表現力ゆたか、とは、たぶん、美辞麗句で、勝手に自説をこねあげ、まくし立て、人をケムリにまくのがうまいというのがことの実態、あるいは、真相だろう。私の学生たちは、今かわいそうに私の英語でケムリにまかれているというところだ」p361
。。だそうである。新学期のためにつくられた学生用の便覧に小田の講義内容を紹介している(小田によれば、なかなかうまくまとめてある、らしい):
[日本研究] 現代日本の批判的文学(このタイトルだけは小田がつけた) p362
急速に変化しつつある現代日本社会の状況の証言者として、また批判者として役立つ代表的長篇小説、短編小説の検討。大部分の学者にはあまりに一般的な概括を日本文学に対して行い、ジャーナリスティックな方法をとる者はありきたりな方法でことを論じる。それらとは対照的に、この講座の講師は、彼自身が、急速に変わりつつある日本の文学的情況へ参加してきた日本の主要な小説家でもあれば、社会批判家でもあって、現代日本文学の多様性とダイナミズムへの洞察を得る機会を学生たちに提供する。
講義: 水曜日 午後六時半~九時半。
ところで、小田実は、いまだに米国では好ましからざる人のリストに入っている。反戦活動、のせいである。空港ではいまでも、小田の名前がコンピュータに出て一騒動おこすことがある、という。
これを書き写しながら私は40何年か前、小田実『なんでも見てやろう』を読んだことを想い出す。小田はフルブライト留学生として米国~欧州、亜細亜を回った。そのフルブライト資格を得るための試験が米国大使館@東京、であった。当時小田は英語はまったくしゃべれない。試験管の口頭試問への回答もちんぷんかんぷん。その回答のデタラメブリが受けに受けて、第一次試験に受かったあと、第二次口頭試問の開始前から、その試験部屋に、仕事中の大使館員が小田の珍答を聴きにゾロゾロ集まり、小田の珍答のたびに大爆笑であった、という。
試験官「貴君は英語がどの程度しゃべれるのか?」
Oda「おれの英語を聞けばレベルは分かるハズである」
試験官「我、了解ス」
昨年10月この大学で、小田のメモリアル集会が開かれたらしい。
##
1. Memorial Service for Makoto Oda
A memorial service for Makoto Oda will be held on Monday, October 15, 2007 in the Javits room on the second floor of the Frank Melville Jr. Memorial Library, State University of New York at Stony Brook from 3:00 to 4:30. Makoto Oda, a famous Japanese novelist, was a visiting professor at Stony Brook from 1992-1994 and taught literature courses in the Japanese Studies Program, supported by the Japan Foundation. On the world stage, he was known for his peace activism, which began during the Vietnam era. He last visited Stony Brook in April 2003, when he gave a lecture on the war in Iraq. He had come to America on the occasion of the publication of his Breaking Jewel in English. Please RSVP to Mary Diaz (Mallow8859@AOL.COM) if you will be able to attend.
Sachiko Murata, Director of Japanese Studies
##
この本でもっとも強い印象を受けたのは90年夏に小田が書いた短文『孤独な青年』である。p124
孤独な青年の名前はクリストファー・ボイス。いま、米国の監獄の中にいる。40年の禁固刑を食らっている(当時は)青年だ。
小田はジョン・ピルジャーの『秘密の国』によりこの青年のことを知ったという。(検索してみた。映画にもなった有名な話らしい)。 John Pilger "Secret Country"
青年はunredeemable criminal(救済措置のない犯罪)を犯したとして、独房の外にいるときもつねに手錠をはめられ、二人の看守が監視する。
この青年は何をやったのか? それを描くには72年にできて、75年につぶされたウィットラム労働党政権のことを知らなければならない。われわれがオーストラリアときくと一瞬おもいうかべる 革新、進歩的。。という印象はこの政権から得たものだ、と。すなわち、ウィットラム政権は、チリのアジェンデ政権を崩壊させた米国を国連で公然と非難し、ウィットラム首相自身が北朝鮮を訪問し、長年オーストラリアで虐げられたアボリジニの土地と人権回復を宣言した。米国のCIAがこの政権打倒を策謀し始めたのは、オーストラリアのどまんなかの砂漠にある秘密基地(CIAの基地もあった)を政権が問題にしたからである。米国はここから立ち去るべし。米国の策動により、ついに、オーストラリアの国家元首であるイギリス女王の代理人たる 総督 が ウィットラム首相の首を切って政権はあえなく潰えたのだ。
<青年>がこの事件にどうかかわるのか? 青年の父親は長年FBIに勤務し、そのコネでこの青年はCIAに職を得た。仕事は暗号解読である。具体的には、この職務遂行中に、ウィットラム政権ぶっつぶしの策謀の一部始終を知るに至った。おどろくなかれ、オーストラリアの総督が、CIAの一員だった、というのだ。 <知りすぎた>青年は秘密を同僚に打ち明ける。そのことから始まってとうとう、ソビエトのスパイに仕立て上げられ、国家反逆罪で捕らえられるのである。取引には一切応じず、青年は 法廷で一切合切を曝露したのだ。
小田はこの事実だけを伝え、こう結んでいる。
。。すべて彼(青年)には本来なんの関係もなかった外国にかかわってのことだ。しかし、外国のことであろうとなかろうと、「こんなことはまちがっている」。このことば、この彼の信念は強い。そして、私の心に重く残っている。それゆえ、このアメリカ合州国においてはもちろんのこと、当のオーストラリアにおいてさえ、知る人のほどんどいない「孤独な青年」が私のきにかかる。
これは、どこか遠い世界の話、ではない。ニッポンに起こりうる話、とおもわない?
ない、っか。
追悼 小田実
教養としての大学受験国語 [Book_review]
一つ前の記事、『サクラ記念日』、にこんな歌?を載せた。けさ、週末にブックオフで仕入れた100円本の一冊、石原千秋『教養としての大学受験国語』(2000年)を読んでいたら、こんな文章を発見。p275
「。。僕は、毛利衛さんとか向井千秋さんとかがアメリカのスペースシャトルに乗ることも、日本国民として恥ずかしいとは思っても、決して誇りには思えないのだ。だって、あれってまるで<車の買えない人が隣の家の車に乗せてもらっている>という感じじゃない?」
ははは。うまいことをいう。スペースシャトルのバヤイは、乗船チケット何千億円も払っているんだからね。ドードーと大船にのったつもりでいればよい。でも、中国が自前でシャトルを打ち上げようと計画しているのに比べると、かなり恥ずかしい。。と思わないのはNHKだけかも(珍しく、NHKを誉めた)。乗りたくないけど、カネだけは寄付しちゃるわい、というほうがスッキリするね。
中国のスペースシャトル。第一号に、ダライラマ、を載せたりすれば、ニュース。
#
石原千秋のこのホンは大学入試科目の現代国語のアンチョコなのだが、<現代思想>のマニュアルとしても使える!と著者は思っているらしい。内容たるや、まさに、<近代とは何か>の、ひとつのアンチョコな答えなのだから。現代国語入試がこんな内容を扱っているなんてわたしは全く知らなかった。
p30
「。。。僕たちは間違いなく「モダン」(近代)という「個人」という思想に取り憑かれた時代に生きている。この時代では、自分の意見を持つことはほとんど生きることと同じ意味を持ちさえする。自己責任ということも、自分の意見を持つところから生まれてくる。 問題は、その「自分の意見」が実は「時代の意見」でもあることに気づくことが難しい点にある。僕たちは、知らず知らずのうちに、「時代の意見」を「自分の意見」と思い込んでいることが多いのだ。「時代の意見」に同調することが悪いと言いたいのではない。「知らず知らずのうちに」そうなっていることが恐ろしいといいたいのだ。そこには主体的な選択もないし、そして恐らく反省もないだろうから。」
「。。実はこうした「個人」の責任を基本とする考え方自体、「主体の消滅」を説くポストモダン的思考からみると、救いがたいくらいに「近代」そのものだと言える。「個人」という実態などは意味を持たず、他との違い、つまり差異のみが意味を持つと考えるポストモダンの議論からすると明らかに時代遅れである」
このホンで扱うテーマは、
近代
二元論
身体
大衆
情報
日本社会
国民国家
である。ということは、入試出題者(業者、あるいは大学のセンセ)がこのテーマを切実だ、とおもっているのではなく、このテーマに関連した書き物が巷に溢れている、ということだ。
わたしが合点いったのは石原が「はじめに」で書いている文章である。p007
「教養という言葉は、いろいろな意味に使われる。「教養がない」と言えば、たいていの場合「ものを知らない」ことを意味する。つまり、知識のことだ。しかし、時と場合によっては、ある階層が身につけていなければならないハビトゥス(慣習)を意味することもある。コンサートホールや高給レストランでおどおどしているのも「教養がない」のである。つまり、ハビトゥスとはある階層が持っている文化の型のことである。」
それで著者は、受験生に対し、多くのことを知って欲しいし、上品なハビトゥスを身につけて欲しい、と言う。このハビトゥスは大学でも必要だし、社会に出ても必要になるモンダ、という。
はぁ。。大学や受験業界に棲息する人々が考えている「教養人」とはいかなるものか、定義してくれているようだ。こんな教養人には全く興味ないが、これも現代世界に巣くっている一種族、と了解し、その存在根拠、その意義を探るのは文化人類学的興味をそそらないでも、ない。
とまれ、こんなくっだらねえ<ハビトゥス>を生徒や学生に埋め込もう、としているとは恐れ入ったでござる(ホンキ、なんだよね?、石原センセは)。飼育、躾、としての受験ベンキョ、をこんなにドードーと肯定しているとは。
#
俵万智さんもむかし現代国語教師だった、と聞いたが。
ブックオフで仕入れたサラダ記念日は、英訳つきである。じっくり読んだが、なかなかいい歌と思えるのが多い、のは意外だった。
昨日NHK ETVで、文化人類学特集をやっていた。梅棹忠夫らが造った 国立民族学博物館(みんぱく)の30周年記念。世界のあちこちの文物を収集している博物館である。こういうものを集めて展示する、という活動自体がもっとも興味深い、民族学的ハビトゥス。主体の消滅~と、差異、は原理的に共存しうるのか?この共存は、ハビトゥスたりうるのか?
番組で鷲田清一がこういう事を言った。
フィールド調査などである民族を理解するという。しかし、理解をするということは、相手のことがよくわかる、ということではない。細かく調べていけば行くほど、あらゆるものが違っている。現象的には同じでもそれに込めた意味の彼我の違いが大きいことに驚く、これを確認することが文化人類学の役割ではないか。
当たり前のことである。文化相対主義の基本である。しかし、この相手は誰か?アボリジニだけではなかろう。ニッポンジン同士であっても同じことだ。ある、コトバ、で何を意味しているか、どういう価値、非価値をそのコトバに込めているかはニッポンジン同士でも異なる。ニッポンジンはミナ同じ~。。などとノーテンキなことを言っているようでは文化人類学者どころか現代人たりえない。民族、という虚構は、言語の統一、統一言語の教育を持って始まる、という。言語は不完全なツールであり、人間支配の道具でもなく、認識を共有するための道具でもない。いかに、人間同士が異なっているかを確認するための道具である。民族、とは言語を共有するひとのあつまり、であるという。とりあえずこれを認めることとしても、言語の共有は価値の共有とは無関係のことである。
ミンパクでは、アイヌの文物を展示している。欧州博物館のアフリカに対する、のとは異なり、みんぱくでは、アイヌ出身者を招いて展示を行った、という。アイヌの子孫とミンパク研究者は親しく交際しアイヌの伝統の行事にも参加している。世界の先進国の近代は人権宣言をかかげ基本的人権を謳いながら、おのれの政策により滅び行く民族をほったらかしにしてきた。<天は人の上に人を造らず>という近代の原理は、口先だけのことだったのである。ミンパクができたとき、政府は、アイヌの存在を認めていなかった。国立博物館のミンパクがはじめて アイヌの存在を公的に認めたのだ、という。
北海道旧土人保護法
国際先住民年
問題は米国の国益追求である 『イスラエル・ロビーとアメリカの外交政策』 [Book_review]

すでに記事にした『イスラエルロビーとアメリカの外交政策』ミアシャイマー & ウォルト著
http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2007-12-04
の翻訳本を図書館にリクエストしていたが、購入してもらえたので借り出した。原著500頁、訳書は上下で計650頁(この程度の厚さなら一巻にまとめて欲しい)。大著、というほどでもない、一日あれば読める長さだが、時間がないので、終章『何がなされるべきか』だけを読んだ(貸出期限は2週間なので一旦返却し、必要があればまた借り出そう)。
本書で言いたいことはこの終章で尽きているのではないか、ともおもえる。目次をかかげておく:
第一部 アメリカ、イスラエル、そしてロビー
第一章 アメリカという大恩人
第二章 イスラエルは戦略上の資産か負債か
第三章 道義的根拠も消えて行く
第四章 <イスラエルロビー>とはなにか
第五章 政策形成を誘導する
第六章 社会的風潮を支配する
(以上上巻)
第七章 <イスラエルロビー>対パレスチナ人
第八章 イラクと中東 体制転換の夢
第九章 シリアに狙いを定める
第十章 イランに照準を合わせる
第十一章 <イスラエルロビー>と第二次レバノン戦争
終章 何がなされるべきか
著者によれば、イスラエルロビーの存在自体はだれも拒むことはできない。前記事でも書いたように、米語区議会とロビー活動は切っても切れない関係にあり、ロビー活動の受け皿として議会がある、ってなもんだろうから(米国だけじゃないが)。著者も、イスラエルロビーを否定しているわけではない。それに易々と載っている米国議会の議員が問題なのだ。
下巻p259で、著者は問うている:
『わたしたちは何をなすべきだろうか。現在の米国の諸政策は、様々な厄災を生み出す悪循環に陥っている。それを好転させるには、新しい戦略が必要だ。これまでとはまったく異なるアプローチを考え出して実行するためには、<イスラエルロビー>の力に焦点をあて、理解する方法を見つけ出す必要がある。これまでなされてこなかった新しい戦略の概要を示すと次のようになる。
1 中東における米国の利益はなにかを明確にする
2 中東における米国の国益を守る戦略を概観する
3 米国はイスラエルとの間で新しい関係を構築する
4 イスラエル・パレスチナ紛争を”二国家共存”という枠組みで解決を図る
5 <イスラエルロビー>を建設的な勢力に転換させる』
この後で著者は個別事項の対処案を掲げている。
上記リストを見れば分かるようにこの本は徹底的に米国の国益を追求した本である。1~4についていえば、著者は、国益を守るために海外に直接介入するのは愚策であり、米国の<伝統的な>、オフショアバランシング(地域外から均衡を図る)という戦略に徹すべき、であると述べている(直接にせよ間接にせよ、米政府が国益のため全世界各地域をウォッチし軍事・政治プレゼンス継続するのを支持することは、米国学者ダケの身に付いた錆、もとい、身だしなみであろう)。
<イスラエルロビー>に対処するには4つの方法がある:(p282)
『理論的にいえば、<イスラエルロビー>の持つマイナスの影響力を弱めるためには、四つの方法がある。
1 <イスラエルロビー>の力の源泉を小さくすることや、<イスラエル・ロビー>が影響力を行使する場合に用いる方法や手段の数を少なくする
2 他の団体が<イスラエルロビー>の政治家や政策決定過程に対して持つ影響力と対抗しようと試みることである。そうすることで、米国の政策はもっと中立的なものとなる。
3 これまで支持されてきた神話を訂正し<イスラエルロビー>の様々な主張に対抗することである。
4 最後に<イスラエルロビー>自体が現在持っている影響力を維持しつつ、これまでとはまったく異なった政策を主張するという肯定的な方向に発展していくことである』
CIAをはじめとして米国の強力な諜報活動を念頭に置けば、なぜ、イスラエルロビーが、書名にしなければならないほど問題となるのかわたしにはまったく理解できない。議員が金にそれほど弱い、ということか?(ニッポンと同じだが)。
訳者代表(実際に本書を訳したのは副島塾の優秀な弟子二人のようだ)である副島隆彦(反米憂国派国際政治学者)によれば、
『。。人々に先んじて本書を読むことは、これからの近未来を確実に予測しようとする日本人にとって緊要のことである。。。(略)
この強大な米国という、私たちの宗主国のように振る舞う超大国が、内部にこれほどの弱点と脆さを抱えていようとは。読めば読むほど驚きと発見の連続である。かつ最先端の米国事情を教えてくれる良書である。(略)
生の政治の泥臭さとものすごさに圧倒され、まさに圧巻である。「どこの国も同じなんだな、世界一の強大な国であるはずの米国の政治家たちも、一人一人はひどい目にあって大変だなあ」と本当に私は心底、同情した』
。。ということになる。
著者は第11章で、2006年の夏、イスラエルが起こした第二次レバノン戦争(イスラエル軍によるレバノンに対する無差別攻撃。市民が多数死んだ)を、<戦時国際法違反>として非難し、これをやめさせられなかった米国の政府の非倫理性・非戦略性を攻撃している。往事の政権なら(カーターや、パパブッシュなど)これにストップをかけたろう、と。しかし、レバノン攻撃はイラク戦争の縮小版であり、イラクに根拠無く侵略した米国が、倫理的、国際法的に、イスラエルの対レバノン無差別爆撃を非難などすれば嘲笑の対象になるだけである。
副島は、あとがきで言っている:
『来年(08年)11月に大統領選挙がある。あくまで私的で、予想の域を出ないが、私はバラク・オバマ上院議員が当選すると早くから書いてきた。今の時点でもそう考えている。オバマ候補の外交顧問に、ブレジンスキーが就任すると報じられた(略)そのブレジンスキーが本書を評して「この本を私は評価する」と発言している。ということはこの本の内容が、09年からの米国の外交政策の要になるということである』
。。で、オバマが政権を取って、何か変わるの?(変わろうとすれば、軍産複合体制が許さないだろう。ケネディ大統領、を想い出せばよい)
私はイスラエルロビーの存在が愚劣なイラク戦争を起こしたのではなく、戦争マシンはあくまで米国の軍産複合体制である、と考える。イスラエルの存在などは米国の軍産複合体制に利用されているに過ぎない(あるいは、もちつもたれつ関係にある、ならず者兄弟)。軍縮、とか、国連によるあるいは国連軍による国際秩序の維持。。など、著者等の関心の枠外のことのようである。
ニッポン政府あるいはニッポンのシンクタンクはこの著者等を破格待遇で、日本に招聘し、ニッポンの国益追求のために働いてもらうよう懇請できないものだろうか。この著者達なら、敗戦後半世紀も経つのに、ニッポンに広大な軍事基地を所有し、莫大な思いやり上納金をふんだくり、政策と予算に口出しする米政府を、<平時国際法違反>として糾弾してくれるかもよ、<ニッポン・ロビー>として。
著者等は、この本に対する批判に対し逐一反論する論文を書いた。下記サイトからダウンロードできる。
http://www.israellobbybook.com/setrecord.html
著者HP:
http://www.israellobbybook.com/book.html
『イスラエルロビーとアメリカの外交政策』ミアシャイマー & ウォルト著
http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2007-12-04
暗黒裁判の国、日本。 『公認会計士vs特捜検察』 細野祐二 (日経BP社)2007年11月26日発行 [Book_review]

この数年、これほど印象深い本を読んだことがない。私はこの本に関する予備知識はまったく持たず近所の書店の新刊書コーナーでタイトルを見つけ、その、はしがき、を読んでたちまち引き込まれたのである。
本の帯: 『粉飾決算はなかった! 会計論争で検事を打ち負かしても、1,2審有罪。「司法の闇」を弾劾する辣腕公認会計士渾身の書』
わたしはまず、公認会計士の職にある著者のその、職業を越えた人間としての正義感に打たれた。本書はビジネスマンにとって必読書であり、若い高校生などにとっても必読書である、とおもう(わたしが間違って高校の教師であったなら、ポケットマネーで10冊くらい購入し図書室に納めて、全生徒に読ませるだろう)。『政治社会』、『公民』教科書などを読むより彼らに、遙かに高いインパクトを与えることは確実である。 日本の司法はどうなっているのか?職業人の人権を個人は守る術はないのか?裁判所や弁護士は個人の人権を保護してくれないのか?検察とは何をするところなのか。
著者ははしがきで、本書を何のために書いたか、を要約している。
- この物語をすべての司法関係者に読んでもらいたい
- 報道記者の方々にも読んでもらいたい
- 公認会計士や税理士といった職業専門家の方達にも切実な課題を投げかけるだろう。そしてもちろん、
- 多くの一般の方たちにも読んでもらいたい、
...と述べている。
はしがきの、最後:
『本書で記述されている捜査当局のずさんかつ非道な捜査(古井戸: 検察、というより、ヤクザ=暴力団、という呼称がふさわしい)、および、一般市民の常識から著しくかけ離れた裁判の実態は、それが社会的に開示されないからこそ可能となっているのであり、その遠因は、司法に対する監視を怠り適切な開示を求めてこなかった。私自身を含むすべての国民の側の怠慢にもある。 この物語により、一人でも多くの方が司法の現実にふれ、国民による監視の必要性を感じていただけれるとすれば、この事件の体験者である筆者の望外の喜びとするところである。
2007年8月20日東京高等裁判所判決後、家内の告別式前夜
公認会計士 細野祐二』
検察の違法な取り調べ裁判所の検察への追従という逆境にありながら著者の冷静さは驚嘆にあたいする。 第一審判決(H18.3.24)で有罪、懲役2年、執行猶予4年を受けた後即刻控訴。控訴審にて、検察の数々の違法な取り調べやでっちあげ調書、偽装証言、新たな証拠が明らかにされたにもかかわらず裁判所はこれらを徹底的に無視し、控訴審判決(H.19.7.11)をくだした『被告人の控訴を棄却する』。 著者は直ちに最高裁に上告した。
日本においては刑事事件で逆転無罪を勝ち得る可能性は万に一つの確率である。 著者の奥様は病弱であった。10年来、再生不良性貧血を患っておられた(しかし、H15年の190日間におよぶ著者の拘置期間中、一日と欠かさず著者を拘置所に見舞ったのである)。二年前に骨髄移植を行ったが2006年9月に白血病を再発、著者の控訴審無罪判決を得るまではと、必死の治療もむなしく、控訴審判決直後の2007年7月31日に病状が悪化し、そのまま8月13日に帰らぬ人となられた。
『家内の位牌を胸に、最後に残された最高裁をもう一度闘ってみたい。人間の魂が究極の悲しみからの怒りを発したときに、この世で何事かできるのか試してみたい。もはや勝負は事実認定でもなければ法令解釈でもないであろう。 高等裁判所は証拠により立証された事実を無視し、偽証罪を乗り越えた真実の証言に聞く耳を持たない。問題は、検察官による証拠を無視した自白偏重型の違法捜査であり、司法の安定という虚構のもとで証拠によらない冤罪判決を濫造する裁判官にある。日本の司法制度そのものに巣食う病根を、私の事件に即して論証しなければ、最高裁無罪はありえないであろう。 7月下旬に、控訴審判決が弁護士を通じて私の手元に寄せられた。家内の再々入院、看病、死亡、葬儀をこなす不眠不休の中で、泣きながら控訴審判決を精読し、最高裁への上告趣意書を書き上げた。。。』(第十九章「上告」)
涙なしには読めない箇所である。
著者は監査法人の代表社員としてある中企業のために親身になってアドバイスした。それをこの企業のトップ(オーナーと幹部)はことあるごとに裏切った。あろうことか、著者による粉飾決算や背任への共謀という事実などないと知りつつ検察のでっちあげストーリによる調書に署名し、偽造証言を行い、大恩人である著者を検察に売ったのである(この偽造調書に基づく偽造証言を、検察はなんと裁判前に40回もリハーサルさせているのである。「証人テスト」といわれている検察のルーチンワークである。) この偽造証言には企業の弁護士までが加担しているのだ。この企業が東証一部上場企業、というのだから呆れてものが言えない。
さらに呆れたことに著者が長年勤務した監査法人はH16.3.9、すなわち、著者の逮捕された日に
「これは個人的色彩の強い事件である」
「重大な信用失墜行為があった」
と理由を発表して著者を解雇した。
こういう検察に尻尾を振る企業が多い環境にあっては、違法捜査、偽造証人偽造調書の無くなる日は遠いであろう。 さらに腹の立つことは順調な経営を続けていた中企業のトップが、健全経営という志の欠けているのをいいことに銀行や証券が先導して株価操作資金を提供する、などの犯罪スレスレの行為をこの企業に働きかけているのである。 (それにしても、著者の属する監査法人が顧客としたこの企業トップの倫理観のなさ。これが上場企業の経営者の実態か、と驚くばかり。著者は何度も、会社の隠し事が露見するたびに肝を潰しているのだ。上場に当たっては、企業代表者の人格、倫理感覚、信用度の厳格な第三者証明が要るのではないか?)
(注)細かいことだが(p220)。検察側が粉飾決算共謀の決定的な物証としているのは、平成15年3月に大友(企業側)から著者に直接手渡された1000万円の現金である。検察はこれを粉飾決算(平成14年12月の有価証券報告書に対する)への謝礼であると主張する。著者と企業側はキャッシュを渡したのは平成14年1月から3月にかけて、であると述べている。著者は、このキャッシュは開封されておらず銀行が付与した銀行統一番号が付してある。これを調べれば<著者が受け取った時期が平成14年初旬である>ことが証明できる、と主張している。しかしこれは証明できるのか?かりに銀行から大友にキャッシュが払い出されたのが平成14年以前であったとしても(平成14年中旬以降ならばなおさら)、それだけで、平成14年中旬以降に大友から著者に(粉飾決算への謝礼として)キャッシュが渡ったことを否定することはできないのではないか?著者が受け取った金が粉飾決算共謀の有無あるいは謀議への謝礼であったか、著者の企業へのアドバイザ代金であったかは、キャッシュ受領の時期とは、そもそも無関係であると思うのだが。著者は、粉飾決算などない、ということが会計学上明白になった、と主張しているのだからこのキャッシュ手渡し時期や、銀行からの振り出し時期にこだわる理由が不明である。さらに、同種の事件が今後発生した場合、公認会計士なり企業アドバイサが<共謀>嫌疑から免れるためにはこの種の謝礼(通常業務への謝礼か謀議への謝礼かの区別)をどう処理すればいいのか?細野氏は現金を受け取ったまま開封せず、オフィスの机の引き出しに保管しており、これを検察に押収された。細野氏のこの現金受領処理は正しかったのか?公認会計士の(対検察)危機管理、という問題である(この種の細かい点について、会計および法律専門家の書評、専門家による裁判批判、ディベートがまたれるところだ)。
なお、本書を佐藤優『国家の罠』の<公認会計士版>とみなしているひとがいる(本書中で、ある弁護士が著者の法廷闘争をそう呼称している)。とんでもないことだ。佐藤優の裁判は、本裁判に比べれば、外務官僚対検察官僚の馴れ合い捜査にしか過ぎない。被告(佐藤優)に対して『これは国策捜査だ』、と取り調べ検察官がシャーシャーと述べているのだからお笑いである。
『私には、この判決が憲法違反であり、著しく正義に反するものであることは疑いがない。しかし日本の司法の闇は想像を絶するほどに深く、その壁は公認会計士の全知全霊をもってしてもなお乗り越えられない。しかし、誰もが乗り越えることをあきらめざるを得ないほどの厳しい試練を神が与えるからには、神は私だけはそれを乗り越えられることもまた知っているのではないか。なぜなら神は私の無実を知っているからである。私の公認会計士としての闘いはなおも続く』
これが本書の締めくくりである。
わたしに企業会計の基礎があればもっと的確な読みと、書評ができたかも知れないのがつくづく残念である。 本書を書店でみつけたら、「はしがき」と最終章の最後の数ページだけは是非是非お読みいただきたい。
本書を読み終わって振り返ると、この著書中、意味不明(専門用語の意味の理解力の無さはさしおいて)の文章、読み返さないとならない文章は、ひとつもなかった。読めば、驚くべし、意味が分かる日本語で書かれている。最近では希有のことである。著者の読者に対する親切、である。
周防正行監督が『それでも僕はやってない』という映画を撮ったのはいつのことだったか?
http://
周防監督はこの本を読んでいるはずである。ぜひ、『公認会計士vs特捜検察』を映画化してもらいたい。最高裁判決が出る前に。早急に、である。 裁判所の職務怠慢と、検察の犯罪を国民の目の前に晒すことナシに日本の未来はないのである。
著者は監査法人解雇後も、会計事務所を設立して活躍しているとのこと。著者の健康と上告の勝利を祈る。

追記、12月10日
本書「はしがき」を再読し、これは引用しておくべき重要な著者のメッセージであると考えるので、長文になるが引用することにした(p4~p6)。
『本書は最悪の場合、証拠提出するつもりで記述したので、その内容は公判に堪え得る事実の厳格性を重視し、したがって、読者の利便性に対する配慮に欠けることがあるかもしれない。それもまた本書の特異な性質を表しており、むしろそのままの形で出していただけるよう出版社にお願いした』
『この物語をすべての司法関係者に読んでもらいたい。戦後62年、日本の司法は国民から切ないほどの信頼を得ているが、その実態はベールに隠されて、国民の目に触れることはなかった。しかし、それを体験したものにとってみると、日本の司法は激しく制度疲労を起こしていると言わざるを得ないのであり、その現実は本書に記載の通りである。 本件のごとき直接的客観証拠の皆無な経済現象が、共犯者とされる関係者の捏造された証言のみで(古井戸注:検事による捏造である)経済事件として立件され、あろうことか、まったくの無実の人間に有罪判決が出てしまうのである。制度疲労は、検察官だけではなく、裁判所にも、そして弁護士にもある』
『報道関係者の方々にも読んでもらいたい。日本の事件報道は、逮捕即有罪を前提したものであり、本件における報道もその悪しき伝統を濃厚に有している。これではあきれるほど長い年月をかけて無罪判決など取ってみたところで、被疑者の名誉回復など不可能ではないか。私は控訴審の過程において少なからぬ司法記者の方々と接触する機会を得たが、驚いたことに、彼らは例外なく捜査機関の不当な取り調べによる事件の捏造や、推定無罪の機能しない裁判の実態を熟知しているのである。それを知りながら、なぜ真実を報道しないのか?司法記者クラブおよび99.9%の起訴有罪率の中で、報道機関自身が本来の健全なる批判精神を忘れ、逮捕即有罪という予定調和に安住しているのではないか?』
『本書は、公認会計士や税理士といった職業専門家の方たちに、切実な課題を投げかけるであろう。検察庁特捜部はその犯罪捜査の主力を経済犯罪におくそうであるが、経済犯罪の現場には常に我々職業会計人の存在がある。我々には職業専門家としての厳格な守秘義務が課せられているが、残念なことに我々が守秘義務で守るべきクライアントは、事件の際には我々を守ってくれるどころか、反対にその責任を押し付け、自らの保身を図ろうとするものである。それでも職業専門家の守秘義務は重い。そこで、参考人としての取り調べ段階においては、業務上知り得た事項はこれをクライアントの了解無く開示できないとして、監査論の教科書に記載されているとおりの対応をしたところ、見事に逮捕されてしまった。現在の経済犯罪捜査は、職業専門家の守秘義務と両立できないのである』
『そして、もちろんのこと、本書を多くの一般の方たちにも読んでもらいたい。 (略) 本書で記述されている捜査当局のずさんかつ非情な捜査、及び、一般市民の常識から著しくかけ離れた裁判の実態は、それが社会的に開示されないからこそ可能になっているのであり、その遠因は、司法に対する監視を怠り適切な開示を求めてこなかった、私自身を含むすべての国民の側の怠慢にもある』
著者の以上の言葉は苛烈ではあるが、それは、司法関係者(アカデミーも含むだろう)、ジャーナリズム(とりわけ、記者クラブ)、公認会計士/税理士、一般人の正義に対するどうしようもないほどの無感覚に対応する。著者は「はしがき」では言及していないが(あまりに当然すぎて)、そもそも著者をこれほどの境遇に置いた原因は、著者の(属した監査法人)クライアントである企業の経営者、およびそれを取り巻く人間たちの、どうしようもないほどの堕落である。ばれなければ何をしてもいい、という人格欠損者がいかに企業に多いことか。彼らは検察に恫喝されて法廷で偽証を行った。控訴審で著者が有罪になった後、彼らは、親身になって企業をサポートしてきた著者を訪れ、偽証を詫びる。しかし、彼らが、上告審で前証言をくつがえすということはありえない。そうすれば、即刻、偽証罪という重罪をくらい、いま付与してもらっている執行猶予が吹っ飛び、背任罪の罪を受けるのだ(当然、のことなのだが)。検察は、偽証罪を犯してまで証言をくつがえすことはありえない、という確信のもとに偽造証言を強いたのである。背任罪は免れたが彼らは多額の借財を背負い、家族の生活もままならぬ状態である。『なんじ嘘をつくべからず』、ということである。法の道を外したものが罰を受けるのは当然だが、そうでないものがなぜ、罰を負わねばならぬのか、ということである。株価操作を行った犯人が罪にも問われず、企業の存続を願って骨身を惜しまず働いたものが罰せられる。検察の描いたストーリ通りに偽証をした何人もの人間の執行猶予付き有罪者を証人席にたたさずに(立てば偽証罪で刑務所行きである)上告審を闘わねばならない。これから始まる闘いの苦労が忍ばれる。
細野祐二公認会計士による無実の訴え
http://
いじめの構図 -7 2007-03-27
http://
http://
「キャッツ」株価操作:細野被告「検察が証人通じ事実捏造」--民主党法務部門会議
細野祐二事務所
蔵本由紀『非線形科学』 自然理解の「述語的統一」 [Book_review]

先日、夜、近所の書店で偶然手にした蔵本由紀『非線形科学』(集英社新書、2007年10月31日)は、ページをめくるなり著者の熱気が伝わってくる、胸の熱くなる書物だった(新書でこのような本は最近めずらしい)。どのページの、どの行も<流して書いたような>記述がなく、著者の意気込みが伝わってくる。主張つまりメッセージを持った人の書である。襟を正して読まねばならぬ、とはこういう本のことだろう。
内容は次の通りである。
まえがき
プロローグ
第一章 崩壊と創造
第二章 力学的自然像
第三章 パターン形成
第四章 リズムと同期
第五章 カオスの世界
第六章 ゆらぐ自然
エピローグ
全体は250頁。参考文献と索引が付いている。
目次から明らかなように線形的科学---わたしの理解によればニュートンあるいは量子力学の運動方程式、に初期条件を与え、積分すれば回答が得られるような世界を明らかにする科学、あるいは、この法則を基に観測対象を宇宙からミクロに設定して描ける世界--- ではなく、日常我々が特別の観測機器を使用することなく目にしている等身大の現象(非線形現象。それがいかに複雑であるか、従来の手法によっては捕らえがたい現象であるか)を、数式を用いずに分かり易く説明している。
わたしが強い印象を受けたのはこの本の端々にあらわれるが、とくに、エピローグに集中的に記された著者の科学観である。あるいは従来の科学観への違和感。
著者のメッセージは明確である。現在の科学の主流たる要素還元主義(超ヒモ理論もそのひとつだろう)への叛逆である。エピローグで著者は次のように述べている。
p244『このような自然観の信者たちは、科学という知識体系を一本の樹木のようにイメージしがちです。樹木の根もとには物質と時空の根源を探求する素粒子物理学があります。そこからはじまって、次には根本原理の応用、そのまた応用による大枝小枝が広がり、複雑多様な経験世界が末端にあります。しかし、このような見方は一部の信者のものというより、大多数の人たちが漠然ともっているイメージに近いのではないのでしょうか。そうだとすれば、ますます恐るべきことと私にはおもわれるのです』
p245『「不変構造」は「普遍構造」とも言い換えることができます。「普遍性と多様性」とは物理学者もしばしば口にする言葉ですが、前者が素粒子物理学の諸法則に、後者が物質科学レベルの諸現象に対応するのが、ごく当然であるかのごとく語られているのを見るのは、とても残念です。科学者はもうそろそろ脱してもよい頃ではないでしょうか』
これは強烈なメッセージである。
p244『樹木の根にさかのぼることなく、枝葉に分かれた末端レベルで横断的な不変構造を発見できるという事実を、非線形科学は確信させてくれました』
p246『よく考えてみますと「不変なものを通じて変転する世界、多様な世界を理解する」というのは何も科学に限ったことではなく、私たちは日々そのようなパターンにしたがってあらゆるものごとを理解し判断していることに気づきます。そうした理解や判断は何よりもまず言葉を通じてなされるわけですから、日常の言葉そのものが「不変なものを通じて変転する世界、多様な世界を理解する」という基本構造をもっていなければなりません。じっさい、私たちは「何がどのようにある」という基本パターンにしたがって、ものごとを理解しています。「何」と「どのようにある」という基本パターンにしたがって、ものごとを理解しています。「何」と「どのように」が変数になっていて、そこに値を入れる、つまり可変部分を不変にすることで知識が確定するわけです。あるいは、「何」を表すタテ軸と「どのように」を表すヨコ軸の交差によって知識を確定するといってもよいでしょう。このように、主語的不変性と述語的不変性の両軸があり、いずれを欠いても認識は成り立たないわけですが、特にここで注目したいのは述語的不変性です。
「愛犬が走る」「マラソンランナーが走る」「新幹線が走る」というように、「走る」ものの実体はさまざまです。「走る」という述語面にさまざまな主語が包まれるといってもよいでしょう。さまざまな実体が一つの述語的不変性によって互いにつながること、これはまさに非線形科学がカオスやフラクタルという概念を通じて、モノ的にはまったく異質なものを急接近させるという構造に酷似しています。とはいえ、これは単なる粗っぽいアナロジーですから、ほどほどのところで満足しておかなければなりませんが。』
p247~248『非線形科学で見出された現象横断的な不変構造は、単に述語的というよりも比喩、とりわけ隠喩に近い働きをもっているようにみえます。隠喩とは、たとえば「玉虫色」とか「氷山の一角」という表現に見られるように、元来何の関係もない異質な二物が突如結びつくことで新鮮な驚きを誘発する表現技法です。それに似た意外性が、非線形科学における現象横断的な不変構造にはあります』
『現象を支配する数理構造というものは外見からはうかがい知ることはできないものですから、共通の数理構造という深層でのつながりが表層では意外性をもつのでしょう。新しい不変構造の発見によって、個物間の距離関係が激変し、新しい世界像が開示される。このような機能が科学にはあるという事実は、もっと広く知られてよいことだと思います。そして、複雑な現象世界には、数多くこのような不変構造がまだ潜んでいるに違いありません。その発掘は、今世紀の科学の主要な課題の一つです』
これが本書の締めくくりのメッセージである。
著者は1999年に同じことを別の表現で語っている。岩波講座『科学/技術と人間』第四巻「科学/技術のニュー・フロンティア(1)」に収録の論文『開放系の非線形現象』。

p174『地上の現象は概して複雑である。その多くは惑星の規則正しい運動とは違って、一本の因果的連鎖をたどることで理解できるようなものではない。多数の因果的連鎖のからみや非線形効果のために予測は容易に裏切られ、突然のカタストロフィーが訪れたり、思いがけない美しい調和が生み出されたりする。近代科学は残念ながらこうした複雑現象を記述する言葉を充分に発達させてこなかった。とりわけ物理学は人間的スケールからかけ離れた世界の探求にはたいへん熱心であったが、そこから主力を撤退させてしまった。 (略) たしかに、物理学は自然の基本構造を説き明かすことをその身上としているが、近年の非線形科学が明らかにしたように、経験世界のまっただ中にも目を凝らせば自然の基本構造が見えてくる。「基本」や「普遍」の意味を少し広く解釈すれば、生身に感じられる自然の「質」を剥奪しないことでかえって見えてくる「基本」や「普遍」があるのだ。』
p180『メタファは、具体的事実を説明するための実体的モデルとは異なり、個別現象の中に自然が潜ませているある普遍的な「仕掛け」を見ようとするのである。したがって、実体的なモデルが確立した後でも、メタファの存在理由は大いにある』
『モノを「主語」とすればコトないし現象は「述語」である。したがって、物理学の体系は自然の「主語的統一」にもとづいた知識体系だと言えるであろう。主語的統一にもとづく意味体系は基本的に樹状の構造をもつ。ある科学的知見は、この階層構造のしかるべき位置に組み込まれたとき、あるいは近い将来組み込まれることが期待されるとき、物理的知見として認知される。ところが、樹状の知識体系の大きな欠陥として、末端に行けば行くほど細分化されるということがある。末端の多様性はすべてアトムから演繹できるとしても、アトムまでさかのぼらず、あくまで複雑な現象世界にとどまりながら統合的な世界像を描こうとすると非常な困難に遭遇する。考えられる唯一の解決法は「多様な現象の中の不変な構造こそが自然のリアリティである」という自然観に立つこと、つまり「述語的統一」にもどづいて自然を理解していくことであろう。そこでは対象の物質的成り立ちは重要でなくなる。 (略) このような述語的な場を発見し、それに明確な数学的表現を与えることが非線形科学の最大の使命ではなかろうか』
##
この分野にはまったく素人であるが、わたし自身の小さな疑問、それに課題:
著者の言う「多様な現象の中の不変な構造こそが自然のリアリティ」であるとする自然観が、なぜ「述語的統一」にもとづいて自然を理解すること、になるのかということである。たとえば、「雨が降る」という現象は文法的には<雨>が主語だが、われわれは主語たる<雨ツブ>が、述語的な<落下する>運動すると、雨現象を理解しているのではない。窓を開けたとき、眼前にひろがる <降雨>という現象を(降雨がある。。という現象が眼前に広がるだけである。なにが主語でなにが述語、というのは恣意的であってよいはず)、西欧からもらった主語・述語図式を強引に適用して <雨> が <降る> と記述しているだけにしか過ぎない(対象がそのような構造をもっているのではなく、さらに、理解する必要もなく、偶然にある時期に発生した(西洋)言語の文法をそのまま保存しているに過ぎないのに、である)。げんに英語であっても、 It rains. と意味のない帳尻あわせの主語=It を強引に記述上(文法上)の理由で登場させている。日常言語における主部・述部パラダイムと、認識における主部・述部パラダイムはレベルの違う話で、前者を保存しても後者に影響は与えないし、後者を崩すのは前者に比べれば遙かに容易のハズである。著者は従来の要素=実体還元的な物理世界観に抵抗しているはずなのだが、「述語的統一」、と従来型の世界把握に戦線を後退?あるいは妥協させているのはなぜか、というのがわたしの疑問であり不満である。
この「述語的統一」は、廣松渉のいわゆる「コト的世界観」とどういう風に関連するのだろうか、さらに、非線形現象ともいえる経済や、政治の世界にこの「述語統一的」記述は適用できるのだろうか。こういうことに興味がある。
(注) 上記の引用中、「不変」と「普遍」は、誤変換ではない。著者は区別して2つの語を使用している。
追悼 小田実 [Book_review]


小田実逝く。2007年7月30日深夜2時5分。都内の病院で。
小田実が末期癌であることは今年初めだったか何かの媒体で知った。1ヶ月前には朝日新聞夕刊に小田の病状、日々考えることを短期連載していた。この死は予期された死であった。
中学生か高校生の頃、わたしはまだ広島の郷里で過ごしていた。その頃、河出ペーパーバックで『何でも見てやろう』を読んで以来、これまで小田の本はもっともよく読んだ本のひとつとなった。じつは『何でも見てやろう』は、その時以後再読していない。(最近、ムスメに読ませようと講談社文庫版を買ってきてやったのだがトント興味を示さない)小田が<先天的無頓着症>をひっさげて、フルブライト奨学生試験に受かり米国から欧州アジアを周回してニッポンに戻ってくる間のこの旅行記はまだ海外を全く知らない田舎の小坊主のワタシには圧倒的な面白さであった。小田はその頃東大生であったはずだが、英語はまったくのブロークン。しかし、フルブライト試験(米国大使館で行われる)を受けたときその物怖じしない、ブロークンな回答が圧倒的に面白く,小田が大使館の一室で試問を受けているとき、その部屋は小田の評判を聞きつけた大使館員が珍答を聞き逃すまいと、鈴なりの賑わいだったという。
小田は大学でギリシャ語を専攻した。ある世界文学全集のギリシャの巻、ホメロスだったかを小田が訳す、という予告がなされたことがある。大いに楽しみにしたのだが結局実現せず、呉茂一(小田の恩師のひとり)の既訳におさまった(小田の弁解を読んだ記憶がある)。小田がなぜギリシャ語を専攻したか?はよくわからない。十代で文学を志し、当時の新進作家=中村真一郎に師事した小田実が、中村から「(中村本人はちゃっかりフランス近代文学をやっているくせに)大学で近代文学をやるなんてアホやないか」とけしかけられてギリシャ語を始めた、らしい。
 小田実全仕事 全10巻(河出出版)1970~71
小田実全仕事 全10巻(河出出版)1970~71
ソクラテスを描いた小田の初期の長編『大地の星輝く点の子』の注釈で、ギリシャ語をはじめた理由をつぎのように述べている:
「。。。やはり西洋のもろもろのミナモトのところを知りたく思ったのである。。。。さらにもう1つの理由があって、その理由は、この西洋のミナモト探求と微妙にからむのである。ギリシャ語なんて勉強するのは、貴族の末エイか大金持の息子だということをきかされていた。オックスフォードかケンブリッジに留学して、ホメロスの詩などを酒席で朗誦して、ついでのことに、日本の庶民はなっとらんな、デモ行進なんてバカがやることだよ、と言ったりする。そういう人の「ギリシャ」に実は私はウンザリしているのである。私が求めていた「ギリシャ」は、文人墨客の「ギリシャ」でもなければ、ペリクレスの「ギリシャ」でもなければ、オックスフォード、ケンブリッジの「ギリシャ」でもなければ、東京大学の「ギリシャ」でもない。たとえて言えば、民衆がゴタゴタと生きていてその民衆は私と何ら変わりなくて、ついでのことにもう一つ言えば、デモ行進するような「ギリシャ」なのである。ギリシャ語を学ぶようになって、最初に読んだ本が、プラトンつくるところの『ソクラテスの弁明』であった。なかに、おしまい近くのところだが「私に死を課した諸君、諸君に私は言いたい」とソクラテスが語るところがある。それは決然とした裁断のことばだが、私は読んで慄然とした。こんなふうにソクラテスにさえ見放された人間たちはどこへ行けばよいのか。私自身が、そうした人間たちの一人ではないのか --- 私は、そのとき、そんなふうに考えたのである。その思いは長いあいだ、私の胸に重苦しく残っていて、60年の1月から2月にかけてはじめてギリシャを放浪して歩いたときも、日本に帰りついた後もとりついて離れないで、ついに、この『大地と星輝く天の子』になった。63年の正月に書き始め、半年かかって完成した」
小田実がこの『大地と星輝く天の子』に後書き(『小田実全仕事3』への収録に際し)を書いたのは71年始めである。彼のギリシアへの関心は晩年まで衰えることなく、ついに、ロンギノス(ギリシャの思想家、西暦一世紀)との<共著>を出版するまで嵩じた。
『崇高について』小田実・ロンギノス共著 河合文化教育研究所 (1999/02)
ギリシャ古代の文人との共著。小田以外のだれがこんな破天荒な出版をココロミル?
小田のその後の活動はすべて、ギリシャ的発想に根拠を置く。 小田は70年前後のベ平連を率いた(小田をこの運動のリーダーとして、見出したのは鶴見俊輔である)。その活動はすでに数多くの著書がある。
彼の文学観について書いておきたい。1991年の座談会「戦後から未来へ」(埴谷雄高、中村真一郎、佐々木基一、小田切秀雄)が小田の文学観を知る上で便利である。『私の文学 -- 「文(ロゴス)」の対話』新潮社、2000年収録。
私の文学 -- 文(ロゴス)の対話 (新潮社) 
小田実「。。。戦後文学は、2つの価値があったと思うのです。。。古代アテナイの一番根本になっているのは言論の自由です。言論の自由のことをギリシャ語では一語で「イソロギア」というのですが「イソス」というのはイコールということです。「ロギア」というのはもちろんロゴスからくることばです。(中略)戦後文学の重要性は2つあった。ひとつは、「イソロギア」に見本をおいた政治観、文学観です。そしてもうひとつは「殺すな」ということじゃないですか。」(略)「せんじつめて言えば、私たちの過去は殺し、焼き、奪ったはての、殺され、焼かれ、奪われた歴史です。その歴史の総体から、殺される被害者が加害者になって殺すということを認識しなければ政治も文学もないということでした。それは私自身も存在しない」
この小田発言をうけて中村真一郎は言う:
「小田の言うとおりで、広島の原爆記念日の平和集会は、毎年、行われることは実に貴重なことだけれど、同じ日が日本軍に侵略された東南アジア諸国にとっては、解放記念日になるという事実、これは日本人のひとりとして、僕は口にするのが実に苦痛なのだけれど、あの集会が、専ら被害者の視点で行われると、周囲の諸外国の共感を得られないと、以前から考えていた。これは現実に原爆の被害にあって死んだ、個々の市民自身が、外国へでかけて加害者になったのではない、ということとは次元の違う問題です」(略)「僕は、小田君に対してでなく、当時の事情を知らない若い読者のために念を押しておくが、人間は加害者と被害者との二重構造の人間だ、という認識を最初に明確にしたのは、戦争中、上海にいた武田泰淳で、僕も日本人としての戦争責任を、一億総ザンゲ的ギマンではなく、正直に突きつめて、戦争直後の、文学者の戦犯追及運動のなかの上っ調子の部分に、戦争中の非国民狩りに似た心性を発見して、恐怖を感じた。そして、ジョイスの弟子のブロッホが、ナチの時代を生きた一般ドイツ市民の消極的に被害者であると同時に加害者であるという二重構造を造形するのに、ゾラ風の一元描写ではだめで、新しい全体小説の形式を発明したのが、僕の全体小説の形式論に大きな参考になった(以下略)」
この座談会の後書きで小田実は次のように述べている:
「私と私よりひとまわり年長の戦後文学者諸氏との距離がこの座談会で、ハッキリ出ている。。。彼らは戦争が来たとき、すでに(戦前に)、左翼の理論であれ、西洋文学であれ、日本古典であれ、何らかの拠り所を持っていた、ところが、私はいわば手ぶらでじかに戦争に対していた。私にとって、出発点は戦争そのものだった。あるいは、その戦争における「惨敗」としか言いようのない敗戦そのものであった。その出発点に立てば、「戦後文学」は、政治上の立場や文学観のちがいを越えて、すべてが戦争を通過した文学として見えた。いや戦後社会そのものが私にはそう見えた。その認識が私の出発点であった」
さらに『私の文学 -- 文(ロゴス)の対話』のあとがき(ロゴスの文学)で次のようにおのれの文学を規定する:
「。。「しゃべりことば」としての「ロゴス」にとって、大事なのは「デイアロゴス」-- 「対話」だ。人間には、もちろん、「ひとり言」ということはある。しかし、それが意味をもつのは、丸山真男流に言えば「自己内対話」としてあるときだけだろう。私は、「文学」はそもそもが「対話」だと考えている。その作品、その書き手と、周囲の他者との「対話」だ。他者には、読み手も社会も世界もがある。そうした他者との「対話」としての「文(ロゴス)が「文学」だ。そうでないものは「文学」ではないと文学ケイサツ官のようなことは言うつもりはさらさらないが、そうした文学は書いてきたつもりもないし書くつもりもない。また、他の人が書いたものとしても興味はない」
このような文学はいわゆる全体文学であり(小田の作品『現代史』など)、サルトルや野間宏などとその文学観は共通するだろう。サルトルは晩年(といっても、60年代だが)、『弁証法的理性批判』という熱に浮かされたような歴史論社会論を書いたが、これを文学でやったのが小田実だろう。ベ平連、の活動が彼を有名にしたが、この活動は彼にとって付録であり、余計なものであったろう、とおもう(もちろん、これが彼の文学を豊かにしたことには間違いなかろうが)。
高橋和己、開高健、小松左京、などと同世代である小田はわれわれ戦後の人間に対し、戦後文学ないし戦後文学者(野間宏、堀田善衛、中村真一郎、大岡昇平など)の解説者として現れた。そのなかで、一番説得性があったのがわたしには小田実であったということだ。

小田・中村『対話篇』1973年
 玉砕 (岩波書店)
玉砕 (岩波書店)
わたしが感動したのは小田実がドナルドキーンとの対談(小田の『玉砕』について。玉砕はキーンが翻訳して英語版も出版された。キーンが本当に感動した戦争文学はこれが初めて、と讃える傑作である)につけた「覚え書き」で<文学に対する「愛」>を語った一文である。小田はつぎのように言う。 『私の文学 -- 「文(ロゴス)」の対話』p296
「(ドナルドキーン氏の)『日本文学史』を読んでいると、近松門左衛門の「曾根崎心中」を彼(キーン氏)がいかに「愛」しているかが明快に読みとれて来る。主人公徳兵衛とお初との最後の「道行」について、彼が「このときの道行は、日本文学史上もっとも美しい文章のひとつと言えるだろう」とする「此の世のなごり、夜もなごり…..」から始まるくだりを引用したあと、「このような言葉でうたわれる愛は、われわれの心の奥底からの共感のみならず、尊敬をさえ呼びさまさずにはおかないのである。道行の徳兵衛は、われわれの目の前で歩きながら、一足ごとに背が高くなる」(徳岡孝夫氏訳)と彼が書くとき、それを読む私(小田実)の眼には、その徳兵衛の「一足ごとに背が高くなる」さまが見えて来るような気がする。その読み手に見えて来る力をあたえるものが近松の「文学」に対する彼の「愛」だ」。
文学に対する「愛」は、人間に対する「愛」であり、人の行為である愛に対する小田の感覚が彼の文学と行動の根拠となっている。小田を現象面から観察して、行動の人、行動派文学者などとひとはいうかもしれない。しかし、小田は感受性の人、ギリシャ的人間愛の人である。その出発点にあたって、民主主義の問題、ソクラテス問題をおのれの問題とした人間である。60~70年代あれほどの大衆運動とギリギリの政治活動(米国人脱走兵の逃走支援など)を行う人間のエネルギが感受性豊でない人から生まれるはずがない。小田のエッセイ、対談集から溢れるその愛情からわたしは大きな励ましを受けてきた。
中流の復興(NHK出版) 
発売されたばかりの小著『中流の復興』(NHK出版)でも、「米国に支援されたアロヨ体制とその共犯者によるフィリピン民衆の人権侵害、経済的打撃および主権侵害」を、「恒久民族民衆法廷」(2007年3月21日~25日)構成メンバーの一人として鋭く告発している。死に至るまで彼の思考に弛みはなかった。
1970年11月、三島由紀夫が自衛隊に突入し自殺するという事件が起こった。小田実はこの事件が小田に大きく決断を迫る事件であった、という。小田はこの事件からふたつのことを考え始めた。「ひとつは、まず、生きつづけること、第二に生きつづけるなら、いかに生きつづけるか。」(『ベ兵連・回顧録でない回顧』、p578以降)。三島がもてはやした『葉隠』にふれて小田実は次のように書いた:
「。。。それは、たとえば、『葉隠』という書物のどこに私自身がいるか、ということだ。なかにこんな話があった。中野杢之助良順という名前の武士が涼みに小舟に乗って隅田川に出る。ならず者が同じ舟に乗ってさんざん乱暴を働く。武士はならず者が小便するところを見はからって首を切る。首は川に落ちたが胴体は舟に残る。人気のないところに埋めてくれれば金をたくさんやると船頭を言いくるめて、その残った胴体を埋めさせる。そうしておいてから、武士は船頭の首を切る。そのあと、もちろん、世の中には何の噂も流れない。」問題は「この話のなかのどこかに、私はいるのか。この話に出て来た三人の登場人物のうちの誰が私なのか」ということだ、と私は書いた。私はその自分の問いに対して答えを次のように書いた。「私がこの話を読んでたちどころに自分を同一化したのは、船頭だった」「彼にはまず名前がなかった。そして、彼は日々のくらしに忙しくて、生きることにまず追われていて、(葉隠が説く武士のカガミのように)『毎日のように死を考える』余裕はなかった。その(死の準備の)ために化粧してまで、日常を美的に生きる余裕などはなかっただろうと私は思う。」
私にとって、三島氏たちはこの話のなかでの「武士」だった。あるいは「武士」の側に身をおこうとしている人たちだった。同じことは、彼らの死によって衝撃を受け、「自分たちの側に三島氏を出さなかったことは自分の敗北だ」と彼らの行為をとらえた「全共闘」運動の指導者にも言えた。あるいは「三島事件はこのどうしようもなくくさりきった時代に対する警鐘だ」という投書に端的に見られるような当時の一種の三島氏らの行動への暗黙の支持の風潮にも、それは言えた。 (略) 「たとえ、それが精神的な意味あいにおいてであろうと、たとえば、武士たちがどのように美しさにみち、けだかい狂気にみちたものであろうと、そうした生き方を示していようとも、私はそこに身をおきたくない。それは私のひとつの決意であり、その決意を、私の生き方、考え方の基本にすえようと思う。」(略)
(船頭の)「その死に、自分の生き方、考え方、感じ方の根本をすえることだった。私がそうするのには、一つには、私自身が私なりに体験した過去の戦争体験があるにちがいない。」「船頭」の死は、まさに私が体験したなかでおびただしく見た「難死」だった。(略) 「私の戦争体験が私に強いた認識は、私があわれな船頭以外の何物でもないという事実だった。その事実を認識することから、私は、自分の反戦運動への参加の原理、そして参加そのものへの基盤をつくり上げて行った」 (『「ベ兵連」回顧録でない回顧』、p581)
 「ベ平連」回顧録でない回顧(第三書館、1995)
「ベ平連」回顧録でない回顧(第三書館、1995)
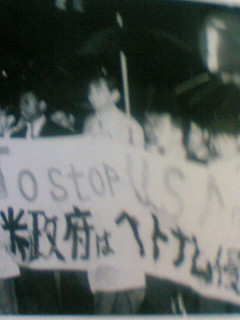
小田の死んだのは本日30日の早朝である。彼の著作を再読、再々読し、小田の精神に対決すること。これが彼への恩返しであろう、とはいうものの今日は朝から一日溜息ばかり、小田実がこの世にいないことの寂寥つきることなし。
小田は、スベテヨシ、と頷いて此の世を去ったのだろうか。
『。。あなたの最後の小説のタイトルの通り、「終らない旅」は確実に多くの次の世代の人びとに受け継がれ、国家と軍隊と暴力から離脱し、個人として自律の道を切り開く旅は、決して終らずに続けられてゆくものと、私は確信します。あなたは千の風どころか、何万という人々の胸の中に居続けることになるのでしょう』
告別式における吉川勇一氏の弔辞の一節である。
http://www.jca.apc.org/~yyoffice/saikin79OdaMakotoSougiChouji%5D.htm
 小田実告別式後のデモ・先頭は鶴見俊輔(朝日新聞8/5)
小田実告別式後のデモ・先頭は鶴見俊輔(朝日新聞8/5)
河出書房・現代の文学 
 (「ベ平連」回顧録でない回顧から)
(「ベ平連」回顧録でない回顧から)

自宅療養中@2007
小田実
作家。1932年大阪生まれ。51年(19歳)小説『明後日への手記』出版。このころ中村真一郎の知己を得る。61年『何でもみてやろう』、63年『大地と星輝く天の子』、小田実全仕事10巻、70~71年。その他多数。
小田実ホームページ
TIME誌記事 Asian Heroes@2006
http://www.time.com/time/asia/features/heroes/oda.html
小田実インタビュー(英文)@2006
http://www.indybay.org/newsitems/2006/03/14/18076761.php
関連記事: 小田実の考えてきたこと http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2008-03-27 小田実『大地と星輝く天の子』 http://furuido.blog.so-net.ne.jp/2009-05-16-1「戦後天皇制は可能か」 渡辺京二あるいは北一輝の天皇制論 [Book_review]
渡辺京二評論集成 第一巻『日本近代の逆説』(葦書房、1999)に、「戦後天皇制は可能か」という渡辺京二の天皇制論が掲載されている。以下、本論文から、抜粋・引用する。<擁立された天皇>という北一輝が示したアイデアを、近代天皇制の秘密についての鋭い啓示としてこれに従いながら、渡辺自身の見解をコンパクトにまとめている。

本書、p215。
『(略)
私(渡辺京二)は、戦前の天皇制と今日の「天皇制」はまったく性格を異にするもので、それゆえにこそ昭和二十年の敗戦はひとつの革命だったのだと信じている。松本清張のように、国王の首がとばねば革命ではない(松本清張『北一輝論』)と信じている阿呆は、このさい論外である。われわれは敗戦と戦後改革とが、まぎれもない一個の革命だったことを、ひややかに承認すべきだと思う。むろんそれは、戦後の「革命家」たちの幻影のなかにあった革命ではなかった。しかしそれは、戦前の天皇制社会の構造を完全に変革したのである。
戦前的天皇制国家が敗戦革命によって消滅したことを承認する以上、戦後の天皇を、戦前における天皇がそうであったようなひとつの思想的原理として相手どろうとするのは、北一輝流にいえば、言葉に対するモノマニアックな固着にすぎない。北が『国体論及び純正社会主義』で主張したことのひとつは、古代的天皇、中世的天皇、明治国家における天皇は、それぞれ性格を異にする歴史的範疇だということであった。それが「天皇」という共通の呼称をもっているからといって、その歴史的性格を混同し、たとえば明治国家における天皇に古代的天皇の歴史的性格を付会するのは、理論的にも実践的にも許されぬ誤謬だというのが、二十三歳の北にとっての「科学的認識」だったのである。
だが、明治国家の天皇に古代的天皇の神権的性格を付会せしめたのは、明治国家の支配エリートの必要であったと同時に、いわゆる皇統連綿たる天皇家の歴史的継続性であった。今日、戦前的な天皇制の消滅を認めながらなお、思想的問題として天皇制を重要視せずにおかれぬ人たちは、おそらくこのような天皇家の歴史的継続性に、おそろしく根の深い民族的固疾を見出し(固疾の固は原文ではやまいだれが掛かる)、その亡霊を思想的敵としてあいてどらずにおかれぬのであろう。
(略)
だが。。。。そのような天皇制の歴史的継続性に関する思いこみは、ひとつの錯視の産物である。戦前日本国家における天皇は、この国の歴史のごく一時期にだけ存在した特異な歴史的現象で、それが体現しているかにみえた神秘性や魔術性は、戦前日本社会という特殊な歴史的民族社会の構造の関数にすぎなかった。そればかりではない。天皇家の歴史をよく見なおして見ると、それが千数百年の生命を誇りえているのは、いくつかの歴史的条件の偶然的に幸運な組み合わせに負う点が多いことが理解される。
(略)
彼(北一輝)は、天皇が明治国家において議会とならんで国家意志を代表する一機関たりえているのは、ただ維新革命によって国家の必要のために擁立されたからであり、天皇家の連綿たる伝統などとは論理的にはまったく無関係だと考えたのである。
つまり北がいわんとしたのは、近代日本国家の天皇は、それまで存在していた中世的天皇(さらにさかのぼれば古代的天皇)とは、少なくとも論理的には何の関係もない「国家」の被造物だということである。彼は、そんなものが維新革命によってつくり出されたのは、歴史の必然的一過程としての錯誤だとさえ考えていた。今日の眼で見れば、この北の直感はおそろしく正確だったことがわかる。徳川家をしりぞけて近代日本国家の神聖君主となった天皇は、じつはそれまでの全日本史の上にかつて存在したことがないような異様な天皇であった。それはこの国の歴史で、わずか八十年だけ存在を許された特異な現象にすぎなかった。いいかえればそのことは、戦前の天皇制国家がすでに生成と死滅のサイクルを了えた一回きりの特殊な歴史現象だといことを意味する。これは戦後の「天皇制」を論ずる場合、何をおいてもおさえられねばならぬ最重要の前提であって、この点をおさえていない議論は一切何をいっても無効だというふうに私には感じられる。
維新革命が創出した近代天皇制はすでにその歴史的使命を終えた。今日存在するものは、戦後市民社会の構造と矛盾せぬかぎりで残存せしめられているその遺物である。
(略)
王制は今日世界的規模で実質を失っているが、形式においても、それが21世紀を通じて生き残らねばならぬ理由は絶無だといっていい。
今日の天皇が千数百年の余栄を負うて発しているかにみえる残光についていえば、そういう歴史的継続性の光輝自体が、明治国家の設計者達が細心につくりあげたフィクションであったとすべきである。戦前の天皇に付与された歴史的光輝や儀飾は、彼らが古代的遺制に手を加えるか、あるいは大幅につけたすかしてつくりあげたものにすぎない。維新前の天皇の性格は、衰亡に瀕した古代専制君主の遺制プラスとるにたらぬ京都近傍の小封建領主であって、もし維新革命の指導者がうちすてておいたならば、革命のもたらす外光と外気に触れて、遠からず頽然と崩れ落つべき運命にあった。幕末にあって天皇は尊皇イデオロギーに浸潤された武士や神官や国学者をのぞく日本人大多数にとって、生存上いささかも意識せずにすませうるような存在でしかなかった。それを千数百年間、たとえ現実の支配権は失っても、たえず日本人の魂の奥底に生き続けて来たものであるかに定位しなおしたのは、まったく明治国家の設計者たちの意識的な労役にほかならない。
(略)
北の論理構成においては国家は国民と同義である。だから彼には、国民が革命のためひろいあげてやった天皇が、自分を神権的国王であるかに思いちがえて国民に対し支配者然と君臨しようとするのは、許しがたい反革命的な倒錯にさえ感じられた。国家がその必要から創設したものなら、国家はそれを「進化」に応じて自由に改廃することができる。
(略)
彼ら(明治国家の建設者)は新しい民族国家を共和国として構想する途を、先験的に封じられていた。なぜなら彼らは、封建領主の家臣としての三百年に近い記憶に縛られており、高貴でより正統な君主を探し出さずには、それまで臣属してきた君候への忠順の義務を解除するために案出された論理だという北一輝のみかたは、その主観的な意図についてはともかく、客観的な役割についてはおそろしく鋭い指摘といっていい。うがっていうならば、彼らが、かつて一度も臣属したことのない天皇の、譜代の忠臣であるかのような自己幻想を昂進させたのは、先祖代々奉公してきた君候を棄て去ったやましさの代償でさえあったかも知れない。
(略)
彼ら維新革命家が一国の国民を<臣>としてしか発想しえない武士階級であったことは、天皇を東洋的デスポットとして新生国家に君臨させた直接の原因だったといいうる。
(略)
彼らは、天皇のために革命をやったのではなく革命のために天皇を必要としたのだという自覚を、意識のかたすみにしっかりと残していた。彼らが天皇を「玉」と呼ぶことがあったのはそのためである。彼らは戦闘専業者の本能からして、何よりも軍事的に強力な国家を求めた。列強に併呑されぬ強国を建設することが、彼らのほとんど唯一の革命のエートスだった。しかも、知的に優秀であった証拠には、彼らは西欧列強の軍事的優越の秘密を瞬時に見ぬいた。彼らの発見によればそれは資本制であった。資本制にもとづく国民国家イークォル軍事的強国。この等式を見ぬいたと信じたとき彼らの進路は決まった。国家による資本制の創設、それが明治国家建設のかならずしも自覚せざる意味のすべてだった。
以下略」
原論文の初出は『伝統と近代』52号(昭和53年5月)

『国体論及び純正社会主義』は101年前の5月9日自費出版、5月14日発禁処分。
http://www.shoshi-shinsui.com/book-kita.htm
関連記事:
東京裁判、北一輝:
http://
天皇問題
http://
白村江以後 石川九楊『書と日本人』 [Book_review]

663年、白村江の戦いは日本古代最大の対外戦。この戦いでヤマト政権の水軍は白村江で唐と新羅の連合軍と戦って壊滅的な敗北を喫し、多くの百済の亡命者とともに畿内政権の軍勢は敗退を余儀なくされた。現在までのところ、第二次大戦で連合国(米国)による占領、それに元寇を除くと、ニッポンが外国の占領下に入る危険が最も高かった敗戦である。いや、独立国としての<日本>が真に発生したのは、白村江の戦いに敗れたのち、というべきか。白村江以前、ニッポン列島には人びとは大陸・半島と自由に行き来していた。劣等の位置づけも大陸・半島の貿易出先機関のようなものであったらしい。この敗戦が、国家・社会・文化、そして対外観に大きく影響を与えた。この戦いでは、九州から東北地方におよぶ広い地域からの募兵をおこなっており、さらに万人単位の大規模な兵力の渡海を考えれば、それは日本史上、空前の大戦争であった。
白村江の戦いに敗れ、半島とそれにつらなる大陸との関係を絶たれたヤマト政権は、中国の政治制度をとりいれた律令国家として独立する。その独立国である新生ニッポンを挙げての文化学習運動が<写経>であった、という(石川、『書と日本人』)。

石川九楊によると、日本の文化の特徴は、
「。。西欧やイスラム世界、インドとの違いは東アジアの漢字・漢語・漢文・漢詩文明圏に属することが第一であり、次いで同じ東アジアの中国や朝鮮半島、越南(ベトナム)と異なるものがあるとすれば、その最大のものは女手=平仮名の誕生と、それによる和語、和文、和歌による文化的表現力の拡張にあります。日本文化史の特質は、漢語と和語、音と訓の二重複線性という点に尽きると言えます」
「奈良時代とりわけ天平時代を中心とする熱心な写経による識字運動の結果、『日本書紀』は漢文、『古事記』では漢文のみならず漢字による音写の書法で倭語を文字言語化することに成功し、『万葉集』はいわゆる『万葉仮名(漢字)』で、倭語の表記に成功しました。ちなみに万葉仮名自体は『万葉集』の成立以前からありましたが、『万葉集』に多く用いられたために万葉仮名と言われます。」
「言<はなしことば>と文<かきことば>との間には必ず落差がありますから、『万葉集』の歌があるからと言って、私たちが朗唱するような歌が無文字の倭にあったとは言い切れません。倭語は『古事記』『日本書紀』あるいは『万葉集』の編纂を通じて書字・書記の現場で作られていったものです。『万葉集』成立以前には、そこに定着された言葉(以上)に、さまざまの語彙や文体、言<はなしことば>の構成法(前倭語)が多様、多彩に存在したと考えられます」
現在でも地名や動植物名など、身近なものであればあるほど各地方によってさまざまな語彙が見られるが、無文字時代の倭にはもっとたくさんの言い方があったはず。
「。。たとえば、漢語・雨<う>に対応する雨<あめ>と言っても、その降る季節や時間帯、さらにはその状態によって、現在でもなお、ハルサメ・サミダレ・コヌカアメ・ユウダチ・トオリアメ・シグレ・ムラサメ・ヒサメ・ミゾレと呼び分けられているほどですから、雨に対して<あめ>ではなく<たれ>や<れ>という和訓、和語が生まれた可能性も考えられます」
「当時はひとつのものに対して数多く語彙があったはずです。そのような多数の語彙のなかから、畿内周辺の知識人の使う語彙から厳選して、ひとつの言葉を定め、ひとつの書法(文体)を定めていくという作業が行われたのではないでしょうか」
すなわち。。。
「漢字を当て嵌める以前は、ひとつのものに対していろいろな名称がついていたが、それが整理され、そのなかからある種の言葉が選ばれて記され、記されたことによって固定する -- そのようにして生まれたのが倭語です。そしていったん書きとどめると、それが標準語のようにひとつの規準として、再度逆に普及し、仮名<かな>文字を使う層が識字階層の周辺に定着していくことになるのです。
この過程は、言<はなしことば>の倭語を文字で固定したというよりも漢字・漢語を媒介に「倭語をつくった」という方が近いと思う。。。文字は言葉を書きとどめる記号に終わるものではありません。逆に文字が発音を規定することもしばしばです」
「たとえば、「あめ」と書かれた音がもともと ame であったかどうかはわかりません。 woamie と発音されていた語を母音と子音の一体化した音節発音記号・音節文字しかない段階では「安免」と表記せざるをえず、はじめのうちは woamie と読んでいたが、やがて平仮名化によって「あめ」と表記されるようになり、「アメ」という発音が固定したとも考えられます。このように文字によって音韻が変化することも多く見られ、無文字段階に現在表記されているような発音をしていたとは考えられません」
「また、奈良時代には八母音であった日本語の発音が平安時代中期以降に五母音に転じたと言われていますが、正確には奈良時代には八母音で書きとどめられただけのことであり、おそらく実際に発音されていた母音はもっと多く、現在の中国語や朝鮮語(朝鮮半島および周辺地域で使用されている言語。大韓民国では韓国語という)に近いものであったと想像されます。五母音も同じで平安中期つまり平仮名=女手誕生以後は、五母音で書きとどめられるということにすぎません。そして書きとどめられることによって五母音化し、綴字発音に従って発音が変化していったのです。
もう少し想像をたくましくすると、朝鮮半島と日本の関係、特に朝鮮半島南部と北九州は同じ海をへだてた、否、海によって繋がれた隣り町に位置しています。したがって、それほど言葉が異なっていたとは考えにくい。にもかかわらず、現在の朝鮮語と日本語の発音は大きく異なっています。それはもともとの発音が違っていたのではありません。朝鮮半島では、長い間民衆は無文字の社会、政治を司る上層部だけが中国語を用いる、という言語形態が長く続きました。それに対して日本では平仮名が生まれ、それに応じて平仮名発音 -- それは母音と子音をひとまとめにした音節発音で、非常に平板な発音 -- が生まれました。これは、平安中期以降、女手(平仮名)が生まれ、女手に合わせて、女手発音化することで、生まれた日本語の発音であると考えられます。
女手つまり平仮名成立以前の『万葉集』の奈良時代の発音は現在よりも、はるかに多彩な母音と子音を持った発音だったことでしょう。その頃は朝鮮語や中国語に近い発音をしていたのではないかと、容易に想像がつきます。日本語の発音が八母音だったのではなく、八母音で書かれたにすぎません。やがて、女手=平仮名ができると五母音になります。この時、八母音から五母音に発音が変わったのではなく、「ンクウァ」や「ンクウェッ」などの発音が「か」や「け」と五母音の文字で書かれ始めたにすぎません。
いずれにせよ、『古事記』『日本書紀』『万葉集』の時代に倭語が書かれ、固定されていくことになります。倭語とは、あくまで漢語を前提として、それとは異なる訓み(よみ)、「訓」として創られた言葉です。
したがって、「倭語」が古来からこの孤島にあった言葉であるとは、言いきれません。もともと孤島にあった言葉とは、前アイヌ語、前沖縄語のような書きとどめられることのなかった前倭語であったと考えればいいでしょう。」
「さて、それでは、これらの『古事記』や『日本書紀』や『万葉集』の記述者はだれでしょう。
当然漢字と漢語つまり当時の中国語に堪能であった人々ということになります。
(略)
それは、現在考えるような外国人(帰化人・渡来人)ではありません。大陸・半島そして孤島の人々が区別なく、いっしょになって新しい律令日本を築いていったのです。
このように、万葉集の時代には、中国大陸や朝鮮半島の人々を含め、あるいは彼らが中心になったといってもよいかも知れませんが、文字を駆使できる書き手が、中国の史書に倣い、文をつくっていきました。
(略)
『万葉集』は、日本でうたわれた歌、あるいはあちこちにあった歌をよせ集めたと言うよりも、あくまで「白村江の敗戦」によって大陸から新たに分離・独立した新生日本の国づくりの歌集である『万葉集』を編むために作られた歌からできていると考えるのが妥当だろうとおもいます。もしも、そうでないとするならば、もっと複雑で、発音も異なり、意味不明の歌が膨大に集まったはずです。」
以上、石川『書と日本人』(新潮文庫)p26~51から長い抜粋・引用を行った。日本語の起源、漢字と日本語の関係についてこれほど明快な解説をわたしは読んだことがない。なお、『日本書紀』の記述に当たったのは、日本の文物をまったく解しないおそらく大陸から渡ってきた中国人であろう、と大野晋は岩波文庫『日本書紀』解説に書いている。
#
石川『書と日本人』新潮文庫の解説で、中西進はつぎのように述べている:
朝鮮半島や越南と違って、「日本の政治支配・幕府は漢字仮名交じりの和風の書風を公用書体とし」ていると、石川九楊が述べていることに関して。。。
「(中国では)これほどに、漢字は支配言語なのである。だから、支配にたずさわった帝王ならびにその周辺の行政官はみんな漢字漢文に習熟し、公文書も漢字で書いた。漢字が男手であることもよくわかる。
ところで一方、中国には極端に少ないテニヲハが、朝鮮や日本には多い。そこで漢文を元にしてテニヲハを表す音標文字を発明した。まず朝鮮で吏読(りと、あるいは、イドウ)と呼ばれるものが発明され、日本はこれをまねて万葉仮名を作り、やがて仮名を完成させた。
そこで日本では日本語をそのまま書くことができるようになった。つまり漢文に独占されていた文字が、和文にも使えるという革命がおきた。
(略)
漢字と仮名を男手と女手というように書き手の区別から眺めてみると、漢字仮名交じり文を公用書体としたことは、支配への生活文化の侵犯であり、限りない男文化への女文化の侵入であった。石川氏はこのような文化が朝鮮にも越南にもないというのだ。
もし日本人がテニヲハを使わなければ、どういうことが起こるだろう。嫋々(じょうじょう)と流れる情緒などは到底望むべくもないだろう。理屈ばった日本人ばかりになる。理と情ということで区別すれば、情緒豊かな日本人の感情は表現できず、反対に論理的な思考法が発達したかもしれない。
またテニヲハとそれ以外を辞と詞によって考えたのが国語学者・時枝誠記(もとき)だったが、日本語はテニヲハつまり辞によってこそ、感情が表現されると考えられる。たとえば、「前」とだけいってもなにやら不明で「前が」か「前を」か「前へ」かによって「前」ということばが生かされる。
こう考えると日本が公用書体としても仮名まじりを許容せざるをえなかった事情がよくわかる。言語としての特性と書体は、鶏と卵の関係だったにちがいない。」
参考書:
網野善彦『日本社会の歴史 上』岩波新書
森公章『「白村江」以後』講談社選書メチエ
関連記事:
中井久夫『関与と観察』 みすず書房 2005年 書評
http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2006-11-09


<明治にクレーしたこの人をミロ>

空海を超える書の巨人・副島種臣 
『芸術新潮』1999/9 特集「明治維新を筆跡で読む: 志士たちの書」より






