『発明マニア』 (毎日新聞社) 米原万里 [Book_review]

http://mainichi-shuppan.com/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=978-4-620-31805-9
まずこのボリュームに驚く: 500頁、二段組、小さな文字でビッシリという分量。この本の内容はサンデー毎日の連載:2003/11/16 ~ 2006/5/21。 ということは、米原万里が癌で亡くなる直前まで、書き続けたと言うことだ。しかも、週刊文春・書評と並行して(『打ちのめされるようなすごい本』)。
米原万里の発明本、工夫本、How to 本。。。というのが本書の案内・宣伝だが、『他諺の空似』、と同じく万里の眼の届かざるところ無く、地球の東西南北、時空を貫く辛口の時事評論、あるいは書評としても十分通用する内容である。
最後のページからめくると。。
2006/5/21 国際化時代に最も不向きな対立回避症克服法
2006/5/7・14 居座る借家人をなるべく金をかけずに追い出す法。。借家の話から、年間六千億円を越える対日駐留経費を踏み倒している米軍。。の話まで。
2006/4/30 不眠症に効く最良最強の薬 2006/4/16 勝利で負けたと見せて実利はガッポリいただく裏技のお手本 チェイニー@イラク、の金儲け方法。。
##
書評なら本を与えられればなんとか書けるだろう。『他諺の空似』のように 諺、とテーマが決まっていれば辞典をひっくり返し、それに時事話をからませれば、なんとかこなせるだろう。。この本のようなかなりセバイ内容をどうやってこなすのだろうか?想像するに、万里ぃは、週刊誌、新聞を読みながらこの本のテーマになりそうなものをチェックし、メモを貯めていたに違いない。など、と考えながら読み進めるうち、p292、#71 「故ローマ法王・ヨハネパウロII世の秘密大発見」まで到達。。。これは。。スゴイ。。KOされてしまった。ここでは絶対に、話せない。とにかく抜群の小話クリエータ、としか言いようがない。その発想の豊かさに驚くと共に、癌におかされ、闘病中にもかかわらず、途切れることのないユーモア感覚と、批評眼の鋭さ。亡くなって一年が経った今、また万里ぃ魂で勇気づけられる。感謝、というコトバしかない。
##
毎回、イラスト付き。 イラストレータ=新井八代 ARAI YAYO 。。これは米原万里の別名である。。
挿絵@最終回2006/5/21 挿絵@2006/5/7・14


4/16 追記
夕べ、床で考えたのだが。。万里さんがサンデー毎日、週刊文春で連載をやっていたのは、闘病生活に耐えるための作戦・発明だったのかもしれないな。闘病だけ、の、日常ではそれこそ耐えられない人生になる。
4/17 追記
読み終わった。毎回、長さにして。。そう、天声人語の4~5倍の短文エッセイだ。とにかく何を書いてもよいとはいうものの、シリーズ名として<発明マニア>と冠している連載だから一応ソレらしい体裁と内容にはしなくては読者と編集部にアイスマヌ、くらいのことは考えたのか。スゴイ、とおもうのは文章をアキさせず読ませる、文章の運び、歯切れ良さ、これは天性のワザ、である。おそらく通訳業から得られた、コトバとはこうあるベキもの、という文章エシックスが万里ぃにはあったのだろう。 出だし、途中、それに、締め、の一句も素晴らしい。 〆の一句をあらかじめ考えて、書き出すのだろうか?それとも、そろそろこの辺で〆なきゃ、というときに〆の一句が自在に浮かんでくるのだろうか。
とにかく、マリィのこのエッセイ、文章のオーラス、〆の一句だけを拾い読みしても面白い。
知的関心、情報量なら『打ちのめされるようなすごい本』、エンタテメントなら『発明マニア』、『他諺の空似』 。。と、とりあえず言えようが、もちろんこの双方の能力、相互に支え合っているのだ。
改めて言うまでもないが万里さんの本を読んで、快適なのは、日本語のリズムがよいこと、どの一行を取っても意味不明の箇所はもちろんない。さらに、内容が薄くない。この本の場合、ファクト(とくに科学に関する、ファクト)に強くないと、一行も書けないタイトルが多い。ファクトに強いからと言って大学の理学部教授には論文は書けても一般庶民が読んで愉しくタメになるエッセイが書けるわけでもない。新聞社の科学部記者よりは万里ぃさんのほうが科学性、論理性に勝る。たとえば、
#64 温暖化による海面水位上昇を食い止める法
#65 同上、その二
#80 森林資源を守りゴミを少量化するための紙の複数回利用法
こんなタイトルで週刊誌見開き二頁にエッセイを書こうとするとカナリの苦労である。材料は科学的ファクトであり、想像の産物だけではこなせない。
p269 #65から抜粋。
「この砂漠化が生じる仕組みというのを見てみよう。
地球温暖化による雨量の減少や気温の上昇、過剰消費状態にある先進国国民の生活を支えるための無茶な森林伐採、土地の酷使などによる土地荒廃によって、地表面の水分が激減し、そのことによって空中の水蒸気が減少し、地表の温度の上昇を促すため、さらなる乾燥が進行し、乾燥した地表面の微粒分子が空中に舞い上がり太陽光線を吸収する。この微粒子は太陽光線を遮り、地表面を冷却する一方で、微粒子が吸収したエネルギーが低空の大気を温め、地表と低空大気の温度差が少なくなる。その結果、降水量が減るため、さらに土地の乾燥化が進むという絵に描いたような悪循環で、しかも加速度がついてきているのだ。」
科学のコトバである。下手に説明するとごてごてする内容を、実にスッキリ説明している。
#65の書き出しは。。。
「前回(#64)はカーボン・ナノチューブで月面に海水を送り込む方法を提案したが、もう少し安上がりかつ手軽に済ませられないものか、愚考した」
ひとを喰った、まさに我が道を行く、というか。知識と度胸、文章力のある実力派でないと書けないエッセイなのである。
 (挿絵)地球からチューブで海水を月に送る。。
(挿絵)地球からチューブで海水を月に送る。。
米原万里 『打ちのめされるようなすごい本』 書評
http://
佐藤優、山川均の護憲論、天皇制 [Book_review]
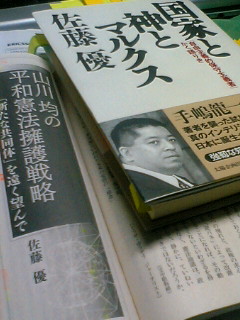
雑誌『世界』5月号に佐藤優(外務事務官、起訴休職中)が
山川均の平和憲法擁護戦略 「新たな共同体」を遠く望んで
という論文を書いている。佐藤は護憲論者なのだそうである。論文の冒頭から引用する:
「護憲論の本質
この5月3日に日本国憲法が施行されて60年になる。過去数年の間に日本の論壇では改憲論が中心となり、護憲派の旗色はよくない。憲法論議を巡っても論者の立場がはっきりしない事例も多い。筆者(佐藤)は、憲法改正問題について議論する際に論者の立ち位置を明確にすることが、論壇における最低限のモラルと考える。筆者は護憲論を支持する。しかも現行憲法の条項には一切、改変を加えてはならないと考えるかなり硬直した護憲の立場に立つ。
憲法改正を巡る議論に関して、筆者はこれまで流通している護憲論のいずれに対しても強い違和感をもっている。まず、憲法第九条を擁護することが、護憲派であるという常識について疑ってかかる必要がある。議論が空中戦にならないように憲法第九条を正確に引用しておく。
<第九条 (本記事では省略する: 古井戸) >
戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認が憲法第九条の骨子であるが、この条項を断固維持したいと主張する大多数の人々が、本音では天皇制を廃止して共和制にした方がよいと考えているのだと思う。ちなみに筆者(佐藤)は「天皇制」という述語に強い違和感をもっている。なぜならこの述語は1932年にコミンテルン(第3インターナショナル)が発表した「日本における情勢と日本共産党の任務に関するテーゼ」ではじめて規定された経緯があり、日本の天皇制をロシア帝国のツァーリ(皇帝)との類比でとらえたもので、日本の国家体制の内在的論理を現すことに成功しなかったと考えるからだ。従って、極力、天皇制という述語を用いずに言説を展開したいのであるが、アカデミズムや論壇において天皇制という述語が一定の市民権を得ている状況で、この言葉を完全に回避することができないので悩んでいる。本稿でもやむを得ず天皇制という言葉を用いる。」
天皇制擁護(国体維持論者)であることはこれまでの著作で明言しているところであるが、9条を含め一字一句変えないという護憲派であるとは意外であった。しかし上記の「天皇制」という語彙に対する違和感はこじつけだろう。もちろん、現在の日本語で「天皇制」といえば明治憲法(大日本帝国憲法)が規定する天皇を戴く国家体制のことである。コミンテルンが何と規定しようと、規定される対象はコミンテルン以前、おそくとも明治憲法が制定されたときには存在したわけだから、この用語に違和感をもつのはヘンテコリンなことである。(用語が存在しないことは、用語によって表現される対象の有無とは関係ない。鎖国は17世紀から取られた方針だが、<鎖国>という呼称は18世紀になって初めて使われ出した言葉だ。現在のわれわれが17世紀の鎖国を鎖国といってなんら誤解は生じない、と同じ理屈であるし、この制度を海外の各国がどう呼称し規定していたかなど、歴史家は別として現代の日本人は考慮するに足りないことだ)。
佐藤は「この条項(九条)を断固維持したいと主張する大多数の人々が、本音では天皇制を廃止して共和制にした方がよいと考えているのだと思う」と言っているが、これはどこで得られた調査結果なのだろうか。私自身は後で述べるが、天皇制を廃止すべきだ(つまり、日本国憲法の第一章、1条から8条までを抹消すべき)と考えているが、これはかなり少数だと思っていた。これに対して九条護持派はほぼ有権者の半数はいるだろう、このほとんどすべてが共和制(世襲制の天皇でなく、元首なり大統領なりを選挙で選ぶ制度、と理解する)を支持しているのだろうか?初耳である。
さて、引き続いて佐藤の文章を引用する。
「日本国憲法は共和制を想定していない。あくまでも立憲君主制である。しかも、大日本帝国憲法第73条の「将来此ノ憲法ノ条項を改正スル必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ」という改正手続きに基づいて、制定された憲法である。宮沢俊義の1945年8月に日本がポツダム宣言を受諾した時点で国家体制に根本的な断絶が生じたとの言説(「8月革命説」)は一面的だと思う。形式、手続きは内容と不可分一体の関係にある。大日本帝国憲法の改正手続きを踏まえたという事実が、明治憲法と現行憲法の間の連続性を示すもので、その根本が現行憲法第一条から第八条までで定められた天皇の規定なのだ。護憲の基本は、この天皇制を擁護するということなのである。「何かを守る」という運動はその本質からして保守的なのだ。現行憲法第一条から第八条を含む現行憲法を擁護しようとする運動は、言葉の本来の意味からいって保守的で、天皇制擁護なのである。
現行憲法は占領下に制定されたものである。占領下に制定された憲法を平和条約が締結され、独立を回復した後に再検討するという動きはごく自然のことだ。事実、日本でも1951年のサンフランシスコ平和条約で日本が独立を回復したときに憲法改正問題は論壇における大きなテーマになった」
以上の佐藤の文章にコメントしよう。
1 まず、佐藤の大きな誤りは、用語にウルサイ割りには、天皇制、という用語を安易に使っていることである。天皇制(これは明治憲法の規定する天皇が統べる制度を言う)と、象徴天皇制(戦後憲法の天皇を含む国家体制)を区別しているのだろうか?明治から敗戦までの天皇、と、戦後の天皇は違うのである。したがって同じ呼称で呼ぶのは(佐藤のように意図的、あるいは非意図的に混乱を与える可能性があるから)よくない、と横田喜一郎もその著書『天皇制』で述べているところだ(私のブログ記事、天皇制についてを参照 http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2006-03-13)。天智天皇の時代の天皇制、と、後醍醐天皇の時代、斉明天皇の時代、それぞれ、天皇という呼称はあったかも知れないが、天皇制度は異なっているはずである。
2 日本国憲法は立憲君主制であるという物言いは初めて聞いた。佐藤は外国にニッポンの政治制度は何か?と尋ねられたら、constitutional monarchy system であります!と答えるのだろうか?私なら立憲民主制、constitutional democracy system であります!と答える。英国の君主(女王)は現在でも政治にちょっかいを出す(出せる)が、ニッポンの天皇は政治的行為は一切禁じられている。したがって象徴天皇制、というのである。もっと正確に、立憲象徴君主制、とでもいうなら認められようが、ニッポンの政治システムを立憲君主制と言っていては時代錯誤だといわるのがオチである。
3 敗戦時の日本に何が起こったか?新生にして犯すべからざる存在であり、権力の集中した天皇から、主権在民に変わったのである。明治憲法は昭和憲法に<全面改正>されただけではなく(つまり明治憲法を排除)、憲法条文を変更して、憲法制定権力(明治憲法は欽定である)が国民に移行したのである。この種の権力の移行は通常、革命というのだ。(外務省職員はこういうことは習わないのか?)。宮沢俊義の8月革命説のどこが奇異なのだろうか?明治憲法と新憲法を比べれば小中学生でもその革命性が理解できよう。「大日本帝国憲法の改正手続きを踏まえたという事実が、明治憲法と現行憲法の間の連続性を示すもので、その根本が現行憲法第一条から第八条までで定められた天皇の規定なのだ」という言い分はこじつけにしか過ぎない。旧憲法を廃絶するのは天皇しかできないこと。廃絶した後、主権者はいなくなるではないか(憲法が無いのだから)。主権者無しの状態から、新憲法でいう「主権者」を立ち上げなければならない。無から新憲法を作成するのである。この事態を革命というのだ。こういう事態(革命)を想定した手順を定めた<超憲法>などどこにもありはしない。
4 「占領下に制定された憲法を平和条約が締結され、独立を回復した後に再検討するという動きはごく自然のことだ」。一般に憲法(に限らずあらゆる法律)が、社会の動きと共に変更を迫られるのは当然のことだ。文言を変更するまでもなければ、解釈によって時代と社会に適合して解釈運用される。それでも間に合わなければ、そのまま運用すると<違憲>状態が発生するから、改憲の必要が生じる。しかし、占領時代に作られたとはいえ、占領後を睨んで憲法は作成されたのでありたった数年で変更を迫られるような憲法ならいったい何をやっていたの?と憲法起草者、承認者らの能力が問われよう。事実、後で述べるように講和が成った51年にはビックリするくらいの「再軍備」運動が起こったようだ。
さて、佐藤優の文章を続ける:
「ここで平和憲法の維持の論陣を張り、非武装中立論の理論的基礎を構築した山川均(1880-1958)の言説を再検討してみたい」
として、戦前、社会主義者として活躍した山川均の憲法擁護論の検討に入る。
(山川均とは<ウィキペディア>: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B7%9D%E5%9D%87)


山川均@1956 『日本の再軍備』岩波新書、1951
山川均の著作は、山川均全集(ケイソウ書房)と岩波新書『日本の再軍備』、あるいは『山川均自伝』、筑摩書房の『山川均集』などが比較的入手しやすいが、いずれも古書店でしか購入できない。
『山川均集』の「平和憲法の擁護」(1951年3月発表)から引用する(これは岩波新書『日本の再軍備』にも収録されている)。山川均は、現実的な安全保障の道を国連に求めている。
「そこでもし、どのような形かで安全を保障される方法がぜひ必要だとしたならば、最善の方法は国際連合によって集団的に安全を保障されることである。わが国の安全という見地からも、世界の平和を維持するという見地からも、特定の国や少数の国々との軍事上の協定に保障を求めることは、最も好ましくない。国際連合の現状は決して肯定されるべきものではない。国連の保障は万全という意味で最善なのではないが、げんざいそれにまさる方法を見出すことができないより善き道だという意味で、最善の道である。このような国際連合の現状は、決して予期された機能を満足に果たしているとはいわれないが、国連が名目的にもせよ世界平和機構として存立している以上、わが国は --なんらかの方法で安全を保障される必要を認める限り -- 国連に保障を求めるほかないとおもう。
もっとも国連に加入すれば、集団安全保障の目的のための軍事上の義務を分担することになる。そのためには軍隊をもつ必要がある。しかし私は、国際連合に向かって、戦争の放棄と非武装主義の憲法をもったままでわが国の加入を認めることを要求すべきだと思う。あるひとは、虫のいい要求だというかもしれない。こういう人たちは、日本が現在の国際関係のうちにそのような立場を守ることこそ、日本が世界の平和に貢献しうる唯一の道だということを、理解しえぬ人である。憲法によって交戦権の放棄と非武装を世界に宣言した日本は、堂々とこのような要求をする道義上の義務があると思う。いったい現行の憲法は、日本の国民みずからの意志により、みずからの選択によって制定したものにはちがいがないが、同時に、それは連合国の占領下に制定された憲法であって、連合国の意志に反して制定されたものではない。それどころか、すくなくともそれが戦争の放棄と非武装主義を宣言した点では、世界における最もすぐれた輝かしい憲法として、全世界の民主主義国から賞賛された憲法である。そのときからわずかに五年をへた。いかに情勢に大きな変化があろうとも、この光輝ある憲法が紙クズカゴに投げこまれなければならないほどの、それほどの価値と原則とをテン倒させる変化があったとはいわれない。日本が世界最初の非武装国家を宣言したことは、ひとり日本国民の誇りだけではない。この新しい型の国家を生みだしたことは、平和を愛好する全世界の国々にとっては、戦争の犠牲によって収穫した貴い歴史的な成業なのである。国際関係の現状のもとで交戦権の放棄とあらゆる目的のための軍備の放棄を宣言した憲法を採用することは、思いつきやおもしろ半分にできることではない。われわれ日本の国民は、異常の決意をもってこの憲法を守りぬく責任がある。と同時に、世界の民主主義諸国もまた、異常の決意をもってこの歴史的成業を擁護しなければならない。このように日本の要求に答えて、国際連合は日本を非武装地域とし、この非武装地域の侵犯にたいしては、国連の集団的な保障を約束すべきである」(山川均集、平和憲法の擁護、p369-370)
「日本再軍備の問題は、第一には、原則として、独立国家というものは自衛のための軍備をもたなければならないものであるかどうかという問題ではなくて、民主化にたいする反動の作用がすでに現実にあらわれているばかりでなく、講和の成立を転機として、この形勢が急転直下の勢いで進展するにちがいないげんざいの段階において、かつての国家主義軍国主義の思想と人間的要素とを復活させ、反動主義に焦点を与える危険のある軍隊をつくるべきかどうかという問題なのである。私は、あらゆる侵略にたいして、日本を衛る熱意をもっている。けれどもわれわれが熱意をもって衛ろうとするもの、われわれが衛るに値する日本は、天皇の日本や軍国主義の日本ではなくて、民主主義の日本である。民主主義の防衛をはなれて、日本の防衛を考えることができない。私はどのような条件とどのような情勢のもとでも、日本はどのような性質の軍隊をももってはならないという原則を、いま主張しようとしているものではない。しかし、すくなくともげんざいの段階とげんざいの情勢のもとでは、反動思想の侵略にたいして民主主義日本を衛ろうとする熱意をもつものは、再軍備に反対しなければならぬ。もしわれわれが日本の民主主義を、平和憲法の擁護という一線で衛ることができないなら、われわれはついに、おそいきたす反動の波をくいとめることができないで、もういちど、反動勢力のまえに屈服するほかないだろう」(p385)。
佐藤優は、山川の文章にかなり凝った解説を加えているが、この文章は当時の平均的国民なら理屈無しに訴えたろうし、当時の情勢(戦争終了後わずか、6年しかヶ生かしていず、この年は、サンフランシスコ講和会議のとしであったこと、さらに、朝鮮戦争の真っ最中であったこと、など)を考慮すれば現在の日本にも翻案可能であろう。
朝鮮戦争:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%88%A6%E4%BA%89
佐藤優『国家と神とマルクス』(太陽企画出版)のなかでは、
第V章 国家という名の妖怪、という白井聡(一橋大学大学院社会研究科博士課程)との対談がおもしろかった。80頁におよぶ長編対談である。
佐藤の発言で同意したところがある。p194
「。。日本国憲法を押しつけだというなら、大日本国憲法はそれ以上に押しつけだということですよ。どこまでが内発的で、どこからが外発的かということを考えるのはあまり意味が無いことだと思います。私たちは洋服を着ているでしょう。これだって、内在的なのか外発的なのかわからない」
そのとおりだ。個人レベルで言えば、この世に生まれたのがたまたまニッポン(あるいは anywhere, any country...)であるだけであり、生まれた個人が成人して、その国の憲法なり、あるいは共同体、家族、社会を、どのように受け入れるか(内在的か、外発的か。。)は、個人の個性と社会の教育、それに制度そのものによ決まることである。
p187で佐藤はこう発言している。
「。。私は、日の丸、君が代は日本国家のシンボルとして大いに結構と考えます。故に、法制化には絶対反対です。なぜなら、法律で決めるものは法律で変えられるからです。日の丸や君が代を法制化するという発想が誤っていると考えます。国旗、国家というのは日本の伝統に属するもので、文化なのですから、それを法制化すること自体がカテゴリー違いなのです。こういう議論が国旗、国家法制化に対するいちばん有効な反対論になるとおもいます。
本来、右派、国家主義陣営から、法制化なんかによって窮屈にされるのはわが国体に反するという議論を展開する論客が出てくればよかったのに、そういう声は大きくなりませんでした。。。云々」
同じことが、天皇にも言えないか?天皇は伝統であり文化である。日本国憲法の第一条は、
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民の統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」
The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the people, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power.
つまり、主権在民の権力構造下で、国民の支持が無くなればその地位もなくなるという現在の象徴天皇制として憲法に規定するのではなく、民間人として伝統を維持するのが安定した天皇制度である、ということなのだ(茶道、の家元と似たようなもの)。つまり、明治以前に 復古、すればすむことである。基本的人権もなく、さりとて、実質的意味のない国事行為だけを義務づけられ、伝統とは縁もゆかりもなく、明治になってアタフタと新規設計された神祇項目をこなすだけのルーチン職務からいい加減解放してくれ、と本人達が思っておられるのではないか。
わたしが唯一真っ当な天皇論と考えているのは社会学者橋爪大三郎が2005年5月30日朝日新聞夕刊に<女帝議論のために>発表した 『血統より存続願う伝統』<「万世一系というトリック」 皇族の人権 尊重を> と題する短文である。 以下これを抜粋・引用する。
##
わが国の天皇システムは、王権の一種である。
王権とは、王がいて、人びとを(たとえ名目的にでも)統治し、その地位を血統によって世襲するものをいう。世襲はそれなりに厳格なルールに従う。
なぜだろう。それは、つぎに即位できる人間を、王の近親者ごく少数に限っておかないと、人びとが納得しないからだ。王の血統は尊い、だから王子は次の王にふさわしい(誰でも王になれるわけではない)、という観念がこれを補強する。
この結果、王の血統は、しばしば断絶する。
即位できる人間の範囲を広げても、女王の継承を認めても、断絶を防ぐことはできない。そもそも、王位を継承できる人間を、王の近親者ごく少数に限るのが王権だからだ。
イギリスを例にあげても、王朝が何回か交代した。これは、人びとが王権をないがしろにしたからではない。むしろ、王権を承認し、王の血統を尊いものと考えた結果だ。王の血統を尊いと考えるから、ふつうの誰かを王にできないのである。
では、王朝が断絶したら、どうすればいいのか。
よくある方法は、よその国の王(または王族の誰か)を連れてきて、新しい王になってもらうことである。あちこちに王家があった時代は、こういうことがやりやすかった。国内にやんごとない血統の貴族がいたら、貴族に頼んでもよい。
王朝の連続性が途絶えても、統治される側の国民の連続性が保たれていれば、問題ない。これも王権のあり方なのだ。
<柔軟性もつ継承ルール>
さて、これらを踏まえて、天皇システムを考えてみると、どいうなるのだろうか。
まず、明瞭な王朝の断絶(交代)がない。これは、継承のルールがかなり「柔軟」に適用されてきたことをいみする。たとえば、天皇にはふつう妻にあたる多数の女性がいて、誰が産んだ子も皇位を継承できた。教会が認めた正式な結婚の子でないと、王位を継承できないキリスト教圏とは違う。また女帝も決して一時しのぎではなく、皇位継承の選択肢のひとつだった。
王朝が断絶しないのは、誰が天皇になるべきかについて、厳重な規則がないこと、つまり、誰であれ天皇が続いてほしいと人びとが願ってきたことをいみする。裏を返せば、天皇の血統そのものを尊いと考えているわけではないのである。
この伝統を、明治政権は「万世一系」とよび換えた。皇室典範では女帝も禁じた。継承のルールがあいまいでだらだら続いてきただけのものを、あたかも西欧の王家のような男系の血統が伝わってきたと見せかけるトリックである。日本人自身もこれを真に受けてしまった。
いまの皇室典範は、ルールが明確だ。だから、適当な皇位継承者がいなくなる「お世継ぎ問題」が起きる。では女帝を認めることにしようかと、人びとはあわて始めた。「誰であれ天皇が続いて欲しい」という、昔ながらの発想である。
<共和制移行の選択肢も>
天皇の血統が断絶して何が問題なのかと、私は言いたい。
天皇システムと、民主主義・人権思想とが、矛盾していることをまずみつめるべきだ。
そもそも皇族は、人権が認められていない。結婚は「両性の合意」によるのでなく、皇室会議の許可がいるし、職業選択の自由も参政権もない。皇族を辞める自由もない。公務多忙で、「お世継ぎ」を期待され、受忍限度を超えたプレッシャーにさらされ続ける。こうした地位に生身の人間を縛りつけるのが戦後民主主義ならそれは本物の民主主義だろうか。皇位継承者がいなければ、その機会に共和制に移行してもよいと思う。
日ごろ皇室を敬えとか、人権尊重とか主張する人びとが、皇族の人権侵害に目をつぶるのは奇妙なことだ。皇室にすべての負担を押しつけてよしとするのは、戦後民主主義の傲慢であろう。皇室を敬い人権を尊重するから、天皇システムに幕を下ろすという選択があってよい。
共和制に移行した日本国には天皇の代わりに大統領をおく。この大統領は、政治にかかわらない元首だから、選挙で選んではいけない。任期を定め、有識者の選考会議で選出して、国会が承認。儀式などの国事行為を行う。また皇室は、無形文化財の継承者として存続、国民の募金で財団を設立して、手厚くサポートすることを提案したい。
## 橋爪論文、引用終わり。
わたしが天皇制にこだわるのは憲法第九条の維持と天皇制が密接に関係するからに他ならない。1978年に退任をせまられた元統合幕僚会議議長・栗栖弘臣は2000年、『日本国防軍を創設せよ』で、わが国の軍事的安全保障について、改革すべき要点16項目の第一として、
(1)天皇との距離を縮める
を挙げていることからもわかるように、けして「国民との距離を縮める」のではない。戦前と同じように軍人は天皇の権威の利用して国民の統制を図っているのである。
佐藤優が引用した山川均の論文『平和憲法の擁護』(1951年8月)から別の箇所を引用する:
「敗戦によって軍隊は解体され、軍閥は解消され、軍人は追放されて、政治上社会上の活動の表面からは姿を消した。しかし、これで日本の国家主義と軍国主義、愛国主義とが死滅したわけではない。70年の長きにわたって国民の信仰にまで完成されていた国家主義、軍国主義、忠君愛国主義の精神が、わずか5年のあいだに清算されるものではない。それらのものは、閉息はしているが死滅したのではない。そして終戦後5カ年間のお仕着せ的民主主義は、国家主義・軍国主義・愛国主義の復活に対する保障となるにはたりないものである。げんざい多数の国民の頭のなかに眠っているこれらの信仰と、5年間につぎこまれた民主主義の精神と、どちらが強いかと聞くほど、ばかばかしい問いはない。
国家主義、軍国主義、忠君愛国が「思想」として「精神」として潜在しているばかりではない。それは生身の人間として残っている。かつては日本の国家主義の勢力を形成していた人間の要素 -- 一外国記者が朝鮮の戦線に利用せぬという手はないと論じた、日本のもつ豊富な戦争と技術と経験 -- は、大部分がそのまま残っている。いま日本が軍隊をつくるとすれば、国家主義、軍国主義のこれらの2つの要素を利用することなしには、とうてい不可能である(注)。日本が再軍備するということは、かつての国家主義と軍国主義との眠っている要素をふたたび活動状態によびさますこと、この潜在的な国家主義と軍国主義とを、もういちど現在勢力に復活し転化することにほかならぬ。
(注)その後、事態はどうなったろうか。最近に吉田首相が、「アジア諸民族を率いる」日本の「新国軍」の準備であることを明らかにした保安隊 -- この偽装の軍隊 -- の幹部幕僚は、その大部分が職業旧軍人の起用によって満たされた。」
最後の(注)は、ジョン・ダワーの『敗北を抱きしめて』も述べていることだ(たとえば、厚生官僚による靖国神社コントロール)。
いくらなんでも、戦後60年も経っているのに<戦前思考>が自衛隊をゾンビのように支配するだろうか?首相をはじめとする二世三世議員は立派に戦前思考の持ち主であるし、そもそも、過去に対する記憶も記録も抹殺しようとする精神の持ち主には、何十年の年月の経過など無きに等しい。佐藤優はこういうことにはまったく安心しきっているようである。
なお、栗栖は改革すべき項目の第四項に
自衛隊は国防軍とせよ
をあげて、
「重大な国防に挺身する部局を単なる総理府内の「庁」に留めるのは、自衛官に対する軽視である。野党民主党代表の鳩山代議士だけは、自衛隊の性格を「軍」と明確に規定すべきだとはっきり言明しているのに、与党政府は何を考えているのか」
と、鳩山を持ち上げている。与党・野党の境界など、二世三世議員には、あって無きがごときもののようである。
関連記事:
天皇問題
http://
日本国憲法の誕生
http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2007-05-13
「戦後天皇制は可能か」 渡辺京二あるいは北一輝の天皇制論
http://
岸田秀の押しつけ憲法論(あるいは反押しつけ憲法論)
http://
佐藤優『日米開戦の真実』
http://
認識の四肢的構造連関と物象化 (廣松渉) [Book_review]

「ヨーロッパの実体主義に対してアジアが潜在的に育んできた「関係主義」の思想を掘り起こし、それを体系化したのが廣松渉の世界観である」(野家啓一)。
廣松渉著作集(岩波書店)が中国語に翻訳されたのを記念して南京大学で行った野家啓一の講演『広松哲学の成立過程』が雑誌『情況』(情況出版)2004年7月号特集「今、なぜ廣松思想なのか」に掲載されている。この講演から廣松哲学の核である「認識の四肢的構造連関」と「物象化」に係る部分を引用する。この講演のなかで野家は廣松の事的世界観や認識の四肢的構造という廣松哲学の核となる概念をスッキリ説明している。以下引用ページはことわりがない限り雑誌『情況』のページを示す。廣松は漢字変換できない文字、や難字をやたらに使うので正確な変換を行わない箇所があることをお断りしておく。
なお、廣松渉の主著は文庫本として数冊が出版されている。廣松の哲学入門書は新書になっている。
#『情況』 引用開始
1 廣松哲学の出発点 (p46)
(略) 廣松さんがこの論文(『世界の共同主観的存在構造』)で提起した哲学的見取り図は、それまでの日本の哲学者たちの重箱の隅をつつくような哲学史研究とは類を異にした、まさに気宇壮大という言葉がぴったりするものでした。それはたとえばつぎのような形で表現されています。
『われわれは、今日、過去における古代ギリシャ的世界観の終息期、中世ヨーロッパ的世界観の崩壊期と類比的な思想史的局面、すなわち、近代的世界観の全面的な解体期に逢着している -- こう断じても恐らくや大過ないであろう。閉塞情況を打開するためには、それゆえ(略)<近代的>世界観の根本図式そのものを止揚し、その地平から超脱しなければならない。認識論的な場面に即していえば、近代的「主観 - 客観」図式そのものの超克が必要になる。』(廣松著作集、第一巻)
「この「主観 - 客観」図式においては、主観は各個人の人称的な意識、つまり個々の「私」の意識であると見なされ(主観の「各私性」)、対象の認識は「意識作用 - 意識内容 - 客体自体」という三項図式に即して理解されます。そこから、主観に直接的に現前するのは表象や観念などの「意識内容」のみであり、当の「客体自体」は間接的にしか認識できないことが帰結します。その結果、近代哲学の枠組みの中では「外界の存在」や「他我の認識」が大きなアポリアとなり、つまるところ「独我論」の袋小路を抜け出ることができませんでした。これが近代的世界観の陥った危機であり、思想的閉塞情況と言われるものの内実です。
それに対して廣松哲学は、主観の「各私性」には「共同主観性」を、対象認識の三項図式には認識の「四肢的構造連関」をそれぞれ対置して「主観 - 客観」図式の乗り越えを図ります。まず「共同主観性」ですが、これは個々人の意識が「私」という閉鎖的な領域に閉じこめられているのではなく、意識活動は思考様式から知覚の仕方にいたるまで、常にすでに社会的に共同化されているという事態を指す概念です。デカルト流に言えば、「私たちが考える(cogito)」とは本来的に「我々が考える(cogitamus)」ことに他ならない、ということです。もちろん、共同主観性がフッサール現象学の基本概念である Intersubjektivitat の日本語訳であることは言うまでもありませんが、廣松さん自身が「われわれの「共同主観的」ということは intersubjektiv という意味にとどまらず zusammensubjektiv そしてまた gemeinsubjektiv という意味を帯びる」 (廣松著作集第一巻54ページ)と述べておりますように、そこには単に複数の主観の相互関係というのみならず、意識が社会的交通や社会的協働を通じて歴史的に協働主観化されているという「意識の社会的歴史的被制約性」の意味が含まれています。これは廣松さんがマルクスの著作から学び取ったものにほかなりません。その意味で、廣松哲学の出発点は、近代的世界観の超克という観点からマルクスを読み直し、そこに「人間主義」と「科学主義」の対立を乗り越える一筋の道を探り出すことにあったと言ってよいでしょう。
2 廣松哲学の基本構図
しかしながら、廣松哲学の全体像は、マルクス主義の枠内にすんなり収まりきるものではありません。たとえば、廣松認識論の中核をなす「四肢的構造連関」にしても、その中には反映論や模写説を奉ずる素朴なマルクス主義者からは「観念論」という烙印を押されかねないような論点が多々含まれています。むろん、廣松さんはそのことを十分に自覚した上で、近代哲学の諸前提を克服するという共通の問題意識から、自身の立場をマルクス主義哲学の警鐘的発展として位置づけているわけです。
その認識の「四肢的構造連関」ですが、これは主観と客観という2つの項が切り離されているのではなく、それぞれ「レアール real」 と「イデアール ideal」 という二肢的二重性をもって構造的に連関し合っているあり方のことを指します。客観の側から言えば、われわれは対象を生のままの所与として受け取るのではなく、それを所与以上の或るものとして意識しているということにほかなりません。たとえば、黒板にチョークで円を描くとしましょう。その際われわれは単に黒板上のチョークの痕跡というレアールな所与を知覚しているのではなく、その所与を「円」というイデアールな意味として把握しているわけです。ただし、レアールな所与とイデアールな或るものは空間的に離れて存在しているわけではありません。イデアールな或るものはレアールな所与において、つまり黒板上のその図形の中にいわば「受肉化(inkarnieren)」していると言えるでしょう。この事態を廣松さんは「即自的な”対象的二要因”のイデアール・レアールな二肢的統一構造」(著作集第一巻、37頁)と呼んでいます。
今度は主観の側ですが、対象知覚の二肢的二重性であればハイデガーの「~として構造 als - Struktur」 やハンソンの「~として見る seeing as」 を引き合いに出すまでもなく、すでに現代哲学の中にその先例を見出すことができます。しかし、主観の二肢的二重性を明らかにし、それによって四肢的構造連関を定礎したことはまさに廣松哲学の独創に属することです。たとえば、鶏の鳴き声を中国語ではどのように表現するのか残念ながら存じませんが、日本語では「コケコッコー」、または英語では "cockadoodledoo"」と表現します。 もちろん、鶏に国籍はありませんのでどの国でも物理的音としては同じ鳴き方をするはずですが、それぞれの母音語に応じてその聞こえ方は同じ鶏とは思えないほど違っています。しかも、母音語を共有する人には例外なく同じ鳴き声に聞こえます。
このことは聞き取る主観(主体)が単なる「私」ではなく「私以上の私」、すなわち「われわれとしての私」であることを示唆しています。これを廣松さんは主観の「自己分裂的自己統一」あるいは「いわゆる”主体”の側もまた、イデアール・レアールな二重構造においてある」(著作集第一巻、44頁)と要約しています。つまり、感覚器官を備えたレアールな私個人が、認識活動の場面ではそれ以上のイデアールな「われわれ」として存立しているということです。この主観の側の二肢的二重性が、意識の共同主観的自己形成と表裏一体の事柄であることは言うまでもありません。それゆえ、主観の二肢的二重性は、経験的主観と超越的主観の関係のようにア・プリオリなものではなく、先ほど母国語を例に取りましたように、社会的協働を通じて歴史的に形成されていくものです。
以上のことから、廣松哲学においては、認識の客観的側と主観的側面とがそれぞれ二肢的に文節化され、合わせて四つの契機から成る連関態として把握されていること、そして主観の二重性が共同主観性の成立と密接な関わりをもっていることがご理解いただけたかと思います。これが認識の「四肢的構造連関」と呼ばれるものですが、廣松さんはそれを「フェノメナルな世界は”所与がそれ以上の或るものにとして「誰」かとしての或る者に対してある”(Gegebens als etwas Mehr gilt einem als jemandem)」(著作集第一巻、54頁)と簡潔に定式化しています。ただし注意しておかねばならないのは、これら四つの契機はあくまでも関数的(機能的 funktionell) に連関し合っているのであり、それぞれ独立に自存するものと捉えられてはならない、ということです。いわば四肢のそれぞれは構造連関という関数に組み込まれた変数なのであり、それを単独で取りだすことは意味をなしません。
この関数的連関から切り離して変数を独立の実体として捉えるところから、いわゆる「物象化的錯視」が生じます。ですから、廣松哲学の立場からすれば、ヨーロッパ哲学の基本概念である「個物」「イデア(普遍)」「自我」「超越的主観」などはすべてこの物象化的錯視の所産ということになります。もちろん、「物象化 Verdinglichung」 という概念はマルクスに由来するものです。その要点を廣松さんは「われわれは概念規定以前的な暫定的表象として、人と人との関係が物的な関係・性質・成態の相で現象する事態、これをひとまず物象化現象と呼ぶことができよう」(著作集第13巻、101頁)と説明しています。マルクス(およびエンゲルス)は人と人との社会関係が物と物との関係として現象する事態を「物象化」と呼んだわけですが、廣松さんはこの概念を社会関係のみならず「自然的・事物的関係」にも拡張して適用することを試みます。つまり、マルクスが「歴史の自然的物象化」の側面を考察したとすれば、その問題意識を継承しつつ発展させ、廣松さんは「自然の歴史的物象化」をも射程に収めようというわけです。それによって「物象化」という概念は「関係規定態の実体化」という、ヨリ一般的な形で規定されることになります。ここから自然科学が前提している物質観・存在論をも物象化の所産として捉え直す視座が拓かれます。この点について廣松さんは次のように述べています。
『読者のなかには、いわゆる精神的現象やいわゆる価値的現象を物的な実在に還元するのは”物象化”であり”錯視”であると”認め”たうえで、しかし、もともと物的な存在である対象を物的な実在態として扱う自然科学はまさに如実の相をそのまま認識しているのであって、それは何も物象化ではないのではないか、物象化という概念は”自然界””自然科学的対象認識”には適用すべくもないのではないか、このように反問されるむきを生ずるかも知れない。 --- だが、われわれの見地にとっては (fur uns) いわゆる物的実在態それ自身が物象化の所産なのである。すなわち、客観的に自存する物的実体、そのような実体の具備している物的性質、そのような実体の間に成り立つ物的関係、自然科学が対象とするこれらの物的実在態それ自身が既にして物象化の所産にほかならない』(著作集第13巻、247-8頁)
##以上、引用終わり
南京大学HPから:
http://www.nju.edu.cn/njuc/chi-jp/zryj/4.htm
人の死は悲しいのか 池田晶子の死 『人生のほんとう』 [Book_review]

「。。親しい人が死ぬと、当然「悲しい」という感情が起こります。ただ、なぜ悲しいのかなと少し距離を置いて考えてみると、おそらく第一に「もう会えない」という思いがあります。その次がたぶん、「かわいそう、気の毒だ」、「死んだひとは悲しいんじゃないか」、そういう思いもありますね。
でも、これはよく考えてみると、わからないんですよ。ひょっとしたらそれも思い込みではないかと考えることもできます。死んだ人が悲しいと思っているかどうかはわからない。死ぬのが本人にとって悲しいことなのかどうか、われわれにはあくまでもわからないんですよ。だって、われわれは死んだことがないわけですから。
(略)
けれど、たいていは、「もう会えない」という感情のほうが、悲しみの内容としては強いのでしょう。でも、その「もう会えない」とはどういうことかと考えてみると、裏から言えば、会えたこと自体が、そもそも奇跡的なことだったと気がつくことになる。つまり、なぜ存在するのかわからない宇宙に、なぜかわれわれは存在していて、なぜだかわからないけれども、その人と出会ってしまったわけです。これはすごく不思議で、これ自体が奇跡的なことだったと気がつくと、悲しんでばかりでもなくなる。驚きとともに、感謝にも似た感情も起こってきますね。
また、会えたこと自体が奇跡ならば、なぜまた会えないことがあるのか、という考え方もできますね。さきほど「無というものはない」といいましたが、いなくなるということは、実は無がないかぎり「ない」のですから、いなくなるということ、無くなるということはないともいえる。おそらくそれが、われわれがなぜだか出会ってしまったという奇跡の意味でしょう。一期一会は存在の構造です」
池田晶子 『人生のほんとう』 (トランスビュー) 2006年6月刊、から。
本書は、著者が西武池袋コミュニティ・カレッジで「人生を考える」というタイトルで行った全6回の講義内容をもとにしている。2004年~2005年。

物も事も、およそ一切の事象は人間の記憶の中にあることをもってのみ、存在する。記憶から消えたときが人間にとっての<死>であるし、死、とは人間にとってしか存在しない。
私の父は一昨年死亡した。そのことは、父が田舎に物理的に実在しなくなる、戸籍から抹消される、ということであるがこれは公的な意味であり変化であるが、私や家族にとっては表層的な意味の変化でしかない。人が死ねば、係わりのあった人は哀しむか?係わりのあった人なら、それ以後、その人を、いつでも心の中で呼び出せるということであり、むしろ、呼び出す人に近づくのである。生存中の父は、物理的に800キロメートル隔てたところにおり、1年に一回も会わない存在でしかなかった。死により、いつでも、眼前に呼び出せる存在になったのだ。

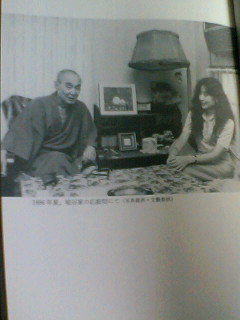
池田晶子はいまごろ、師匠であった埴谷雄高と静かに語らっているのであろうか。
池田晶子(いけだ・あきこ、本名・伊藤晶子=いとう・あきこ)。2月23日、腎臓がんのため死去。享年46歳。
米原万里 『打ちのめされるようなすごい本』 書評 [Book_review]
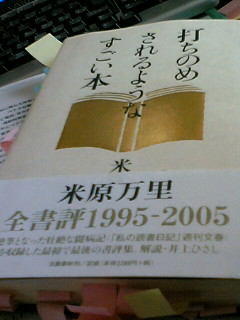
2006年(昨年)5月25日に卵巣癌により56歳で亡くなったロシア語通訳者米原万里の遺著、書評集である。文藝春秋社、発行。週刊文春書評が、本書第一部300頁を占める(2001年から2006年5月18日号まで)。本書後半の200頁は、週刊文春以外の新聞雑誌に書いた1995年以後の全書評を収録している。 週刊文春の書評は原稿用紙12枚前後。数冊を書評しているから一冊当たりは2~3枚であろうか。週刊文春に発表した書評の長さは200文字から数枚までさまざま。アウトプットすることを意識しながらの高速リーディングを1995年~2006年の10年間続けたわけだ。 紹介される本は幅広いジャンルから、。。文学、ノンフィクション、辞典事典、。。からおおよそ300冊、胸躍るブックガイド。
朝日新聞2006/6/6の追悼記事で、米原万里から「師匠」と呼ばれていた徳永晴美(上智大教授、男性)は次のように米原万里を紹介した:
「チェコスロバキアに派遣された父親のもとで在プラハ・ソビエト学校に5年間通った彼女はきれいに響くロシヤ語を身につけた。帰国後、東京外大から東大の大学院修士課程を経て職探しを始めた。だが、共産党幹部の娘。就職先は見つからず、しばらくは、日本とチェコとソ連のメンタリティーのハイブリッドとして漂流していた。その頃だった。廃刊寸前のロシア語学習誌の編集ボランティアとして彼女が僕の仕事部屋に無料原稿の執筆を頼みに来た。20代後半の妖艶な彼女に圧倒された僕は、すぐに外の喫茶店へと連れ出した。そこで「仕事が見つからないの」と話す彼女に、「通訳をやろう」と誘った。
(略)
「情報の核」を大胆に抽出する米原流の通訳は、我が国マスコミに重宝がられた。
(略)
心の色彩陰影が幅広いひとだった。それが作品にも滲み出た。
(略)
万里ちゃんは、よく「あらゆる職業を疑似体験できるのが通訳の訳読」と話していた。」
「通訳で活躍しながら集めた豊富な「異文化交流ネタ」を痛快なエッセーにしたためて、次々と賞を授与された。ユーモリストで、自虐自嘲を好んだ万里さんは、「通訳でお金を貰って、そのとき見聞きしたのを本にしてまた貰って、一粒で二度以上おいしい」と笑っていた」
##
『打ちのめされる。。』には米原万里の妹の夫君、井上ひさしによる解説が付いている。抜粋しよう。
「書評は手間暇はかかる、稿料はやすい。。。よほどの本好きでないと続かない困難な作業である。
通訳生活を長く続けているうちに、彼女は透明でいることに耐えられなくなり、その反作用として、書評家という名の堅い岩石になるのを好んだのではなかろうか。
大事なのは、彼女の文章が、いつも前のめりに驀進しながら堅固で濃密なことだ。別にいえば、文章の一行一行が、箴言的に、格言的に、屹立している。
。。。(本書は)活用次第では、丸谷文学や大江文学への案内書にもなり、犬や猫の飼育入門書にもなる。通訳という名の透明人間をつづけながら、米原万里は膨大な知識と知見を貯え、そして思索を練っていたのだ。そのすべてがこの一冊に噴出している。」
わたし(古井戸)は、2000年頃から、週刊文春の書評欄を読みはじめた。立花隆が(一月に一度当番が回ってくる)書評をしていたからだ(立花以外の書評はパス)。2001年、米原万里が登場した頃、おいおい米原は通訳だろう?出しゃばりすぎないか?と心配していたのだが、書評の内容の鋭いこと、中身の濃いこと。そのころから立花の取り上げる本はゲテモノ趣味に傾きはじめていたので、わたしは、米原万里の月一度の書評をたのしみにした。

枝葉を棄て、幹をむんずと掴み、別の言語で再生する。Interpreterの神髄である。おどろくなかれ、読めば理解できる日本語。エンタテメントにして、知ることのよろこびを味わわせる。本書の魅力を箇条書きにしてみよう。
■取り上げる本のジャンルの豊富さ。米原の経歴からもわかるように東欧、ロシア事情に強く、この地域の歴史文学政治事情が頻繁にとりあげられる
■前著(遺作)『他諺の空似(ことわざ人類学)』にも顕著であるが、彼女の放つ痛烈な時事評論。
■週刊文春には発表時<私の読書日記>とタイトルを冠している。これは書評であると同時に<日記>でもあるのだ。本を語ると同時に、米原万里という人間そのものを吐露している。米原という小説家を志す(事実、小説も書いている「作家」だが)ほどの言語感覚と鋭い感受性を備えた個性の、日々の生活と思考をわれわれは目の当たりにする(ことに、亡くなる3ヶ月前からの3回分は読書日記は、闘病日記に切り替わっている)。
『他諺の空似』(光文社)http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2006-09-04の前書きとして作家・阿刀田高はつぎのように書いているが、これはこのまま本書にも通用するだろう:
「。。。このエッセイを読むと。。なにより米原さんの外国語への知識に圧倒されてしまう。そして、それがどんどん比較文化論へと傾き、国際政治、ブッシュ大統領批判、日本政府への苦言、ありうべき未来社会へ、と、米原節がどんどんよくなり冴えわたる。凡庸なことわざ解説をはみ出して、
-- 米原マリィ、ここにあり--
まちがいなく社会にサムシングを訴えてやまない現代の警世家のエッセイとなっている。」
『他諺の空似』は月刊誌『宝石』への連載をまとめたものである。その<警世>的エッセイの一部を紹介(最終回『終わりよければ全てよし』p285から):
「ところが、ここのところ、アメリカという名の勝者の忠実なる飼い犬役を嬉々として演じ、アメリカ系金融外資と財務相=銀行の使い走りを健気に演じている小泉&竹中売国奴コンビは、首尾一貫して銀行業界には公的資金を惜しみなく提供し続けてきたし、郵政の潤沢な資金を外資と銀行業界に売り渡しつつある。こうして郵便貯金という庶民の確実な貯蓄手段は奪われ、国民を多国籍保険会社の餌食にすべく健康保険制度と年金制度は壊滅させられてしまった。このままいくと、圧倒的多数の日本人の老後は惨憺たるものである」しかし、。。
「もっとも、国力が衰弱していくのは、悪いことばかりとは限らず、「憲法が変わって集団自衛権が入り、戦争できる国になったけれど、実際のところいまの日本に戦争をする力はない。一度は核兵器を持ったけれど、結局、維持管理する費用が高すぎて、こっそり第三国に売ってしまった」というどんでん返しになりそうである。何事も最後までわからないものだ」。。と皮肉も忘れない。(万里さんが生きていたら、安倍首相就任後3ヶ月をなんと評するだろうか?)
さて『打ちのめされるようなすごい本』。
上述のように、米原のとりあげる書物のジャンルは驚くほど広い。これは通訳としての職業上の必要(クライアントが放つ、どのような話題にもフォローせねばならない)というより、職業を離れた人間米原万里の関心の赴くところ、自由に新刊、旧著を巡り歩いた、というのが事実だろう。事典、辞典、民族史、文学史、スポーツ、宗教、日露領土問題、魏志倭人伝、ホロコースト、恋愛小説、自己責任、魏志倭人伝、戦争犯罪、犬の科学、農業と食の問題、チェチェンという地獄、メディアと個人の良心、女性蔑視発言、血液浄化装置、作家の収入、霊柩車の考察、建築の歴史、象徴天皇制、下山事件、情報分析官(佐藤優)、翻訳者と作品。。。目次から拾ったキーワードである。分野の広さが想像してもらえよう。
わたしの現在の関心からすれば、外務省職員(現在休職中)、佐藤優氏の二著、『国家の罠』と『国家の自縛』の米原評(いずれもこの本に収録されている)が気になるところ。とくに、米原と佐藤優には交流があった、と知った後、ますますその書評の落差(佐藤優『国家の罠』への絶賛、と、次作『国家の自縛』への痛烈な批判と)が興味深い。これはブログに別記事として書いた。とくにこのブログ記事に寄せられたコメントで、2005年末に佐藤優が雑誌『新潮45』に掲載した米原万里とのやりとりを描いていて興味深い。是非ブログ記事の参照を願う。http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2006-12-18
佐藤優『国家の罠』を2005年のベストスリーに入れた米原万里も佐藤の次作『国家の自縛』には厳しい評価を下している。これだけは引用しておきたい。『打ちのめされるようなすごい本』 p290-291。
「『国家の自縛』は。。。佐藤の限界というか佐藤自身の「自縛」状態も顕在化させている。
(略)
外務省には絶対に戻らないと言い切る佐藤が(古井戸注:『獄中記』では、判決後、外務省は、佐藤(現在休職中)を懲戒免職にするだろう、と何度も述べている)「現職の内閣総理大臣を全力でサポートしていくってのが役人の仕事ですし、それが国のカネで育成された専門家としてのあり方なんですよ。そのモラルを崩したくない」と述べて、小泉批判を自重し、靖国参拝からイラク派兵までを正当化するくだりは、上滑りで説得力がない。
国=現政権と自動的に受け止める役人的思考回路が自由闊達な佐藤の思考を、そこの所だけ停止させていて勿体ない。佐藤は首相がヒットラーでも忠実に仕えるつもりなのか。また国家権力に寄り添って生きた惰性なのか、権力者や強者の論理にとらわれすぎていて国内的にも国際的にも弱者や反体制派の視点が完全に欠落している。公僕は、まず誰よりも僕(しもべ)で「国のカネ」は国民の税金であり、憲法と現法体系に忠実であるべきだ。それに、作家は、自身の見解を率直に偽りなく語るべきで、権力者におもねったり遠慮したのでは、言葉が力を失う。それとも佐藤は、まだ役人生活への未練があるのか。 」
これは『国家の自縛』に対する米原万里の書評だが、私には『獄中記』を含む、佐藤のすべての本に該当すると思える(わたし=古井戸、は『国家の罠』も評価しない)。
まず、この著作でもっともすぐれた<書評日記>である2002年2月28日の週刊文春に掲載された<打ちのめされるすごい小説>をとりあげたい(『打ちのめされるようなすごい本』という書名は、この できすぎた 書評日記から取られている)。これはネットで全文が読める。
http://www.impala.jp/bookclub/html/dinfo/10303502.html
米原の知人で小説家のHから1年前に紹介された米国の人気ミステリー作家トマス・クックの『夜の記憶』を、まず紹介する。「重層的な構成といい、緻密な細部といい、たしかにHが感心するだけのことはある。しかし、「もう書く意味がない」ほどの傑作かというと、いや、同じように現在と過去を絶え間なく往復する構造ながら、もっと打ちのめされるようなすごい小説を、しかも日本人作家のそれを読んだことがあるような・・・・・・それが何だったのか思い出せないもどかしさを抱えたまま、トマス・クックの最新作『心の砕ける音』(文春文庫。文春へのキクバリかい、万里ぃさん!)を手に取る」。そして、「物語が佳境にさしかかったところで、アッと叫びそうになった。例の日本人作家とその作品を思い出したのだ」!!!
その作品とは、丸谷才一の小説『笹まくら』(昭和41年7月河出書房)である。
 新潮現代文学、丸谷才一集
新潮現代文学、丸谷才一集
笹まくら、とは、草枕と同義。大辞林によると「[草を束ねた仮の枕、の意から]旅。旅寝。くさのまくら」。新潮社の<笹まくら>案内に寄れば、「…旅寝…かさかさする音が不安な感じ…やりきれない不安な旅。戦争中、徴兵を忌避して日本全国に逃避の旅をつづけた杉浦健次こと浜田庄吉。20年後、大学職員として学内政治の波動のまにまに浮き沈みする彼。過去と現在を自在に往きかう変化に富む筆致を駆使して、徴兵忌避者のスリリングな内面と、現在の日常に投じるその影をみごとに描いて、戦争と戦後の意味を問う秀作」。
米原に寄れば、。。。
「書き言葉の日本語は、これほど柔軟で多彩で的確な表現が可能だったのか。丸谷の筆によって描き出される状況も人物たちも、悲惨で深刻であるとともに滑稽で矮小で、作品内の随所で笑わせてくれる。この人間たちの入り組んだ内面に翻弄された後は、ミステリー畑では抜きんでて細やかなはずのクックの文章の肌理が可哀想になるぐらい粗く感じられ、登場人物たちが仰々しく単細胞に見えてくるのだから、罪作りではある。」
人気推理作家トマス・クックを 前座に使った、このできすぎた構成の<書評日記>。(『笹まくら』を思い出せないなんてありえない。。。万里ぃの意図的な演出としかおもえない。。)
わたし(古井戸は)は、70年代のはじめ、学生時代、講談社文庫でこの小説を読んだ。殆ど印象にないが、徴兵忌避者の、重苦しい人生、としか記憶に残っていなかった。米原万里はこの小説の主人公、浜田庄吉が得た結論、「国家の目的は戦争だ」を追体験し、現代の問題と考えているのである。
この小説は時間を反転して終わる。主人公浜田が、徴兵忌避を決意し、名前を、杉浦健次に変えて、逃亡の旅に出向くところで終わるのである。
米原万里は遺作『他諺の空似』の最終ページ(<終わりよければ全てよし>)でこう言っている。「小説だって、たしかに<最初が肝心>で、初めの十頁までで読者の心を掴まないと、最後まで読んでもらえる可能性は低いが、最後の終わり方が尻切れトンボでは、読者に満足感を与えられはしない。丸谷才一は「日本の小説は終わり方が下手だ」と指摘しているが、純文学作品にはそれが顕著である」
丸谷才一『笹まくら』の最後を引用する。浜田庄吉が徴兵を忌避して名前を杉浦健次に変え日本各地に放浪の旅に出立する、という逃避行の発端を著者は小説の最後に置いた:
「杉浦はタクシーをとめ、東京駅へやってくれと頼んだ。運転手は「紀元は二千六百年・・・・・」と鼻唄で歌いながら車を走らせ、途中、鳥打帽の客が万世橋のへんで、細かくちぎった紙を前から捨てるのをバックミラーで見た。そして杉浦は思っていた。あの国家から来た呼び出しの手紙も、こういうふうにして捨てればよかったかな。しかし、おれはもう彼ではない。呼びつけられ、闘い、そして死ぬ、あの従順で善良な彼らのなかの一人ではない。彼らには彼らの、共通の運命がある。その共通性が、彼らの運命をいたわってくれるだろう。祝福してくれるだろう。そしてぼくにはぼくの・・・・・・孤独な運命がある。ぼくはその運命を生きてゆくしかない。おれは自由な反逆者なのだ。
車が淡いたそがれの東京駅に着いた。彼は宮崎ゆきの切符を財布から出し、改札口を通った。さようなら、さようなら。彼は二列に並んでいる長い行列の末尾につき、貧しい身なりの群衆のなかの一人となって待った。さようなら、さようなら。行列が進み出し、駅員が叫び、そして人々は走り、彼もトランクをさげて走った。さようなら。しかしそれが何に対する、どれほど決定的な別れの挨拶なのかは、二十歳の若者にはまだよく判っていなかった」
新潮文庫『笹まくら』の解説で、川本三郎はこの<最後に始まりがきている>ことの意味を、「丸谷才一は、浜田庄吉に旅をさせ、そして、もう一度、あの魅力的な阿貴子に会わせたかったのではないか。そう考えるとき『笹まくら』は、未完に終った悲しい恋の物語としてもみごとに立ち上がってくるのである」と言っている。が、わたしには、丸谷が、三十年後、四十年後のニッポンを見据えて、三十年後、四十年後の読者に、<国家の目的は戦争だ>と浜田と共に警告しているとしか思えない。浜田庄吉は、徴兵忌避を選択して過去を捨て、放浪の旅に出た。読者よ、きみたちは、どうするか?この作品がかかれた30年前より、いまこそ、この問いは切実である。いや、国家がなくならない限りこの問いはつねに切実な問いでありつづける。この小説から切実な問いを受け止める米原万里に共感せねばこの書評集は受け入れにくいだろう。この書評集に紹介された三百冊のうち米原万里が<打ちのめされ>た本は『笹まくら』だけなのだ。(すなわち、米原万里が生きておれば、この書評集に、『打ちのめされるようなすごい本』などというタイトルをつけるわけがない。この小説こそ若き彼女が、自身の家庭と、国家を重ね合わせながら、息を詰めるようにして読み込んだ小説であるに違いなく、<打ちのめされるような>とは彼女がこの小説だけに捧げた唯一無二の形容であるはずだからである。編集者がこんなタイトルを提案したら「ば~か。あんた、何、考えてんの!」と米原に一喝されたろう)。
##
2001年8月2日の読書<日記>のエピソードも、忘れがたい。
この年の6月2日、米原はロシアに旅をした。そのときたずねた、プラハの小学校時代の同級生がひどく落ち込んでいたので、元気付けるため彼女に日本への往復チケットをプレゼント(6万円)し、彼女を米原の家に滞在させたおりの話である。その友だちは大江健三郎の大のファン。米原は大江文学作品の解説を求められたがなかなか納得してもらえない。結局、新しい大江作品『取り替え子 チェンジリング』(大江の義兄である映画監督の自死を扱った作品)をロシア語に<口頭翻訳>して彼女に聞かせる破目になり、途中、二人で何度も議論しながらこの口頭翻訳は進行した。小説中、妻の視点で書かれた箇所では、米原と友人、何度も二人で涙した。さて、二週間かかって米原の口頭翻訳が終了した後、その友人は、夫が自殺したことを米原に明かしたというのである。
「歴史学者だった夫はソ連邦崩壊という環境の激変に精神的についていけなかったのだろうと周囲は一般的説明をつけようとする。そんな簡単に片付けないで欲しい、と思う一方で、彼女自身、山のようにたくさんの疑問を残していった夫の自死に早く決着をつけようとした。けれど、間違いだった。どんなに時間がかかろうと、亡くなった夫と対話していこうと思う。それを『取り替え子』は教えてくれた。そう言って、彼女は帰っていった。」p54。
このエピソードには呆然とする。米原の友人に対する友情。友情に答えて、納得するまで、とことん何かを求める米原の友人。この真率な交際は書評の枠を超えてわれわれに迫る。語学の才能に加え、米原に文学的才能、友人への、人間へのそして文学への深い愛情がなければこういう体験も、日記も、そして書評も、結実しまい。2001年のある二週間、米原万理の自宅で進行した魂の交流を想像し、わたしは感動した。書評日記、とは、<書評>と<日記>の混成物。書物と著者への愛と、深い人間理解をもった人物でなければこのようなエピソードが生まれることはない(日本といわず世界で何人の人間にこのようなエピソードが生まれ得ようか?)。このあと米原は翻訳作業について述べ、このエピソードを締めくくる:
「彼女の久しぶりに晴れ晴れとした笑顔を見て、これはもしかして、翻訳のあり方の理想の形なのではないか、と思えてきた。本が書かれた言葉を母語とする者と翻訳される言葉を母語とする者の共同作業があって初めて十全な翻訳が可能になるのではないか」。
##
さらに、もう一冊紹介したい。2001年5月24日、p36~39、に米原はロシア18世紀の激動期を生きた思想家アレクサンドル・ゲルツェンの長大な自伝『過去と思索』(筑摩書房、全三巻、各9800円!!)をとりあげ、熱烈紹介をやっている。ゲルツェンのこの長編、実は私も好きで古書で取り寄せ(筑摩書房、世界文学大系、82-83。これは抄訳、といっても全体の85%を収録している)、ときおり目を通す。ただ、あまりに長編、いまだに通読していない。
 世界文学大系『ゲルツェン1,2』 筑摩書房
世界文学大系『ゲルツェン1,2』 筑摩書房
ゲルツェンはマルクスやエンゲルスと同時代人。政治的には双方は対立し親交はなかった。翻訳者金子幸彦によれば、マルクスはロシア語をこの『過去と思索』から自習した、というからおもしろい。金子によると『資本論』初版の注にあった ゲルツェンに対する当てこすりも、第二版以降では削除されている。 さて。。ゲルツェンとはいかなる生涯を送ったのかはWeb記事があるから読んで貰いたい。
http://www.asahi-net.or.jp/~wu3t-kmy/2_gerzen/gerzen.htm
米原万里はこのゲルツェン「自分史」を読み出したら止まらない、と、三頁にわたって紹介した。その最後の記述を引用する:
「わたし(米原万里)がたまらなく惹かれるのは、以下のようなくだり。『コペルニクスの太陽系の分析的解明』という論文を書き、優秀な成績で卒業したゲルツェンは、そのときの指導教官で天文学界の第一人者だったペレヴォシチコフ教授と卒業後、食事をする機会があった。教授は、ゲルツェンが天文学を続けなかったことをさかんに惜しむ。「でも誰でもかれもが、先生の後について天に昇るというわけには行かないでしょう。わたしたちはここで、地上で、何かかにか仕事をやっているのです」と答えるゲルツェンに教授は反論する。
「どんな仕事ですか。ヘーゲルの哲学ですか!アナタの論文は読ませていただきました。さっぱりわかりません。鳥の言葉です。これがどんな仕事なものですか」
鳥の言葉。何といいえて妙なのだろう。人文系の学問に携わる人々の言葉が、恐ろしく難解になっていく一方で、一日平均30語で事足りている若者たちの群れ。この二者間の距離は絶望的に隔たるばかりで、同じ民族どころか、同じ人類とも呼べない状況になってきている現実は、同時通訳として、あれこれの学会の通訳に動員されるたびに、思い知らされている。でも、150年前のロシアでもそうだっのかと思うと、悲壮がってた自分が可笑しくなる。」
どうだろう?米原の批評日記は、寄せて、返す。寄せ=書物の批評の直後、返す波=おのれの職業(通訳)や取り巻く文明に対する厳しい批評が後を追う。自分を客観視する眼がある。
一日平均30語で事足りている若者たちの群れ。。を<一日平均xxx語で事足りている翻訳者の群れ>と読んだ私(商売=翻訳業)は背筋がサブクなった。
##
2006年に入ってから、米原の病状は末期に入っているようである。2006年2月、3月、4月の書評日記は<癌治療本を我が身を以て検証>と題した闘病記である。さまざまな癌治療(治療不要)本が紹介され(トンデモ本も含め)、米原はこれぞとおもう数々の治療法をおそらく藁をもすがる気持ちで受けている。5月18日付の最後となった読書日記の、治療体験を記した、最後の数行を引用しよう。
「。。(治療の)効果に疑問を持った私は、治療直後の検査を依頼した。すると、34.1%、2302とわずか30分以内にリンパ球が激減している。「私は幸運な70%以上の人々には入らないのでは」と問うと「平均すると増えていくものなんだ」「平均と言っても私の場合はどうなんです」「科学は平均を基準に置くんだ」「医学は応用科学ですから、個別具体的な患者に合わせて適用されるのでは」「いちいちこちらの治療にいちゃもんをつける患者ははじめてだ。治療費全額返すから、もう来るな」という展開になったのだった。こうして刺絡療法と共に爪もみ療法もただちに止めた。効く人もいるのだろうが、私には逆効果だった(週刊文春、2006/5/18)」 これがおそらく米原、最後の文章。直後の25日に亡くなった。
井上ひさしの解説から再度引用:
「「私の読書日記」が最後に近づくにつれ、<私が10人いれば、すべての療法を試してみるのに。>、<隅から隅まで読みたい本が出た。>、<万が一、私に体力気力が戻ったなら・・・・>といった語句がふえてくるが、しかし彼女は決して弱音をもらさなかった。最後まで感傷に流されずに思索を続けたつよい精神が、この一冊にいまも棲んでいる」
岩波文庫編集部がまとめた「読書のたのしみ」への彼女の寄稿:
「現在、曲がりなりにも私が母語の日本語と第一外国語のロシア語を使いこなし、両者のあいだを行き来する通訳という仕事で口を糊することができるのは、ふたつの言葉で多読乱読してきたおかげだと思っている。新しい言葉を身に付けるためにも、維持するためにも、読書は最も苦痛の少ない、しかも最も有効な手段である。だから、
「通訳になるにはどのくらいの語学力が必要なのでしょうか」
と尋ねられるたびに、私は自信満々に答えている。小説を楽しめるぐらいの語学力ですね、と。そして、さらにつけ加える。外国語だけでなく、日本語でも、と。」
私には通訳はとても無理だ、と、自信満々に言える。彼女の文章は速読できる。なぜか?文章にリズムがあるからである。彼女の日記やエッセイに色濃い<イデオロギ>に辟易の人々もこのリズムの良さ、テンポのある文章という点に関しては同意せざるを得ないだろう。
知人友人に愛された、感情豊かで、正義感と才知あふれる人間を癌という病が奪ってしまった。米国ジャーナリスト、ジョン・ガンサーが最愛の一子ジョニーを二十歳前に脳腫瘍で失ったときに放った言葉(著作タイトルにもなった)を想起せずにおれない。
死よ奢るなかれ。 Death , be not proud。
英国詩人、ジョン・ダンJohn Dunneの詩の一節である。
米原万里。2006年5月25日、鎌倉の自宅で死去。戒名「浄慈院露香妙薫大姉」。
佐藤優 『獄中記』 (岩波書店)、 『ナショナリズムという迷宮』(朝日新聞社) 書評 [Book_review]

元外務相主任分析官佐藤優(現在休職中)は宗男疑惑に連座、<国策捜査>により512日間、独房に閉じこめられ検察から聴取を受けた。そのおりの記録を60冊に及ぶノートに残したがそれを抜粋圧縮したモノである。佐藤のデビュー作である『国家の罠』(新潮社)は、逮捕の前、検察の取り調べ、判決などを扱っているが、この本は独房で読んだ本、思考した内容、弁護団とのやりとりを掲載しているから時期的にはスッポリ重なるが、内容的には重ならない。
この本を読み始めて一瞬想起したのは ドストエフスキーの作家の日記であり、地下生活者の手記。。等の初期作品である。ドストエフスキーは、チェルヌイシェフスキー事件(反政府運動が発覚)で死刑判決を受け、死刑の直前になって恩赦を受け(これはツァー政府のヤラセ、であった)その後、シベリア流刑という壮絶な体験をした。
佐藤はどうか?
佐藤に罪の自覚はない。そもそもこれは連座事件である。宗男を抹殺すべく(田中真紀子と合わせて)仕組まれた事件である。『国家の罠』を本屋で立ち読みしたとき、眼に飛び込んだのは佐藤を取り調べた西村検事が『これは国策捜査だ』と、佐藤被告に述べた、というくだり。笑ってしまった。これは馴れ合い捜査なのである。ホリエモンや村上(ファンド)に検察が、『これは国策捜査だ』と言うだろうか?ばかばかしい、というしかない。馴れ合い捜査だ、ということをシャアシャアと書く佐藤を含めて、だ。(佐藤によると、ホリエモンが検察の逆鱗に触れ、逮捕されたのは、ホリエモンが天皇制はおかしい、大統領にスベキ。。と発言したから、という(『ナショナリストという迷宮』)。もし佐藤が検察であってもホリエモンを逮捕したろう。佐藤は「国体」護持派であることを隠していない)
『獄中記』の末尾(付録)「塀の中で考えたこと」で佐藤は言う。「起訴された2つの事件について、
1 国後島ディーゼル発電機供与事業に関して、三井物産に漏洩するような不正行為に直接間接私(佐藤)が関与したことは一切無い。
2 テルアビブ大学主催国際学会への日本人学者などの派遣等に伴う資金供出は、外務省の組織決定に従ったのであり佐藤に刑事責任はない。」
佐藤は「国策捜査と、冤罪は違う」と何度も繰り返しているが、どこが違うのだろうか?これが私には分からない。国策捜査とは本来刑事事件でないものを政治目的で事件をでっち上げ(すなわち冤罪)て逮捕することである。冤罪は一般人に対するでっち上げ、であるところが異なるだけである(05年2月佐藤は有罪判決、懲役2年6ヶ月を受けたが即時控訴した。冤罪と認識するからこそ控訴したのではないのか。国策であるから控訴するのではあるまい)。佐藤に実際に経済罪があるのであれば、逮捕捜査するのは検察の義務であり国策ではない。
捜査することは検察の職務なのであり、検察のチョイスの問題ではない。冤罪はイコール国策ではない。佐藤のいうように捜査の過程で無罪とわかっていてもメンツのため有罪を押し通すこともあろう。しかし、国策捜査は最初から権力により意図された、冤罪なのである。大学大学院で神学や哲学を専攻した佐藤にとって上記の罪に問われようと内心の痛みはさらさら無く、衣食住申し分ない500日程度の独房生活はなんら負担でも無かろう。それでも、この『獄中記』を読むと、後半になると徐々に精神的な深みに達する記述=実存的な記述が多くなる。佐藤の独房の隣には、死刑囚が配置されるらしい(死刑囚は一般囚に比べて待遇がよい。しかし、いつ死刑になるかもわからない囚人の狂ったり泣きわめいたりする現場に立ち会うことになる)。
『獄中記』には佐藤(および鈴木宗男)の主張する北方四島返還方式が説明されている(岩波の雑誌『世界』に獄中から投稿されたがボツになった記事=ボツにしたのは弁護団の配慮である)。要は、四島一括返還方式に対し、鈴木宗男や佐藤らは2+2返還方式を主張し推進してきた(まず二島の返還をもとめ、残り二島は潜在主権を認めさせる。二島の放棄ではない。ここがなかなか理解されなかった)。この主張が、なまぬるいロシア派から出された、として当時のアメリカ一辺倒=コイズミ一派から目の上のたんこぶ扱いにされた。親中国の真紀子もろとも処断されたのである(鈴木宗男が<刺し違えた>)。(追記:しかし、無能あるいは政権にとって意味のない官僚や大臣はただちに更迭するのが当然である。税金の無駄遣いをしてはならない。企業では当たり前のことだ)
国家の罠を読めば、佐藤優は鈴木宗男議員と行動、思想を共にしており外務省の一職員として行動しているとは思われない。鈴木宗男とのやりとりで、佐藤(外務省職員)は、当時の田中真紀子外相を、「田中の婆ア」と呼んでいる(『国家の罠』)。佐藤優を外務省から追い出す過程でみられるのは外務省という一組織内のいざこざであり、もはや組織の体をなしていない。佐藤は、過去のロシア交渉の敬意を無視した米国一辺倒政策への変化(コイズミ等の新自由主義政策)を「パラダイム転換」と呼んでいるがそんな上等のモノ、大規模なものではない。単に、政治屋の新政策にしか過ぎない(二島先行返還に、日本がこだわる強い理由はない)。問題は、官僚とは何か?である。官僚は国民が選んだモノではない。公務員試験に合格した事務屋にしか過ぎない。国民が選挙で選んだ国会議員や、議員から選んだ内閣(政府)に従う義務がある。内閣が替われば官僚の仕事のやり方も変わって当然である。米国では民主<->共和の政権交代に伴って高級官僚らは自主的あるいは他律的に退任する。佐藤優のようにロシア政府要人とも深いつながりがありロシアの思考方式が手に取るように分かる連中にとって、日本政府のとるべき対露政策に確固とした定見があるのは理解できる。しかし、内閣や外務大臣が打ち出す政策には従わざるを得ない。外務大臣や首相を説得できなければ、
1 それに従って自らの定見を退け、新方針で臨む
2 定見を変えるのを潔しとせず、退官する
このいずれかをとるしかあるまい。これが官僚の限界である。
(もちろん、実際はこの規矩を越え、官僚が国会議員、政権を操っているのである。官僚とは国家に棲息する『宿便』か?佐藤優ももし<国策逮捕>されることがなければ臭い宿便として生涯を終えたろう。国民にとっても佐藤にとっても逮捕はラッキーであった。もちろん、この<逮捕>は企業であれば通常行われている人事異動、もしくは、更迭、でしかない。たかが更迭ですむところ、捜査や裁判などに無駄な税金を使うな、といいたい)
ニッポン(というより、米国をはじめ世界の先進国が大なり小なりもっている)の問題は、あらゆる省庁で官僚が力を持ちすぎることである。トロツキ『裏切られた革命』に、「国家が官僚に従う」とある。現在のニッポン(&世界の)政治の癌は、官僚なのである。佐藤はそれに気付いていないようである。官僚に対する<国策捜査>とは官僚内部の(税金を使った)乳クリアイ、にしかすぎない。
わたしの敬愛するロシア語同時通訳、故米原万里は書評家としてもその名を馳せた。遺作『打ちのめされるようなすごい本』(文芸春秋)では、佐藤優の『国家の罠』を2005年のベストスリーとしている。(わたしは同意しない。外務省内のどたばた劇を国民に知らしめた、という功績なら認めるが)。『国家の罠』(2005/5月、新潮社)に続く佐藤の次作『国家の自縛』(2005/9月、サンケイ新聞社)を米原万里はつぎのように評する:
##『打ちのめされるようなすごい本』から引用 p290-291
『国家の自縛』は。。。佐藤の限界というか佐藤自身の「自縛」状態も顕在化させている。。。
外務省には絶対に戻らないと言い切る佐藤が(古井戸注:『獄中記』では、判決後、外務省は、佐藤(現在休職中)を懲戒免職にするだろう、と何度も述べている)「現職の内閣総理大臣を全力でサポートしていくってのが役人の仕事ですし、それが国のカネで育成された専門家としてのあり方なんですよ。そのモラルを崩したくない」と述べて、小泉批判を自重し、靖国参拝からイラク派兵までを正当化するくだりは、上滑りで説得力がない。
国=現政権と自動的に受け止める役人的思考回路が自由闊達な佐藤の思考を、そこの所だけ停止させていて勿体ない。佐藤は首相がヒットラーでも忠実に仕えるつもりなのか。また国家権力に寄り添って生きた惰性なのか、権力者や強者の論理にとらわれすぎていて国内的にも国際的にも弱者や反体制派の視点が完全に欠落している。公僕は、まず誰よりも僕(しもべ)で「国のカネ」は国民の税金であり、憲法と現法体系に忠実であるべきだ。それに、作家は、自身の見解を率直に偽りなく語るべきで、権力者におもねったり遠慮したのでは、言葉が力を失う。それとも佐藤は、まだ役人生活への未練があるのか。
##引用終わり
これは『国家の自縛』に対する米原万里の書評だが、私には『獄中記』を含む、佐藤のすべての本に該当すると思える。
佐藤によれば、米原万里は佐藤優の知己であり、『獄中記』の出版を求めたらしい。佐藤優はこの↑書評を読んでいるはずである。キチンと応える義務がないか?『獄中記』にその答えは見つからない。
佐藤の著作に、国家の利益、国益という言葉は何度も出現するが国民の利益、国民の意見という言葉が出てくることはない。つまり、佐藤は優秀な官僚、ということであろう。
故米原万里は『獄中記』(岩波)をどのように評するであろうか?。
佐藤優は発表媒体として古くから佐藤を支援している岩波と、サンケイ新聞社(左翼と右翼!)を使っている。最近出した『ナショナリズムという迷宮』は朝日新聞社。『日米開戦の真実』は小学館。媒体により発言の内容にも気を配っているようである。
http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2006-06-14
http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2006-03-15
『ナショナリズムという迷宮』(朝日新聞社)の魚住昭「あとがき」によれば:
佐藤優の母は1930年、沖縄県久米島の生まれ、那覇の女学校に入った。14歳で沖縄戦を迎え、日本軍の軍属として激戦地を巡った。米軍の毒ガスを浴びたり、日本軍が降伏した後も摩文仁の丘で徹底抗戦を続けたりするなかでおびただしい人々が死ぬのを目撃した。このため戦後「天皇のため死ぬなんてとんでもない話だ。もっときちんとした自分の基軸を探したい」と思うようになってキリスト教に触れ、洗礼を受けた。ただし「みんな仲良く」という教会の偽善的体質や、高みから与えてやるという姿勢は嫌いで「こんなものは本物じゃない」と教会に積極的にコミットしなかった。。。
母の影響で佐藤が物心ついた時には既に神がいた。。。母は佐藤にほとんどキリスト教の話はしなかったが、神社仏閣では「ここには神様はいないから」と拝ませず、「人間の作ったものを拝んではいけない」と徹底して教えたという。佐藤はクリスチャンである。


なお、『ナショナリズムという迷宮』は共同通信社出身のノンフィクション作家魚住昭との対談本。これは面白く読めた。コイズミの2005年選挙勝利を、マルクスの『ルイボナパルトのブリュメール18日』と対比させるなど、卓抜。その他、ファシズム論、ナショナリズム論なども。『獄中記』でも哲学や思想にかかわる記述は大いに啓発を受けた。しかしこれなら他人でもできる。佐藤優にやってもらいたいのは、近代政治の癌、である官僚制批判、である。ネーションが必要悪、であるように官僚も必要悪なのであろうか?
佐藤優は、獄中で 廣松渉、ハーバマスと並んで宇野弘蔵を読んだと言っている。宇野学派の経済学者伊藤誠が講談社学術文庫として 新刊「『資本論』を読む」を出している。最終節「資本論をどういかすか」で伊藤誠は、現代の資本主義は、「資本論」が原理的に解明して原理的な相貌を随所にあらわしてきた、として現代の経済(グローバリズム、新自由主義)を概括している: 引用、p469~470から。
##
現代の資本主義は、1970年代に生じた深刻な経済危機を介して、情報技術の高度化と普及をすすめ、それにもとづき製品市場、労働市場、さらには金融市場に競争的な市場活力を再生させる試みを展開し、それを広くグローバルに推進する傾向を強化してきた。新自由主義はそれを経済政策の面で反映し、国家の役割を縮小してさまざまな公的規制を緩和、撤廃し、公企業を民営化し、福祉政策を削減して、市場原理による私的企業の負担や制約を軽減し、その競争的活力を再強化する方針を基調としている。それらの結果、19世紀末以降の資本主義が、金融資本の独占組織、労働組合の成長、および国家の経済的役割の増大の三面から競争的市場原理を制約する方向をたどっていた発展傾向は、全面的に反転されて、個人主義的で無政府的な市場での資本の自由な営利活動が経済生活の基本として尊重される状況が再現している。それは企業中心社会としても特徴づけられている。
それにともない、現代の資本主義は、自由な市場の競争的なしくみにもどづく資本の価値増殖運動の展開が、古典派経済学や新古典派経済学の想定するような調和的で効率的な経済生活を実現するものではなく、むしろ『資本論』に示されているような、労働者の階級的な抑圧、社会的な資産や所得の格差拡大、さらには内的矛盾の発現としての経済生活の不安定性をもたらすことを、はっきりと露呈してきている。その意味では、戦後の高度成長期に、労使協調路線で、日本でも一億総中流化といわれるような経済格差の縮小傾向が、国家による雇用政策や福祉政策への期待をともなって実現され、経済秩序が安定性を示していた状況は一変している。グローバルな新自由主義の政策基調とともに、現代の資本主義は、『資本論』の経済学が批判的に解明していた資本主義の原理的な作動を再強化し、いわば原理的な相貌を随所にあらわにしてきているのである。
##
佐藤優は魚住昭との対談『ナショナリズムという迷宮』で、新自由主義について、次のように発言している:
p87 ~
このまま新自由主義が進むとどうなるのか。。。ひとつは、資本主義のシステムが機能しなくなるほど弱者層が荒廃する。経済的困窮や将来への不安などから、治安が激しく乱れたり、少子化傾向に拍車が掛かって、労働力が十分に再生産されなくなるでしょう。ふたつめは、そこまで荒廃が進行する前に社会的弱者が横の連帯を模索し、強者との間で階級的対立が起こる。。。
東西冷戦が終わり、共産主義陣営の脅威はなくなりましたね。もはや資本主義社会において手厚い福祉政策はやめたっていいわけです。。。
国家は国民に自助努力を求めています。落伍者に対しては、”今日生きて逝くだけの食べ物だけは与えてあげるよ”程度の施し。エンゲルスが19世紀半ばに著した『イギリスにおける労働者階級』で描かれる救貧政策を私はイメージしています。救貧院という収容施設がつくられ<食物は極貧の就業労働者のものより粗末であるが、労働はそれよりもはげしい。そうしないと、極貧の就業労働者は、そとでの悲惨な生存よりも救貧院に滞在するほうをえらぶだろうからである>。
魚住昭: そんな酷い状態になるんだったら、資本主義システムは機能しないのでは?
佐藤優: ですから、救貧政策は困窮者への「いたわり」の衣をまとってでてくるでしょう。それに時々、国家は社会主義者・資本家や企業の不正を<暴いて>血祭りに上げ、弱者に対して<清潔な政府>をアピールしてきます。そうしたイメージ操作に成功すれば、社会的弱者は「いたわってくれる」国家と直接つながり、包摂されているんだという国家への「帰属意識」を抱くでしょう。実際は階層間は大きく断絶しているのに、どういうわけかまとまってしまうのではないでしょうか。そうしてファシズムが完成するというわけです。
##
『ナショナリズムという迷宮』でもっとも良いとおもうのはp167前後からの 官僚論、である。佐藤によると、官僚がせり上がってきたのは226事件以後、ということらしいが。わたしは明治維新(ひょっとして江戸期から?)に建設された官僚制(富国強兵、その前提としての教育制度)にその基礎があるとおもう。立花隆『天皇と東大』は、日本官僚史とも読める。タイトルをなぜ『日本近現代史』としなかったか?の理由が分かる。立花は明治以後を『天皇の世紀』とみている。東大とは、<官僚>での謂である。『天皇と東大』で最初異様におもったのが岸信介の取扱が大きいこと(しかし、満州、満鉄の記述はほとんどない。東大卒の官僚で戦後、首相まで上りつめた原点は岸信介の満鉄時代にあったのだが)。しかし、雑誌現代思想2007年1月号、特集<岸信介>が戦前の遺産(人的ネットワーク、国家改造計画)を戦後に引き継いだ革新官僚としての岸信介を明らかにしている。岸信介は、北一輝の発禁本である『国家改造案原理大綱』を、夜を徹して書き写したりしている。私有財産を無条件に承認しない人物であった、少なくとも戦前は。当然ながら、天皇機関説の支持者であった。
愛国心とは何か、あるいjは官僚の自縛: 佐藤優と米原万里
http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2007-01-08
関連ブログ記事:
http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2006-05-12
追記1:
2007 1/28、朝日新聞書評に、柄谷行人による『獄中記』の書評がある。
柄谷によると、
「。。本書の「知性」が魅力的なのは、それが外向的、行動的だからである。通常、それは知的であることと矛盾する。だが、著者の場合、通常なら矛盾するようなことが、平然と共存するのだ。たとえば、著者は「絶対的なものはある、ただし、それは複数ある」という。そこで、日本国家と、キリスト教と、マルクスとがそれぞれ絶対的なものとしてありつつ、並立できるのである。」
。。。だそうである。知性的でない私にはよくわからない、絶対矛盾的自己同一というやつ?
絶対的なモノとしてありつつ、並立できる? つまり、相対的価値しかない、ということではないのか?刑務所の中では知性的になれ、価値の並立を享受できる、が、現実の官僚としては、四島一括返還ではなく、二島先行返還、という特定の政策を取り、国策捜査に嵌められた。佐藤優が国策捜査である、と検事から告げられても安寧でいられるのが私には不審であった。<現実的なモノが理性的である>、と諭した哲学者の学徒ならば話は別か。国体護持論者である佐藤優が同時にキリスト信者である、ことには自身、矛盾は感じていないようである。官僚、としての思考と、(官僚に戻ることはないと断言している著者の)私人としての思考は、<矛盾なき並立>なのであろうか?
追記2: 1/31/2007 佐藤被告、二審も有罪
「外務省関連の国際機関「支援委員会」の予算不正支出をめぐる背任罪と、支援委発注の国後(くなしり)島発電施設工事入札をめぐる偽計業務妨害罪に問われた外務省元主任分析官佐藤優被告(47)の控訴審判決が三十一日、東京高裁であった。高橋省吾裁判長は「支出は自己の利益を計っており、正当化できない」などとして、懲役二年六月、執行猶予四年の一審・東京地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。
佐藤被告は上告する方針。
判決理由で高橋裁判長は「情報収集に多少なりとも役立てば支出できるというような野放図な支出は許されない。決裁を経ていても、違法でないとはいえない」と背任罪の成立を認めた。
(略)
佐藤被告側は「支出は事務次官や条約局長らの決裁を経て認められていた。与えられた職務を遂行しただけ」と主張。偽計業務妨害も「関与していない」として、無罪を訴えていた。
(略)
一審東京地裁判決によると、佐藤被告は支援委事務担当の元外務省課長補佐(42)=有罪確定=と共謀。二〇〇〇年三-六月、イスラエルで開かれた国際学会に日本人学者らを参加させる費用など計約三千三百万円を支援委に不正に支出させた。また支援委が発注した国後島ディーゼル発電施設工事で、入札前に予定価格の情報を三井物産側に漏らし、支援委の業務を妨害した。」以上引用、中日新聞、1/31/2007 から。http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20070131/eve_____sya_____011.shtml
 東京高裁に入る佐藤被告、31日午後、朝日新聞夕刊から
東京高裁に入る佐藤被告、31日午後、朝日新聞夕刊から
佐藤は
<国策捜査は、日本国家が『ある時代』から『次の時代』への転換をとげるためには必要であるとすら思っています> (獄中記)
さらに
<リスクを負って仕事をした人々が国策捜査の対象となり、失脚するような状況が続けば誰もが自己保身に走る。「不作為体質」が蔓延することにより、結局、国益が毀損される>
。。とも言っている。
国益が毀損されるのであればその原因は、国策捜査にあるのだろう?自らが<国策捜査を必要>と認めておきながらなんという言い分だろうか?さっさと、第二審の結果を受けいれて上告を取り下げたらどうか。裁判の費用と手間には国税が使用されているのである。
佐藤は、国策捜査を、
国家が、自己保存の本能に基づき、検察を道具にして事件を作りだしていくこと、
と定義している。いったい国家とは誰のことを指すのか?考えたことも佐藤はないだろう。たかだか、検察を操れる時の政権中枢でしかない。これを国家利益と(意図的あるいは非意図的に)錯誤すること、さらに国策操作を認めることに、官僚としての甘え、と、官僚気質を脱しきれない佐藤の言行の矛盾が発している。 上告するなら、そこに援用される、自己都合でない国民誰にも妥当する公のジャスティスを国民に示すべきである。


この国のかたち ~ 姜尚中『愛国の作法』 [Book_review]

姜尚中『愛国の作法』で最も重要な、こころして読むべき章は、第三章、日本という「国格」、である。(国格、とは河上肇の用語らしい)。
明治憲法から戦後憲法までの、この国のかたち、においてエポックメーキングな出来事を要約している。
第一章「なぜいま愛国なのか」p15
「市場経済の新自由主義的なグローバル化は、自然な法則的傾向ではなく、明らかにひとつの政治的なプロジェクトであり、それを推進していく上で、国家の役割と機能は決定的なカギを握っているからです。現に1980年代の日米構造協議から今日の郵政民営化や規制緩和、財政赤字の削減に至るまで、どれひとつとして国家(政府)の強力な介入、働きかけなくして実現された者はありません」
さらに、
「市場を、もっと市場を、と叫ぶ「改革」の政府が、国家(政府)の強力な介入を通じて国民国家という制度の「軟化」を推し進め、結果として、政治や公共的なものが経済や市場に取って代わられる「政治の終焉」をたぐり寄せつつあるからです。そこには、強力な「改革」の政治が、グローバル化にを薦めれば進めるほど、国民国家が政治の「墓堀人」になっていくという皮肉な構図が浮かび上がってきます」
しかし、この潮流はすでに、140年前の明治維新、120年目の明治憲法の制定から約束されていた、ともいえよう。
第3章で明治から昭和へのこの国のかたち、の変遷を姜尚中は要約している。この章はジックシと読むべきだ。
一箇所引用しよう:p108
「。。このような戦後の「この国のかたち」の「始まり」には、ハッキリと占領者の痕跡が刻み込まれていました。それは、明らかに戦後60年余り一貫して変わらないアメリカと日本の、保護者(パトロン)と顧客(クライアント)の関係を忠実に反映していたのです。
先の年頭詔書(天皇が昭和21年冒頭に発表した)で言えば、「五箇条之御誓文」が昭和天皇の意向によって付け加えられたということ、そして詔書がGHQの指導のもとに取り仕切られたということ、さらに、詔書がマッカーサー憲法草案および「憲法改正案要綱」発表の伏線であったということ、これらのことをつなぎ合わせてみるとき、それらは、アメリカの「日本派」主導による対日宥和的な「ソフトピース」という虚構のタペストリを織り上げていったのです」
欧米からの侵略から国を守り、さらに、不平等条約撤廃を目標にした明治政府の作業からどれほどのことを上積みしたのか?ふたたび<富国強兵>の道を歩むのか?
生きた化石=博物館行きの国家になるかもよ。あはは。
この章では、丸山真男やその師である南原繁の発言が盛んに引用される。丸山と南原(国体思想の残滓が残っている感じ)とはどういう関係だったのか?
『愛国の作法』は、『政治学入門、日本近代政治史概論』とでも読み替えて、最近のレジュメ本『姜尚中の政治学入門』(集英社新書、近代~現代西欧政治思想の歴史)の続編として読むべきだろう。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4087203301/sr=11-1/qid=1164245930/ref=sr_11_1/250-4394691-2059415
先日本屋で、ふと、気になり、司馬遼太郎の新潮文庫『司馬遼太郎が考えたこと1~15』のうち、とりあえず、1980年以後の発言集10~15(書評、講演、追悼文、推薦文など)の6冊を買った。昨日は、司馬遼太郎の「この国のかたち」1~6を注文。司馬遼太郎が考えていたが、「言語にしなかったこと」を、これらの本から読みとるのである。
姜尚中 『愛国の作法』を読む 書評 <忠誠も存せざる者は終に逆意これなく候> [Book_review]

はじめに
第一章 なぜいま「愛国」なのか
1 なぜいま「愛国」なのか
2 「愛する」とはどんなことか
第二章 国家とは何か
1 国家と権力
2 国家と国民
3 国家と憲法
4 国家と国家
第三章 日本という「国格」
1 「自然」と「作為」
2 「国体」の近代
3 戦後の「この国のかたち」
4 「不満足の愛国心」
第四章 愛国の作法
1 何が問題か
2 「愛郷」と「愛国」
3 「国民の<善性>」と「愛国」
4 「愛国」の努力
むすびにかえて
目次をずらずら、と書き写してみて、かなりむなしい気がする。それほどこの本はかったるかった。
(国家論は主題ではない。愛国心に関する議論は第一章と第四章だけで足りる)。
愛国に相当する英語はPatriotismである。
Oxford ConciseにはPatriot(愛国者)しか項目を立てていない。
Patriot: A person who vigorously supports their country and is prepared to defend it
Oxford Concise Dictionary of PoliticsにはPatriotismとして次の定義を揚げている(最初の数行):
Patriotism has always been defined as love of one's country or zeal in the defence of the interests of one's country.
愛するという行為は心的な行為、意識的な行為であって、上記Dictionary of Politicsにあるように、所属する国の利益を守るためにその国を守る情熱である。姜尚中はp37で(第一章2)で、エーリッヒフロムを引用しながら、愛国心の 愛する、は技術である、と言っている。しかし、この定義は静的にすぎる。ここでいう「愛する」の、主語はひとりの国民である。では、愛されるのは何か? この目的語を「国」とみなすから、議論が静的になり、膠着するのである。国とはなにか?土地や建物というハードウェアだけ、を指すのではない。ハードウェア上で機能している諸々の活動であり、とくに、中央や地方政府が、国民の支持する一定の活動方針に従って、提供する行政サービスのことをいうのである。ここで重要なのは、活動方針や、活動の環境は時間と共に変化するとういことだ(もちろん、国際政治においては国際環境の変化もこの中に含まれる)。すなわち、国を愛すること、とは、実際には 時々刻々変動する活動方針、綱領、プログラムを自らの意志で判断し、選択し、支持する/反対する、一連の行為のことをいうのである。たとえば、戦争を支持/反対、憲法改定を支持/反対、公人の活動方針を支持/反対、など。とうぜん、支持/反対に基づいて行われる行政活動は 国民がその活動を委ねた専門家(公務員、政治家)により担われることになり、この活動の監視も、国民の活動(支持/反対)の一部となる。国を愛するとは、支持/反対を含む政治(文化)活動の総体が、国民の厚生を維持増大しているかどうかを国民が判断して活動をコントロールすることを<熱心に>おこなう心的エネルギ(関心、awareness)を保持することを言うのである。
以上は私の愛国心の理解、解釈である(姜尚中の議論とは関係ない)。
姜尚中の議論には上記の 変動する政治環境における個人の継続的な意志決定過程、という時間的な要素がスッポリ欠けているのである。ある個人をとった場合、生まれて死ぬまでの、個人vs国家の関わり方(参加、選択、観察、意志決定- 同意/拒否、監視など)の行為全体に、<愛国心>はどう位置づけられるか、が問題なのである。姜尚中の議論はこの動的過程が欠け静的になっている。
丸山真男、石橋湛山、ベネディクト・アンダーソン(『幻想の共同体』、『比較の亡霊』)、橋川文三。。らの言葉を引用してるが訴えるところがない。ただ、キーワードとなるのは、丸山真男の 「忠誠と反逆」であろう(論文名であると同時に書名『忠誠と反逆』筑摩書房)。
忠誠と反逆、とはどういうことか。国に忠なるゆえに(仕える君主に)反逆する、ということだ。現在の民主主義的福祉国家でいえば、主権者たる個人と国民の厚生理念に背く政府に反逆する、という行為は 愛国の一種(しかも、重要な)なのである、ということだ。<忠誠も存せざる者は終に逆意これなく候>
注: 但し、封建時代じゃない現代では、主権者=国民に公務員(天皇、国会議員、裁判官)が仕えている。さらに、国とは国民のことである。国民が国民を愛せよ、と 国民に仕える立場にある公務員が国民に説教を垂れようとしている現在のニッポンの状況は、滑稽千万というしかない。
イラク戦争開戦前に、イラク大量破壊兵器国連査察団の一員であった海兵隊上がりのスコット・リッターを覚えておいでだろう。姜尚中も同席した会合において彼は聴衆の前で、開口一番、次のように宣言したという:
「わたしはこの戦争に反対する。なぜなら、わたしはパトリオットだからだ。わたしはアメリカを愛する。アメリカの憲法を愛する。だからこの戦争に反対する」。
姜尚中は「この若きアメリカ人のなかに、。。「忠誠」と「反逆」の弁証法的な緊張が見事に生きていると思いました」と書いているp187。
リッターの宣言こそ、愛国心とはなにか、を象徴的に表している発言である。
あるいは、姜尚中によると、。。明治の歴史家、竹越与三郎『人民読本』を引用してるp184。国家の目的は、個人の生存と進歩を抜きにしてはありえない、国家が誤りを犯すならば、これを糺し、「矯正」することこそ「愛国心」である、と竹越は言っている。
なお、安倍晋三『美しい国へ』、藤原『国家の品格』など、が頻繁に引用され批判されている。
わたくしの結論:
愛国心、など 公僕たる議員、政府や公務員、官僚が、主権者たる国民に要求したりしつけりするモノではない。 <頭(ズ)が高い!>のである。 ある時払いの催促無し、なんよ、愛国心なぞ。
追記:
愛国心とは、nationalismであるとか、patriotismであるとかいうが、機能的には、
awareness, involvement
関わり、関心、関与、であるとおもう。継続的な関与過程において、愛憎の感情がともなう。感情 mind(忠誠、反逆、愛情憎悪)は本質ではない。 継続的機能(関与)が本質である。
スコットリッター、リンク:
http://no-yuji.cside.com/iraq/RitterLink.htm
丸山真男『忠誠と反逆』:
http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0564.html
遠山啓 『代数的構造』 [Book_review]

日本評論社、1972年刊行。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4535601224/sr=1-1/qid=1163980805/ref=sr_1_1/250-4394691-2059415?ie=UTF8&s=books
いま品切れのようである。
内容は。。
第一章 構造とは何か
第二章 数学的構造
第三章 群
第四章 環と体
第五章 ガロアの理論
第六章 構造主義
とりあえず、本論2,3,4章を除いた概論である第一章、二章、六章を読む。素晴らしい。
さっそく、この本の元本である、筑摩書房の数学講座10『代数的構造』を古書店に発注した。
第六章で遠山は現代思想としての<構造主義>に言及し、数学的<構造>、とその限界についてコメントしている:
「。。これまで述べたように数学的<構造>は現代数学のきwめて強力な武器であることがわかった。しかし、はたしてそれは万能であろうか。
まずそれは時間的というよりは空間的である点に最大の特徴がある。ブルバキ(フランスの数学者集団)がそれを建築物にたとえたことからもわかるように、それは空間的であり静的である。
構造に限界があるとしたら、まさにその点にあるといえよう。時間的なものを完全に空間的なもののなかに解消してしまうことができないかぎり、時間的なものは構造からこぼれ落ちる他はあるまい」
。。として、構造主義者でありながら、構造間の発展に注目(したと私には思える)フランスのピアジェの構造理解を示す。p230
「。。この(思想運動としての)構造主義がややもすると陥りがちな硬直からそれを救い出し、その生産性を回復するために書かれたと思われる心理学者のピアジェの構造主義論を紹介しておこう。
彼は構造の条件として、つぎのような3つの条件を提示する。
1 全体性
2 変換性
3 自己制御
ピアジェは1の全体性についてつぎのように述べている。
「構造固有の全体性の性格ははっきりしている。というのは、すべての構造主義者たちが一致して認めている唯一の対立は、構造と集合体 -- すなわち全体とは独立した要素から成り立っているもの -- との対立だからである。
(略)
しかし、このように、全体と部分とを氷炭相容れない対立概念にみることは、誤りであろう。そのことについてピアジェは次のように述べている。
「あらゆる領域で、認識論的態度が、構造的法則をもった全体性の承認か、それとも要素から出発する原子論的合成かといった二者択一に記せられると思い込むのは誤っている」
簡単にいうと、要素無き全体か、全体なき要素か、という問題設定そのものが誤りである、というのである。事実は、全体が要素への分解をどの程度まで許すかという問題になるだろう。化合物を元素に分解することは一つの全体を要素に分解することに他ならないが、さらにそれらを合成することによって元通りのものが得らることもあり得る。
この場合は、全体と要素が互いに移行しうるものであり、したがって、両者を排他的に分離することは正しくない。
もちろん、いちど分解してから合成すると、元にもどらないものも少なくあるまい。そのような場合には全体と要素は互いに移行し得ないものとなる。
だが、このような非可逆性も、技術の発展によって可逆的となることもやはり少なくないだろう。」
↑私(古井戸)は、この箇所で、レヴィストロースが『野生の思考』で、非難、揶揄した論敵、サルトル(『弁証法的理性批判』)を思い出した。レヴィストロースのサルトル観は現在に至るも変わっていないのだろうか?
ピアジェと構造主義の関係は(さらに、レヴィストロースの数学知識の不十分、フーコーの数学知識は皆無。。であること。しかし、レヴィストロースの仕事には歴史的な価値があること。。)最近ちくま学芸文庫になった、山下正男『思想の中の数学的構造』の まえがき、に略述してある。
山下『思想の中の数学的構造』(80年)は、山本義隆『重力と力学的世界 -- 古典としての古典力学』(81年)と並んで、70年代、雑誌『現代数学』に連載されたあと単行本化された。
山下正男は文庫版あとがきに、出版時の時代背景を知るため、としてつぎのような簡単な年表を付けている:
1962年 レヴィ=ストロース『野生の思考』出版(仏)。 構造主義ブームを起こす。
1968年 フランス五月革命起こる
68-69年 日本の新左翼学生運動起こる
1970年 日米新安保自動延長。以後学生運動退潮。
1989年 ベルリンの壁崩壊
1991年 ソ連解体
山下は、同じく、文庫版あとがきで 「。。。1980年という年の思想的状況はマルクス主義と構造主義が対立していた時期だといえる。本書はそうした対立する二者のうち構造主義にすり寄ったかのように思われるかもしれない。しかし事実はちがう。本書は構造主義の意味を認めながらもその不徹底さを厳しく批判したものだからである」とし、思想史上の人物として 哲学者と数学者を兼ねていた、タレスとデカルトをとりあげている。
遠山啓 1909 - 1979 [Book_review]

文化としての数学、1973年、の末尾で遠山啓は言う:
「もし自然科学者の眼が素通しの眼鏡のようなものであったら、誤った仮説が生まれてくることはなかったであろう。しかし自然科学の歴史はおびただしい誤った仮説の堆積のうえに築かれているのである。
(略)
たとえば近代の天文学を創りだしたケプラーは一つ一つの遊星は妙なる音楽を奏しながら太陽のまわりをめぐっているものと想像し、その音楽の音譜さえ書き残している。このように過剰なほどの豊かな想像力が彼を大天文学者にしたのである。」
「数学が、さらに広くいって自然科学が人間の自由な想像力とは無縁である、という誤解を生みだしたものは、これまでの数学教育、自然科学教育であるといっても過言ではない。既成の知識をできるだけ多量につめこむことにのみ力を注ぎ、それらの真理が多くの誤謬を犯しながら獲得されたという過程を子どもたちに追体験、もしくは拡大的に再体験させるという不可欠な手続を抜かしているからである」
遠山啓『文化としての数学』光文社文庫
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4334741614/sr=1-1/qid=1163718483/ref=sr_1_1/250-4394691-2059415?ie=UTF8&s=books
1973年発行された大月文庫の再刊である。今回は79年に遠山が没した直後に発表された吉本隆明の長い追悼文が付いている。
敗戦の余塵がまだ醒めない時期、遠山啓は「量子論の数学的基礎」の自主講座を焼け残った学舎で開き、工場動員のため地方に散っていた吉本隆明のような皇国青年が多く参加し、熱心に耳を傾けた。
吉本隆明は追悼文のなかで次のように述べている:
「講義の内容は切れ味の軽快さよりも抜群の重みを、整合性よりも構想力の強さを背後に感じさせるようなものである。このような印象は、ある一つの対象を理解するために不必要なほどの迂回路をとおって到達した証拠であるように思われた。」
「国家ははたして敗戦後も存続しうるのか。大学なるものは存立が許されるのものなのか。本土内での抗戦はおこりうるのか。はたして人々はどうやって生存と生活の手段を獲得したらよいのか。こういうことの一切が未経験で不明であり、一切の指示がどこからも与えられなかった時期が、いま存在していた」
「。。けれども私(吉本)が何度でも確認したいとおもうのは、この無権力的な混乱の時期に、わたしたちは何かをおこすことも何かの指示をうけとることもなかったということである。つまりは左右をとわずすべてどんな勢力も諸個人も、何の想像力も力ももっていなかった。このことは無条件降伏であったか否かという法制上の論議の以前に、はっきりさせておかなくてはならない。」
「敗戦とはなにか、大学とはなんなのか、学問とはいったいなにかを回答することなしに、大学がまたぞろ再開されようとする姿が醜悪で、嫌悪だけがどうしようもなく内訌しくすぶっていた」
「遠山さんには敗戦の打撃からおきあがれない若い学生たちの荒廃をどこかで支えなければならという使命感が秘められていて、その情感と世相への批判が潜熱のように伝わってきた」
敗戦とは何か、学問とは何か。教育とは何か。
いまだにだれも、回答しようとせず、いまや、問おうともしていない問いである。ひとりの遠山啓もなく、遠山にあった教育理念も外部にもたず、教育者に使命感なる語は死語となって久しい、いま、われわれは個人の自立を自分自身で獲得しなければならない。すなわち、精神の自立。脱学校。脱国家。脱社会。
国家に何かを期待すること自体が愚劣である。
参考:
ウィキ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E5%95%93
中井久夫『関与と観察』 みすず書房 2005年 書評 [Book_review]


この書物は精神科医中井久夫の講演やエッセイのうち戦争や災害に関するもの、それに書評を収録している。
2004年末、中井が行った講演『日本社会における外傷性ストレス』p14~p40から:
##
中国戦線での戦争神経症者は被害よりも加害体験によるものが多いはずです。私はある詩人の子息のことを思い出します。彼は中国戦線から帰国後、座禅をもっぱらとしていましたが、毎晩、血なまぐさい悪夢にうなされていました。兵士として残虐な場面に無感覚になるために、訓練として中国兵士を銃剣で刺殺させられた原体験がありました。
いわゆる南京の虐殺はその代表的なものです。直後に交替した軍司令官は「作戦一段階と共に軍紀風紀漸く頽廃、掠奪、強姦類の誠に忌はしき行為」の頻発を日記に記しています(『畑俊六日誌』1938年、1月29日、みすず書房、『続・現代史資料4』、1983年)。彼は天皇に軍規の厳正化を誓い、1938、9年には軍規違反は減少します。
現地にいた作家石川達三は南京事件を『生きている兵隊』に書いています。彼は処罰されました。しかし、事実は帰還兵によって本国に知られてゆき、小学生だった私も軍人が祖父に語っているのを直接聴いています
##
p31
##
また、戦後五十年、「戦友会」がさかんに催されましたが、中国戦線参加兵士の戦友会は、しばしば口論、喧嘩、乱闘に終わったそうです。この集団の葛藤と外傷の深さを示唆する事態です。
##
p36
##
日本の古くからの伝統に、「清め」と「鎮魂(魂しずめ)」があります。
(略)
「魂しずめ」は、自分に対して怨恨を持っている魂を鎮めて、自分に「祟り」を起こさせないようにすることで、エゴイスティックな動機によるものです。それは「他者の行う清め」です。
しかし、「祟り」を恐れることは、伝統的な日本人の道徳的抑止力となっていました。「清め」の重視は太古における先住民族の殺戮と関係していたのかもしれません。たしかに殺害され集団的に埋葬された縄文人の骨が山陰地方で発掘されていますが、その規模は明らかではありません。弥生人と縄文人の混血が広く行われたのはまず間違いないでしょう。天皇に対する反逆者さえも祭られるのです。靖国神社も戦死者の怨みを鎮めるために生まれたのでしょう。私は戦時中の靖国神社の大祭のラジオ放送の記憶がありますが、まったく勇壮さから遠い、悲哀にみちたものでありました。
A級戦犯の靖国神社への合祀が問題になっています。当時の日本国民は彼らを支持し、そしてその後見捨てました。そのことも一種の疚(やま)しさをうんでいるのかもしれません。。。
(以下、省略。貴重な講演につき、是非、原文に当たって欲しい)
##
著者は地元で発生した大災害、1995年の阪神・淡路大震災の被害者ケアに係わった。救援活動に関する興味深い記述がある:
p20
##
すべては強い共同体感情の下に行われました。ある米国の医療人類学者は、悲惨さとお祭りの雰囲気とが同居していると指摘しました。この自発的救援の実行によって、戦後初めて日本人は自尊心を取り戻しました。
##
さて。。本書中、わたしが最初に注目し、読んだ記事は本書末尾に収録されている書評、
石川九楊『日本書史』を読む
である。初出、2004年11月。
石川九楊は書家。NHK ETVの番組で書の初歩を指導したこともある。
筆触、や、日本語の特徴に数々の著作があるがそのなかで、10年前に著した『中国書史』と本書は別格であろう。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4876980306/sr=11-1/qid=1163041222/ref=sr_11_1/250-4394691-2059415
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4815804052/ref=pd_sim_b_1/250-4394691-2059415
p304
中井は言う:
##
私が本書を読んで、まず得たものは、個々の歴史的人物を書によって切る面白さであった。
(略)
私の感触では、著者による筆触分析の方法は深層心理の分析法に近い。深層心理の分析は何も心の奥に隠れているものを引っ張りだすのではない。それは、些細なしぐさや言葉づかいのはしばしから出発する。著者の分析も筆触から出発する。書家はそれを偽ることができない。筆触は文字の無意識面である。ある人の文字言語的無意識、さらにその人まるごとの無意識である。
それだけではない。本書の究極の見どころは、この孤島文化の集合的無意識、歴史的無意識を洗いだすところにある。これはひょっとすると他の方法では容易に到達し得ない面ではないか。
##
。。として、石川による聖徳太子、聖武天皇/光明皇后の書への言及にコメントしているが、。。
##p310以降
もっとも衝撃的なのは、空海の書についての判断である。。
(略)
。。 空海は卓越した学僧で、見事に中国の書をマスターしているが、「ぶ厚い中国の知識を背景としながら和様のはしりをみせる空海は、知識に飢えた日本の、権力と、地域に無縁の大衆の両者を翻弄する怪物僧であったように、書からは思える。空海を神秘化する空海論は一度冷静に再検討いされるべきではないだろうか」と著者(石川)は結んでいる。
##
さらに、著者中井は、中国人留学生の興味深いエピソードを載せている。
##
。。彼ら留学生には 平かなはごく覚えやすいという。彼らの文字意識には原漢字とのつながりがなお見えるらしい。「カタカナ」に閉口し、これを嫌うのは、別の漢字あるいは無意味な記号に見えるからであろう。
中国は現在も営々としてすべての文物を中国語に置き換えつつある。元素の名ばかりでなく、すべての化学基(radical)に固有名を与え、これを以て、すべての薬品を漢字で表現する。。。。漢語化していない文物に「いまだ名あらず」と注記してあるとき、「まだ中国世界に市民権を与えていないぞ」という気迫を感じてしまう。日本語が全面的にカタカナ語を使っているIT用語にも断固、漢字で対応している。そちらをみて「ああそういうものか」とヒザを打ったこともある巧みさである。
##
何も考えずにカタカナに置き直すのは、確かに外国語を<日本語化>するのに手っ取り早い方法ではある。しかし、辞書上の語彙数の豊富は智慧の豊かさを保証はしまい。
http://www.yorozubp.com/0203/020322.htm
http://www.ncs.co.jp/china/chinese_it_words.html
日本書史、目次:
http://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN4-8158-0405-2.html
石川九楊は故白川静を私淑していた。石川が近代日本第一の書家、とするのは明治の民権家副島種臣である。
http://www.keibunsha.jp/soejima-1.htm
http://www.city.saga.lg.jp/up_images/s3491_20060317034259.jpg
中井久夫 『分裂病と人類』 魔女狩りという現象 書評 [Book_review]

今、中井久夫の『時のしずく』を読んでいます。
タマタマ、国際シンポジウムでのハナシ。原稿を眺めている私(中井)に、同時通訳者がこういった:
「原稿をそのまま棒読みされるなら、ご自分で逐次通訳してください。ナマの話し言葉でないと、同時通訳はできません」
『私(中井)ははっとした。同時通訳は究極の聴衆だ。話し手が、ここぞと勢い込んだり、言いよどんだり、言葉を選ぶのに迷ったりするところ。それに対する聴衆の反応。全体を包む場の雰囲気。これらがあって、初めて同時通訳が可能なのだ。これは、話し言葉の世界、対話が生み出す世界である。話し言葉と書き言葉との間には深淵がある』
中井久夫のエッセイは無駄がなく、簡潔、内容も深い。最近のエッセイと専門書(精神医学)を、数冊まとめて注文してしまった。 10/28

##
中井さんは著名な精神科医、ですが文章を読むと、文人、という感じがします。内省的な人です。神谷美恵子と親しいようで、神谷美恵子論などもあるよう。わたしは、ハンセン病隔離問題(ブログに書いたhttp://blog.so-net.ne.jp/furuido/2006-07-09)で神谷さんには?を抱いていますので、隔離問題を中井はどう考えているのか意見を読みたいと思っています。先日推薦した 民族という虚構の、著者小坂井敏晶、ですが。。http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2006-07-19
異邦人のまなざし、という自伝(パリ遊学するまでの軌跡)があります。
http://cse.niaes.affrc.go.jp/minaka/files/etranger.html
これも読もうかな、と思っています。
10/29
##
昨日届いた中井久夫『分裂病と人類』(東大出版)。82年の著作である。書中、第三章、西欧精神医学背景史、は150頁を超える力作、中井はこれを1972-1978に渡って書きついだ。
どの頁、どの行からも、その学識の深さ、粛然とせざるを得ない。
たとえば。。p115 魔女狩りという現象、から。
#
魔女狩りが中世の事件であるという通念は全く誤りである。魔女狩りはおおよそ1490年すなわちまさにコロンブスがアメリカを発見し、ヴァスコ・ダ・ガマがインドに到達するのとほぼ同時期に始まり、17世紀 -- 部分的には18世紀まで継続した、3世紀にわたる現象であって、ルネサンスから近世への転換期にほとんど全ヨーロッパの精神病狩りを含むものである。。。
魔女狩りは魔術に対する弾圧と同一視できない。古代ローマ世界以来、魔術はつねに存在した。魔女狩りの最中においても、多くの魔術師たちはまったく安全であった。確かに魔女狩りの対象になったものもあったが、女性に対する男性の犠牲者の比は百対一、あるいはそれ以下であったのが定説である。筆者はここで、多くの叙述と立場を逆にして、まず魔女狩りを行った側から述べてみよう。
(数頁略)
。。。 グーテンベルクによる印刷術の発明と識字率の増大とが、魔女狩りの普及に拍車をかけた。不十分で曖昧な情報が恐慌をよぶことは周知のとおりである。
(数頁略)
以上のように魔女狩りは実に種種の要因があるけれども、基本的には生産力の減退にかかわるものであり、それと関連してその地の政治家官僚の責任転嫁であったことを支持する証拠は、第一に魔女狩りがつねに「その地域の問題」であったことである。
(数頁略)
しかし13世紀以後、らい院(古井戸:らい病のらい、ハンセン病のこと)による隔離が進み、そして最後にペストが虚弱な彼らをらい院の集団生活のなかで侵すことによってほとんど絶滅させたらしい。。。これに代わって精神病者を収容する動きが始まる。したがって初期の収容原理がハンセン病において成功した、生涯にわたる隔離と此岸的なものへの断念であったとしても不思議はないであろう。
このあと、注として、日本においてなぜ魔女狩りがなかったかの理由を考察している。興味深いハナシを要約しておこう:
理由は、宗教の世俗化過程に魔術的なモノがまぎれこまなかったからである。
1 信長が 比叡山を焼き払い、僧侶を皆殺しにした 。 一揆の撲滅、医療からの神官、僧侶の追放 。 (幻術、魔術的方法を排除、一気に世俗化へ)
2 浄土真宗が森の文化を根こぎにした。民話、民謡、伝説、怪異譚を欠くことで、世俗化への道を促進。
##
このような深い書物をこのところ読んだことがない。
中井(神戸大学教官)が神戸大震災の際、沈着な報告、自己観察を行えたのも極めて納得のできることであった。
http://www.book-navi.com/book/syoseki/toki.html
http://www.kobe-np.co.jp/sinsai/2003interview/030507nakai.html
http://www.msz.co.jp/titles/06000_07999/ISBN4-622-07175-4.html
追記:
> 。。。 グーテンベルクによる印刷術の発明と識字率の増大とが、魔女狩りの普及に拍車をかけた。不十分で曖昧な情報が恐慌をよぶことは周知のとおりである。
歴史を顧みる必要もなく、情報や情報化あるいは情報遮断、が 差別、イジメの要因であり、手段、であることは現在のニッポンの状況を見ても明らかだろう。
高田明典 『世界をよくする現代思想入門』 ちくま新書 2006年1月刊 書評 [Book_review]
現代思想とはなにか。哲学とどう違うか? p29
現代思想の目的は、哲学の目的と異なる。前者は「目的を離れて、正しいとか正しくないとかを議論することはできない」とする。「色々な目的をもっている人たちが全員完全になっとくできるようなものの考え方」というものは「考えられない」p29
つまり、現代思想は「普遍的真理の存在を否定する」 p29
現代思想の特徴は「目的と方法は分けて考えることができない」という立場を取ること。現代思想は哲学と異なり、「初学の学」という立場を放棄する。
まとめると:
1)世界認識は目的により異なる。
2)目的を達成するための方法も、目的により異なる。
したがっていかの枠組みが生まれる。
1)対象領域を限定し、対象となる事物事象を明確にする
2)対象となる事物事象をどのような状態に誘導したいか、と言う意味での 的(まと) をおく。
3)その目的を達成するための方法を、対象となる事物事象の観察を通して構築する
4)その方法を実践する。 p32
何らかの目的を達成しようとするとき、まず、対象とは何か、対象となる世界がどのようなものか、を考える。「世界がどのようなものか」を深く考えたのはフッサールである。フッサールは、目に見えたものを そのまま、人間は認識できない、とする。解釈がかならず介在する、解釈は目的に従う、その従う方向性のことを、「志向性」と呼んだ。
意識が、世界、を把握しようとする。この意識が、志向性である。(ニーチェでは、「力への意志」) この志向性により世界は分節化される。文節化は言語記号により行う。この過程で重要なのは、
最初に意志が存在する
ことである。人間の言語は、世界を ありのままに みることはできる道具ではない。(フィルター=眼鏡を掛けてしか見えない、脳に支配された網膜を経由しなくては見えない)。
言語の登場。。。。
使用する言語により「世界の認識の方法が別々である」、つまり、「言葉の世界の主人は、もはや、人間であるとはいえない」ということ。言葉は人間が作り出した物であり、個人の言語使用(パロール)の蓄積が言語体系(ラング)であるにもかかわらず、人間は、言語に束縛されるということになる。
人間は、自由に自分の意志を表現し、自由に世界を認識する、ために言語を使っていると感じているが、その実、思考や世界の認識を方向付けているのは言語である。。。つまり、「言葉の世界の主人が言語になっている」=言語の専制。
よい、わるい、の定義:
善悪というものは、事前にではなく、事後に、毎日の生活の繰り返しにより形成されるものである。毎日の営みとは、この社会に既存する様々な制度(=言語)により規定されている。
制度は、人間が、人間社会をよりよく運営するために生み出したもの。しかし、その制度が人間を疎外し、束縛、苦しめる。これは言語も同様。ウィトゲンシュタイン(以下Wt)によれば、言語もまた制度である。
(このねじれを、矯正し、主人の座を人間にとりもどそうという実践が、デリダのいう脱構築)
言語ゲーム by Wt
Wtの言語ゲームが明らかにしたのは、『主体』は存在しない、ということ。存在するのは言語制度である、しかし、「他者は存在する」ということ。私、は存在しない、存在するのは「超越確実性言明の束」を無根拠に引き受ける機能としての自我のみである。この自我(=私)は言語制度の機能により発生するものであり決して「超越的に存在するものではない」
p188
さて。。そろそろ結論に。。
p193
。。世界を良くする上での行為をしたり、思考をしたりする主体として自分が存在する。世界を良くすることを考える(一種の行為)の行為者(主体者ではない)は「私」である。<<しかし、その世界は、他者が引き受けているものでしかありえません。 自分(自我)は誰かの「他者」として、世界を引き受けているという立場を持っているにしかすぎない>>
この状態を「利他的な行動こそが、正しい行動である」と読み誤ってはならない。「利他的な行動」というのは「私にとっての利他」である。「世界を<よく>する」という行為の主体者は世界そのものである。そして 世界 とは 言語、である。
p193 今、「たいへんな地点」に向かいつつあるということにちょっと注意して読み進めてください、と著者(高田)は念を押す。。。
p205
問題がすこしずつ明らかになってきた。。。これまで私たちは「主体は個体に存在する」という「個体というドグマ」にとらわれるあまり、「言語制度の発生する場所」と「言語制度に従う個体」を同一なものと考えてきた。しかし、「個体は言語制度に従う存在」だが、言語制度の発生する場所は「個体・個人」ではない。「言葉が生まれる場所」は共同体である。
著者いわく「この考え方は、おそらく即座には受入れにくいものだと感じられるでしょう。「言葉は個人の知的機能である」と考えられる場合が多いからです。しかし、ここまでの思想家・研究者の考え方を綿密に精査するならば、上記の考え方が妥当なものであることがわかるとおもいます」
唖然。急転、納得せざるを得ない結論。
懇切なブックガイド、用語説明、それに索引まで付いて、260ページ、780円プラス税。
結構な読書タイムでありました。
本書の続編のようである高田の『私のための現代思想』光文社新書も購入。
著者は、広松渉の『科学の危機と認識論』を基礎文献中の基礎文献として推奨している。私の持っているこの本の購入日付を見ると74.7.25とある。かき込みなどがあるから一応読んだことにはなっているのだが。広松全集版で再読しよう。全集版第三巻『科学哲学』の巻に収録。この巻には広松のマッハ論、相対性理論関係論文(アインスタイン論)、も収録。
民族という虚構 自壊する帝国 丸山真男講義録 書評 [Book_review]
この3連休(7/15-17, 2006)、親父の一周忌で田舎(廣島)に戻った。途中新幹線で読むための本を何冊か持って行った。
小坂井敏晶『民族という虚構』 東大出版会 1999
丸山真男講義録第二冊 東大出版会 2002
佐藤優 『自壊する帝国』 講談社 2006
佐藤優 『国家の崩壊』 (+宮崎学) にんげん出版 2006
小坂井の本は既に読んだのを再読するつもりだった。
丸山講義録は全部で七冊ある。わたしはそのうち最初の五冊を買ったがまだ一部しか読んでいない。この講義録は1949-67にかけて丸山が行った講義を、丸山自身の講義メモや資料、聴講生の筆記ノートを元に再編したものである。講義録全体に「日本政治思想史」、という総タイトルが付されているがこのうち、第三巻は「政治学」を扱う異色なもの、他は日本の政治思想史を扱っている。ただし、第二巻(1949年)だけは、幕末から明治初期のナショナリズムに話題を絞っている。この第二巻がおもしろそうだったので今回持って帰った。その序説p15-45は次の構成を取る。
序説 国民(ネーション)および国民主義(ナショナリズム)についての若干の予備的考察
1 ネーションとナショナリズムの定義
2 近代的国民主義の特性
3 ナショナリズムの構成要素
4 ナショナリズムの変容
国家(至上)主義
人種的民族主義
帝国主義
5 ナショナリズムの諸類型
本巻のまえがき(p1-13)とこの「序説」を車内で読み、まさにこれは巨匠の講義、という感を深くした。先年読んだ、小坂井『民族という虚構』に述べてあることが、終戦から数年もたたない、今から50年前の講義でズバリズバリと(アドリブを交えて)指摘されているのである。
『ネーションあるいはナショナリティという社会的統一体を可能にするエレメントを支えているものは究極において、矛盾するようだがナショナリティの意識、いわゆる民族意識以外にないということである。ここに国民あるいは国民意識なる範疇の最大の歴史的特色がある。つまり民族(国民)という基体がまずあって、それのイデオロギー的反映として民族ないし国民意識があるのではない。民族とは、民族意識--つまり共通のネーションに属しているという意識--によって結合している社会的実体なのであって、国民意識を除き去れば国民というものは存立しえないのである』p17
(わたし、古井戸、流にいいかえれば、存在が意識をけっていするのではなく、意識が存在を決定する。あるいは、意識->存在->意識->存在->意識、という限りない増殖。もちろん、存在、といっても、物理的存在ではなく、意識される限りの存在、に昇華されていく)。
そこで、国民や民族に実体はなく、
『民族意識が民族(ネーション)をつくるのであって、民族が民族意識をつくるのではない』(オッペンハイマー)
ということになり、結局、
『国民とは畢竟、国民たろうとする存在に他ならない』p18
ということになる。
小坂井の本は、このテーゼ(民族は実体ではなく、人間がつくりあげた虚構)を社会心理学的な実証データにより裏付けたものであり、重要なことは、民族(国家)を虚構として退けるのでなく、それを、人間は虚構なくしては生きていけない存在、民族概念も不可欠なものとして位置づけているのだ。
小坂井は、民族は虚構の物語であると一貫して主張し、
『個人心理の機能から社会的秩序成立の過程まで、あらゆる次元において虚構が絡み合って人間生活は可能になっている。しかし人間生活の虚構性を繰り返し確認したのは、虚構から目を覚まして自由な存在として生きよと主張するためではまったくなかった。逆に、人間の生にとって虚構がいかに大切な機能を果たしているかを説いたのだった。』
『差別が客観的な差異の問題でないことは部落差別を考えても分かる。いかなる文化的、身体的基準によっても判別できない人々を、その「家系」を探ることによって執拗に異質性を捏造する作用力が問題なのであり、何らかの異質性が初めにあるのではない』 おなじことをユダヤ人差別に、あるいは天皇制(万世一系)についても適用できる。
『象徴的価値を通して主観的に感知される民族境界が保持されるおかげで、他の集団の文化価値を受け入れながらも自らの同一性感覚を失わずにすむ。そしてまた、自らの同一性を維持しているという感覚が保証され、無理矢理に変身させられる危惧がないときに、影響あるいは異文化を抵抗無く受け入れることができる』
『言語、宗教、道徳価値、家族観などをはじめ、どんな文化要素でも時間と共に必ず変化してゆく。民族や文化に本質はない。固定した内容としてではなく、同一化という運動により絶え間なく維持される社会現象として民族や文化をとらえなければならない。あるいはこういってもよいだろう。もし文化と時代を超えて人間存在を貫く本質があるとすれば、それはまさしく、本質と呼ぶべき内容が人間には備わっていないということに他ならない、と。』p191
あとがきで、著者は次のように言う:
『世界が虚構によって支えられているということは、我々は無根拠から出発するしかないことを意味する。般若心経に 「色即是空、空即是色」という誰でも知っている章句がある。本書が力点を置いたのはこの言葉の前半部よりも、後半部であることはもうすでにあきらかだろう。世界は夥しい関係の網から成り立ち、究極的な本質などはどこまでいっても見つけられない。しかし、その関係こそが強固な現実を作り出している』
『人間は他者を根元的に必要とする他律的存在である。しかし、この他律性を自律性として感じとる他に人間の生きる術はないという否定性から出発しつつも、それを積極的な意義に転換する道を探ることを本書は暗黙の願いとしている』
「転換する道」を、個人の倫理としてだけでなく、共同体の、そしてグローバル社会の倫理として確立できるだろうか?
この著者の前著である『異文化受容のパラドックス』(朝日選書)同様、注にも興味深い主張が盛り込まれ、200ページというコンパクトな分量だが密度の高い議論が行われている。
詳細な目次を下記サイトに掲載している。この目次によりどのような内容を議論しているかおおよそ想像できよう。
http://cse.niaes.affrc.go.jp/minaka/files/ArtifactualRace.html
##
佐藤優の『自壊する帝国』と、『国家の崩壊』は今年の5月、3月にそれぞれ相次いで出版された。扱うのはソビエト連邦の崩壊である。前著は外交官としてソ連に85年に赴任した佐藤個人の眼から見た崩壊の過程であり(外交官としてのソ連高官や、ソ連の友人知人との交渉が中心となる)、後者は、宮崎学らとの勉強会「いかにソ連は崩壊したか」をまとめたもの。前者が主観的な見解、後者は客観的な見解、であり、双方の著書に重複はない、と佐藤は述べている。
双方とも私は読むつもりはなかったが、雑誌文学界で、ロシア文学?の専門家らしい亀井郁夫が『自壊する帝国』をべた褒めなので気になって両方を買ってしまった。亀井は
「どれほど混沌とした時代にも、一つの状況、ひとつの現象を作り出してしまう天才がいる。そうした天才の類稀な「人間力」を見せつける凄まじい一冊、それが『自壊する帝国』である」
とのべている。凄まじい賞賛ぶりである。
わたしは、佐藤の著書『日米開戦の真実』を貶したばかりだ。『自壊する帝国』は出だしこそ、グレアムグリーンか、ルカレか?というような期待を抱かせたが、読み終わる頃になると失望を禁じ得なかった。佐藤は語学の天才とまではいかなくても優秀な語学力をもっているとはいえよう。大学(同志社)では、神学を専攻したらしく、外交官としても交渉相手に相当なプレッシャを与えることはたしかだし、信頼も得たろう。しかし、日本人だからそういえるのであり、英米など世界に眼をやれば佐藤程度の外交官ならゴロゴロいるはずだ。ソ連共産党の崩壊過程などを語るにふさわしい人間はそれこそ掃いて捨てるほどいたのであり、その、一つのエピソードとしての価値以上のものをこの本は与えていないとおもう。佐藤の身分は大使館における外務次官であり、交際費は使いたい放題に近く、その身分と学識を生かせばソ連のかなりの高官ともサシで会え、電話などにより多くの情報も得えられよう。日本国から佐藤程度の情報収集をやったのは、佐藤しかいなかったのか?という疑いをむしろもたせ、わたしなどはお寒い限り、と感じた。英米などは外交官はもとより、ジャーナリストでも佐藤以上に権力中枢に迫っていたはずだ、と考えるのが当然だろう。
ソ連の崩壊過程を描いたドキュメントとしてわれわれはジャーナリスト岩上安身の『あらかじめ裏切られた革命』(1996年講談社、2000年講談社文庫)をもっている。この本は10年前に書かれたものだ。佐藤の上記の本は岩上の本に比べて何を付け加えたか?岩上の本には、ゴルバチェフのつまらなさ、エリツインの狡猾さ(宮崎学はエリツインをこれでもか!と持ち上げる。なにか裏でもあるんじゃないか?)、はもとより、佐藤の本にない、マフィア事情、チェチェン紛争の詳しい状況がある。
すでに1996年、岩上はつぎのように言っている(文庫、836ページ)。
『。。ジョージオーウェルはスターリニズムのカリカチュアとして1984年を書いた。二重思考とはボリシャビキの思考と言葉のねじれに他ならない。脱共産党化をはかったはずのエリツイン政権が、あの嘘と欺瞞と矛盾だらけのボリシェビキの「二重思考」をそのまま踏襲しているのだ』
岩上の本、2000年に文庫化されたがそれには政治学者カンサンジュンの解説が付く。
カンサンジュン『1991年8月クーデターに先立つ5月9日、著者の手の届く距離にいたエリツインは、絶大な群衆の歓呼の渦の中にいた。しかし、そのエリツインは「真っ青に青ざめていた」(岩上の引用)のである。「世界の主役」に躍り出て、「時代精神の体現者」にみえた稀代の英雄は、著者(岩上)の直感的なひらめきが正鵠を得ていたように、「戦車の上の世界精神」どころか、「嘘と欺瞞と矛盾だらけのボリシェビキの『二重思考』の忠実な後継者だったのだ』
『エリツインが進めた「脱共産化」の革命とは、実際には「空前のスケールの『マフィア資本主義』という怪物」の跳梁跋扈を招いただけだった』
カンサンジュンはさらにアンダーソン『想像の共同体』に言及し、
『もちろん、言うまでもないことだが、革命に成功した指導者達は、「旧国家の配線」 -- 官僚、情報提供者、ファイル、関係書類、公文書、法律、財務記録、条約、通信など -- を相続し、それをふんだんに利用したのである。この点で「裏切られた革命」より「あらかじめ裏切られた革命」の方がより罪が深く、またあさましいともいえる。。。エリツインは、。。。ロシアという「帝国」の恥も外聞もない「切り売り」を国際的なマフィア組織に委ねてしまうことになったからである』p846
岩上は、ロシアのチェチェン侵攻は決して容認することはできない、としてその理由を述べ、(p810以降)さらに、
『(西側諸国が)チェチェン人を見殺しにした代償は、いつの日か「共犯者」も必ず支払わなくてはならないだろう。「固有の領土」である北方領土の返還をロシアに求めておきながら、同じく「固有の領土」での独立した生活を望むチェチェン人へのジェノサイドを漫然と看過している日本政府に、果たしてその覚悟はあるのだろうか』岩上p830。
岩上のこの10年前の問いを、ソ連駐在元外交官である佐藤勝に、してみたい。
佐藤は、ソ連におけるバルト三国問題は、かつての日本における大東亜共栄圏問題、と気の利いたことを言っている。それならば、佐藤の称揚する大川周明が今生きていたら、チェチェン問題にどのような発言をしたろうか?ついでに佐藤に尋ねてみたい。
どうでもいい、過ぎ去った昔の問題には無駄口をタタキ、肝心の現在ただいまの問題には相手やおのれの「国体」に気遣って、触れようとしないのは、元外交官の麗しき習性か。
追記1:
「。。生物は過去と物質的に連続しているが、そのことをもって、ただ一つの生命が存在すると考えるのは誤っている。そのような発想をすると、次のような不条理に行き着く。父親の精子が母親の卵子と結びついて発生した胎児が成長することを通して人間は再生産される。私を構成した最初の細胞は両親の物質からできあがっている。すなわち私は両親の肉体の一部だ。今日私が生きているのは当然ながら両親だけでなく、彼らの両親、そしてまたそのまた両親というように、現在の私に到達する血統に属する先祖の誰もが、子供を残す前に死亡しなかったからに他ならない。そのうち一人でも生殖年齢に達する前に死亡していたら、この私はあり得ない。そういう意味では我々の誰もが必然的に「万世一系」である。
私は一つの受精卵が細胞分裂して生成した存在だから、現在の私を構成する細胞はどれも初めの受精卵との物質的連続性をもっている。そして私が発生してきた受精卵は両親の肉体の一部である。このアルゴリズムを繰り返していった時、アダムとイヴという一組の男女に行き着くのか、複数の人間集団に行き着くのかという点は別にしても、どちらにせよ最初の人間に行き着くだろう。したがって、我々人類はすべて同じ起源に物質的に連なっていることになる。
しかしここでもアルゴリズムが終了するわけではまったくない。人類はサルから進化してきた。そしてサルも他の哺乳類から進化している。突然変異という質的変化はあっても、物質的連続性がたたれているわけでは当然なく、先のアルゴリズムは人類を越えて貫通される。したがって、より原始的な動物を経て、細菌も越え、最終的には「原形質」のようなところにまで私は物質的に連続している。言いかえるならば、過去現在未来のすべての人間だけでなく、すべての動物、そして植物、すべての生きとし生けるものが物質的な連続性で結ばれる。
さらには現在の生物学の知見によると、生命がデオキシボリ核酸(DNA)というある物理化学的特性を持つ単なる物質に還元される以上、究極のところ、私と世界を物質的に隔離する境界は生物界でさえもなくなってしまう。単なる無生命物質とも私は結ばれている。それにまた、生殖以外による物質的連続性を考えることもできる。私という細胞群が死んで大地に帰り(それでも物質にあることには変わりない)、それが植物、動物など生態系の循環を経て、他の人間の抗生物質の一部になってしまう。このように、私は世界と切れ目無くつながっている、私は世界であり、世界が私であるという奇妙でかつ不毛な結論に帰結してしまうのである。」
以上、小坂井『民族という虚構』p55の注(9)から引用。
これは、般若心経、でいう 色即是空の世界である。柳沢桂子の般若心経、心訳で解説している世界。しかし、この程度の知見なら、高校の現代生物学で教えているだろう。人間であれ、動物であれ植物であれ、いや鉱物でさえもすべて当てはまる、したがって、何も言っていないと同じ議論になる。小坂井の議論はここから出発するのである。(空即是色)。
『滅びゆく国家』 立花隆著 書評 [Book_review]

『滅びゆく国家』 副題:日本はどこへ向かうのか 立花隆著、日経BP、2006/4/17刊
500ページ、2200円。日経BPのWebサイト『立花隆のメディア ソシオ・ポリティクス』の中から若干の編集を加えてまとめたもの。この本では読者の便を考えて、Web発表の時間順序はくずして、主題別にまとめてある。章編成は次の通り。( )内の数字は割り当てたおよそのページ数。
第1章 ライブドアショック ---- 会社とは何か (90)
第2章 天皇論 ---- 女性天皇・女系天皇の行方 (50)
第3章 靖国論・憲法論 ---- なぜ国立追悼施設はできないのか (120)
第4章 小泉改革の真実 ---- その政治手法と日本の行く末 (60)
第5章 ポスト小泉の未来 ---- キングメーカーの野望 (60)
第6章 イラク問題 ---- ブッシュ政権の欺瞞と日本の責任 (40)
第7章 メディア論 ----- 耐震偽装・NHK問題の本質 (50)
まず第四章と第五章はもはや話題性に欠けている。賞味期限も過ぎている内容は、本にするにあたっては削除しても良かった(第六章も、か)。
記事全体として繰り返しが多い(ウェブ記事だからしょうがないが)。パソ画面を印刷しただけなのだから、ハードカバーでなくソフトカバーとし、値段も下げられなかったか?それに、そのまま紙にするだけでは脳がない。読者の反響もすこしは取り入れたらどうか?
立花の文章は口述筆記のようなまるっきり、飾り気のない文章(そのぶん、サッサと読めるという利点はあるが)、ただし、ダラダラ感、あり。ぼんくら東大生などを顧慮せず、小難しい語句など交えてくれると眠気防止になるのだが。。。
以下、章別にコメント。
●第1章 ライブドアショック
結論として、国民が本当に知りたい闇の世界に一歩もつっこめていない。
堀江社長(と株主が)が外資リーマンブラザーズに、「むしり取られた」、というオナジミの構図を明らかにしている。すべてのストーリとあり得る事態を「想定した」プランはすべてリーマンブラザーズが立てたのであり堀江はその構図の中で踊らされていた。(検察の登場、ということもリーマンブラザーズの想定内であったろう。なにが生じようと、ぼろ儲け、なのだ)。検察や政治家の行動パターンに関する記述は立花のお手のものだろう。その分信頼を以て読める。
気になったことを一つ。
堀江がニッポン放送を乗っ取った事件について、立花は
「メディアの中でもラジオほどインターネットとの融合に不適当なものはない。ラジオはそもそも手が離せない、眼を使わなくて良い仕事をしている人の「ナガラ聴取のための」メディアだから、手と眼を必要とするインターネットと組み合わせることがいちばん難しいメディアなのである」p59でいっているがこれはおかしい。逆である。「ながら聴取」ができるからこそ素晴らしいのだ。わたしはこの2ヶ月TVなしで過ごしてきた。いつも椅子の直ぐ横に置いている24時間点けっぱなしのTVが故障したのだ。そのかわり、TBSラジオを24時間点けている(NHKはほとんど聴かない。コンテンツがつまらないのだ)。パソで仕事をしながら「ナガラ聴取」ができるヨロコビを満喫している。TBSは政府批判などをNHKとは違い自由にやっている。それに、重大なニュースや海外情報もチャンと入れている。庶民の声も電話ですくい上げている。つまり世の中のことは耳でわかるのだ。気になる情報を聞き取れば、ただちに、パソで検索すれば文字情報は得られるのだ。TVの場合はどうか?「音声+画面」情報のパッケージで視聴者に伝えるメディアだからナガラ聴取、というわけにはいかない。耳だけでは伝えたいことが伝わらないのだ。わたしは、ラジオは十分生き延びるメディアであると思う。ラジオにもニュースチャネルを設けて、海外ニュース(LDN、NYK、北京、パリ、イラク、。。)のホットニュースを流してくれるのは大助かりである。いちばん良いのは新聞やTVと違い「眼を向けることがいらない」ことなのだ。米軍のニュース(AFN)の定時ニュースでなにをやったか、あるいは米国メディア、BBCのトップ10ニュースは何か、を定時に入れるだけでもラジオの価値は十分ある。たとえば、TBSが立花と契約して、「立花の本日のニューストップ5」という情報を電話インタビュしたらどうか?電話でのTBSキャスタとの応答は、一方的な(チャットでないかぎり)書き込みとは違う話者のもつ情報に対する観点を引き出せるのだ。もちろん、引き出す側のキャスタの実力も問われる(NHKには信用できる、つまり権力に尻尾を振らない、キャスタがいないのである)。立花クラスの情報通を何十人と契約しておけば(支度金、ダイジョービ?)、コンテンツばっちしだろう。海外レポート(現在でもある)も、現地滞在のビジネスマンと契約して、ドンドンその都度ベースで入れれば、一日中、ラジヲ点けっぱなしだよ。(もちろん、外国語大丈夫であればいまでも海外ニュースはオンラインで聞けるが)。
もひとつ。検索エンジン(グーグル)のはなし。グーグルの商売を説明している。グーグルは利用者の利用記録を徹底的に収集し、加工して、利用可能なデータ群を顧客企業に販売して収入源としている。(むろん、個人情報にふれない抽象データとして)。立花はグーグルサービスのひとつであるGmailについて説明している。立花が、メールに
「最近おれのパソコンが故障したよ」
と打ち込むと、即座にパソコンの宣伝が出現したそうだ。
「こんど、xxxを殺ってやろうじゃないか」
などと打ち込むと、鉄砲(闇商売ね)や包丁、ノコギリ販売店が、出現するのか?
堀江事件でもわかったように、いくらパソからメールを削除しても専門家なら簡単にディスクから復元できる。中国などはグーグルが政府にすり寄っているから、個人情報など簡単にアクセスして個人の思想信条など調査しデータベースを作れるだろう。米国では電話会社がホイホイと通話記録をCIAに差し出した。世界の大都市にはグーグルの巨大ビルができつつあるという。「ビッグブラザー監視社会」というより、ベンタムが夢見たパノプティコン(集中監視型刑務所)を国民の目の届かぬ裏世界(バーチャル)に構築するのは現在の技術なら朝飯前であろう。Web上の魑魅魍魎。ネット社会、とは管理社会、監視社会の別称である。
http://www.ntt-west.co.jp/solution/hint/jpn/story/0509/pop_01.html
http://www.h5.dion.ne.jp/~allinone/words/panopticon.html
●第2章 天皇論
女性天皇でおかしくないこと、天皇は国民の支持があってこそ認められるものだ(憲法第一条)ということを説得的に述べている(『天皇と東大』の主題と重なる)。Y染色体論のナンセンスを述べ、ミトコンドリア説を展開。皇室典範など簡単に変更できる、ということを述べている。
●第3章 靖国論・憲法論
p214以降の憲法論は、あたりまえのことを述べているに過ぎないが、これは立花がなにも参考にせず打ち込んだ箇所だと思う。(憲法99条の重要性)さらに、「憲法第九条はグローバルスタンダード」という9条論p223、から基本的人権論をつづけるp250までの憲法論などこの本でもっとも優れた記述とおもう。とくに記述に参考書を使用したわけでもなく、立花の知識の一部を、一筆書きに、はき出したに過ぎないのだろう。さすが、である。
コイズミは中国韓国を訪問し、理由を説明して、靖国を参拝するのなら中韓もみとめるだろうという提案など。
それにしても、中国大陸で日本が何をしたか、など誰も教育していないのだからひどすぎる(小中高校だけじゃなく大人も、中国大陸ですくなくとも1000万人が死んだことを知らない)。これで、中韓が反日教育をするな、などとはいえまい。
私のブログ記事「東京裁判」との関連について。立花はこの章で「東京裁判を勝者の裁判として無視したがっている連中がいるが、東京裁判の結果を承諾する、とニッポン国政府は1951年の サンフランシスコ講和条約 で約束したのだ。その前提をひっくり返すのなら、あの戦争の当事国すべてと、交渉をし直す必要があり、もちろん、国連から脱退する必要がある。当然のことながら、常任理事国入りなどという野望は夢の夢」 と述べている。当然である。私の記事は、公式には立花のいうおりだが、同時に、立花も認めているとおり、法的におかしい部分は存在する(そも、戦争の終結にだれしも異存ない決着の仕方などあり得ない)のであり、その部分を、ニッポンジンはどのように理解して、自己の感情と、正義感に収まりをつけ、自己了解すればいいのか、という問いに対する私の回答である。
この章で指摘している重要な事実は、最近の、中国の学術と技術のエネルギのすごさだ。p271 学術論文誌に掲載される論文誌の質、と量はそのうち、日本においつき、凌駕していくであろう、と。立花にいわれなくても、その逆を、予測することは誰も困難と、日本国民は意図的に選別報道される報道から、うすうすは予感しているだろう。
ある日本人専門家の意見 「。。若手研究者の人材の厚みが違う。あと5-6年もすれば科学技術分野のほとんどあらゆる分野で日本は中国に追い抜かれる。一般の日本人はそういう事情をほとんど何も知らないから、科学技術は日本が上と思っている。科学技術分野で中国に抜かれたら、経済上の日本の優位もすぐに消えます」
反日教育をしてもらっている、いまが、花、であり、そのうち、見向きもされなくなるということか。
(中国共産党の将来を、どう予測しているのだろうか?専門家は)
●第7章 メディア論 p446
月刊現代2005年9月号の魚住昭の記事「『政治的介入』の決定的証拠」を掲載しているのがありがたい(この雑誌、わたしは読み損ねたから)。
魚住は入手源をあきらかにしていないが、中川議員と松尾(NHK放送局長)とのなまなましいやりとり(朝日の本田記者との)を掲載している。
##
松尾 「北海道のおじさん(中川議員)は凄かったですから。そういう言い方もするし、口の利き方もしらない。どこのヤクザがいるのかと思ったほどだ。」p450
##
本田 「放送中止を求めたのですか」
中川 「まあ、そりゃそうだ(略)」
本田 「これは報道や放送に対する介入だとは思いませんか?」
中川 「俺たちと逆の立場の人間から言えばそうだろう。オレは全然そうはおもわない。当然のことをやった」
(立花: 中川代議士は、圧力を掛けたことそれ自体はこういう形で認めているが、同時にこんなことも言っている)
中川 しかしだね。連中もそんなもん毅然として拒否したらいいじゃないか。そのほうが、君たちの言い分としても筋が通っているんじゃないの?
本田 全くその通りです。
##
これに続けて立花は、「筋論としては、中川の言うとおりで、政治家が何を言ってこようが、NHK側が毅然としてそれを拒否していれば、問題は起きなかったろう」とのべている。p452
ぶっ飛んだよ、おれ。
中川に「君たちも毅然として拒否したらいいじゃないか」と言われて、朝日は何をやったのか?社内の内部調査をして、だれが、この記録を魚住に漏らしたのかを探査しただけである。どうしてこれで、NHKを批判できるか。
あきれてものが言えない。どおりで、中川がでかいツラ、しつづけられる分けだ。NHKの能無しぶりはいまさら言ってもしょうがないが、恫喝政治屋にコケにされて恥ずかしくないのかい?朝日は。
滅びゆく国家。
国家を滅ぼすのは、権力に尻尾を振ることしか知らず、職業倫理に欠けたマスゴミである。
●追記:
第7章。耐震偽造問題を追及し続け、民社党馬淵議員との連携で話題を呼んだ「きっこの日記」。立花も注目しており、この きっこ、たる人物の正体を推定している。p482 アネハに近い人物が情報源である、としている(もっとも、立花の予測、あまり当たっていないようだ、たちばなし、として聴こう)。わたしも、だいぶ前まできっこの日記を読んでいたがいつのまにか止めてしまった。つまらないのだね。 立花には、ライブドアやこの耐震偽造、「官僚問題」として追及して欲しかったのだが。やってもしょうねえか、いまさら。。。
関連記事:
公共放送はNHKだけの独占物ではない http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2006-03-23-2
ライブドアの行方、あるいは官僚たちの春 http://blog.so-net.ne.jp/furuido/2006-03-15



