谷川俊太郎『定義』と吉本隆明『言葉からの触手』をめぐって [吉本隆明]
アマゾン古書店に注文した吉本隆明『言葉からの触手』が届いた。千九百八十九年六月十日発行の初版である。売価は一圓、郵送料二百五十円、締めて、二百五十一圓の出費。美本なり。
吉本自身はあとがきで本書を「断片集」と読んでいる(雑誌『文藝』に連載された)。先週図書館で借りた吉本隆明全詩集(千八百頁)の末尾にこの『言葉からの触手』全編が収録されている。したがって詩集として読むことも可能だろう。
「筆記 凝視 病態」を引用する(十二頁以降)。
たぶん現在は、書かれなくてもいいのに書かれ、書かれなくてもいいことが書かれ、書けば疲労するだけで、無益なのに書かれている。これが言葉の概念に封じ込められた生命を、そこなわないで済むなどとは信じられない。現在のなかに枯草のように乾いた渇望がひろがって、病態をつくっている。だがそれは個体が生きている輪郭といっしょに死滅してしまう。ほんとにそこなわれた概念の生命は、個々の生の輪郭をこえて、文字を媒介に万延してゆくだろう。想定できるいちばんひどい損傷は、やがて文字と概念のむすびつきがこわされてしまうことだ。たとえば生命という文字のかたちが[生命]という概念とむすびつく必然はなにもない。そうおもえるようになったとき、じっと眺めているとどんな文字でもそれがそんな恰好なのはへんだとおもえてくる。視線が文字の形をとおりぬけてしまう病態は、どこまでも蔓延してゆくにちがいない。そのときには、文字とその像とをじかに対応させるシステムをつくりあげているほかない。つまり概念に封じ込まれた生命が萎縮し、破棄されたあとは、文字がじかに対応する像とむすびつかなければ生きのびられない。文字の像が意味をなくして網膜上に氾濫するところを想像してみる。そして概念はもう生命をつくれなくなっている。批評はそのとき文字をたどりながら、意味ではなくて無意識にできあがった文字自体の像を語らなくてはならない。
ひとつの文字、それから組みあげられた語を、じっとみつめているとへんな感じにおそわれて、その文字、その語がそんな視覚的なかたちをもち、そんな意味をもつことが疑わしい気分になってくる。だれでもがどこかで、何度か出遇ったことがあるそんな体験には、普遍的な意味がある気がする。わたしたちが植物みたいだったとき、どんなかたちも、かたちの内在性であり、かたちとしてはみえなかった。わたしたちが動物になったとき、あらゆるかたちは、かたちの視覚像だったが、かたちには[意味]がなかった。わたしたちが人間になったときはじめて、あらゆるかたちは、かたちの像(イメージ)としてみることができた。それといっしょに、かたちの理念としてつかまえることができるようになった。じっと文字や文字を組みあげた語を眺めていると、その文字がそのかたちであることが不思議でならないとか、その語がその[意味]であることになんの必然もないと感じられてくる。そんな奇妙な不安を体験するとき、その体験は文字の誕生までにいたる[概念]の、ながいながい胎児期を反芻していることになっている。人間の胎児体験がぼんやりとした無意識の理念化であるように[概念]の胎児体験もまた、ぼんやりとした視覚像の理念化であるといえる。
[概念]はそこに封じこまれた生命の理念としては最高度な段階にあるはずなのに、どうして生きいきしていない抽象や、鮮やかでない形象の干物みたいにしか感じられないのか。これにたいする解答のひとつは、はじめにあげたように、書くという行為とその結果のもたらしたデカダンスが、感受性の全体を摩耗させてしまったということだ。あえてしかめつらしい言い方をすれば、自然としての生命と、理念としての生命の差異をひろげてしまったのだ。その意味では最初の原因は、文字の誕生のときすでにあった。文字が誕生してからあと、わたしたち人間は理念の生命を原料に、[概念]をまるで産業のように、大規模に製造できるようになったのだ。文字による語の大量生産体制の出現は、ひろがってゆく一方の過剰生産の系列をうみだした。それは必然的に[概念]のなかに封じこまれた生命の貧困化を代償にするほか、源泉はどこにもなかった。現在ではほとんどすべての文字、それを組み上げた語は、自然としての生命などを土壌に使わずに、人工的に培養しているといったほうがいい。
(以上、断片「筆記 凝視 病態」の全文)
ある漢字、たとえば、「味」でもいい、「字」でもいい、「生」でもいい、じっと見つめているとなぜこれらの文字が、味、字、生の意義をもっているのかわからなくなる、という体験はおそらく誰にもあるだろう。吉本のこの断片はその違和感をふくらませた断片である(言語学者ならもっと要領よく数行でまとめるだろう)。この断片でなにか疑問がクリアになったか、解答がえられたか、というと何もクリアになっていない。問題が鮮明になっただけだ。吉本はいきなり「文字」を持ちだしているが人類の起源以降、文字の歴史は新しいことに属し、無文字の時代が長かった。その時代でももちろん、人間同士(あるいは人間と家畜のあいだ)にはコミュニケーションはあった。文字ではなく絵や音声を介してである。中村元によればインド古代には「生命」という名詞はなかった、あったのは「生きる」という動詞だけである。西洋でもフーコーによれば、人間にも植物動物にも適用される概念としての「生命」という名詞ができたのは18世紀のことでありそれ以前は個別に「生きる」という動詞があったに過ぎない、という。動詞から名詞を生み出したことによりわれわれの知的境位が、われらの祖先と比べて高まったか?せいぜい要領よくものごとが表現できるようになった、つまり効率の問題にしか過ぎまい(現代人は、効率がいい、ということをエライ、といっているのだ)。釈迦やソクラテスと比べて現代人が賢くなったとはだれもおもっていない。しかし科学はちがう、というのだろうか?過去の遺産に接ぎ木を重ね重ねて巨木にしてしまっただけではないか。時代が下れば人類の累積歩行距離、重量が増大するのは当然のことである。その距離と重量を桎梏とせぬ知恵が人類に備わっているか、どうかが問われる。知見の量や、飛び交う文字、蓄積される文字の数は経年とともに増えるのは自明だ(蓄積すれば、だ。何千万年も今後、捨てずに溜め続けるのか?)。
吉本のこの断片はメディア論である。彼はその後もメディア論を書き続けるがこれは『言語にとって美とはなにか』で書き残したことをフォローしているともいえる。ヒトは教えられなくても二足歩行能力を有し、文法規則を操る能力をもっている(ただし、幼児の基礎訓練を欠くと死ぬまで言葉を操れなくなるという。幼児に母親が手を貸さないと人間も死ぬまで四つ足歩行を行うのだろう)。文字の発明により、長い長い無文字の歴史から人間は解放された。文字の発明は人間にとって解放であったのか?人間が増え続けると食糧危機になり人類は滅亡する、というのは経済学者(マルサス)の予言であった。たしかに自主規制あるいは権力による強制として産児制限を人類がやらなければ人類は滅亡するのではないか、という事態を我々は感じている。音声による伝達の言葉が文字により規制を解かれ記録可能な媒体と成るや語彙やしたがって概念の細分化、増大は留まるところを知らなくなった(しかし、アルファベットを増やそうとか、漢字を増やそう、という運動はないようだ。これから何万年経過してもアルファベットと漢字は現在のママ保存されるのだろうか。奇異なことである)。言語にはマルサス問題は無いのか?
「。。。文字による語の大量生産体制の出現は、ひろがってゆく一方の過剰生産の系列をうみだした。それは必然的に[概念]のなかに封じこまれた生命の貧困化を代償にするほか、源泉はどこにもなかった。現在ではほとんどすべての文字、それを組み上げた語は、自然としての生命などを土壌に使わずに、人工的に培養しているといったほうがいい。」
地球上のエネルギは有限である、ゆえに、持続可能な範囲にわれわれの生活パターンを規制しよう、という認識に達したのはまだこの数十年のことにしか過ぎない。表現の世界にも<持続可能な限界点>がわたしは存在すると考えているのだが。もちろん人工知能を駆使して翻訳をやり、大量記憶装置で片っ端から文物、アートを記録し検索しても、それを自然ではない、とは私は言わない。人工的、は自然の一部である。自主、強制の産児制限~避妊をやらないのとの違いは、産児制限しなければ途端に殆どの人間の生活が成り立たない、死に至る道であることが計算上も、事実からも確認できているのに対し、メディアについてはいまだに滅亡の道が示されていない、示すことにためらいを感じている。メディアの世界は、他の分野が近代にいたりパラダイムチェンジをせざるを得なくなったのに対し、いまだにマルサス以前の<古き良き時代>の夢を見続けているのである。
谷川俊太郎『定義』(千九百七十五年出版)から「不可避な汚物との邂逅」を引用しよう。
路上に放置されているその一塊の物の由来は正確に知り得ぬが、それを我々は躊躇する事なく汚物と呼ぶだろう。透明な液を伴った粘度の高い顆粒状の物質が白昼の光線に輝き、それが巧妙に模造された蝋細工でない事は、表面に現れては消える微小だが多数の気孔によっても知れる。その臭気は殆ど有毒と感じさせる程に鋭く、咄嗟に目をそむけ鼻を覆う事はたしかにどんな人間にも許されているし、それを取り除く義務は、公共体によって任命された清掃員にすら絶対的とは言い得ぬだろう。けれどそれを存在せぬ物のように偽り、自己の内部にその等価物が、常に生成している事実を無視することは、衛生無害どころかむしろ忌むべき偽善に他ならぬのであり、ひいては我々の生きる世界の構造の重要な一環を見失わせるに至るだろう。
その物は微視的に見れば、分子の次元にまで解体し、他の有機物と大差ない一物質として科学の用意する目録の中に過不足ない位置を占めるだろうし、巨視的に見れば生物の新陳代謝の、また食物連鎖の一過程として、既に成立している秩序の内部に或る謙虚な機能を有しているとも言い得るだろう。事実そこには何匹かの蛆が生存を始めているし、如何なる先入観もなく判断し得ると仮定すれば、その臭気すら我々の口にする或る種の嗜好物のそれと必ずしも距たってはいないのだ。
光にさらされ、風化し、分解し、塵埃となって大気に浮遊し、我々が知らずにそれを呼吸するに至るまでの間は、その存在に我々が一種の畏怖を覚える事は否定できぬ事実であって、そのような形でのその物と向かいあう人間精神は、その畏怖のうちにこそ、最も解明し難い自らの深部を露わにしていると言えよう。
(以上、「不可避な汚物との邂逅」全文)
「汚物」とは糞(ウンチ)のことである。読みながら笑いがこみ上げてくる。この詩集を代表する(と、私は思っている)このウンコ詩は別名「色即是空、空即是色」と名付けてよい。かたちあるもの、かたちなし。かたちなきもの、かたちをなす。脱構築と構築。詩人(および幻想に生きるわれら衆生)にとって重要なのはもちろん空即是色である。
谷川俊太郎はこの詩について、大岡信との対談で、つぎのように述べている:
「。。。この詩を僕は大真面目で書いたつもりだったんだ。自動車の運転免許で覚えさせられた法令の奇妙な、しかし一語でも間違うと点を引かれる苛酷な文章というものが意識下にはあったと思うんだけど、とにかくわりと真正面から書いた。(略)
あるいは、本当に正確な散文で駅から自分の家までの道筋を書こうとしてみると、最後にはどうしてもそれによっては我家に辿りつけない不思議なものになってしまう。そういう言語自身の変質というか自律性みたいなものがある。(略)
そこから先は自分でもよくわからない一種の言語の自律性みたいなものに引き回されている感じで、詩が自分の予想を越えたものになっていった。そういう言語それ自身の変質みたいなものが、この詩集にはずいぶん出ていると思う。それで結局、定義はできないのである、これは定義のパロディーである、ということに最終的になってしまった。(略)
言語表現を抜きにして物としての汚物を考えてみても、もしそれを分子レヴェルで微視的に見てしまえば、これは汚物じゃなくなるわけですよね。人間のからだの組成と同じただの蛋白質とかなんとかになっちゃう。だから言葉によって見る場合でも、或る人間的な距離というのがあるのじゃないかな。つまり、言葉で顕微鏡みたいにいくらでも微視的になれるし、あるいは望遠鏡みたいにいくらでも巨視的になれる。そしてそのどちらの視点をとっても、そのとき言語というものは或る人間的な手ざわりを失っていく。
そういうところに俺は一種の憧れを持っている。そういうふうに言葉で分解してしまいたい。分解してしまったところで逆に他のものとの関連が出てくるという面白さを少し意識しているようなところがある。だから汚物を臭くなく書こうとは意図しなかったけれども、結果として汚物の臭いや手ざわりを喚起しなかったということで、自分としては成功した作品だという印象があるね。でもそれがはたして詩なのであるかどうかという点は、俺としてはつねに疑問としてあるわけよ。だから『定義』にも『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』にも「詩集」とはどこにも入れていない。おそるおそる「これは詩でしょうか」と差し出しているわけだ。と同時に、詩でなくたってかまわないということでもあるんだ。それが言語の一種の面白さを現していれば、別に詩とよばれなくったっていいじゃないかと」
分子レベルで汚物を見れば、汚物でなくなる。。という谷川の言明は科学的(化学的)には危うい。食物を食うときから排便するまでを内視鏡ビデオなどを使って子細に撮影したとする。そのフィルムを逆転すればあら不思議、汚物から食物が発生した、きれいで清潔な食物を汚物に変換する原因はひとえに人間の内部(脳を含む内臓)にあって外部にはない。しかし、食物と汚物では分子の総量は不変であっても、分子間の結合状態(構造)は明らかに変わっている。負のエントロピと熱量(カロリー)を体内で費消した代償が、臭いと形態の醜さ!であり、フィルムの逆転は実世界では起こりえない、とより正しく説明することもできよう。この点は吉本の上記の断片のほうが事態をより正しく説明している、とわたしはおもう。文字の構造の不安定さ=恣意性に言及し、しかもその起源を人間が胎内にあったときの記憶にまで遡及させており、吉本の起源論やハイイメージ論につながる思考も見える。ただし、こういう事実の危うさがあっても、科学的妥当性のみ、を詩に求めても仕方がないし、この詩の面白さが失われるわけではない。しかし、谷川俊太郎が自作を解説して言う:
「だから汚物を臭くなく書こうとは意図しなかったけれども、結果として汚物の臭いや手ざわりを喚起しなかったということで、自分としては成功した作品だという印象があるね」
。。は納得しがたい。この詩の最終段がもっとも重要な箇所であり、そこに言う:
「光にさらされ、風化し、分解し、塵埃となって大気に浮遊し、我々が知らずにそれを呼吸するに至るまでの間は、その存在に我々が一種の畏怖を覚える事は否定できぬ事実であって、そのような形でのその物と向かいあう人間精神は、その畏怖のうちにこそ、最も解明し難い自らの深部を露わにしていると言えよう。」
これは自分のひった、臭いにおいと異形を物ともせず、汚物、としてまじまじと観察している詩人の姿がある。なぜ清潔で構造を保った食物が、熱と構造を失いこのような醜いものに成った(変形した)のか。これはたしかに畏怖である。人間の内蔵を設計した神以外であれば畏怖以外にない事態である。もちろん、ある種の医学者ならばこれを当然のこととして一片の畏怖心をいだかないかもしれない。
生活時間を一旦保留し、地上の物体を観察する宇宙人のようでもある。想像力という内視鏡を何本も突っ込み言語平面に写像する、これは詩の機能である。
で、問題は、結果として汚物の臭いや手ざわりを喚起しないのは、谷川の詩の一つの特徴だが、これは、美点ではなく弱点だと私はおもっている。
対談相手の大岡信は次のように述べている:
「言葉とか絵画とかは、言ってみれば人間が発明した、物に関しての一種の記号であって、記号は物自体と違うからこそ記号なんだ。だからその記号で元の物自体を完全に表現することは不可能であると一応は言えるわけだ。けれども想像力というものが人間にはあるらしくて、想像力が参加すると「記号」がもう一回「物」になるというところがあるのじゃないか。
例えばフェルメールの絵に描かれている光りなんかは、近寄ってみると白い斑点の塊りにすぎないわけよね。それが少し遠のいて見ると光りそのものと見えるのは、一つには網膜の作用もあるけれども、網膜が受けたものを「あれは光りだ」と認定する力はどうも想像力というふうなものではないのか。記号をもういっぺん物の次元に戻す作業を、人間の能力の中では想像力という働きが担っているという気がするね。
(略)
君の場合の精神の傾向性というのが、こういう詩の作り方に出ているんだけれども、突きつめていくと「AはAである」というところへ無限に近づこうとしていくものなんじゃないかな。言いかえると、同語反復のなかに最も真理があるということで、数学的思考なんだね。数学者というのはおそらく思考の原点にいつでも同語反復というものを置いている人たちじゃないか。」
谷川「科学そのものが同義反復であると言った人がいたね」
大岡「そういうものだと思う。だから君の頭脳はやっぱり非常に科学者的なんだよ」
(ここで、では「科学者」とは誰?同義反復を得意とする人たちのこと?などと茶々をいれてはいけません。)
以上の対談は1977年『批評の生理』(思潮社)から引用。この本は、最新刊である谷川・山田『ぼくはこうやって詩を書いてきた』という弛緩した対談集に比べ、谷川と大岡という実作者による、詩とは何か、に迫る鋭い対論になっている。
谷川『定義』は10年後に出版される吉本『言葉からの触手』を先取りしているところがある。このふたつの断片集~詩集は、谷川・吉本の初期の詩篇と呼応している。言葉に対し疑念と不安と確信(開き直り)なくして詩は書けぬだろう。
谷川の詩は海外でも翻訳されて、とりわけ中国では文学賞を受賞をするなど好評という。中国で谷川の詩を紹介・翻訳している中国の詩人・田原(ティエン・ユアン)氏の『谷川俊太郎論』(岩波)がまもなく出版される。
今夜は谷川の新詩集の夢を見そうである。この詩集によりノーベル文学賞と平和賞をダブル受賞となれば目出度い。詩集名は『尖閣』 。
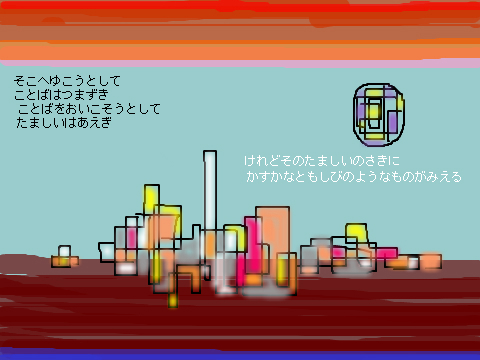




コメント 0